税金・相続
相続税や所得税など、土地活用にまつわるさまざまな税金の仕組みや特例などについてご紹介しています。
まずはこの記事をチェック
税金・相続 新着記事
-

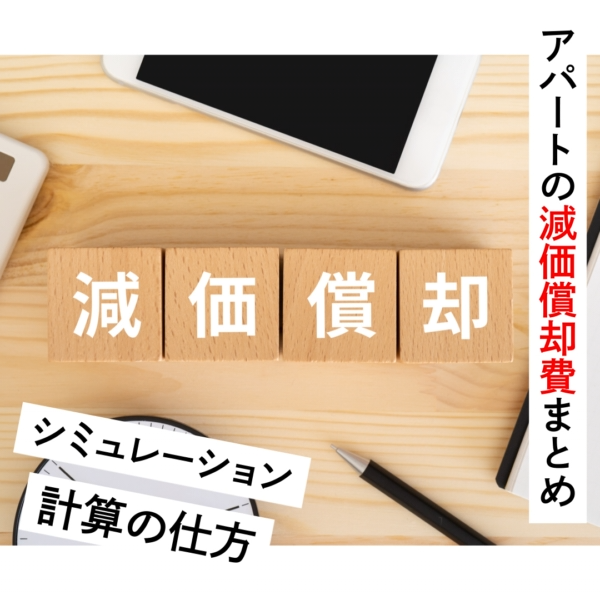
アパートの減価償却費まとめ|シミュレーションから見る計算の仕方
アパート経営を始めるうえで知っておくべき知識の一つに、減価償却があります。減価償却とは建物などの固定資産の購入費を、使用期間に応じて分割計上する会計処理のことで、上手く活用すれば所得税などの税金負担を軽減できます。そこで本記事ではアパートの減価償却費の計算について、実際のシミュレーションを用いながら詳しく解説します。
-

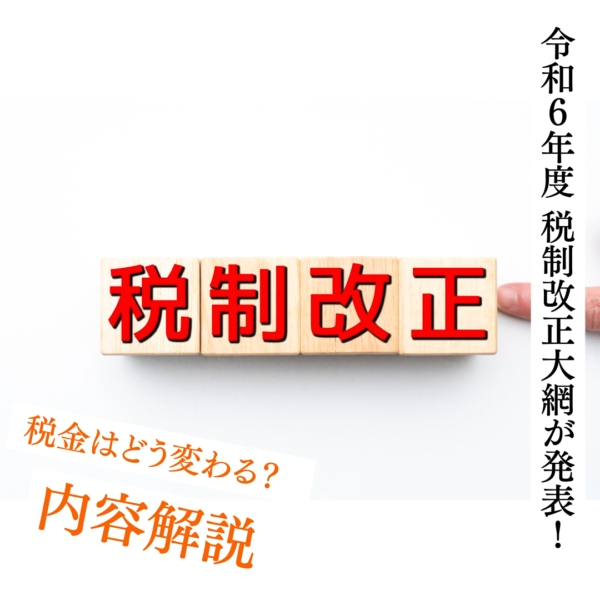
令和6年度(2024年)の税制改正大網が発表! 税金はどう変わる?
【令和6年度(2024年)税制改正要望から読み解く】今から読み解く税制改正とは!? にて内容を予測しましたが、その後の準備具合はいかがですか? 今回は、ついに発表された令和6年度の税制改正大網について解説していきます。
-

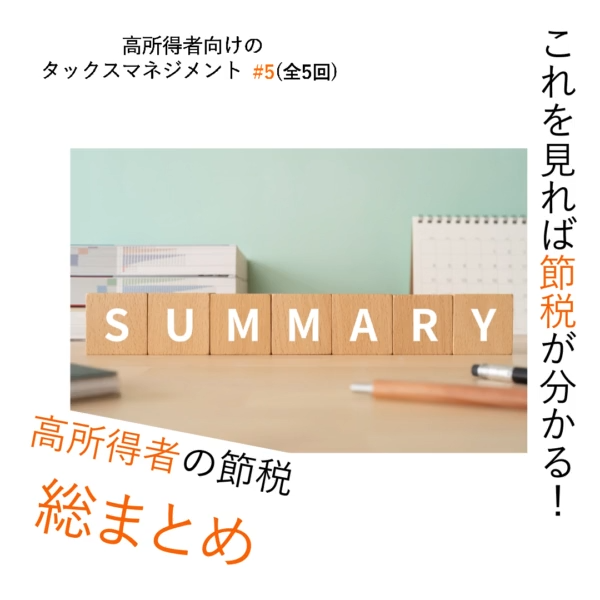
高所得者向けのタックスマネジメント ~総まとめ~
高所得者にも関わらず手取り額が少なくなるのは「税金(と社会保険料)」が原因です。税金は国民全員が一律ではなく、高所得者ほどに税額が高くなる「超過累進税率」という制度になっています。その結果、少しくらい年収が高くなってもほとんど手取り額が変わらなくなっているのです。超過累進税率を採用した日本の所得税の税率は、以下のようになっています。
-

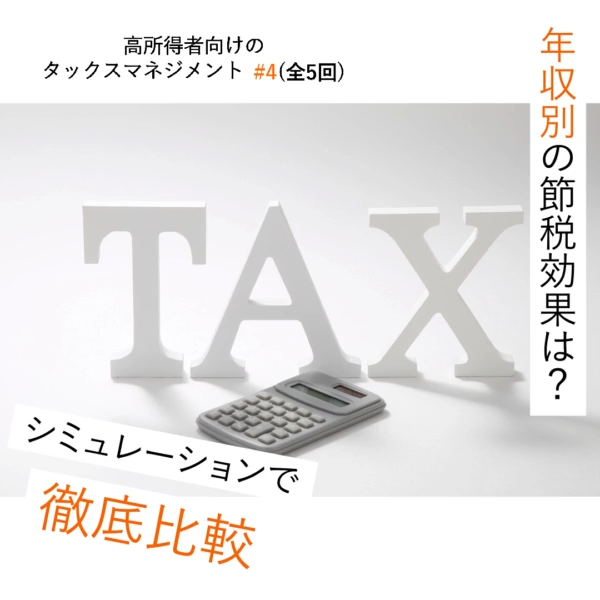
年収別の節税効果をシミュレーション比較
今回は、「築25年の(中古の)木造賃貸物件」を購入したという前提でシミュレーションしましょう。木造の賃貸物件の減価償却期間(法定耐用年数)は22年ですが、上記のように購入時点で減価償却が終了している場合は、「法定耐用年数の20%の期間(1年未満切り捨て、最短2年)」を減価償却期間とすることが可能です。
-

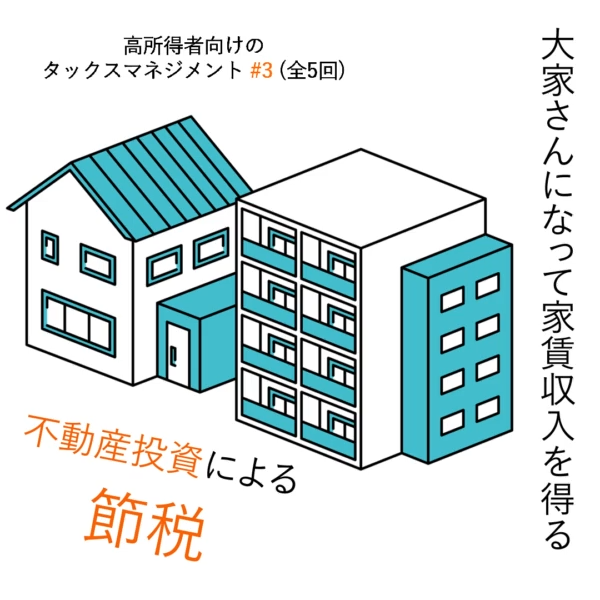
不動産投資を活用した節税
不動産投資とは「大家さんになること」が必要です。土地に賃貸建物を建てて人に貸し、家賃収入を得ます。そして、この賃貸経営において「計算上の赤字」を出すことで、その赤字分だけ給与などの他の収入を減らすことができ、節税に繋がるというのがスタンダードな考え方です。
-

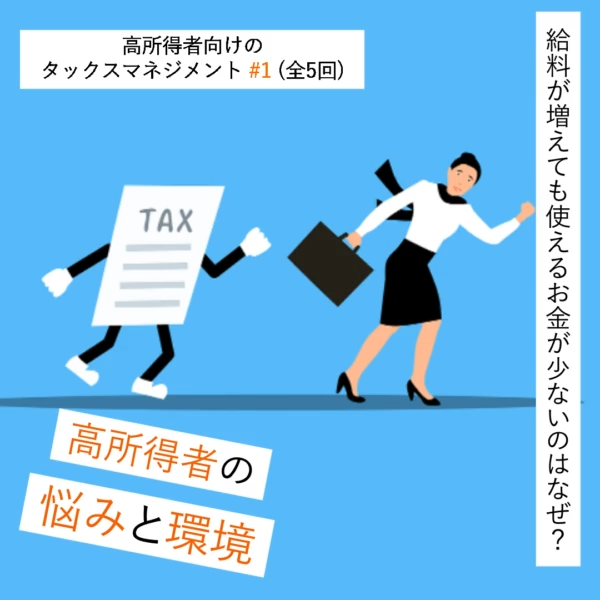
高所得者の悩み・高所得者の取り巻く環境とは
世間では、そもそも低賃金かつ給料が増えないという声が一般的ですが、実際には「高所得者」に分類されるような方でも事情は変わりません。ご相談をお受けして、むしろ、高所得者ほど高度かつ長時間の仕事をしているにも関わらず、状況が厳しくなっていると感じます。これは一体なぜなのでしょうか?
税金・相続 / 固定資産税 記事一覧
全9件-

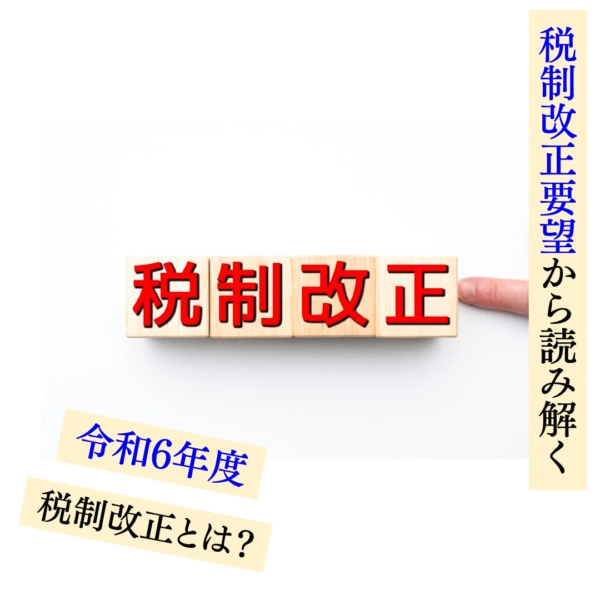
【令和6年度(2024年)税制改正要望から読み解く】今から読み解く税制改正とは!?
国土交通省より、令和6年度の税制改正要望が発表されました。これは年末に公表される政府の税制改正大綱の予測資料となります。今のうちから税制改正要望を紐解くことで、税制改正への準備もできます。 令和6年度の税制改正に備えて、相続・資産承継関連/保有税関連/所得税関連/建替・環境に関することを抜粋してお伝えします。
-


ついに発表!令和5年度、税制改正によって保有税・所得税・相続税はどう変わる?
税制改正大網とは、端的に言えば「税制改正案の試作品・たたき台」のことを言います。政府与党に続き、財務省(政府)で作成された税制改正大網を元に国会で議論され、次年度・・・令和5年度の税制改正が法案として成立・決定・・・翌年令和5年度から施行されるのが基本の流れです。本コラムでは、いよいよ発表された税制改正大網について解説していきます。
-


【試算】マンションの固定資産税はいくら?計算方法や目安、軽減措置
マンションの固定資産税の特例措置、軽減措置を踏まえて具体例を交えて計算方法を解説します。また固定資産税の基本を解説しています。この記事を読むことでご自身の所有物件や購入予定物件の固定資産税の目安が把握できるようになります。
-


空き家の固定資産税は跳ね上がる!?
2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことによって、空き家を放置すると、多額の固定資産税等が課税される可能性があります。
-


土地所有における税金(固定資産税・都市計画税編)
最終更新日:2022年3月16日 はじめに 不動産という資産は、持っているだけ...
-


土地にかかる固定資産税とは?計算方法と税額を軽減させる方法
近年、固定資産税が上がった、下がったというニュースを目にすることも多いと思いますが、急激な税負担を防ぐために「負担水準の均衡化を図る為の負担調整措置」がされています。 とはいってもできればそれ以上に税負担を下げたいと考える方が大半なのではないでしょうか。 土地活用の方法によっては建築費がかかる半面、税金の軽減措置などを利用して上手に負担感を軽減していくことが可能です。 この記事では固定資産税額の算出方法や計算例をふまえて納税義務者の税負担を減らす方法を解説していきます。
-


令和4年度税制改正の住宅に関するところを徹底解説します!
以前、寄港させて頂いたコラム「リスク回避のために!国の方針を読み解けば税制改正を先読みできる!?」(https://www.kentaku.co.jp/estate/navi/column02/post_195.html)では、リスクマネジメントの観点から考え、「そもそも税とは?」という原理原則のお話しから、税制改正の具体的な内容、そして、税制改正の時間的な流れを知り、先読みすることの大切さをお伝えしました。 みなさんから「もう少し、2022年度の税制改正について、教えて欲しい」という要望を多数頂けたということで、ありがとうございます。今回のコラムは、2022年度の税制改正について、賃貸経営の面から見て重要だと思われる具体的な内容や今後の流れについて、もう1歩踏み込んだお話しをさせて頂こうと思います。
-


建物賃貸事業における税金(固定資産税・都市計画税編)
不動産とは、所有しているだけでも維持費が必要です。しかし、税制や特例を理解すれば税金を抑えることができます。 つまりそれだけ、維持費を抑えることができますから、その分だけ収益に繋げていくことも可能です。 今回は、建物賃貸事業を通した固定資産税・都市計画税の基本と各種特例、空家等対策の推進に関する特別措置法についてお伝えします。
-


土地の税金はいくら?|固定資産税の仕組み
不動産を所有していくうえで土地と建物に係る税金として「都市計画税」と「固定資産税」については特に知っておくべきです。納税額、算出方法を解説。
税金・相続 / 相続税 記事一覧
全25件-

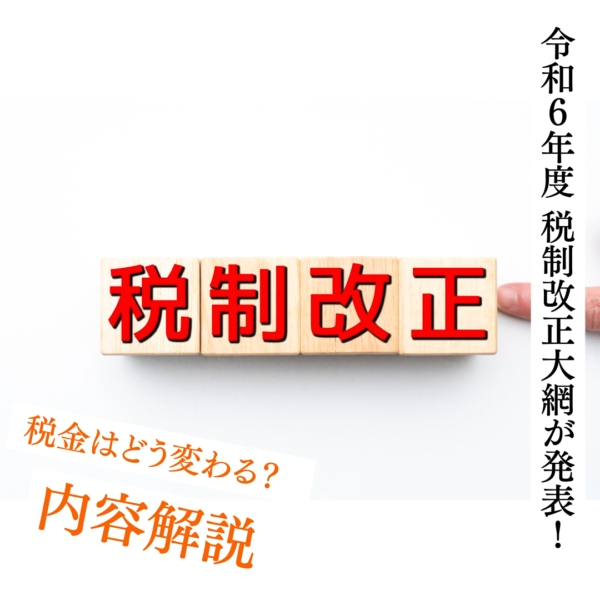
令和6年度(2024年)の税制改正大網が発表! 税金はどう変わる?
【令和6年度(2024年)税制改正要望から読み解く】今から読み解く税制改正とは!? にて内容を予測しましたが、その後の準備具合はいかがですか? 今回は、ついに発表された令和6年度の税制改正大網について解説していきます。
-

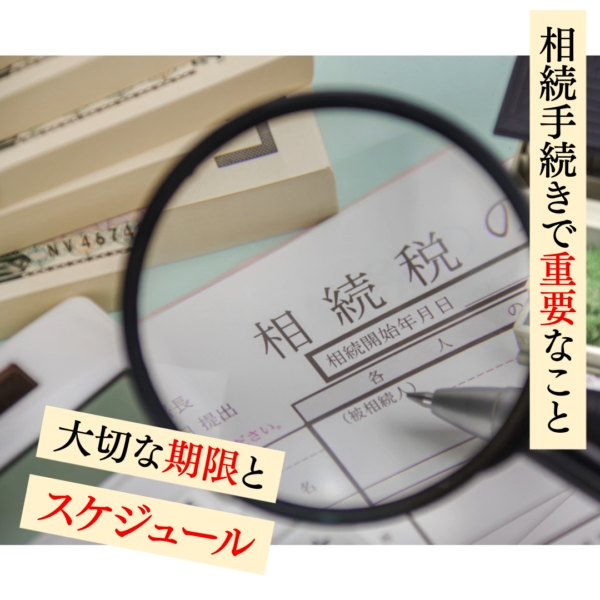
相続手続きには期限がある?大切な資産を引き継ぐために重要なこと
相続が発生した際、期限のある手続きがあります。期限を守らなければ、法的罰則や軽減税制が適用できないなど、経済的な損失が起こる可能性があります。この記事では、相続手続きの種類、期限、注意点などを詳解します。手続き期限の把握を通じて、大切な資産をスムーズに引き継ぐために必要な行動が理解できます。相続手続きに関心がある方は、ぜひ参考にしてください。
-

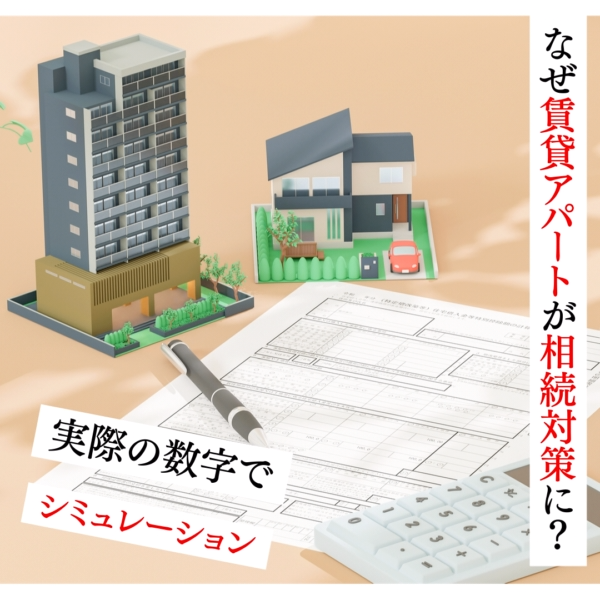
賃貸アパートが相続対策になる理由は?実際の数字でシミュレーション
不動産を相続するとき、ポイントとなるのが相続税です。相続税は相続財産の評価額に応じて税率が大きくなる「累進課税制度」を採用しているため、財産の評価額を抑えたほうが結果的に税金が安くなります。有効な対策の一つにアパート経営があります。そこで本記事では土地の評価額を下げる方法、相続の流れのポイント、数字を用いたシミュレーションを解説します。
-

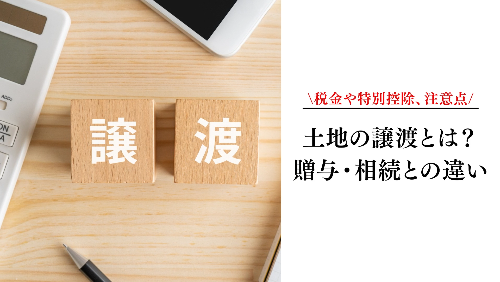
土地の譲渡とは?贈与・相続との違い│税金や特別控除、注意点
土地の譲渡、贈与、相続には明確な違いがあります。3つとも土地を誰かに譲り渡す行為ではありますが、土地や建物等、不動産においてはそれぞれに要件が定められています。また、譲渡、贈与、相続によって適用される税金や特例の種類が異なるため、定義をしっかりと理解しておくことが大切です。そこで本記事では土地の譲渡の定義や贈与・相続との違い、税金や特別控除、注意点について解説します。
-


ついに発表!令和5年度、税制改正によって保有税・所得税・相続税はどう変わる?
税制改正大網とは、端的に言えば「税制改正案の試作品・たたき台」のことを言います。政府与党に続き、財務省(政府)で作成された税制改正大網を元に国会で議論され、次年度・・・令和5年度の税制改正が法案として成立・決定・・・翌年令和5年度から施行されるのが基本の流れです。本コラムでは、いよいよ発表された税制改正大網について解説していきます。
-


相続で遺産の一部を放棄できる?放棄したい時の対処法と生前対策
相続手続きにおいて悩みとなるのが、故人(被相続人)が借金や売れない不動産などのマイナスの遺産を持っていた場合です。相続したくない財産がある場合、一部放棄することは可能なのでしょうか。また、そのメリット・デメリットはどういったものがあるのでしょうか。
-


不動産にかかる贈与税の計算方法は?税負担を軽減できる制度
不動産を贈与した場合にどのような税金がかかるか、基本知識と具体的な計算方法を解説。また相続との違いや相続税精算課税制度など贈与に対するポイントがわかる。
-


賃貸建物における相続税について
今後はいわゆる団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)になり、多くの相続が発生するこ...
-


失敗から学ぶ 早めの相続対策を検討する理由
相続対策には、遺産分割対策、節税対策、納税資金対策の3つがあります。 深く理解しないまま対策をすると節税にならなかったり、家族間でトラブルが生じて家族がバラバラになったりしてしまうケースもあります。 本記事では、相続対策で失敗しないために、相続対策を行うステップについて解説するとともに、相続対策のよくある失敗例をご紹介します。
-


まだ間に合う相続税の還付!広大地を使った相続税の見直しは最後のチャンス
相続税は税金で唯一、申告者によって、納税額が変わってくる税金です。 特に、土地や建物という不動産は、さまざまな評価減の特例が利用できるため、計算の仕方によって、算出する相続税額に大きな差が発生するということも少なくありません。そのため、一定の要件を満たすことで払いすぎた相続税についての還付が受けられる制度があります。本記事では、還付実績が豊富な税理士法人レガシィに「相続税の還付制度」の概要と、還付事例について、解説いただきました。
-


賃貸事業による節税~相続税の計算方法と気を付けること~
平成27年の税法改正により課税対象となる方が増えたため、今まで自分には関係ないと思っていた方からも「相続税」を気にする声をよく聞くようになりました。一方で相続税は、特例の要件を整えたり、建物賃貸事業をしたりすることで節税が可能です。 そこで今回は、相続税の基本と建物賃貸事業による節税の基本、相続税の節税対策検討時の留意点についてお伝えします。
-


よくあるお困り事例から考える! 相続税の納税対策
最終更新日:2022年6月13日 2015年に相続税の基礎控除が縮小されて以降...
-


土地を生前贈与する際の手続きは?かかる費用や節税に使える制度
生前贈与とは、所有者が生きている間に財産を対価なく譲り渡すことを指します。 この記事では、生前贈与の手続きの方法や費用、その税率についてご説明します。 後半では相続対策として活用できる相続時精算課税制度についてもご紹介します。最後までぜひご覧ください。
-


土地にかかる相続税を計算するには?節税に使える控除の例
自分の両親や親族などから不動産相続をする可能性のある方は、相続税の知識をつけることをおすすめします。 資産価値の高い土地や建物の場合、準備や対策をせずに遺産相続すると、相続税が非常に高額になるケースもあるためです。 そこで本記事では相続税額の求め方や計算例、特例適用の条件などを詳しく解説します。
-


土地所有における税金(相続税・贈与税)
最終更新日:2022年7月13日 不動産を所有・運用していると様々な税金が...
-


マンション投資で税金対策ができる仕組みと大切な心構え
最終更新日:2022年7月6日 マンション投資の主な目的として、収益の獲得のほ...
-


相続税の基本の「き」 ~計算方法から基礎控除まで~
相続税は、一括で現金納付するのが原則です。相続発生後10ヵ月以内という納付期限があるので、短期間に多額の現金を用意しなければならないことになります。納税資金を捻出するために、大切な土地を売らなければならないケースも出てきます。課題の発見・対策の検討から、対策の実行により効果を得るまでには長い時間を要します。近年では遺産分割対策にも注目が集まっていますが、まずは、相続税の計算方法を知り、おおよその税額を事前に見積もっておく必要があります。
-


アパート経営で相続に備える!今から始める相続対策
相続対策には賃貸経営(アパート経営・マンション経営)や生命保険の活用などさまざまな手法がありますが、具体的にどうしたらいいのかわからない方も多いようです。そこで、相続対策の具体的な方法などについてご紹介します。
-

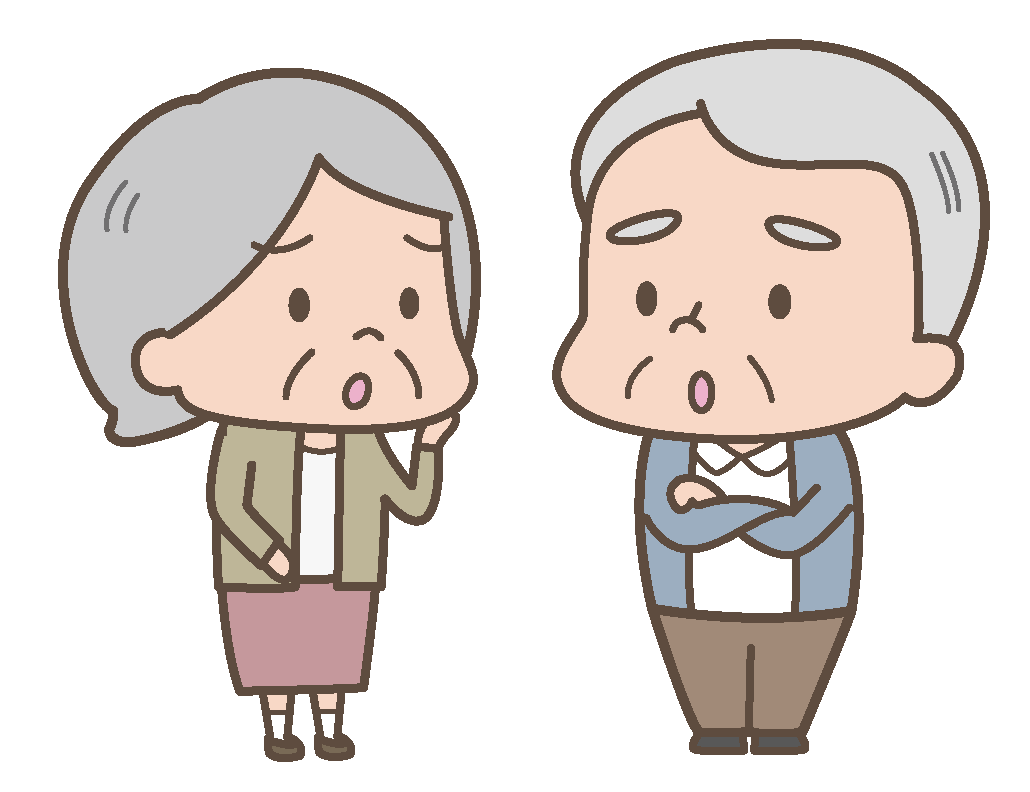
相続税の申告・納税スケジュール
平成27年度の税制改正で、相続税の増税が行われました。 課税対象となる人が増えることで「うちも、相続税を払うことになるのだろうか?」と気になり始めた人も多いのではないでしょうか。 今回は、相続税の仕組みと相続に関するスケジュールについて確認しましょう。
-


相続の基礎知識~相続人と相続財産~
「終活」という言葉や、エンディングノートというものが知られるようになり、 相続対策について気になり始めた人も多いのではないでしょうか? 「相続」に関する知識を得ようとする際、相続税額の計算方法等、具体的な内容 に注目してしまいがちですが、そもそも「相続」の仕組みはどうなっているのか、 まずは基本的なことから確認しましょう。
-


【相続税対策】土地の評価額と相続税の関係を知る
相続税対策のポイントは、相続財産の評価額を減らすこと。土地オーナー様の大半が、...
-


賃貸経営が相続対策に効果的な理由
相続税対策には、賃貸経営が有効だという話をよく耳にしないでしょうか。しかし、実際...
-

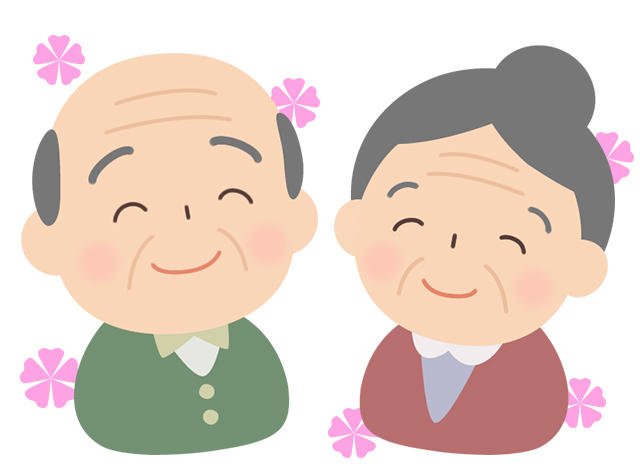
安心な老後生活のための資金準備の秘訣
公開日:2018.01.17 老後の生活にはどのくらいお金が必要なのだろうかと漠...
-


借地権の相続に関する基本知識
借地権が設定された土地でも、借りた土地の上に自己所有の建物を建てることができます...
-


資産を受け継ぐあなたへ① 相続税法改正と土地活用
親が持っている土地の相続について話し合ったことはあるでしょうか?いざその時が来たときに大変な思いをするかもしれません。もし、将来あなたに相続される土地があるのであれば、相続後にどんなことが起こるのか話し合っておきましょう。
税金・相続 / 所得税 記事一覧
全32件-

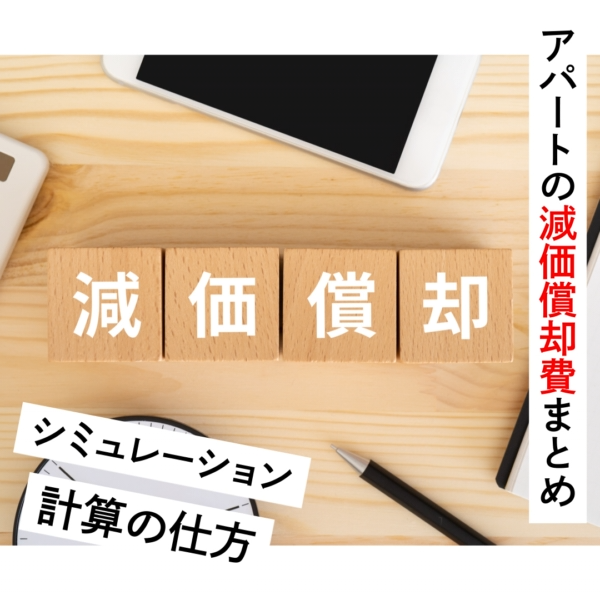
アパートの減価償却費まとめ|シミュレーションから見る計算の仕方
アパート経営を始めるうえで知っておくべき知識の一つに、減価償却があります。減価償却とは建物などの固定資産の購入費を、使用期間に応じて分割計上する会計処理のことで、上手く活用すれば所得税などの税金負担を軽減できます。そこで本記事ではアパートの減価償却費の計算について、実際のシミュレーションを用いながら詳しく解説します。
-

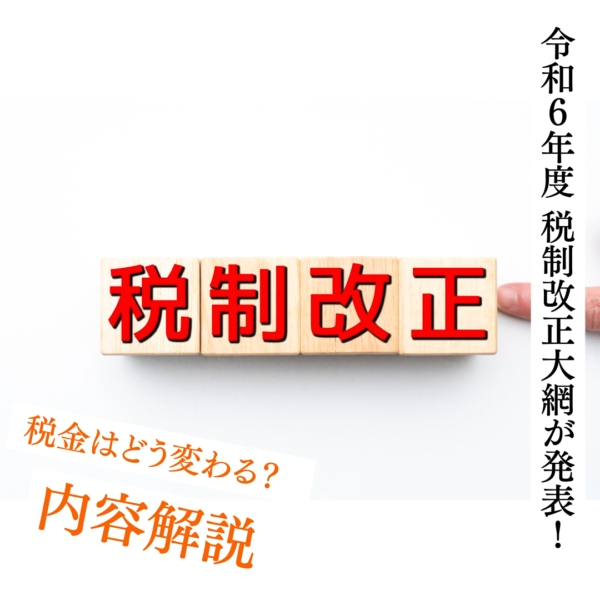
令和6年度(2024年)の税制改正大網が発表! 税金はどう変わる?
【令和6年度(2024年)税制改正要望から読み解く】今から読み解く税制改正とは!? にて内容を予測しましたが、その後の準備具合はいかがですか? 今回は、ついに発表された令和6年度の税制改正大網について解説していきます。
-

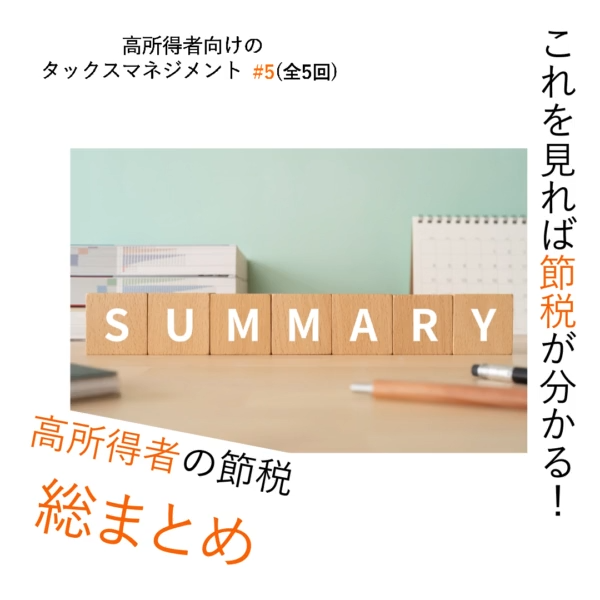
高所得者向けのタックスマネジメント ~総まとめ~
高所得者にも関わらず手取り額が少なくなるのは「税金(と社会保険料)」が原因です。税金は国民全員が一律ではなく、高所得者ほどに税額が高くなる「超過累進税率」という制度になっています。その結果、少しくらい年収が高くなってもほとんど手取り額が変わらなくなっているのです。超過累進税率を採用した日本の所得税の税率は、以下のようになっています。
-

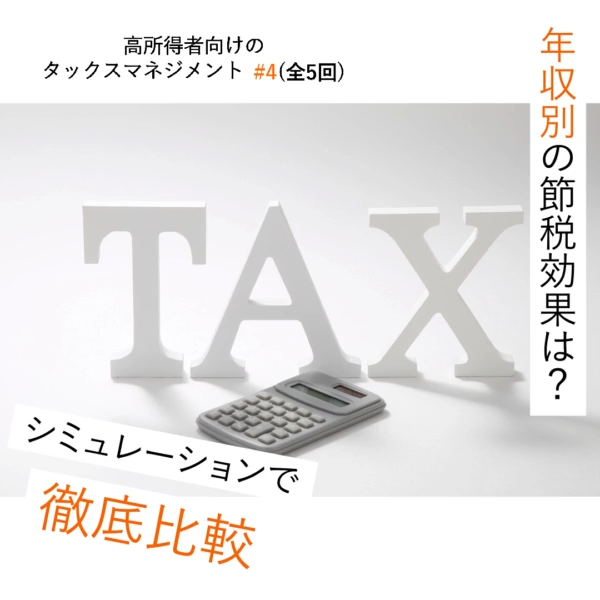
年収別の節税効果をシミュレーション比較
今回は、「築25年の(中古の)木造賃貸物件」を購入したという前提でシミュレーションしましょう。木造の賃貸物件の減価償却期間(法定耐用年数)は22年ですが、上記のように購入時点で減価償却が終了している場合は、「法定耐用年数の20%の期間(1年未満切り捨て、最短2年)」を減価償却期間とすることが可能です。
-

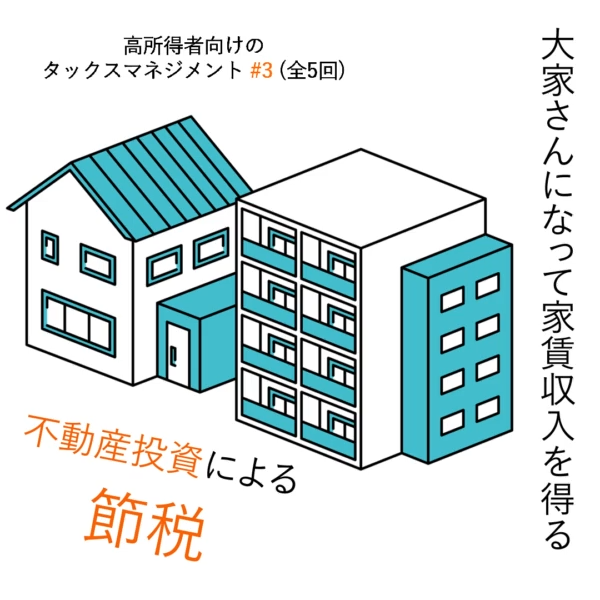
不動産投資を活用した節税
不動産投資とは「大家さんになること」が必要です。土地に賃貸建物を建てて人に貸し、家賃収入を得ます。そして、この賃貸経営において「計算上の赤字」を出すことで、その赤字分だけ給与などの他の収入を減らすことができ、節税に繋がるというのがスタンダードな考え方です。
-

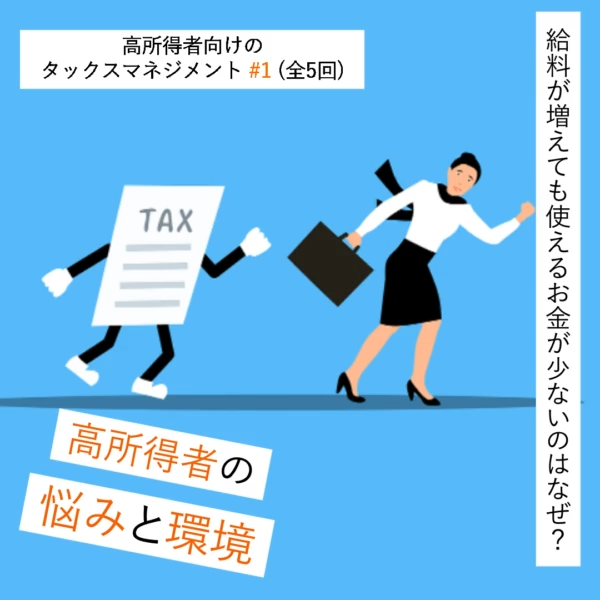
高所得者の悩み・高所得者の取り巻く環境とは
世間では、そもそも低賃金かつ給料が増えないという声が一般的ですが、実際には「高所得者」に分類されるような方でも事情は変わりません。ご相談をお受けして、むしろ、高所得者ほど高度かつ長時間の仕事をしているにも関わらず、状況が厳しくなっていると感じます。これは一体なぜなのでしょうか?
-

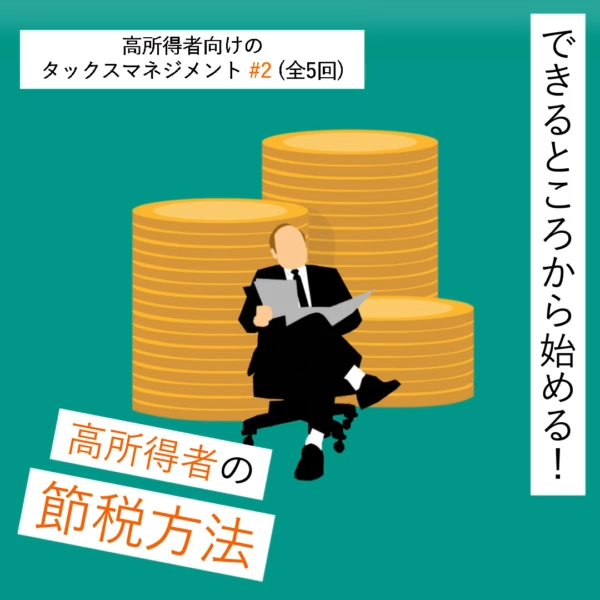
高所得者の節税(タックスマネジメント)について
節税対策の方法はいくつかあります。ご自身が目指す投資効率を目標に、できるところから始めてみましょう。最終的にはご自身に合ったいくつかの適法な方法を組み合わせて実行し、節税効果の最大化を目指すことが大切です。この感覚を元に、一つずつ見ていきましょう。
-

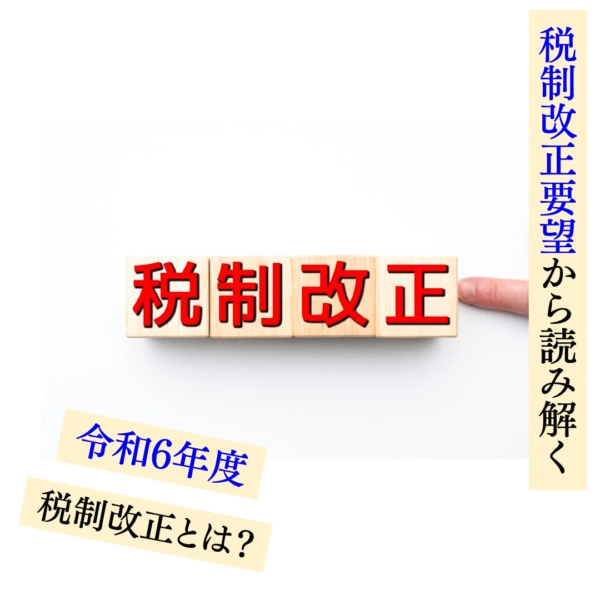
【令和6年度(2024年)税制改正要望から読み解く】今から読み解く税制改正とは!?
国土交通省より、令和6年度の税制改正要望が発表されました。これは年末に公表される政府の税制改正大綱の予測資料となります。今のうちから税制改正要望を紐解くことで、税制改正への準備もできます。 令和6年度の税制改正に備えて、相続・資産承継関連/保有税関連/所得税関連/建替・環境に関することを抜粋してお伝えします。
-

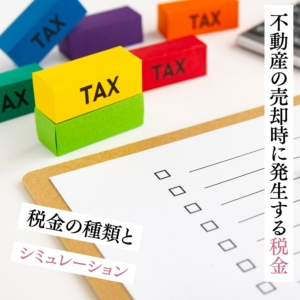
土地を売ると税金がかかる?実際の金額を使ったシミュレーション
建物や土地等の不動産は、売却時に諸費用が発生します。中でも、税金は金額も大きいことからどの程度かかるか確認しておきたいところです。 この記事では、売却費用の中でも特に税金にスポットをあて、説明します。
-

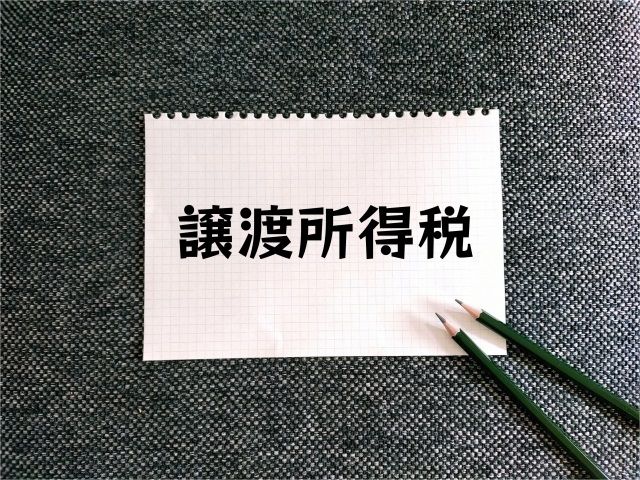
短期譲渡所得とは?長期譲渡所得との違いや適用される特別控除の例
土地や建物を売却する際は、所有期間に注意が必要です。 売却時の税金計算の基礎となる所得は所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられ、短期譲渡の方が税率が高いからです。この記事では短期譲渡所得の概要や長期譲渡所得との違い、税金の計算時に適用できる特別控除などについて解説します。不動産売却のタイミングを見極めることなどで節税につながるよう、ぜひ参考にしてください。
-


不労所得にかかる税金と計算方法│いくらから確定申告は必要?
世界的な物価上昇や老後の年金問題などの影響でお金への不安が高まる中、不労所得への注目が集まっており、実際に投資や資産運用を始める方も増えています。 しかし、不労所得にも一定の税金が課せられるため、税率や計算方法などを理解して、収入に対して税金の負担はどの程度になるのか、事前にシミュレーションしておくことが大切です。 そこで本記事では不労所得の種類や税金の計算方法について解説します。
-

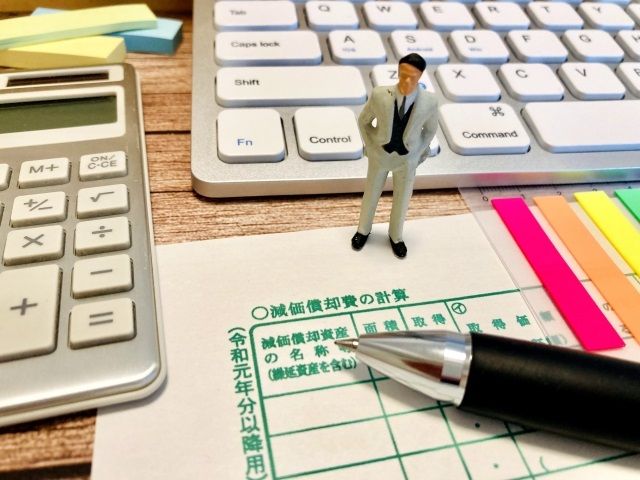
建物の減価償却とは?耐用年数と計算方法【算出シミュレーション】
賃貸経営などの事業用不動産を所有する不動産オーナーにとって、減価償却費は押さえておきたい費用です。減価償却費とは、不動産所得に対する所得税を節税する効果があります。このコラムでは、そんな減価償却費に関する基礎知識や計算方法、定額法と定率法の違いなどについて説明します。
-


土地売却で確定申告は必要?無申告のペナルティ、必要な書類と書き方
家屋や土地を売却した後、必要となるのが確定申告です。確定申告はその年にあった所得を税務署へ申告し、所得税・住民税を決定するものです。そこで今回は、土地売却における確定申告についてご説明します。基礎知識から具体的な手順まで詳細に説明しますので、ご一読ください。
-


ついに発表!令和5年度、税制改正によって保有税・所得税・相続税はどう変わる?
税制改正大網とは、端的に言えば「税制改正案の試作品・たたき台」のことを言います。政府与党に続き、財務省(政府)で作成された税制改正大網を元に国会で議論され、次年度・・・令和5年度の税制改正が法案として成立・決定・・・翌年令和5年度から施行されるのが基本の流れです。本コラムでは、いよいよ発表された税制改正大網について解説していきます。
-

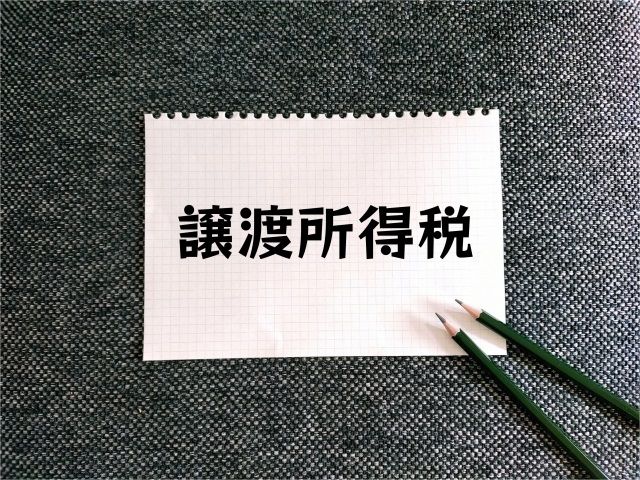
譲渡所得の特別控除とは?不動産投資で使える控除の種類と概要
資産を売却して譲渡所得を得た場合、その所得に対して所得税や住民税が課税されます。土地や建物などの不動産売却時には大きな利益を得ることも多いため、その分、税金も高くなりがちです。しかし譲渡所得にはさまざまな特別控除があり、制度を有効活用すれば税金の負担も軽減できるので、事前に種類や適用条件などを確認することが重要です。
-


土地所有における税金(所得税・住民税・法人税・事業税)
不動産を所有・運用していると様々な税金がかかります。不動産運用は大きく分けると...
-


今からでも間に合う、アパート経営一年目の確定申告丸わかり
アパート経営を始めると、その翌年には確定申告をする必要があります。 中には、確定申告は、アパート経営で利益が出たときだけすればよいと考えている方もいらっしゃるでしょう。もちろん、法律的にはその理解で問題ありませんが、実はアパート経営においては毎年きちんと確定申告をしたほうがよいのです。 ここでは、アパート経営一年目の確定申告において知っておくべきポイントについて紹介します。
-


不動産投資の還付金とは?確定申告による所得税・消費税の還付
個人の確定申告といえば、面倒な手続きをしなければならないと思いがちです。しかし、確定申告をすることで還付金が戻ってくることがあります。不動産所得や消費税の還付金とは。
-

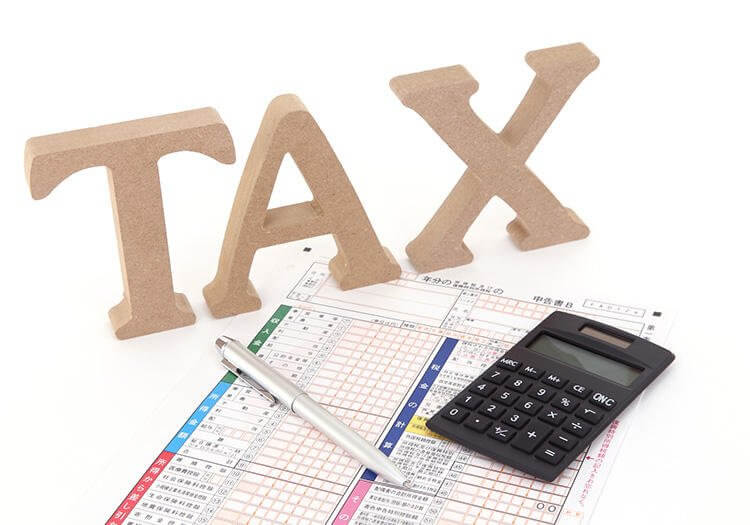
【2022年版】確定申告について徹底解説! コロナ禍対応の給付金は課税・非課税どっち?
土地オーナーの方は、家賃収入や地代収入などで不動産所得が発生すると、確定申告をし...
-


土地活用関連の令和3年度税制改正について解説!コロナ禍への対応は?
< { "@context": "http://sch...
-

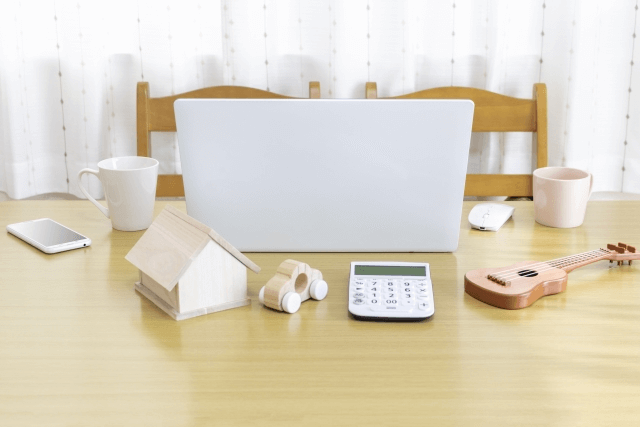
経営者・個人事業主の方におすすめ。小規模企業共済とは
最終更新日:2022年3月17日 昨今では年金2,000万円問題やさまざまな税...
-


不動産投資における減価償却とは?実施するメリットと計算方法
減価償却とは固定資産の取得費用を法定耐用年数に応じて配分し、その年に相当する分の金額を経費計上することです。適用できるのは年数経過によって資産価値が低下する資産です。
-


不動産投資に確定申告は必須?手続きの流れと経費計上できる項目の例
{ "@context": "http://schema.o...
-


建物賃貸事業のキホン~所得税対策編~
相応の資産を持つ方向けに、建物賃貸事業経営が節税になる話はよくあります。 一方でその仕組みや方法などについて、イマイチ分かりにくいという声が多いのも事実です。 そこで今回は、テーマを所得税に絞り、建物賃貸事業経営を通した節税の基本や損益通算、法人化などについて幅広くお伝えします。
-


マンション投資で税金対策ができる仕組みと大切な心構え
最終更新日:2022年7月6日 マンション投資の主な目的として、収益の獲得のほ...
-

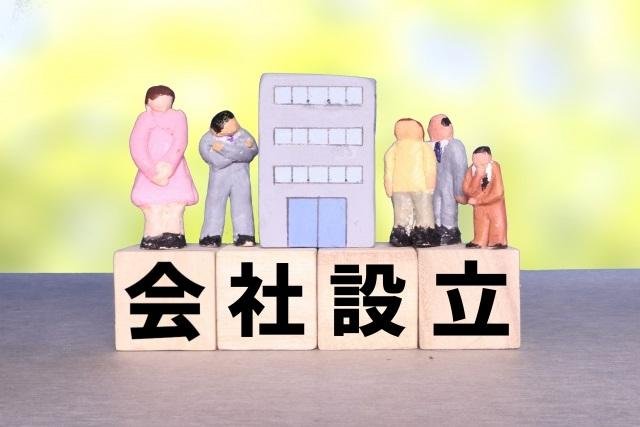
法人化の種類とメリット~なぜ税金対策になるか?~
不動産賃貸業をおこなっている方もしくはお考えになっている方の中には所得税対策に法人化が良いという話を聞いたことがある人は少なくないのではないでしょうか。 このコラムでは不動産賃貸業における法人化の方法とメリットや手順を説明します。
-


不動産投資の法人化から手続き終了後までの手順|法人化する基準は?
当初は個人事業主として不動産投資を行っていた方も、不動産所得が増加したことをきっかけに法人化するケースがあります。 事業規模、所得が大きくなると法人化した方が節税効果が期待できるためです。 しかしながら法人化するタイミングやリスク、手続きや注意点がわからずに不安を感じている人も多いのではないでしょうか。 この記事では、不動産投資における法人化のタイミングやポイント、法人化するための手順を解説していきます。
-


不動産所得のある大家さんの確定申告の種類と方法は?
不動産の経営によって家賃収入を得た場合は、確定申告が必要になる場合があります。...
-


不動産所得に消費税はかかる?~個人事業主の確定申告~
不動産投資は賃貸物件の入居者から得られる家賃収入により利益を上げるビジネスです。不動産投資は税法上では「不動産所得」に該当するため、確定申告をする必要があります。の確定申告について紹介しました。今回は個人事業主として賃貸経営をしている大家さんへ向けて、事業的規模や、青色申告を利用することで受けられる特典などを中心に、確定申告の知識紹介します。
-


減価償却とは?節税に役立つ知識を解説
全ての資産が減価償却の対象となるわけではありません。建築物や部屋附帯の設備など時の経過とともにその価値が下がっていくようなものが減価償却できます。
-


青色申告のメリット/青色申告できる人できない人~不動産所得に関わる確定申告~
2023年(令和5年)の確定申告期間は、2月16日(木)から3月15日(水)までです。 この期間中に2022年(令和4年)の1年間(1月1日~12月31日)に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告・納税する手続きを確定申告と言います。 家賃収入のある大家さんはこの申告期間内に年一回の確定申告をする必要があります。その際、「青色申告」を行えばさまざまな「特典」を受けられる可能性があり、大きく節税できるかもしれません。今回のコラムでは、「青色申告」の申請条件から、必要な書類まで詳しく解説します。確定申告の前にぜひチェックしてください。
-


不動産投資の経費まとめ|認められるものと認められないものは?
不動産投資は安定した家賃収入が得られるメリットがある一方、修繕費、管理費などさ...
税金・相続 / 資産承継 記事一覧
全31件-


実家は相続して住む?それとも売却する?考えられる選択肢と判断基準
少子高齢化が進む中、親の実家を将来どのように活用すべきか、悩んでいる方も多いでしょう。 相続して住む方法もありますが、自分の住居を別に所有している場合は、「売却する」「賃貸に出す」などの方法を考える必要があります。そこで本記事では、実家を相続した方や相続する可能性のある方に向けて、考えられる選択肢や判断基準、特定空き家の基準について解説します。
-


農地を相続放棄することはできる?手続きの流れと相続した際の使い道
遺産相続において問題となりやすいのが、田んぼなどの使う予定のない不動産を相続する場合です。農地等は農業従事者以外は利用しづらく、相続税や固定資産税の納税が負担になりがちです。 今回は、農地を例に使う予定のない不動産の処分方法として、相続放棄を詳しく説明します。処分の流れや手続き方法について、ポイントを絞って解説しますので、最後までチェックしてみてください。
-


知ろう!家族信託。備えよう!認知症。
家族信託に関してメリットやデメリット、後見制度などと比較しながらどのようなことができるのか解説しています。
-


【無料プレゼント】ご家族で考えておきたい「ご所有地の今後の活用方法」
この度、ご所有地に最適な土地活用方法がわかる『無料土地診断(エリアマーケティングレポート)」とあわせて、『資産承継を考える!スターターセット』のプレゼント企画を実施しています! 最新の市場環境を把握し、将来の適切な活用方法について、ご家族内で検討しておくことが、結果的に円満・円滑な資産承継につながります。
-


相続で遺産の一部を放棄できる?放棄したい時の対処法と生前対策
相続手続きにおいて悩みとなるのが、故人(被相続人)が借金や売れない不動産などのマイナスの遺産を持っていた場合です。相続したくない財産がある場合、一部放棄することは可能なのでしょうか。また、そのメリット・デメリットはどういったものがあるのでしょうか。
-


不動産にかかる贈与税の計算方法は?税負担を軽減できる制度
不動産を贈与した場合にどのような税金がかかるか、基本知識と具体的な計算方法を解説。また相続との違いや相続税精算課税制度など贈与に対するポイントがわかる。
-

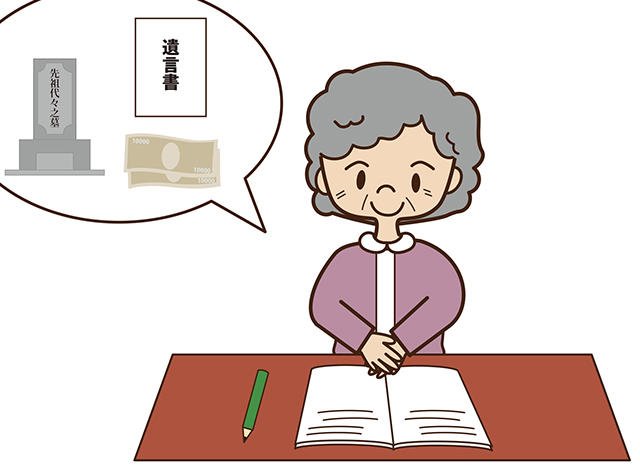
相続を円滑に進める「遺言書」の書き方
最近相続にまつわる家庭裁判所への相談件数と遺産分割事件(家事調停・審判)の件数は年々増加傾向にあります。 2009年の13,505件と比較すると2018年は15,706件1と約16%の増加が見られます。(裁判所 統計情報)特に、分割が難しい財産とされる不動産が相続財産金額全体の約4割強2を占めており、遺産分割に関する相続トラブルが生じることも少なくありません。円満・円滑な資産承継をおこなうに、「遺言」という方法があります。今回のコラムでは、遺言書の書き方について整理していきたいと思います。
-


新たな資産承継対策「家族信託」のメリットや流れを解説
資産を円満円滑に引き継ぐための、代表的な方法のひとつに遺言があります。以前は長男...
-


資産を受け継ぐあなたへ① 相続と新たな土地活用
2015年の相続税法の改正以降、相続税の基礎控除枠は減額され、税率も変更になりました。これまでは相続税を支払う必要のなかった人も課税対象となるケースが増えました。 皆さまは親が持っている土地の相続について話し合ったことはあるでしょうか?いざその時が来たときに大変な思いをするかもしれません。もし、将来あなたに相続される予定の土地があるのであれば、相続後にどんなことが起こる見込みがあるのか、どんな対策が必要になるのか、ご家族で話し合っておきましょう。
-


資産を受け継ぐあなたへ② アパート経営、相続したらどうする?
親が元気なうちにアパートなどの資産をどうするのか、今のうちからご家族みんなで話し合っておくことが大切です。 本記事では、アパートなどの不動産資産を相続する予定がある方に向けて、今からできる将来の経営改善に向けた指標やチェックポイントをお伝えします。
-


2019年税制改正要綱、不動産関連の税金変更点まとめ
2019年10月、消費税率8%から10%に引き上げられることが予定されています。 前回の消費増税では、増税後の買い控えが発生しました。その反省を踏まえ、2018年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱では、消費の冷え込みを防ぐために、税制措置を行うことが予定されています。 そこで今回は、税制改正で不動産関連の税金がどのように変更されるかについて、変更前と変更後を比較していきます。
-


得なの?手続きは?みんなが集まる時期だから話しておきたい生前贈与
通常保有している資産額によっては、相続時に高額な相続税がかかる場合もあります。そのため、相続よりも前に財産を譲る「生前贈与」を検討している人もいるでしょう。というのも、生前贈与をすることで、相続時に発生する税金を抑えられる可能性があるからです。そこでこの記事では、生前贈与に関しての概要や生前贈与の種類・仕組み、および注意点などを詳しく解説していきます。
-


令和2年の税制改正、土地活用関連で知っておくべき内容は?
土地活用では、事業として収益を得るとともに、いかに節税するかも大切なポイントの1つです。令和2年(2020年)には、30万円未満の減価償却資産に関する特例をはじめとした、各種住宅税制に関する特例の延長や、相続・空き家問題に関する対策がなされます。また、平成30年(2018年)に民法改正によって施行される「配偶者居住権」なども知っておく必要があるでしょう。本記事では令和2年の税制改正や税に関する変更点から、土地オーナーやアパート・マンションのオーナーに関連する内容を解説します。
-

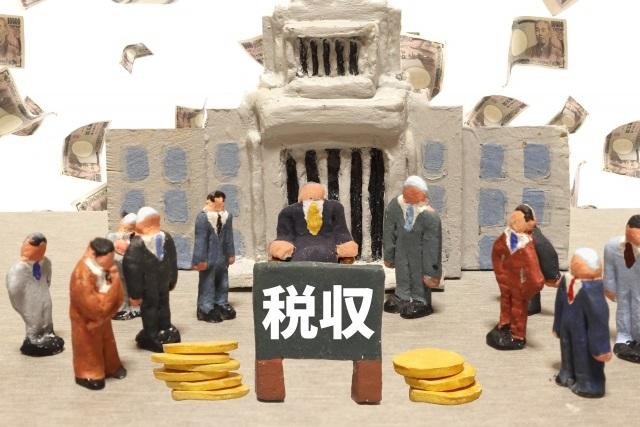
リスク回避のために!国の方針を読み解けば税制改正を先読みできる!?
今回は「税制」へのリスク対応について、考えていきましょう。 毎年12月中旬になると、来年度の税制改正が大きなニュースとなります。前回の「自然災害へのリスク対応」と違い、人為的な事柄のため、ある程度の未来予測が成り立つのがこの「税制へのリスク対応」となります。どのように対応(保有・移転・損失制御)していくのか?というのを解説します。
-


土地の相続の流れとは?名義変更の登記手続きと税金について
最終更新日:2022年3月3日土地や建物を所有している方は、将来自分の子供への...
-


これで円満承継!『争族』を回避するコツ
最終更新日:2022年3月18日相続対策には、3つあります。納税額を適正な方法...
-

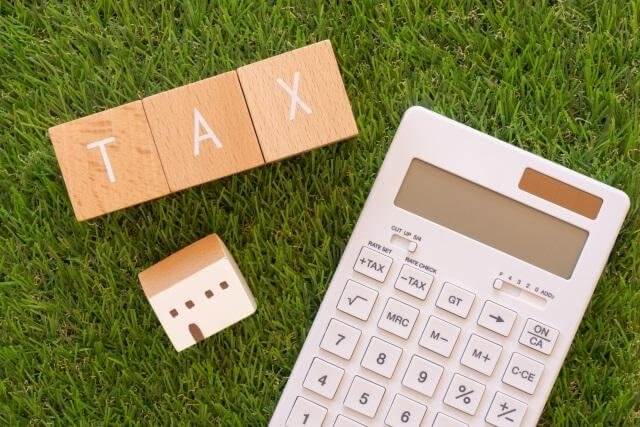
不動産投資にかかる税金の種類は?発生するタイミングと節税の効果
不動産投資はインフレ対策として有効ですが、物件の購入時、運用時、売却時にさまざまな税金がかかります。特に運用時にかかる税金は、毎年発生、長期に渡る負担になります。
-


土地にかかわる税金について(不動産取得税・登録免許税・印紙税編)
最終更新日:2022年4月4日 はじめに 不動産を購入・取得する時には、さまざ...
-


『円満』な資産承継を考える際の注意点。トラブル事例と承継までの流れ
最終更新日:2022年6月15日 最高裁判所「司法統計」によると、「相続関係の...
-


不要な土地は相続放棄できる?放棄するまでの手続きや注意点
遺産相続が発生した場合、相続人が相続放棄するためには、「相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければなりません。 いざという時のために判断できるよう、ポイントを押さえておくことが重要です。 本記事では、相続放棄の概要や具体的な手続き、注意点について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
-


令和5年度税制改正要望から読み解く『今から備える税制改正』とは!?
令和4年8月、国土交通省から令和5年度の「税制改正要望事項」が発表されました。ちなみに税制改正要望事項とは、各省庁や業界団体・税理士会などが、財務省または総務省に、毎年8月頃に提出する「税金ルールに関する要望」をまとめたものになります。 税制改正の影響を直接的に受けやすい事業者にとっては、極めて気になる内容のはずです。そこで今回は、この税制改正要望事項の中から、特に大家さんに関係しそうな重要な部分をピックアップしてお伝えします。
-

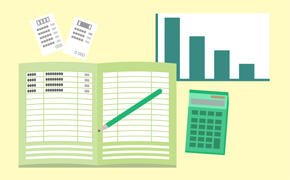
土地活用の前に知っておきたい土地にかかる税金
土地には常に税金が関係してきます。どのような税金が課せられ、それに対してどのよう...
-

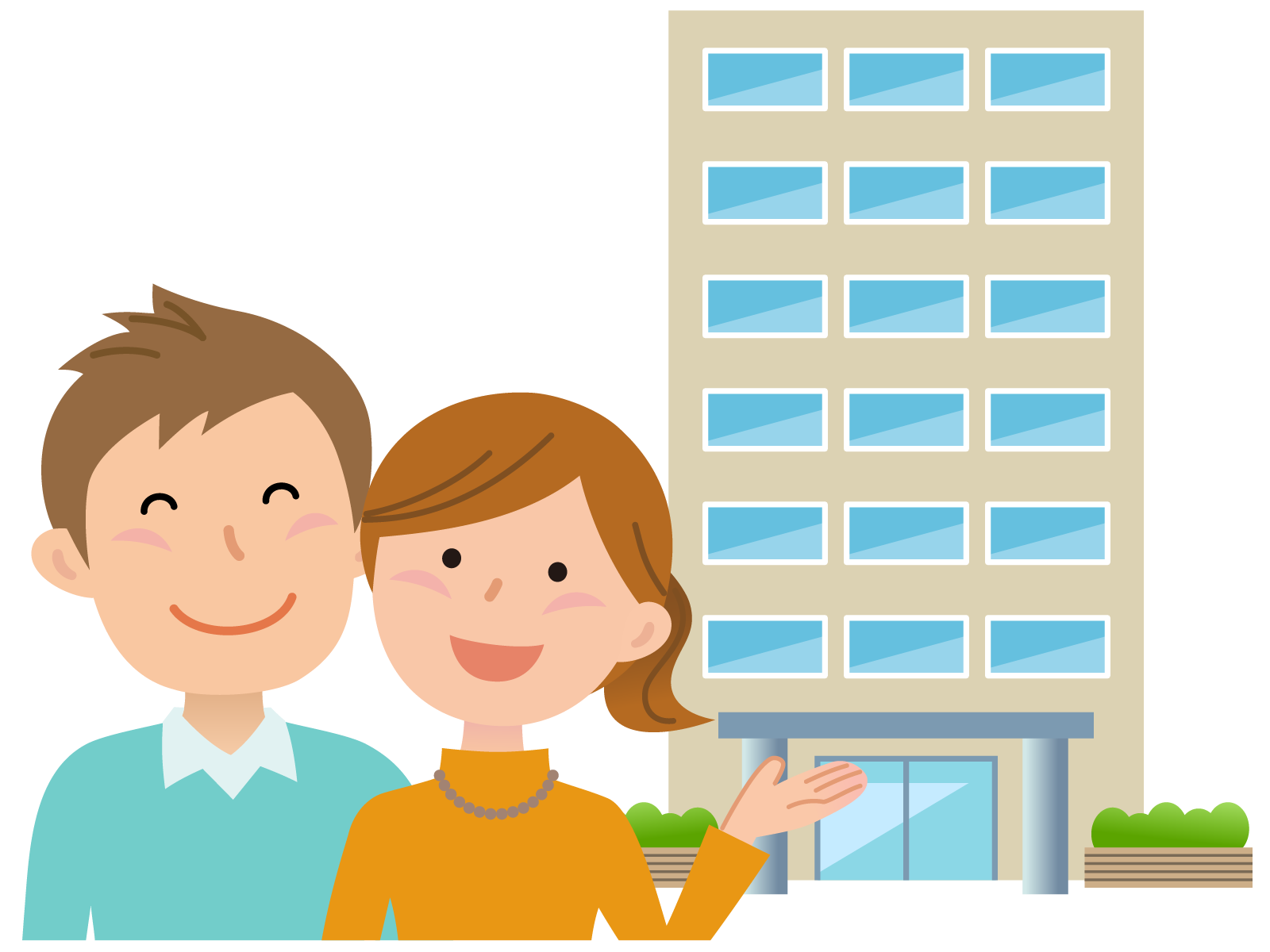
不動産の取得・保有・売却でかかる税金
土地や建物といった不動産には、取得時、保有期間中、売却時、贈与時や相続時など、さまざまなタイミングで税金が発生します。 土地活用を行っている方は税務処理や節税について税理士などの専門家のサポートを受けている方も多いですが、土地活用の検討を始める場合には、自身でこれらの税金について基本的な知識は持っておきましょう。
-


相続の基礎知識~相続人と相続財産~
「終活」という言葉や、エンディングノートというものが知られるようになり、 相続対策について気になり始めた人も多いのではないでしょうか? 「相続」に関する知識を得ようとする際、相続税額の計算方法等、具体的な内容 に注目してしまいがちですが、そもそも「相続」の仕組みはどうなっているのか、 まずは基本的なことから確認しましょう。
-


アパート・賃貸経営の法人化とその方法|節税対策や相続対策にも!
アパート経営やマンション経営は、個人事業主としてスタートする場合が多いですが、事業規模や売上が大きくなると、節税の観点から法人化を考えるオーナーも多くなります。
-


生前贈与で相続対策
平成27年1月施行の改正相続税法により相続税額の算出方法が見直されたことで、相続財産から差し引かれる基礎控除額が縮小されました。相続税の課税対象者になったり、あるいは課税額が増加した方が全国的に増えたことから、円満円滑な資産承継手法として、生前贈与が注目されています。
-

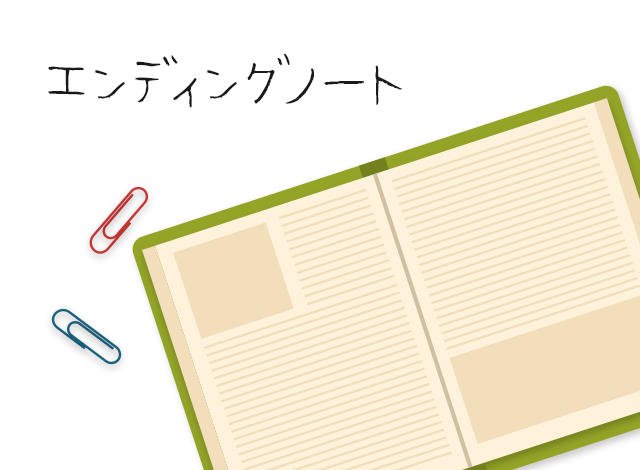
上手な資産承継の第一歩!エンディングノートの書き方とは?/無料プレゼントあり
最近、「エンディングノート」という言葉をよく見聞きにするようになりました。 エンディングノートとは、これまでの自身の歩みを振り返り、人生をより充実したものにするために、今後どのように暮らしていくかを考え、整理するためのノートのことです。実はこの「エンディングノート」、どのように資産を次世代に引き継ぐかを検討している土地オーナーにとっては、心強いツールとなり得るのです。今回のコラムでは、エンディングノートとその活用方法についてご紹介します。
-

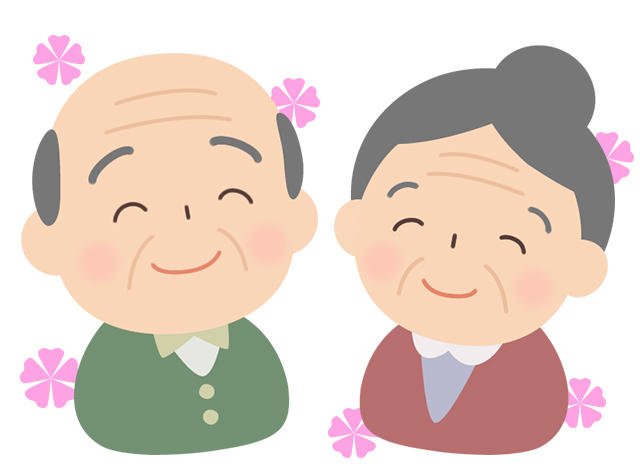
安心な老後生活のための資金準備の秘訣
公開日:2018.01.17 老後の生活にはどのくらいお金が必要なのだろうかと漠...
-


借地権の相続に関する基本知識
借地権が設定された土地でも、借りた土地の上に自己所有の建物を建てることができます...
-


資産を受け継ぐあなたへ① 相続税法改正と土地活用
親が持っている土地の相続について話し合ったことはあるでしょうか?いざその時が来たときに大変な思いをするかもしれません。もし、将来あなたに相続される土地があるのであれば、相続後にどんなことが起こるのか話し合っておきましょう。
-

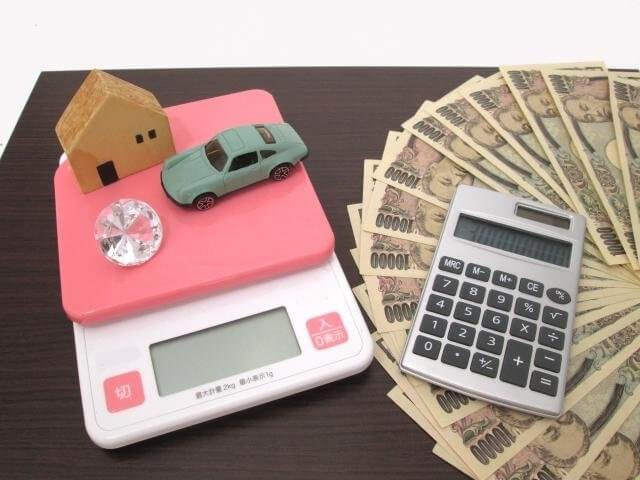
節税・納税・分割~資産承継3つの対策~
はじめに ご自身でこれまでしっかりと築き上げてこられた資産。預貯金、有価証券、...
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング









