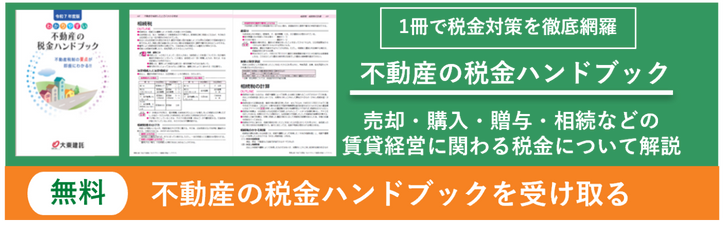不動産にかかる贈与税の計算方法は?税負担を軽減できる制度
公開日: 2022.11.21
最終更新日: 2025.10.27
土地や不動産などの贈与時に発生するのが贈与税です。
高額な資産ほど、贈与にするか相続にするか悩む人も多いのではないでしょうか。
一般的に相続税は基礎控除額が大きいため、相続税のほうが節税対策になると思うかもしれません。
ただ、贈与税でも一定の条件を満たせば、非課税枠の利用ができます。
この記事では、贈与と相続の違い、贈与税の計算方法、贈与税の非課税制度について説明します。
大切な資産を守るためにも贈与税の仕組みを理解しましょう。
目次
1-1.生前贈与する財産に課せられる税金のこと
1-2.贈与と相続の違い
1-3.贈与税が課せられる対象
4-1.相続時精算課税制度とは
4-2.不動産の贈与で相続時精算課税制度を利用するメリット
1.贈与税とは
ここでは贈与と相続の違い、贈与税が課せられる対象について説明します。
1-1.生前贈与する財産に課せられる税金のこと
生前贈与とは、贈与者(渡す人)が生きている間に、受贈者(受け取る人)に無償で財産を渡すことです。贈与は一般的には親子間、配偶者間、祖父母から孫などで、お金を直接渡すケースも少なくありません。
相続トラブルを避けたい、受贈者の相続税負担を減らしたいなどの理由で行われることも多いです。個人間の贈与で贈与税は発生しますが、個人が法人に贈与する場合は贈与税ではなく所得税となります。
1-2.贈与と相続の違い
贈与は贈与者(渡す人)が生きている間に、無償で受贈者(受け取る人)に財産を渡すことです。一方、相続は所有者が亡くなってから、相続人に引き継がれます。財産を生きている間に贈与するか、亡くなってから相続するかで税金が変わります。
贈与税の基礎控除は110万円で、1年ごとに利用可能です。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人です。それぞれ基礎控除後の課税価格に対し税率を掛けます。
基礎控除額が高い相続の方が、節税対策になると思うかもしれません。要件を満たさないといけませんが、あとで説明する相続時精算課税制度を選択すれば、贈与でも特別控除を利用できます 。
1-3.贈与税が課せられる対象
贈与の対象になる財産は、金銭、有価証券や貴金属、不動産などがあります。物件や土地などをプレゼントすると、受贈者に対して贈与税が課せられます。
税額が大きくなるケースもあるため、贈与税の対象について理解しておく必要があるでしょう。
以下は、思わぬ贈与税がかかってしまった一例です。
- 本来の不動産の価値が3,000万円なのに300万円で売却したような、本来の価値より大幅な差額がある場合
- 借金の返済や住宅ローンの支払いを肩代わりした場合(金銭を渡したとみなされる)
- 生命保険の保険料を払っていない者が保険金を受け取った場合
2.不動産にかかる贈与税を求める方法
贈与税の求め方は「一般贈与財産の税率」「特例贈与財産の税率」または「併用」のいずれかになります。求め方のシミュレーションも行っていますので、参考にしてください。
2-1.不動産の価額を求める
贈与でも相続でも不動産の価額を算出しないといけません。原則、時価を使用します。現金1億円だとそのまま1億円が時価になりますが、不動産の場合は不動産売却額や購入額ではなく、土地や建物の「相続税評価額」となります。
土地の相続税評価額は、路線価が定められている場合は「路線価方式」となり、路線価が定められていなければ「倍率方式」で求められます。どちらに該当するかは国税庁のホームページで確認ができます。
建物(家屋)の場合は固定資産税評価額から求められます。毎年送付される固定資産税課税明細書、もしくは市区町村が所有している固定資産課税台帳で確認できます。
マンションの場合は、土地と区分所有する建物のそれぞれの相続税評価額の合計で算出可能です。
3.贈与税の税率を求める
贈与税の税率には「一般贈与財産の税率」と「特例贈与財産の税率」の2種類があります。それぞれ順を追って説明します。
【一般贈与財産の税率(一般税率)】
第三者間や夫婦、兄弟、親から未成年の子への贈与は「一般贈与財産の税率」が適用されます。
|
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
〜200万円以下 |
10% |
なし |
|
200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
|
300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
|
500万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
|
600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
|
1,000万円超〜1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
|
1,500万円超〜3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
|
3,000万円超〜 |
55% |
400万円 |
【特例贈与財産の税率(特別税率)】
直系尊属である親から成人の子、祖父母から成人の孫への贈与は「特例贈与財産の税率」が適用となります。
|
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
〜200万円以下 |
10% |
なし |
|
200万円超〜400万円以下 |
15% |
10万円 |
|
400万円超〜600万円以下 |
20% |
30万円 |
|
600万円超〜1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
|
1,000万円超〜1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
|
1,500万円超〜3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
|
3,000万円超〜4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
|
4,500万円超〜 |
55% |
640万円 |
3-1.計算式に当てはめて贈与税額を算出する
贈与税の額は「(不動産の価格 − 基礎控除額)× 税率 - 控除額」で求められます。
不動産の価格は1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた合計額となり、基礎控除額は一律110万円です。
以下は不動産の価格が2,000万円の場合の「一般贈与財産の税率」と「特例贈与財産の税率」の計算例です。
【一般贈与財産の税率】
2,000万円 - 110万円 = 1,890万円
1,890万円 × 50% =945万円
945万円 - 250万円 =695万円
不動産の価額2,000万円の場合、695万円が贈与税額となります。
【特例贈与財産の税率】
2,000万円 - 110万円 = 1,890万円
1,890万円 × 45% =850.5万円
850.5万円 - 265万円 =585.5万円
不動産の価額2,000万円の場合、585.5万円が贈与税額となります。
【一般贈与財産の税率と特例贈与財産の税率を併用する】
18歳以上で第三者から(一般税率)と、祖父から贈与されたとき(特例税率)に使用します。それぞれ1,000万円贈与されたときの計算方法です。
まずは2つを加算すると合計2,000万円となり、そこから割合に応じて計算します。
- 一般税率
2,000万円 - 110万円 =1,890万円
1,890万円 × 50% =945万円
945万円 - 250万円 =695万円
割合に応じて算出します。
695万円×1,000万円/2,000万円 = 347.5万円①
- 特例税率
2,000万円 - 110万円 =1,890万円
1,890万円 × 45% =850.5万円
850.5万円 - 265万円 =585.5万円
割合に応じて算出します。
585.5万円×1,000万円/2,000万円 = 292.75万円②
①347.5万円と②292.75万円の合計 640.25万円が併用時の贈与税額となります。
【出典】「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(国税庁)
4.不動産を贈与する際に有効な「相続時精算課税制度」
高額になる不動産を贈与する場合に有効である相続時精算課税制度。メリットや注意点について説明します。
4-1.相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子もしくは孫に対し贈与が行われた場合に活用できる制度です。2,500万円までであれば、贈与税の特別控除が適用され、非課税となります。
複数回に渡って贈与しても累積で2,500万円に達するまで何度でも利用できます。
2,500万円を超すと一律20%の贈与税が課税されますが、不動産などの金額の大きな財産に利用したい制度です。
この制度を選択する場合、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに必要書類を添付し、贈与税の申告書を提出する必要があります。
4-2.不動産の贈与で相続時精算課税制度を利用するメリット
- 大型の特別控除が受けられる
従来の暦年課税制度では、基礎控除は最大110万円までとなり、高額になる不動産ではあまり恩恵がありません。相続時精算課税制度を利用すれば最大2,500万円の控除が受けられます。
- 不動産の価値が上昇する前に贈与できる
不動産を贈与または相続する場合、不動産の評価額をもとに税額を求めます。土地の場合、駅前開発などで土地の評価額が上昇するケースもあり、贈与した時点での評価額で計算されます。
相続時精算課税制度を利用すれば、土地の値段が上がる前に贈与ができるため、税金を抑えることも可能です。
4-3.不動産の贈与で相続時精算課税制度を利用する際の注意点
- 相続税が課せられる
贈与財産であっても相続税の負担がなくならないのがデメリットです。相続時精算課税制度で2,500万円控除されましたが、相続時にはその2,500万円の控除は受けられず、場合によっては加算となり、相続税を支払う必要があります。納税の先送りと言われており、相続税対策にはなりません。
- 暦年課税の控除が適用されなくなる
暦年課税とは年間110万円までの非課税枠が利用できる制度です。相続時精算課税制度と暦年課税は併用できません。
本年に相続時精算課税制度を選択すると、その年から暦年課税は利用できなくなります。
一度、相続時精算課税制度を選択すると変更もできません。長い期間を視野に入れて、有利不利を判定しましょう。
- 小規模宅地等の特例が利用できない
小規模宅地等の特例とは、ある一定の条件を満たせば居住用の宅地や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
不動産の種類によっては相続税の負担を大きく減らすことが可能で、小規模宅地等の特例を利用したほうが税負担を小さくできるケースもあります。
小規模宅地等の特例の一定条件に当てはまるか、また相続時精算課税制度を選択したほうがいいのか、比較する際は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
5.税負担が軽減できるかは早めに専門家に相談しましょう
不動産評価額の計算や申告の手続きが複雑になる贈与では、自分で調べようとしても時間がかかってしまうケースもあります。
調べている間に相続しか選べなくなると後悔するかもしれません。
税負担が軽減できるかは、早めに専門家にアドバイスをもらいましょう。
また事前に弁護士に相談することで、相続トラブルも避けられます。
無料相談もありますので、お気軽に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
■執筆者プロフィール
税理士法人みらいサクセスパートナーズ・代表
宮川真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上。
現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っている。
また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事。
【保有資格】 税理士、CFP®
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング