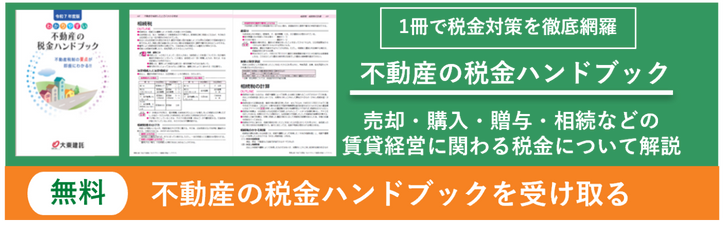空き家の固定資産税はいつ6倍に上がる?法改正に伴う影響
公開日: 2022.10.28
最終更新日: 2026.01.27
2023年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。この法律では空き家を管理が行き届いていない状態で放置することに対する罰則規定が設けられており、対象となった土地は固定資産税等が多額になる可能性があります。そのような事態を回避するためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか。今回はこの法律について、改正の影響を詳しくご紹介します。

この記事のポイント
- 市町村長から「特定空家等」の判断を受けた場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって多額の固定資産税が課税される
- 「特定空家等」に認定された場合、「住宅用地の特例措置」は非適用となり、課税額が大きく跳ね上がる
- 「特定空家等」に認定されないようにするには、常日頃からしっかりとした管理が重要
1. 空き家と「空家等対策の推進に関する特別措置法」
令和5年の住宅・土地統計調査によると全国の空き家は900万戸にのぼり、その数は年々増加しています。もし、管理が不十分な空き家が増加すると、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景観面での悪化等多岐にわたる問題を発生させる可能性が高まります。
そこで、その対策として2015年に施行されたのが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。その規定に基づいて、市町村長が「特定空家等」の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合には、固定資産税等の住宅用地の特例措置の対象から当該「特定空家等」にかかわる敷地を除外できるようになりました。つまり、空き家を放置すると、多額の固定資産税が課税される可能性があるということです。
2.「特定空家」と「管理不全空家」の定義とは?
令和5年に空き家対策特別措置法が改正され、従来から存在した「特定空家等」に加え、新たに「管理不全空家」が認定の対象となりました。この改正により、自治体は放置された空き家に対してより早い段階で指導や勧告を行うことが可能となり、固定資産税額の軽減措置が解除されるケースが増えることが予想されます。これにより、所有者の税負担が増加することが懸念されています。
2-1.特定空家とは
「特定空家」とは、適切な管理が行われず、周辺環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家のことを指します。例えば、1年以上誰も住んでおらず、管理や手入れがほとんどされていない家が対象です。こうした家は、更地にするための解体費用が高額になる場合があり、解体を検討する際には自治体への相談が必要となります。
2-2.特定空家の定義
空き家が「特定空家」と認定されるかどうかは、その状態と周囲への影響の両面から判断されます。
以下のような状態に該当すると、自治体から是正措置の対象となる可能性があります。
- 放置すれば倒壊などの危険がある場合(建物の安全性に問題がある)
- 放置すると衛生上の問題が生じる可能性がある場合(害虫や悪臭など)
- 適切な管理が行われておらず、景観を著しく損なっている場合
- 近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすと判断される場合
特定空家に認定されると、指導や勧告を受けるだけでなく、最終的には行政代執行による強制的な解体が行われる可能性もあります。また、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、課税標準が引き上げられることになるため、税額負担が増加する点も注意が必要です。
2-3.「管理不全空家」とは
「管理不全空家」とは、1年以上誰も住んでおらず、管理が十分に行われていない空き家 を指します。このような状態の家は、今後「特定空家」に指定される可能性があるため、早急な対応が求められます。
2-4.「管理不全空家」の定義
「管理不全空家」は「特定空家」よりも広範な空き家が該当する可能性があり、以下のような状態の家を指します。
- 建物の安全性が疑われる(倒壊の危険がある)
- 環境や衛生面で問題が生じている(ごみの放置、害虫の発生など)
- 地域の不動産価格やコミュニティに悪影響を及ぼす可能性がある
- 空き家を放置することで、犯罪リスクが高まる(不法侵入や放火のリスク)
このような空き家は、所有者にとって資産価値の低下を招くだけでなく、周囲の住民にも大きな影響を与えます。「特定空家」と同様税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性もあるため、賃貸や売却などの活用方法を早めに検討することが重要です。
【出典】法令検索 「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号) 」(定義)第二条2
【出典】国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」P3
3. 空き家の税金(固定資産税)はいつから6倍に跳ね上がる?
土地に対する固定資産税や都市計画税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。これは、「固定資産税等の住宅用地特例」と呼ばれているものです。
| 固定資産税 | |
|---|---|
| 空き地(更地) | 課税標準額 × 1.4% |
|
小規模住宅用地 200㎡以下の部分 |
課税標準額 × 1/6 × 1.4% |
|
一般住宅用地 200㎡を超える部分 |
課税標準額 × 1/3 × 1.4% |
※「住宅用地の特例措置」は固定資産税と都市計画税に対して適用されますが、ここでは固定資産税の特例措置について紹介します。
具体的には、小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートル以下の部分)に当たる場合に、固定資産税の課税標準額(課税される金額)が6分の1となり、一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分)においても、課税標準額が3分の1となります。
しかし、「特定空家等」と「管理不全空家等」に指定された場合は、指定された翌年からこの特例が適用できなくなります。
例えば、住宅用地180㎡で築50年の木造2階建ての場合を見てみましょう。

上記事例で試算すると、小規模住宅用地に該当するときは固定資産税標準額の6分の1に軽減できますが、「特定空家等」と「管理不全空家等」に認定された場合は満額の16.8万円が固定資産税額となります。なお、固定資産税の課税額に反映されるのは次の年の1月1日です。もし勧告を受けても、年内までに空き家の状態を改善すれば固定資産税の支払額は増えないので、早めに対策を講じましょう。
4. 固定資産税等の「住宅用地特例」を維持するために
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行される前は、空き家を所有していても、解体するには費用がかかるなどの理由から、自然に朽ちるまで放置をしていたとしても固定資産税の「住宅用地の特例措置」の適用が維持されているケースが多くみられました。
しかし、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されている現在、 対策を講じておかなければ「特定空家」と認定され、「住宅用地の特例措置」の適用維持ができなくなってしまう可能性があります。
では、どのような対策を講じておけばよいのでしょうか。 対策にはさまざまなものが考えられますが、 重要なのは、「特定空家等」と認定されないようにしっかりとした管理を行うということです。 いくつか管理例を紹介します。
管理例1:別荘(自己使用)として管理
たまに使う自分用の別荘として利用、管理するというのも一つの方法です。しかし、所有している空き家が遠方にあるなどの理由から、自分で利用することが難しい場合もあります。その場合、固定資産税評価額や都市計画税を考慮しながら維持管理をする必要があります。
管理例2:賃貸物件(建物活用)として管理
整備をしたうえで賃貸物件として活用すれば空き家に認定されることを回避できるうえ、賃貸収入を得ることもできます。空き家だった物件を賃貸として貸すメリットとして、相続人への資産承継時の相続税対策や、毎年の固定資産税額の軽減措置を受けられる可能性があります。どのような準備がいるかという点では、建物の標準額や課税標準を把握し、適正な賃料設定を行うことが重要です。
関連記事:賃貸経営で戸建てを選ぶメリットとデメリットは?注目される理由
管理例3:賃貸物件(土地活用)として管理
空き家を解体して青空駐車場など別の方法で土地活用する方法もあります。ただし、駐車場の場合、固定資産税の住宅用地の特例適用を維持することはできません。固定資産税の増加分をカバーするだけの収益を上げることができるかどうか、シミュレーションが必要です。駐車場経営をするメリットとして、定期的な収入を得ることができ、一般住宅用地よりも柔軟な運用が可能です。
駐車場の種類にはコインパーキングと月極駐車場があり、最適な方法を選択するにはそれぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが欠かせません。
駐車場以外の土地活用方法については、不動産売却のほか、トランクルームや貸し農園などの活用事例もあります。
管理例4:管理の委託を行う
さまざまな企業で月1回の定期清掃や郵便物の回収など、サービスは色々ですが、空き家の管理を行っている会社もあります。そのような企業に空き家の管理をお願いすることもできます。
空き家管理サービスがやってくれるのは、敷地内の除草や害虫駆除、建物の安全確認、助言の提供などです。
室内の目視確認、部屋の換気、水道管の通水、電気設備の動作確認など、定期的なメンテナンスを行うことで、建物の評価額を維持できます。
管理が難しい場合は?
そもそも、費用等の面で管理が難しい場合は、売却をするという方法も一案です。売却はまとまった現金を比較的すぐに得たいときの選択肢となり、税負担の軽減にもつながります。維持管理費などのランニングコストもかからなくなるため、負担を減らせます。土地を売却して得た利益に対しては譲渡所得税がかかるため、計算方法を把握しておくことが重要です。
一度手放してしまうと再び取り戻すのは困難なため、条件やタイミングをよく検討する必要があります。売却が難しい場合、不動産会社と相談し、賃貸や管理委託の可能性も考えるとよいでしょう。
5. 固定資産税が増えないよう、空き家の有効活用を検討しよう。
空き家問題は、固定資産税や都市計画税の負担増加、解体費用の発生など、所有者にとって大きな経済的影響をもたらします。特定空家や管理不全空家に指定される前に、活用方法を検討し、適切な管理を行うことが求められます。不動産会社や自治体に相談することで、最適な対策を講じることができるでしょう。
大東建託では、不動産に関する無料の診断サービスを提供しています。ご所有地の資産価値・賃貸需要シミュレーションや、ライフプラン診断、相続に対する資産診断、賃料相場や入居率のシミュレーションなど、幅広い診断が可能です。お気軽にお問い合わせください。
参考
「税金・相続」関連用語集
- 青色申告
- 青色事業専従者
- 確定申告
- 私的年金
- 固定資産税
- 節税対策
- 相続税
- 不動産取得税
- 任意後見制度
- 定期借地権
- 年末調整
- 印紙税
- 贈与税
- 所得控除
- 登録免許税
- 都市計画税
- 住宅取得控除
- 借地権
- 遺言書
- 成年後見制度
最新コラムの更新情報以外にも、少しでも皆様のお役に立つ
資産継承や賃貸経営に関するホットな情報をお届けします。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング