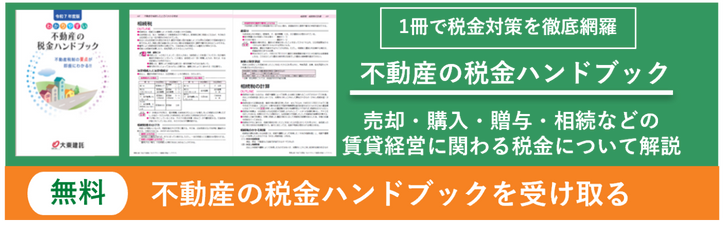賃貸経営が相続対策に効果的な理由
公開日: 2022.10.28
最終更新日: 2025.10.23
相続税対策には、賃貸経営が有効だという話をよく耳にしないでしょうか。
しかし、実際に「なぜ節税になるか」「いくら節税になるか」「どのように対策するのか」というような詳しい仕組みや効果を理解しようと思っても少し複雑です。
不動産のように評価額が大きい財産を相続する場合、相続税対策をするか否かで納付すべき相続税額が大きく変わります。今回は、アパート経営・マンション経営が相続税対策に効果的である理由を解説します。
>>関連記事:マンション経営の種類|それぞれのメリット・デメリットは?

この記事のポイント
- 2015年の税制改正によって相続税の基礎控除額が減額、相続税額・課税対象者が増加
- 相続税の節税対策のポイントは相続財産の評価額を下げること
- 賃貸経営は相続財産の評価額を減額できる
- 賃貸経営は信頼できる建築会社や専門家へ相談することが大切
税制改正によって、実質的な増税へ
2015年1月の税制改正により相続税の基礎控除が引き下げられ、実質的な「増税」となりました。
・改正前の基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
・改正後の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
このように、基礎控除の金額が少なくなり、課税対象が増加。
財産の評価額が3,000万円を超えると相続税が発生する可能性が出てきます。
また、改正前には6段階だった税率も、8段階となりました。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ーー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
1億円を超えると、その相続税率は40%となり、3億円を超えたら50%にものぼることになります。
ですので、しっかり相続税の節税対策をしておかないと、せっかくの財産が目減りするばかりです。
それを防ぐための節税手段として有効なのがアパート経営やマンション経営なのです。
相続税の節税対策のポイントは財産の評価額を下げること
相続税は累進課税ですので評価額が大きくなるほど税率が高くなります。つまり、相続税対策のポイントは対象となる財産の相続税評価額を低くすることと言えます。
預貯金などの現金はそのまま評価されますが、土地や建物などの不動産は、実勢価格ではなく路線価を基準に評価額を算出しますので現金よりも不動産の方が評価額が低くなるのが一般的です。また、その不動産の利用方法も評価額を左右します。
したがって、預貯金などの現金では節税が難しくても、不動産なら利用方法次第で節税が可能となるのです。
そしてもう一つ、マイナスの財産である借入金があると、課税評価額はその分だけ評価額から差し引かれます。
たとえば、3億円の評価額に対して3億円の借入金があれば評価額はゼロとみなされます。
土地や建物など不動産の節税ポイントの概要を以下に列挙します。
※適用要件などの詳細については、税理士にご確認ください。
節税ポイントその1:貸家建付地
土地、建物はその用途によって評価額が変わります。とりわけ、貸家建付地は大幅な減額が見込めます。
貸家建付地の要件は、自分の土地に自分の所有する賃貸物件を建て、他人に継続的に貸していることです。
そのため、相続前に貸家建付地になっていなければなりません。
つまり賃貸住宅経営は被相続人の生前から行う相続税対策なのです。
・貸家建付地評価額の計算方法
自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
※「借地権割合」及び「借家権割合」は地域により異なります
借地権割合70%、借家権割合30%の地域で土地の評価額が1億円のケース
1億円×(1-0.7×0.3×1)=7900万円
1億円の預貯金だと評価額はそのままの1億円ですが、賃貸用の土地であれば路線価評価額が1億円でも評価額は7,900万円になるのです。
であれば、現金で残すより賃貸物件にしておいた方が節税になるということになります。節税ポイントその2 :小規模宅地等の特例
節税ポイントその2 :小規模宅地等の特例
貸貸家建付地の他にも「小規模宅地等の特例」が利用できます。貸家建付地と合わせて評価額の減額が可能です。賃貸事業で活用している土地の場合、減額対象になる面積の上限は200㎡で減額率は50%です。200㎡を超える土地は対象外ということではなく、仮に500㎡の土地であれば200㎡までの範囲は50%減額されます。
※ 小規模宅地の特例は相続時に選択ができます。
※「特定居住用宅地等に該当する宅地等」の特例を利用できる場合など、限度面積の範囲内で最も有利な特例の選択や、併用での適用を検討します。
「ただし、この特例を受けるためには、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が貸付事業をしていた宅地であることに加え、以下の要件をいずれも満たさなければなりません。
①事業継続要件
被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、貸付事業を申告期限まで継続すること(被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が貸付事業をしていた宅地である場合には、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。)
②保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有すること
節税ポイントその3: 建物も評価額が減額
建物については建築費の50~70%が固定資産税評価になるので、仮に賃貸アパートの建築価格が1億円であれば評価額は5,000万円~7,000万円程度になります。相続する建物が賃貸用であれば、更に評価額が減額されます。
賃貸用の建物における評価額の計算式
自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
※借家権割合は30%、賃貸割合は満室を100%として空室があると低下します。/サブリースをした場合は入居率100%と計算できるので賃貸割合100%となります。
建物の評価額
6,000万円×(1-0.3×1)=4200万円
もし1億円の預貯金であれば評価額はそのままですが、建物であれば概ね6,000万円になります。そしてそれを賃貸物件にすれば評価額が概ね4,200万円になるので、結果として5,800万円も評価減することができるのです。
節税ポイントその4:金融機関からの借り入れ
金融機関から融資を受けて建物賃貸事業を行う場合、債務控除が適用されます。その場合、借入額が遺産額から減額されるので更に節税になります。とはいえ、いくら節税のためとはいっても、現金を使用しても同様の効果が得られますし、無謀な借金は禁物です。
借り入れが多くなれば、それだけ金利負担が大きくなり賃貸事業の収益を圧迫することになります。
賃貸経営は信頼できる建築会社や専門家へ相談することが大切
今回は、賃貸経営が相続税の節税対策に有効な理由をご紹介しました。
マンション・アパート建築のメリットはご理解いただけたでしょうか。
税金知識を正しく知ることで節税効果を得ることができます。
相続税の節税対策でアパート経営やマンション経営を行う目的は、価値のある財産を良い形で次世代に引き継ぐことです。
しかし、一時的に節税ができたとしても長きにわたる賃貸事業が安定経営できなければ、かえって次世代に負担をかけることにもなりかねません。
賃貸経営のデメリットや注意点、リスクも正しく理解をして対応することが重要になります。
また本記事でご紹介したもの以外にも生前贈与や相続税精算課税制度や配偶者控除の上手な考え方がありますが、
詳しくはさまざまなノウハウと実績を持っている専門家の意見を聞き、信頼できる「パートナー」を選択することを心掛けましょう。
「土地活用」関連用語集
- 不動産所得
- 路線価
- 土地活用
- 容積率
- 用途地域
- 債務不履行
- 元利均等返済
- 収益還元法
- 住宅金融支援機構
- 住宅ローン
- サービス付き高齢者住宅
- 賃貸併用住宅
- 基準地価
- 等価交換
- 地上権
- 貸宅地
- 貸家建付地
- 元金均等返済
- 公示地価
- 土地貸し
最新コラムの更新情報以外にも、少しでも皆様のお役に立つ
資産承継や賃貸経営に関するホットな情報をお届けします。
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング