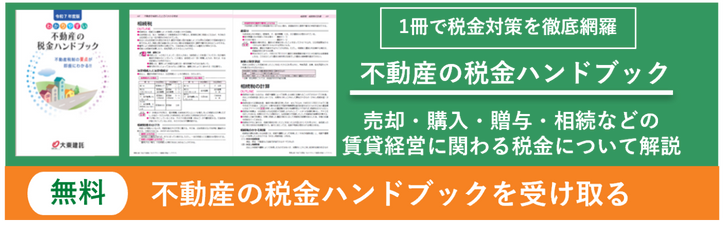不動産投資における減価償却とは?実施するメリットと計算方法
公開日: 2022.10.28
最終更新日: 2025.10.27
不動産投資で節税を図るためには、減価償却を活用する方法が有効です。
しかし、そのためには物件の用途や種類ごとに定められている減価償却期間を把握する必要があります。
また、減価償却を活用した損益通算の計算方法を理解することも重要です。
本記事で詳しく解説するので、節税を主な目的として不動産投資を始める方は、ぜひ参考にしてください。
不動産投資における減価償却と法定耐用年数とは
初めに不動産投資における減価償却の基本的な内容と、物件の用途や種類ごとに定められた法定耐用年数の解説をします。減価償却を上手に活用すれば、高い節税効果が見込めるため理解を深めておきましょう。
減価償却とは
減価償却とは固定資産の取得費用を法定耐用年数に応じて配分して、その年に相当する分の金額を経費計上することです。
減価償却が適用できるのは年数の経過によって資産価値が低下する資産であり、対象となる資産を「減価償却資産」といいます。
不動産の場合、建物部分のほかに、付属する設備も減価償却資産の対象となりますが、土地部分は年数が経過しても資産価値が低下しないため対象外です。
なお、減価償却期間の開始時期は、所有者がその資産を使用し始めた時からとするのが基本となっています。
法定耐用年数とは
法定耐用年数とは固定資産の資産価値が消滅するまでの期間を定めた年数のことです。
国税庁によって定められた期間であり、正確に税金を徴収することを目的にした年数であるため、実際に居住できる期間とは異なります。
アパートやマンションなどの住宅用建物の場合、法定耐用年数は建物の構造によって以下のように定められています。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 金属(鉄骨)造 ※(骨格材の厚み4mm超) | 34年 |
| 金属(鉄骨)造 ※(骨格材の厚み3mm超、4mm以下) | 27年 |
| 金属(鉄骨)造 ※(骨格材の厚み3mm以下) | 19年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)・鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
減価償却と法定耐用年数の考え方
法定耐用年数とは建物を利用できる限界の年数ではなく、あくまで減価償却の計算に使うための指標です。
そのため、実際の使用可能期間とは異なり、法定耐用年数を過ぎたとしても、建物が即座に利用できなくなるわけではありません。
また、よほど劣化していなければ、法定耐用年数を超過したことにより、建物の価値が急落する可能性も低いと考えられています。
では、節税効果という観点で考えた場合、減価償却期間が長い建物と短い建物では、どちらが望ましいのでしょうか。
この点に関しては、減価償却を長期的に実施する場合、短期的に実施する場合、それぞれにメリットとデメリットがあるため、どちらが優れているかとは一概に決められません。
減価償却費は定額法の場合「物件の購入価格×定額法の償却率」によって求められますが、償却率の数値は耐用年数が長いほど低くなります。
※定額法の償却率の数値は「減価償却資産の償却率等表」より確認できます。
したがって、減価償却期間が長い建物(新築物件など)では、長期間の節税が見込めますが、単年での節税効果は低くなります。
一方、減価償却期間が短い建物(中古物件など)では、節税が見込める年数は短期間になりますが、単年での節税効果が高く、早期の資金回収が期待できます。
適切な減価償却期間は、物件の運用方法や運用年数、オーナー自身の価値観などによって左右されるため、それぞれの特徴をよく理解したうえで、望ましい建物構造や、新築・中古どちらにすべきかなどの選択をするようにしましょう。
不動産投資で減価償却費を経費計上するメリットと注意点
不動産投資で減価償却費を経費計上することによる主なメリットを紹介します。
また、減価償却を行う際の注意点も解説していきます。
減価償却を行うメリット
減価償却を行えば、アパート経営やマンション投資で得た利益にかかる税金を節税できる場合があります。
具体的には減価償却の計上により発生した帳簿上のマイナス分を、オーナー自身の所得から差し引く損益通算を行うことで節税を図れます。
実際に減価償却費を経費計上する場合は、投資用不動産の購入時の金額を耐用年数に合わせて経費を処理します。
減価償却を行った際の例
建物価格が8,000万円の鉄骨造(骨格材の厚み3mm超、4mm以下)の中古マンションで賃貸経営を行い、オーナーの給与所得が900万円、家賃収入300万円だった場合の例を考えてみましょう。
減価償却費は定額法で行うものとした場合、購入費用を法定耐用年数で割った数値になるため、以下の計算の通りです。
減価償却費:8,000万円(建物価格)÷27年(法定耐用年数)≒296万円
※ここではわかりやすくする為、1万円未満の端数は四捨五入しています。
このうえで必要経費を家賃収入の15%程度(45万円)かかったと仮定した場合、不動産収入の合計は以下の通りです。
不動産所得:300万円(家賃収入)-45万円(必要経費)-296万円(減価償却費)=▲41万円
したがって、帳簿上は41万円の損失(赤字)が発生することになります。
この損失金額を以下の通り損益通算すれば、課税所得の削減が可能です。
所得額:900万円(給与所得)-41万円(不動産投資の損失額)=859万円
損益通算により、所得額が900万円から859万円に減少したことがわかります。
所得税の速算表より、所得が900万円以上になると、税率が23%から33%に上昇することから、給与所得が900万円前後の方は、減価償却によるマイナス分を損益通算することで、大きな節税が可能となるでしょう。
上記のような方法による節税を目的にマンション経営を始め、実際に税金対策をしている投資家や不動産投資家も少なくありません。
ただし、事前に収支シミュレーションを行い、キャッシュフローがどの程度になるか予測を立てておくことが大切です。
減価償却を行う際の注意点
減価償却は節税の手段として有効ですが、2つほど注意すべきポイントがあります。
1つ目は物件の用途や種類ごとに法定耐用年数が定められているため、利用できる期間に上限がある点です。
定められた法定耐用年数を超えた物件では、減価償却費が計上できないことを想定しておく必要があります。
減価償却を利用した損益通算によって節税対策を行っていた場合は、翌年から所得税などの税金が大きく上がるリスクがあるため、前もって対策を考えるようにしましょう。
2つ目は建物本体部分と設備部分で減価償却期間が異なる点です。
建物と設備では別々に法定耐用年数が設定されているため、減価償却が終了する時期が一致しないケースがほとんどです。
また、設備の場合、修繕やリニューアル工事を行えば、減価償却期間が初期状態に戻るため、再度経費を計上できます。住宅設備などの改修は、節税目的だけではなく、美観・機能の改善による競争力向上も見込まれるので、費用対効果を踏まえたうえで適切な実施を心がけましょう。
以上を踏まえると、築年数が浅く設備の新しい物件は減価償却の残存年数が長いため、長期で所得税を削減しやすい傾向にあります。
ちなみに築年数が古く設備の修繕工事などを実施してこなかった物件は、
減価償却期間が短く(中古資産の償却年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2)、節税・安全・安定などさまざまな点で適切な修繕工事を検討する必要もあるでしょう。
なお、減価償却は個人で不動産投資を行う場合、必ず行わなければなりませんが、法人の場合、任意とされている点も覚えておきましょう。
減価償却費の計算方法
減価償却費には定額法、定率法の2種類の計算方法があります。それぞれの計算方法や適用される条件を把握しておきましょう。
定額法
定額法は法定耐用年数の期間中、毎年同じ額の減価償却費を計上する方法です。
例えば1,000万円の資産を10年で償却する場合、減価償却費は毎年100万円となります。
定額法の減価償却費を計算式に表すと、以下の通りです。
減価償却費=取得価格×定額法償却率
定率法償却率は建物の法定耐用年数によって異なります。
※出典:「減価償却資産の償却率等表」(国税庁)
定率法
定率法は取得時の価格から減価償却累計額を差し引いて償却率を掛けて算出する方法です。
例えば1,000万円の資産を10年で償却する場合、1年目は20万円、2年目は16万円というように、経過年数が長ければ長いほど償却率が低くなっていきます。
定率法で減価償却費が計算できるのは建物に付属する設備のみであり、なおかつ2016年3月31日までに取得した設備に限定されます。
したがって建物の減価償却では適用されません。定率法の減価償却費を計算式で表すと、以下の通りです。
減価償却費=(取得価格-前年度までの減価償却累計額)×定率法償却率
減価償却を活用して節税に繋げよう
不動産投資ではさまざまな節税方法が存在しますが、減価償却の利用は最も節税効果が期待できる手段の一つといえます。
特に給与所得など不動産以外の収入が多く、高額の税金を納める必要がある方は、減価償却を活用した損益通算を用いることで、課税所得を大幅に圧縮できる場合があります。
ただし、減価償却期間は長い場合と短い場合、それぞれにメリットとデメリットがあることを覚えておきましょう。
今回は、減価償却による節税の仕組みについて見てきましたが、もし不動産投資の節税効果やお金に関する疑問点があれば、信頼のできる不動産会社へ相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
大東建託では資産運用や相続、土地活用に関する相談を税理士などと連携して無料で受け付けていますので、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
伊野文明
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。
【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者
「税金・相続」関連用語集
- 青色申告
- 青色事業専従者
- 確定申告
- 私的年金
- 固定資産税
- 節税対策
- 相続税
- 不動産取得税
- 任意後見制度
- 定期借地権
- 年末調整
- 印紙税
- 贈与税
- 所得控除
- 登録免許税
- 都市計画税
- 住宅取得控除
- 借地権
- 遺言書
- 成年後見制度
最新コラムの更新情報以外にも、少しでも皆様のお役に立つ
資産承継や賃貸経営に関するホットな情報をお届けします。
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング