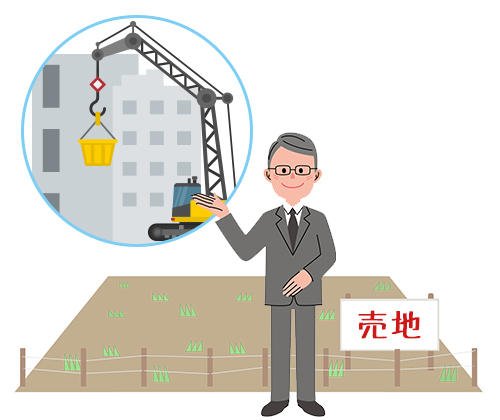賃貸アパートが相続対策になる理由は?実際の数字でシミュレーション
公開日: 2023.09.06
最終更新日: 2025.07.24
不動産を相続するとき、ポイントとなるのが相続税です。
相続税は相続財産の評価額に応じて税率が大きくなる「累進課税制度」を採用しているため、財産の評価額を抑えたほうが結果的に税金が安くなります。有効な対策の一つにアパート経営があります。
アパート経営を通じて土地活用すれば、活用していない土地を相続するより相続税の評価額を下げられるためです。
そこで本記事では土地の評価額を下げる方法、相続の流れのポイント、数字を用いたシミュレーションを解説します。
>>関連記事:アパート経営完全ガイド|建築プラン立てから完成後の業務まで
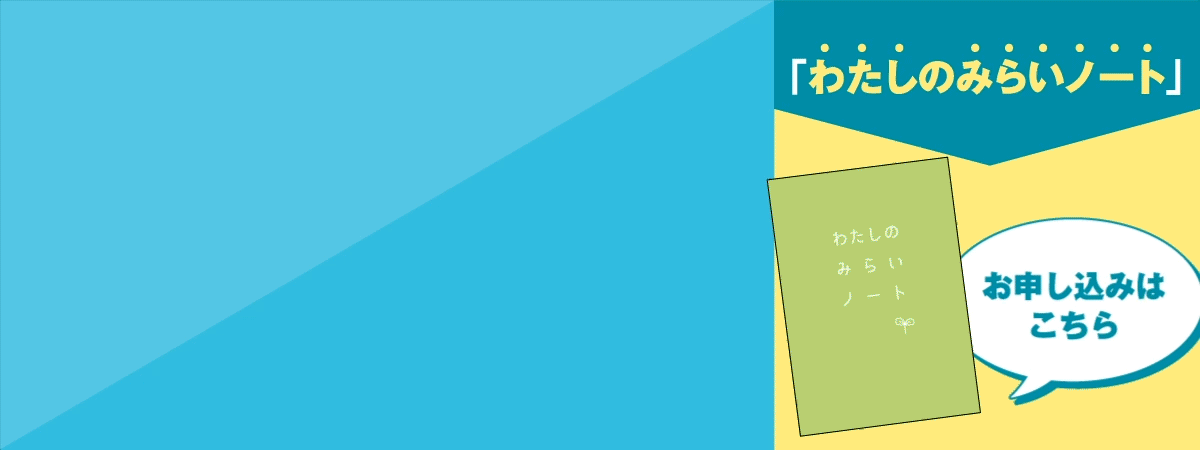
1.アパート経営が相続対策の1つとして選ばれている理由
アパート経営は有効な相続対策になると考えられています。
以下にその理由を4つ紹介します。
なお、ここで紹介するアパート経営は、「いきすぎた節税」として問題視され、見直しが予定されているタワマン節税とは内容が異なるものです。
1-1.土地にかかる相続税の評価額が下がるため
アパート経営を行えば土地にかかる相続税の評価額を下げられます。
基本的に自宅や空き地、簡易的な駐車場のように自由に利用できる土地のほうが、相続税の評価額が高くなりがちです。
一方、アパートやマンションのような貸家を建てると、その土地は「貸家建付地」として評価し、時価よりも土地評価額が下がるため税金が抑えられます。
1-2.建物にかかる相続税の評価が下がるため
アパート経営は建物の相続税評価額を下げるためにも効果的です。
一般的に建物の相続税評価額は建築費用の約60%程度とされており、建物を建てる際の実際の費用に比べて、評価額が抑えられるためです。
さらにアパートやマンションなどの貸家を建てる場合、課税対象となる建物の相続税評価額が30%程度下がる傾向があります。
これにより相続税の支払いを軽減できます。
アパート経営を行うことで評価額が下がり相続税の負担を軽減できる理由としては、他者に建物を貸すことで所有者の利用に制限が生じることや、空室が発生するリスクへの補填と考えられています。
また、小規模宅地等の特例が適用されると、さらに評価額は下がります。
適用するためには面積など複数の条件を満たす必要があるほか、相続時の申告時に複数の書類を添付する必要があるので、事前に内容をよく把握しておきましょう。
1-3.納税資金への備えができるため
定期的に入居者から賃貸収入が得られるため、納税資金確保の手段としても有効です。
相続前に家賃収入を預貯金に回しておけば、相続税の納税資金として充てることが可能です。
また、相続後についても定期的に入る賃料収入が生活基盤を支える収入源として活用できるでしょう。
もし入居率が下がり、万が一空き家の状態になったとしても、資産価値の高い物件であれば不動産売却によって資金を得ることが可能です。
1-4.債務控除が適用されるため
アパート経営では債務控除を適用できます。
債務控除とは相続財産から借入金額を控除する仕組みのことです。
たとえばアパートの建築費用の一部をローンで借り入れる場合、その借入金額の残債が債務控除の対象となります。
なお、手元資金を投入した場合も同様の効果があります。
2.相続税対策でアパートを建てた際のシミュレーション
相続対策でアパートを建てた場合、どの程度の節税効果が期待できるのか、実際のシミュレーションを通して確認しましょう。
なお、納付すべき相続税額を計算するときは、まず課税遺産総額の基礎控除額を求めるために、以下の計算式を用います。
【基礎控除】
・3,000万円+600万円×法定相続人の数
本シミュレーションでは都合上、相続人を配偶者(妻)一人としているので、相続税評価額から3600万円(3000万円+600万円×1人)の基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
子供がいる場合は、それだけ法定相続人が多くなるため、基礎控除も増加する点に注意しましょう。
相続税額は課税遺産総額(相続税評価額から債務など控除し、基礎控除を差し引いた金額)を法定相続分で按分した金額に対し、取得金額に応じた税率をかけ、さらに一定の控除額をマイナスして求めます。
税率と控除額は以下の「相続税の速算表」を活用します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税額 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
以上の内容を踏まえたうえで、4つのパターンに分けた相続税のシミュレーションを実施します。
なお、土地の評価額は坪単価130万円程度(2023年時点の東京都の土地価格の中央値相当)で計算しています
2-1.【事例1】土地と現金のみを相続した場合①
まず土地と現金のみを相続した場合のシミュレーションを行います。
条件は以下の通りです。
・土地の評価額は1億円
・土地の面積は80坪
・現金は2,000万円保有している
・相続人は妻1人
現金は100%で評価されるため、2,000万円がそのまま相続税評価額になります。
また土地の評価額は路線価をもとにしますが、活用されていない土地の場合、原則として路線価評価額から控除されるものはありません。
したがって、この場合、相続税評価額は以下の通りです。
【相続税評価額】
・1億円(土地の評価額)+2,000万円(現金)=1億2,000万円
相続税を求める際は、基礎控除3,600万円を差し引いて課税遺産総額を求めます。
【課税遺産総額】
・1億2,000万円(相続税評価額)-3,600万円(基礎控除)=8,400万円
これに対し速算表の税率をかけ、控除額を差し引きます。
【相続税】
・8,400万円(課税遺産総額)×0.3(税率)-700万円(控除)=1,820万円
したがって、1,820万円がこのパターンの相続税です。
2-2.【事例2】土地にアパートを建てて相続した場合①
次に土地にアパートを建てて相続した場合のシミュレーションを行います。
条件は以下の通りです。
・土地の評価額は1億円
・土地の面積は80坪
・現金は2000万円保有している
・建築費用は8000万円
・現在のローン残高は2000万円
・借地権割合は70%
・借家権割合は30%
・賃貸割合は100%
・固定資産税評価額は建築費用の60%
・小規模宅地等の特例は適用しない
・相続人は妻1人
土地と現金は事例1と同様の条件ですが、土地は貸家建付地となっているため、借家人の有する権利を考慮しなければなりません。
また、8,000万円の建築費用で建てたアパートがあるため、建物部分の相続税評価額をプラスする必要があります。
アパートの評価額を求める場合、固定資産税評価額を基準としますが、本事例では建築費用の60%に当たる4,800万円を固定資産税評価額とします。
これに対し借家権割合30%、賃貸割合100%を考慮して相続税評価額を求めたうえ、さらにローン残高2,000万円を差し引きます。
このようなケースでは、以下の計算式を用いて土地の相続税評価額、建物の相続税評価額をそれぞれ計算した後、合算することで求めます。
【土地の相続税評価額の計算方法】
・土地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
【建物の相続税評価額の計算方法】
・建物の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
したがって、以下の計算で求めます。
【土地の相続税評価額】
・1億円(土地の評価額)×(1-0.7×0.3×1.0)=7,900万円
【建物の相続税評価額】
・4,800万円(建物の評価額)×(1-0.3×1.0)=3,360万円
相続税評価額の合計は、上記に現金を足して求めるため、以下の通りです。
【相続税評価額の合計】
・7900万円(土地の相続税評価額)+3,360万円(建物の相続税評価額)+2,000万円(現金)=1億3,260万円
上記に対し基礎控除3,600万円と、さらにローン残高は2,000万円を差し引いて課税遺産総額を求めます。
【課税遺産総額】
・1億3,260万円(相続税評価額)-3,600万円(基礎控除)-2,000万円(ローン残高)=7,660万円
最後に速算表の税率をかけ、控除額を差し引きます。
【相続税】
・7,660万円(課税遺産総額)×0.3(税率)-700万円(控除)=1,598万円
したがって、1,598万円がこのパターンの相続税です。
土地だけの事例1と比較して、相続税額が下がったことがわかります。
ローンがある不動産を相続するときは、返済のリスクを不安視して相続放棄したがる方もいますが、このように相続税評価額から控除できるメリットがあることも踏まえて考えるようにしましょう。
2-3.【事例3】土地と現金のみを相続した場合②
土地と現金のみを相続した場合で、事例1とは異なるケースのシミュレーションを行います。
条件は以下の通りです。
・土地の相続税評価額は3億円
・土地の面積は240坪
・現金は6000万円保有している
・相続人は妻1人
この場合、相続税評価額は以下の通りです。
【相続税評価額】
・3億円(土地)+6000万円(現金)=3億6000万円
相続税を求める際は、基礎控除3,600万円を差し引いて課税遺産総額を求めます。
【課税遺産総額】
・3億6000万円(相続税評価額)-3600万円(基礎控除)=3億2400万円
これに対し速算表の税率をかけ、控除額を差し引きます。
【相続税】
・3億2,400万円(課税遺産総額)×0.5(税率)-4,200万円(控除)=1億2000万円
したがって、1億2000万円がこのパターンの相続税です。
事例1と比べると相続税評価額は3倍ですが、相続税は6.5倍以上上がっています。
評価額が上がるほど税率が上昇することが、両者を比較することでよく理解できます。
2-4.【事例4】土地にアパートを建てて相続した場合②
土地にアパートを建てて相続した場合で、事例3とは異なるケースのシミュレーションを行います。
条件は以下の通りです。
・土地の相続税評価額は3億円
・土地の面積は240坪
・現金は3000万円保有している
・建築費用は1億円
・現在のローン残高は4000万円
・借地権割合は70%
・借家権割合は30%
・賃貸割合は100%
・固定資産税評価額は建築費用の60%
・小規模宅地等の特例は適用しない
・相続人は妻1人
事例2と近い条件となっていますが、金額が大幅に上がっています。
まずは事例2の手順通りに土地と建物それぞれの相続税評価額を計算します。
なお、建物の評価額は建築費用1億円の60%なので、6,000万円となります。
【土地の相続税評価額】
・3億円(土地の評価額)×(1-0.7×0.3×1.0)=2億3,700万円
【建物の相続税評価額】
・6,000万円(建物の評価額)×(1-10.3×1.0)=4,200万円
【相続税評価額の合計】
・2億3,700万円(土地の相続税評価額)+4,200万円(建物の相続税評価額)=2億7,900万円
【課税遺産総額】
・2億7,900万円(相続税評価額)-3,600万円(基礎控除)-4,000万円(ローン残高)=2億300万円
これに対し速算表の税率をかけ、控除額を差し引きます。
【相続税】
・2億300万円(課税遺産総額)×0.45(税率)-2,700万円(控除)=6,435万円
したがって、6,435万円がこのパターンの相続税です。
事例3と比較して、相続税が半分近く減少しています。
遺産総額が億単位になる場合、アパートなどの賃貸物件の有無によってどれほど相続税が変わるかが、よく理解できる事例といえます。
【出典】財産を相続したとき(国税庁)
3.相続対策でアパート建築を検討する際に押さえておきたいこと
相続対策としてアパート建築を実施する前に知っておくべきポイントを紹介します。
3-1.賃貸需要の有無がポイント
アパート経営の成功には周囲の賃貸需要が大きく影響します。
賃貸アパートの経営は、入居者から家賃を得て収入に充てるビジネスなので、空室状態が続くと収入が得られず経営悪化を招くことが注意点としてあげられます。
人気エリアであれば空室リスクを低くできるだけでなく、家賃を高く設定でき、収益性を高められる可能性もあるため、賃貸需要の有無は経営を大きく左右するといえます。
したがって、アパート経営を始めるときは、そのエリアの市場動向を調査して、需要の有無を把握することが重要です。
たとえば人口の増減、競合物件の有無、建設予定地の周辺で求められている物件の需要など、できるだけ詳細に調査するようにしましょう。
3-2.アパートを経営する目的をはっきりさせる
アパート経営は建築がゴールではありません。
継続的な収益を生み出せるよう、適切な経営を行う必要があります。
賃貸経営で継続的な収益を上げるためには、情報収集を徹底することが大切なので、市場動向や物件の需要を十分に理解しておきましょう。
また、相続時の節税目的でアパート経営を始める場合、所有者が死亡した後、多くの場合は相続人がアパート経営を引き継ぐことになります。
そのため、被相続人と相続人の両方が賃貸経営について理解し、協力することが重要です。
3-3.資産は分割しにくくなる
アパートは不動産の特性上、現金などと違って公平な分割が難しいデメリットがあります。
遺産の相続トラブルを避けるため、どの資産を誰に引き継ぐか、不動産の持ち分はどう配分するか、共有名義にするかどうかなど、できるだけ分割方法を具体的に決めておくことが重要です。
また、共有名義の場合は不動産を売却するなどの「変更行為」については、すべての共有者の同意を得なければ行えないリスクが伴います。
そのため、経済的利益を受け取る権利である「信託受益権」として不動産を共有するといったリスクを見越した対応が必要になるでしょう。
もし取り決めがなかった場合は、法定相続人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に合意した内容をまとめたうえで相続手続きを進める必要があります。
この際の協議が難航して「争続」に発展するリスクを防ぐためには、遺言書を作成することが有効です。
遺言書とは故人の財産を誰にどのように相続させるかを取り決めた書面です。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、それぞれ証人の有無、保管方法などが異なるため、事前に内容をチェックしておきましょう。
なお、相続登記が2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。
相続登記とは不動産のオーナーが亡くなった後、不動産の名義人を相続人へ変更するための手続きで、所有権移転登記の一種です。
今後は相続開始から3年以内に名義変更する必要があり、特別な事情がなく期限内の手続きを怠った場合、罰則が適用される可能性があります。
ただし、相続登記を行う際は登記申請書と併せ、遺産分割協議書(遺言がある場合は遺言書)、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など多くの必要書類を法
務局に提出しなければなりません。
書類をそろえるのに時間や手間がかかり、登記申請書の記載も簡単ではないため、手続きに慣れてなく知識のない方は司法書士や弁護士へ早めに相談したうえで登記手続きを進めることをおすすめします。
3-4.経営にはリスクが生じる
アパート経営にはリスクが潜んでいるため、事前に起こり得るリスクを把握し、適切に対処できるよう備えることが重要です。
リスクの例として、空室発生、賃料減少、入居者トラブル、修繕リスク、自然災害などがあります。
それぞれの問題への対策を自分なりに考えつつ、不安な点があれば不動産管理会社へ対応方法について相談することをおすすめします。
なお、アパート経営のリスクに関しては、以下の記事を参考にしてください。
>>関連記事:アパート経営のメリットと利回りは?かかる経費やリスク、対処法
4.アパート経営による相続税対策は事前準備が大切
賃貸アパートで相続対策をする場合は、事前の準備が重要なポイントです。
資金計画、利回り、相続対策できる額などをシミュレーションし、イメージを固めるようにしましょう。
また、計画地が老朽化した賃貸建物である場合、現入居者の転居や解体など工程や時間が余分にかかる可能性が高いことも、あらかじめ考慮しておくべきしょう。
このような事前準備を経験が浅い一般の方だけで行うのは非常に困難といえるでしょう。
そのため、アパート建築や賃貸経営のパートナーとなる会社選びや、司法書士、税理士などの専門家との連携も大切です。
相談先を選択する際には、アパート建築、不動産投資、売却実績の有無、評判などを見て総合的に判断するのが選び方のポイントです。
良い不動産会社に出会えれば、適切なプランやアドバイスを提案してもらえるので、スムーズに経営が進められます。
気軽な無料相談を実施している会社もあるので、一度連絡してみることをおすすめします。
■監修者プロフィール
税理士法人みらいサクセスパートナーズ 代表
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上。
現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っている。
また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事。
【保有資格】 税理士、CFP®
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング