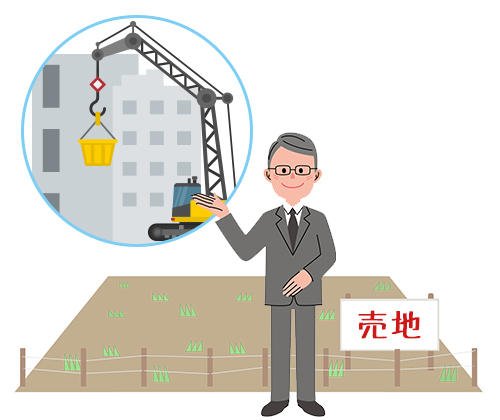アパート経営完全ガイド|建築プラン立てから完成後の業務まで
公開日: 2022.11.30
最終更新日: 2025.07.22
アパート経営は代表的な土地活用法の一つです。
複数の入居者と契約するため、安定した家賃収入が得やすいほか、空室が発生しても収入がゼロになるリスクが少ない点がメリットといえます。
しかし、アパート経営を始めるには、現地調査、事業計画書の作成、融資相談、建築プランの策定、物件の建築などさまざまな段階を経る必要があるため、実際の流れを理解しておくことが大切です。
そこで本記事ではアパート経営のメリット・デメリット、建築プラン立てから完成後の業務までの具体的な流れを解説します。
>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方

1.アパート経営のメリット・デメリット
まずは、アパート経営の概要を押さえるため、メリットとデメリットを説明します。
1-1.アパートを経営するメリット
資産形成ができる
アパート経営のメリットの1つ目は、不動産という資産を持つことができる点です。
不動産は株式や仮想通貨などに比べ、価格変動のリスクが低いことで知られています。
特に居住用の物件は生活に必要不可欠な資産であるため、経済情勢に左右されにくい特徴があります。不動産から毎月得られる安定的な家賃収入は、所有者に万が一のことがあった場合でも、家計を支えることでしょう。
また、不動産は生命保険の代わりとしても活用できる側面もあります。住宅ローンを組むほとんどの場合に加入する団体信用生命保険は、所有者に万が一のことがあった場合にローン残高と同額が保険会社から金融機関に支払われるものです。
つまり、家族にローン残高を残すことなく不動産を相続することができます。
これらの点から、賃貸住宅は長期的な資産形成に向いていると言えます。
家賃収入が得られる
アパート経営のメリットの2つ目は、アパートの入居者から毎月家賃収入を得ることができる点です。
株式投資の場合、配当金が入ってくるのは年1~2回が一般的です。アパート経営の家賃収入は毎月入ってくることから、収支の見通しが立ちやすいというメリットがあります。また家賃収入は不労所得の特徴があることから、兼業大家の方でも本業の収入を補う副収入の目的として活用することもできます。
特にアパートの一棟所有は、複数戸を運営することから、戸建てやマンションの区分所有(いわゆる区分マンション投資)に比べ空室リスクを分散しやすい特徴があります。ただし、一棟所有であっても空室リスクがゼロになるわけではないので、対策が不必要になるわけではないことも覚えておきましょう。
税金対策になる
アパート経営を含む不動産投資は、相続税の節税効果をもたらす場合があります。
一般的に不動産は現金よりも相続税評価額が低いので、多額の現金を相続するよりも、不動産を相続したほうが、税金が安くなるケースが多いためです。
また、小規模宅地等の特例が適用できれば、土地の相続税評価額を最大80%まで減額できる場合があります。
さらに一定の面積以下の住宅用地であれば、小規模住宅用地の特例が適用でき、固定資産税の課税標準額を最大6分の1に軽減できるため、税金負担を大きく軽減できるでしょう。
このほか減価償却を利用した損益通算により、所得税を圧縮する方法などもあるため、税金対策として有効といえます。
ただし、行き過ぎた相続税対策は脱税と見做されると否認される場合もあります。節税効果はあくまで副次的なメリットであることを認識し、税理士などの専門家に確認しながら計画することをおすすめします。
1-2.デメリット
相応の自己資金が必要
アパート経営を含む不動産投資のデメリットとして、初期投資が大きいことが挙げられます。
初期投資の中で多くを占めるのは取得費用(工事費用や物件購入費)ですが、そのほかにも登録免許税や不動産取得税、印紙税などの諸費用が発生します。
そのため、事前に必要経費を洗い出し、キャッシュフローを算出しておくことが成功のコツと言えるでしょう。
なお、不動産投資では銀行などの金融機関から融資を借り入れ、自己負担額を少なくすることが可能です。さらに、自宅の一部を賃貸に出す賃貸併用住宅であれば、自己の居住部分が全体の50%以上を占める場合、住宅ローンを利用できるケースがあります。
住宅ローンは投資物件を対象としたローン(アパートローン、マンションローンなど)より金利が低めに設定される傾向があります。購入費用に合わせ、適切な返済額と返済期間を設定しましょう。
>>関連記事:アパート経営はまとまった資金なしでもできる?「土地あり」の人が資金を得る方法
築年数が経過すると収益性が落ちる可能性がある
現物資産である以上、老朽化は避けられません。
物件が古くなり、美観や機能が周辺物件より見劣りする状況となってしまうと、空室率が上がり、賃料は下がってしまう傾向にあります。
しかし、このリスクは事前の対策を練ることで最小限に抑えることができます。計画時に、老朽化に伴う賃料収入の減少や修繕費や空室対策費を見込んでおき、物件の状況に応じて適切な対応を取ることで、物件の魅力を維持するようにしましょう。
ランニングコストがかかる
不動産投資には、以下のようなランニングコストが発生します。
・ローン返済の元金・金利
・固定資産税・都市計画税(都市計画地域の場合)
・不動産所得に対し発生する所得税・住民税
・保険料
・修繕費
・管理委託手数料(不動産管理会社に管理を委託する場合)
・不動産仲介手数料(新たな入居者の客付け時に発生)
・減価償却費(※既に投資した資産を費用として毎年分割計上するもので、実際のキャッシュアウトはなし)
上記以外にも、災害や修繕、家賃滞納などのリスクも発生します。
シミュレーションを立てる際にこれらのコストやリスクを見込み、正しく計上できていないと、思わぬ赤字に見舞われてしまう場合もあります。税金や修繕費などは簡単には算出できないため、不動産投資のプロのアドバイスを受け、何にいくらかかるのかはきちんと把握しておきましょう。
2.【アパートの取得】アパート経営が始まるまでの流れ
アパート経営を成功させるには、さまざまな指標を適切に読み解く必要があります。
そのなかでも特に重要な利回りと経費について解説します。
2-1.アパート経営の利回り
投資した金額に対する収益の割合を利回りといいます。
アパートのような賃貸経営の場合、基本的に1年間の家賃収入をベースにして考えます。
利回りは物件の収益性を表す指標の1つとして用いられており、物件の建築・購入を検討する際の重要な要素なので、必ずチェックするようにしましょう。
なお、利回りには大きく分けて表面利回りと実質利回りの2つが存在します。
表面利回りは物件の建築・購入価格に対する年間の家賃収入の割合を現した数値です。
一般的に「利回り」というと、表面利回りを指すケースが多く、不動産のポータルサイトなどでは主にこちらの数値が用いられます。
一方、実質利回りは空室率や年間の維持管理費用、建築・購入費用などを考慮するため、計算は困難になりますが、表面利回りより正確な数値が導き出せます。
2種類の利回りを計算式で表すと、次の通りです。
表面利回り(%)=年間家賃収入÷物件建築・購入価格×100
実質利回り(%)=(年間家賃収入-年間経費)÷(物件建築・購入価格+取得時の諸経費)×100
2-2.アパート経営の経費
アパート経営の経費は、主に初期費用と維持管理費用に分けられます。
初期費用はアパートの建築費など、経営を始めるまでに必要な経費、維持管理費用はアパートの修繕費など、経営を続けていくために必要な経費のことです。
初期費用と維持管理費用の主な例は以下の通りです。
【初期費用】
・土地代
・建築費
・不動産取得税
・登録免許税
・ローン手数料
【維持管理費】
・管理費
・修繕費
・固定資産税
・都市計画税
・水道光熱費
なお、アパート経営では毎年、減価償却費を経費として計上できます。
減価償却費を上手く活用すれば、税金の圧縮を図ることが可能です。
>>関連記事:アパート経営の利回りの理想と最低ラインの目安は?計算方法や注意点
3.【アパートの取得】アパート経営が始まるまでの流れ
アパート経営を始めるにはさまざまな手順を踏む必要があります。その代表的なポイントを解説します。
Step1.賃貸経営について相談する
まず不動産会社や建築会社に土地活用の相談をします。賃貸経営の目的や実現したいことを伝えるようにしましょう。購入したい物件のエリアや規模、用意できる自己資金、どのくらいの収益を得たいかなど、できるだけ明確にしておくのが理想です。
目的が明確であれば、適切な提案を受けられるためです。
また、一社のみの提案で決めず、なるべく複数の会社と相談し、比較検討することをおすすめします。
>>関連記事:土地活用の相談先7選|成功させるために重視したいポイント
Step2.現地調査を行う
次に不動産会社や建築会社の担当者による現地調査を行います。
賃貸物件の建設が問題なく行えるかどうかを、プロの視点で確認します。
同時に周辺地域の賃貸物件の状況把握を実施することも大切です。
特に賃貸需要と物件供給のバランスは、賃貸経営が成功できるかどうかの一つの目安になるので、しっかりと情報収集するようにしましょう。
Step3.賃貸経営の計画を立てる
現地調査で問題がなければ、賃貸経営の計画を立てる段階に移ります。
不動産会社や建築会社と協力し、収支シミュレーションを行いながら進めるようにしましょう。
たとえば賃料の設定は、賃貸需要と物件供給、競合物件との比較、建物の規模や設備などを見て判断する必要があります。
適正な賃料がどのくらいか判断するためには、市場調査を行うと共に、プロの意見を取り入れることも重要です。
Step4.融資を申し込む
アパート経営には多額の資金が必要です。
ほとんどの場合、自己資金だけでは賄えないので、金融機関から融資を受けなければなりません。
ただし、融資可能額や金利、返済期間や保証人の有無など融資条件は金融機関によって異なるので、比較検討したうえで判断することが大切です。
また、融資を申し込む際は、身分証明書、収入証明書、土地や建物の契約書など多数の書類が必要になるので、事前に確認するようにしましょう。
>>関連記事:不動産投資で融資を活用する流れや必要な書類は?
Step5.アパート建築を依頼する会社を選ぶ
融資が決まったら、アパート建築を依頼する会社を選びます。
安全かつ確実に工事を進めてくれる施工会社を選ぶためには、実績や信頼度を確認することが必要です。
また、入居者に魅力的なアパートにするためには、設計や提案力が高い会社を選ぶ必要があります。
依頼するときは一社のみでなく、複数社の意見を聞き、プランや見積内容を比較検討するようにしましょう。
なお、建物を建てる技術は高くても、建築後のアフターサービスや管理運営業務に関しては対応していない会社も少なくありません。
できれば建築後のことも考え、質の高い管理や入居者に魅力あるサービスを提供できる会社を選ぶことをおすすめします。
Step6.建築工事を開始する
アパートを建築する会社の選定が終わり、建築プランが決定したら、建築工事に移ります。
施工管理は基本的に施工会社が行い、進捗状況も定期的に報告されます。
ただし、オーナー自身もできるだけ現場に赴き、工事の進捗などを確認することが大切です。
設計通りに工事が実施されているか、安全性に問題はないかなど自分の目でしっかりチェックしましょう。
工事が完了すると役所による完了検査が行われ、問題なければ引き渡しとなります。
Step7.入居者を募集する
アパートの建築を開始し、竣工・引き渡し時期の目安が決まった辺りで、入居者募集を開始します。
募集は広告の配布や賃貸情報サイトへの掲載などによって行われます。
また、アパートの管理運営・メンテナンスは、不動産管理会社へ委託するのが基本なので、事前に管理会社の紹介を受けるか、自分で探しておくことをおすすめします。
4.【入居開始】アパート経営が始まってからの主な業務の流れ
アパート経営を始めた後は、不動産会社の協力を得ながら建物をメンテナンスし、家賃収入を維持・向上させることが重要となります。ポイントをチェックしていきましょう。
4-1.入居者の決定と賃貸借契約の締結
入居者の斡旋は、地域の仲介会社に依頼します。入居希望者が見つかると、提出される申込書を確認し、家賃の支払い能力を確認します。
家賃保証会社との契約を必須にする場合は、保証会社による審査の結果も判断材料としましょう。入居を認める場合、賃貸借契約を取り交わします。
敷金・礼金などの初期費用を受け取った後、鍵を引き渡して居住開始となります。
4-2.入居者管理
管理委託、サブリースの場合は不動産会社が行いますが、自主管理の場合はオーナーが入居者管理の業務を行う必要があります。
入居者との契約更新などの手続きや退去時の立会い、設備の不具合やクレームへの対応など、その業務は多岐にわたります。
4-3.賃貸管理
自主管理の場合は、毎月振り込まれる家賃を確認し、滞納している入居者に対しては督促を行います。
アパートなどの賃貸住宅の契約期間は2年が一般的です。それ以降も延長して住み続けたい入居者に対しては、賃貸借契約の更新手続きを行います。更新手続きの案内を出し、改めて賃貸借契約を締結しましょう。
最初に結んだ契約によっては、契約の更新料を収受できます。その相場は家賃の1カ月分となります。
ほかにも、火災保険の更新料、保証会社への更新料などが発生する場合もあることから、それらを合わせて入居者に通知しましょう。
4-4.建物の管理やメンテナンス
建物の資産価値を低下させないためには、共用部の清掃、植栽の整備、消防設備やエレベーター定期点検が日常的に必要となります。
自主管理の場合、清掃や植栽は自らでされているオーナーが多いようです。設備の点検は専門業者に依頼し、老朽化した箇所の修繕を行いましょう。
部屋内のメンテナンスは、退去者が出たタイミングで行います。室内クリーニングを行うと共に、必要であればクロスの張替えや設備交換などのリフォームを行いましょう。忘れてはならないのが、10~15年に1度の大規模修繕です。屋根や外壁の塗装は劣化すると建物内に雨水を浸入させる原因となります。大規模修繕のタイミングで定期的に塗り直し、建物の寿命を伸ばしましょう。
また、大規模修繕に向けて、修繕費用は毎年少しずつ積み立てていくことを心掛けましょう。
5.アパート経営で起こり得るリスクと対策
アパート経営にはさまざまなリスクが付き物です。アパート経営を成功させるためには、リスクを把握して事前に対策しておくことが欠かせません。その代表的な事例を紹介します。
5-1.空室リスク
入居者が見つからず、空室期間が続く状態を指します。
アパート経営は入居者から集める賃料が収入源となるため、空室率の増加や長期化は収支の悪化に直結するでしょう。
したがって、リスクの存在を認知し、アパートの建築前から対策するのが望ましいといえます。
空室リスクへの対策の例としては、アパート経営を行うエリアの賃貸ニーズを理解して、ニーズに合った間取りを取り入れる、利便性の高い設備やシステムを導入する、定期的なリフォームを実施する、などの方法が考えられます。
5-2.賃料下落リスク
賃料下落リスクとは、所有する物件の家賃が下がってしまうリスクのことです。
たとえば周辺の競合物件が増加し、賃貸需要が低下すると、周辺の賃料相場が下がる可能性が高まります。
周辺の賃料相場が下落する中、同じ家賃の水準を保ち続ければ、入居者は獲得しにくくなるでしょう。
また、築年数が経ち建物が老朽化すれば、賃貸物件としての魅力が低下し,競合物件のほうに入居者が集まりやすくなるため、家賃を下げることも検討しなければなりません。
こうした賃料下落リスクを軽減するためには、市場動向や競合物件の変化に常に気を配ることが大切です。
同時に物件の老朽化により魅力を失わないように、修繕やメンテナンスを徹底し、必要に応じて設備のリニューアルを行うことも重要です。
5-3.家賃滞納リスク
入居者が家賃を滞納し、回収が困難になるリスクのことです。
家賃を滞納した入居者に対しては、入金の申し入れや督促などを行う必要がありますが、精神的な負担が大きいうえ、時間や手間もかかります。
家賃滞納は入居者自身の問題なので、契約前に入居者の信用調査をしっかりと行うことが重要です。
入居者の経済的な安定性、過去の履歴などを慎重に評価し、信用性の低い人とは契約しないようにすれば、家賃滞納リスクを軽減できるでしょう。
オーナー自身で信用調査を行うのは困難なので、不動産管理会社と連携して対応するのが大切です。
5-4.入居者リスク
入居者リスクとは物件の入居者がトラブルを起こすリスクなどです。
複数の入居者が集まるアパートでは、マナーなどに問題のある人が入居する可能性も十分考えられます。
特に多い事例として、騒音問題が挙げられます。
騒音問題が起こった歳、騒音の発生主に対して他の入居者が直接注意すると、入居者同士で揉め事になり、トラブルに発展してしまうケースがあります。
そのため、騒音クレームが発生した際は、オーナー側が注意喚起しなければなりませんが、中には態度を改めない人もいるでしょう。
入居者リスクをオーナー個人で解決するのは非常に難しいため、不動産管理会社へ対応を委託するのが有効な対策といえます。
5-5.建物の修繕・維持管理リスク
建物の修繕・維持管理リスクは、予期していなかった修繕が必要となるリスクや、管理費が高騰するリスクなどを指しています。
定期的な点検やメンテナンス計画を立て、建物の状態を適切に管理する必要があります。
適切な時期に修繕を行っていないと、急に設備のトラブルが発生したり、漏水や雨漏りなどの重大事故が発生したりする可能性もあります。
不動産管理会社と連携しながら、修繕やメンテナンス計画を立てると同時に、10~20年前後のスパンで大規模修繕を実施することも大切です。
5-6.自然災害リスク
自然災害リスクは火災や地震などにより建物が被害を受けるリスクのことです。
災害の規模によっては被害額が数千万円規模になったり、建物を失ったりする可能性も考えられるので、対策はしっかりと講じておくことをおすすめします。
火災保険、地震保険への加入が有効な対策となりますが、同時に避難方法、避難場所などは普段から把握して、何かあったときのための行動を考えておくことが大切です。
なお、1981年以前に建築された物件は耐震基準が現在とは異なる、古い基準で造られています。
古い耐震基準の場合、震度6~7程度の大規模地震を想定しておらず、大きな地震が発生した際、倒壊する可能性が高いことも把握しておきましょう。
5-7.金利上昇リスク
金利上昇リスクとは、金利の上昇に伴って利息が増加し、ローン返済の負担が大きくなる状況のことをいいます。
金利上昇リスクに対処するためには、金利の動向を常に確認することが大切です。
また、金利が一定の期間変動しない固定金利を選択することが有効な対策になります。
固定金利であれば変動金利と違い、もし金利の上昇があっても影響を受けず、返済額にかかる利息は変化しないためです。
ただし、一般的に固定金利は変動金利より契約時の金利が高めなので、収支バランスをよく考えたうえで判断するようにしましょう。
5-8.管理会社の倒産リスク
アパートの管理業務を委託していた不動産管理会社が倒産するリスクのことです。
管理会社が倒産すると、管理業務の中断や入金手続きの遅れなどが生じる可能性があります。
たとえば設備点検や清掃が実施されなくなったり、入居者から回収済みの家賃がオーナーへ送金されなかったり、さまざまなトラブルが発生することが予想されます。
自分で管理業務を行うこともできますが、アパートの管理をオーナー自ら実施するのは大変なので、ほとんどのオーナーが次の管理会社を探すことになるでしょう。
こうしたリスクに備えるためには、信頼性の高い管理会社を選定すると同時に、経営状況にも目を配り倒産の兆候などがないか、チェックする意識を持つことが重要です。
>>関連記事:賃貸経営の5つのリスクとは
6.アパート経営で成功するために大切な要素
アパート経営には適切な計画やパートナー選びが欠かせません。詳細を以下で解説します。
6-1.建築計画
アパートを建設する際の詳細な計画や設計のことです。
建築する物件に関する情報がまとまっているので、構造や階数、建築費などがオーナーのニーズに適った内容になっているかどうか、しっかり目を通し確認するようにしましょう。
また、着工から竣工までの工期や着工前の打ち合せなど、スケジュールの確認も大切です。
6-2.事業計画書
アパートの経営全般に関わる内容をまとめた計画書で、物件や土地の情報、収支の計画などが記載されます。
アパート経営をどのように行っていくかがまとまった書類であり、金融機関から融資を得る際にも必要となる書類です。
金融機関は融資をする人の資産状況や物件の立地条件だけでなく、事業計画書の内容も詳しく見て融資をするかどうかを判断します。
高額な融資を受けるためには、説得力のある事業計画書を作成することが重要といえます。
6-3.パートナー選定
アパート経営には専門的な知識が求められる場面が数多くあります。
そのため、一緒に経営を進めるパートナー選びが重要です。
特にアパート経営の経験が少ない方は、信頼できるパートナーからアドバイスを受けて進めると良いでしょう。
>>関連記事:アパート経営を始めて30年後に起こり得ることは?出口戦略の例
7.アパート経営で毎月の家賃収入を手に入れよう
今回は、アパート経営についての概要や流れを説明しました。
アパート経営に代表される不動産投資は、他の資産運用に比べ価格変動が少なく、安定した家賃収入が入ることから長期間の投資に向いています。ただし、自主管理の場合は日常管理や修繕などの手間がかかります。不動産投資特有のランニングコストもあるため、基礎知識を把握し、収支計画を立てたうえで信頼の置けるパートナーと共に進めていくことをおすすめします。
また、アパート経営ではさまざまなリスクが存在しますが、その種類と対策は概ね決まっています。
空室リスクや家賃下落リスクは不動産投資の経験が少ない方でもイメージしやすい内容ですが、その他、入居者リスクや自然災害リスクへの対策も怠らないようにしましょう。
大東建託では、不動産投資の相談を無料で受け付けています。土地活用や賃貸経営のノウハウに関して、担当者が丁寧にサポートいたします。不安な点や疑問点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
動画で分かる!
土地診断
■監修者プロフィール
宅地建物取引士/FP2級
伊野 文明
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。
【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング