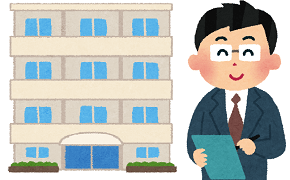アパート経営の利回りの理想と最低ラインの目安は?計算方法や注意点
公開日: 2023.02.08
最終更新日: 2026.01.13
アパート経営を検討する際、収益性の指標となる1つに、「利回り」があげられます。
「理想は利回り何%なのか」「最低ラインはどのくらいか」と、具体的な数字の正解を探して悩むオーナー様は少なくありません。 ただし実際は、物件ごとの個別要因により最適な利回りは異なるため、一概に「何%が正解」とは言えません。
この記事ではアパート経営における利回りの基礎知識や計算方法、収支シミュレーションについて解説します。
利回りを引き下げるリスクや安定した収益を維持するコツも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
6-2. 土地を持っている状態でアパート経営を始めると利回りはどうなりますか?
6-3. 新築アパートと中古アパート、どちらのほうが利回りが良いですか?
6-4. アパート経営はどういった要素が利回りに影響しますか?
7. アパート経営は「許容できるリスク」に合わせて収支計画を立てよう
1. アパート経営の利回りはどれくらいが理想?
アパート経営の実際の利回りや想定利回りなどに「何%以上なら絶対安全」という共通の正解はありません。
経営するアパートごとに理想の利回りが異なるためです。
ここでは、理想の利回りが決まっていない理由を詳しく解説します。
1-1. 決まり切った答えが存在しない理由
アパート経営に理想の利回りとなる答えが決まっていない理由は、物件ごとの個別要因が収支に大きく影響するためです。 インターネット上にある「利回り何%以上必要」といった情報は、あくまでひとつの目安にすぎません。
例えば、新築物件でも都心部か地方かによって、空室リスクや維持費、金融機関の融資条件も異なります。 利回りの数字だけに囚われると、かえって本質的な経営の安定性を見誤る可能性があります。
表面的な数値だけでなく、経営する物件に合う基準を持ちましょう。
1-2. 土地の有無で求められる利回りは異なる
土地を所有しているかどうかで初期費用のコストが変動するため、必要な利回りが異なります。具体的には、次のような状況です。
|
土地の有無 |
必要な利回り |
理由 |
|
新たに購入する |
高い |
土地代の回収が必要なため |
|
所有している |
低い |
土地代がなく、初期費用が抑えられるため |
親から相続した土地などを活用する場合は、必要な初期費用が比較的少なくなるため、低い利回りでも手元に資金が残りやすくなります。
また、インターネット上でよく公開されている利回りの情報は、こうした土地の有無といった条件が不明なケースも少なくありません。
そして、本来なら土地以外の要因によっても目指すべき利回りの数値は変わってきます。
したがって、「表面利回り〇%以下は絶対にダメ」と一括りに決めつけることはできないのです。
1-3. リスクの大きさによって適正な利回りは変わる
目標とする利回りは、オーナー自身がどこまでリスクを許容するかによって数値が変わります。
インターネット上で見る「高利回り物件」の事例は、空室対策や管理の手間をすべてオーナー様が引き受けるハイリスクな条件が多い傾向です。
逆にリスクを避けた安定性を求めると、リスク対策の費用がかかり、利回りは下がります。
例えば管理会社に依頼する「サブリース(一括借り上げ)」を利用すると、家賃保証などの対価として受け取る賃料が少なくなるため、利回りは下がります。
しかし、家賃保証により空室発生や家賃滞納などによる収入減少のリスクを抑えることが可能になります。
そのため、利回りは下がったとしても安定した賃貸経営が実現しやすくなります。
結論を言うと、インターネット上の高利回りな事例と比較する必要はありません。
大切なのは、利回りの高さだけで判断するのではなく、リスク対策が組み込まれていて安定した計画を立てることです。
2. アパート経営の利回りの種類と見るべき数字
アパート経営の利回りには主に3つの種類があります。
● 実質利回り
● 表面利回り
● 想定利回り
経営の実態を正しく把握するために見るべき利回りは「実質利回り」です。
ここでは、それぞれの違いと計算式、なぜ実質利回りを重視すべきなのかについて解説します。
2-1. 実質利回り
アパート経営の計画を立てる際は、「実質利回り」の確認が重要です。
空室率や年間の維持管理費用、購入費用などを考慮し、手残りに近い数字になるためです。
<実質利回りの計算式>
実質利回り(%)=(年間家賃収入-年間経費)÷(建築費+取得時の諸経費)×100
固定資産税や管理費、修繕積立金、保険料などが経費として計上され、現実的な収益力を表しています。
経営の実態を見極めるには、欠かせない指標です。
2-2. 表面利回り
表面利回りは、一般的に不動産会社の広告やポータルサイトなどで「利回り」と記載されるケースが多い数値です。
<表面利回りの計算式>
表面利回り(%)=年間家賃収入÷物件購入価格×100
アパート経営にかかる経費を考慮しない単純な計算のため、実際の利益よりも高めの数値が出やすくなります。
最初の目安として使うには便利ですが、表面利回りだけを信じないように注意しましょう。
なお、広告等に掲載されている表面利回りは、一般的に満室時を想定した収入で計算されています。
2-3. 想定利回り
想定利回りは、物件の購入価格に対し、満室が続くと仮定した場合の年間家賃収入の割合を表した数値です。満室利回りとも呼ばれます。
<想定利回りの計算式>
想定利回り(%)=空室0の場合の年間家賃収入÷物件購入価格×100
特に新築アパートの収益性を検討する際、物件がもつ最大の利益率を測るために用いられることが多くあります。
将来発生する空室リスクや経費は考慮されていないため、実際の利益との乖離が大きくなりやすい点に注意しましょう。
3. 実質利回りを用いてアパート経営をシミュレーションする
実質利回りの数字は、アパート経営の収支にどう影響するのか、同じ条件でシミュレーションします。
前提条件は、次のとおりです。
【シミュレーション前提条件】
● 建物:10部屋の新築アパート
● 建築費と取得時の諸経費:1億5,000万円
● 建築時の諸経費:1,500万円
● 総投資額:1億6,500万円(建築費+諸経費)
● ローン条件:借入額1億5,000万円、金利1.5%、期間30年
※年間のローン返済額は約622万円
ここでは、利回り5%と3%の2パターンを用意して、見回りの変化が収支にどれほど影響するか確認しましょう。
3-1. 実質利回りの収支シミュレーション【その1】
まずは実質利回りが5%になるケースのシミュレーションです。
● 年間家賃収入(満室時):1,200万円
● 入居率:90%
● 実質の年間家賃収入:1,080万円
● 年間経費(維持管理費等):255万円
まずは年間の実質収益を計算します。
実質収益=1,080万円(年間家賃収入)-255万円(年間経費)=825万円
次に、実質収益を総投資額で割ると実質利回りは5.0%です。
実質利回り=825万円(実質収益)÷1億6,500万円(総投資額)×100=5.0%
また、実質収益の825万円からローン返済額の622万円を引くと、キャッシュフロー(税は考慮せず)はプラス203万円となります。
3-2. 実質利回りの収支シミュレーション【その2】
次に、空室や修繕費の増加により、実質利回りが約3.0%に低下したケースのシミュレーションです。
● 年間家賃収入(満室時):1,056万円
● 入居率:75%
● 実質の年間家賃収入:792万円
● 年間経費:300万円(修繕を行ったためその1シミュレーション時より増加)
まずは年間の実質収益を計算します。
実質収益=792万円(実質家賃収入)-300万円(年間経費)=492万円
次に、実質収益を総投資額で割ると実質利回りは約3.0%(2.98%)に低下したことがわかります。
実質利回り=492万円(実質収益)÷1億6,500万円(総投資額)×100=2.98%
最後に実質収益の492万円からローン返済額の622万円を引くと、キャッシュフロー(税は考慮せず)はマイナス130万円です。
今回のシミュレーションでは、実質利回りが2%低下すると収支が「203万円の黒字」から「130万円の赤字」に変化しました。
ただし、重要なのは「利回りが3%になると良くない」ということではありません。あくまで今回の融資条件で利回りを3%に設定した結果、黒字だった収支が赤字になったというだけです。
実際のアパート経営ではローンの返済期間を長くしたり、自己資金を増やして借入額を減らしたりすれば、利回り3%であっても黒字化できることはあります。
そのため、個人でシミュレーションするだけではなく、専門家に相談した上で理想的なシミュレーションを組むことをおすすめします。
4. アパート経営の利回りを下げるリスクと注意点
アパート経営は長期的な事業であるため、当初のシミュレーションでは考慮できない利回りを下げる要因が発生します。
ここでは、アパート経営における6つの主要なリスクと具体的な対策について解説します。
4-1. 空室・家賃滞納リスク
アパート経営における最大のリスクは、入居者が決まらない空室や、賃料が支払われない滞納です。
予定していた家賃収入が途絶え、利回りが大きく低下してしまいます。
リスクの分散には、所有する部屋数やアパートの棟数を増やすと有効です。
例えば1部屋だけの経営では、空室になると収入はゼロになりますが、10部屋あるアパートなら、1部屋空いても収入は10%減少で済みます。(ほかにも家賃保証会社を利用する方法があります)
物件を増やすにはそれなりの費用がかかるため、自己資金だけでは限界があります。そのため、アパートローンの利用が有効な手段です。
ただし、利回りを確保した計画を作成して借り入れしましょう。
4-2. 家賃下落リスク
建物は築年数が経過するにつれて老朽化し、市場価値が下がっていきます。加えて競合物件が出現すると、家賃設定も徐々に下げざるを得なくなるのが一般的です。
総務省の調査によると、一般的な借家の経年劣化による家賃の下落率は、年率約1%程度とされています。
例えば、新築時に家賃7万円だった物件は、10年後には約6.3万円に、20年後には約5.6万円まで下がる計算です。
家賃収入が減れば、利回りも低下します。家賃の下落幅を少しでも抑えるためには、定期的なメンテナンスやリフォームなどを実施し、物件の競争力を維持する対応が必要です。
【出典】:借家家賃の経年変化について(総務省)
4-3. 建物の修繕・維持管理リスク
アパート経営では外壁の劣化や給湯器の故障など、予期せぬトラブルに対する修繕やリフォームが発生します。 修繕しないまま放置すると、入居者が退去する原因となるため修繕が必要です。
しかし、修繕対応による出費は、キャッシュフローを悪化させる要因になります。 アパートの老朽化により修繕は必要になるため、日頃から家賃収入の一部を修繕積立金として確保しておくといいでしょう。急な修繕にも慌てず対応でき、経営の安定につながります。
4-4. 住民トラブルリスク
騒音やゴミ出しのルール違反などの入居者によるトラブルもリスクの1つです。対応を誤ると、ほかの入居者が嫌気を感じて退去してしまい、空室率が上昇して利回りの低下につながります。
対応策として、トラブルやクレームに対する体制が整っている管理会社を選ぶことが、被害を最小限に抑えるポイントになります。
4-5. 金利上昇リスク
アパートローンで変動金利を選択していると、市場金利の上昇に合わせて借入金の金利が上昇します。
金利上昇により毎月の返済額が増えるため、キャッシュフローが減少し、実質利回りが低下します。
金利上昇への対策としては、次の対策が効果的です。
● 金利上昇に備えた資金の確保
● 金利変動の影響を受けない固定金利の選択 ※借り入れ当初の段階で有効な対策
● 元金を繰り上げ返済し、借入残高を減らして利息負担を軽減
変動金利を選んだ場合は、将来の金利上昇を見越して対策しましょう。
4-6. 災害リスク
地震や台風、火災などの自然災害は、アパート経営の収益に大きく影響します。
突発的な多額の修繕費は、利回りを低下させる要因です。 こうした不可抗力のリスクに備える有効な手段が、損害保険への加入です。火災保険や地震保険へ加入する際には、立地エリアの特性に合わせて適切な補償を付けるようにしましょう。
万が一被災しても資産価値をカバーできる補償内容にしておくことが、長期的な投資利回りを守るために有効です。
5. アパート経営で高い収益と安定性を実現するコツ
一般的に、アパート経営は、築年数が経過するとともに家賃収入の減少と修繕費の増加が進み、利回りが低下しやすくなります。
しかし、適切な対策により、長期にわたる高い収益性の維持が可能です。
ここでは、安定した経営を実現するために重要な3つのコツを解説します。
5-1. 建築プランを最適化して収益性を最大化する
アパートの収益性は、建物が完成する前の「プランニング(設計)」の段階で大半が決まります。
収益性を最大化するためには、建設地となる土地のポテンシャルを最大限に引き出す建築プランが欠かせません。
同じ土地の広さでも、賃貸可能な総面積を広く確保すれば、家賃収入が高くなり、利回りの上昇につながります。
ただし、立地エリアの賃貸需要を見極め、ニーズに合った部屋の広さや間取りの建築プランが大切です。
5-2. 空室リスクを抑えやすい魅力的な物件を建築する
どれだけ収益性の高いプランを立てても、実際に入居者に選ばれなければ家賃収入は得られません。
そのため、空室を防いで収入を安定させるためには、入居者にとって魅力的な建物にすることが大切です。
例えば「オートロックや防犯カメラを設置してセキュリティ面を強化する」「エントランスや外観などをおしゃれにする」「無料インターネットや宅配ボックスなど人気設備を導入する」など、利便性や安全性が高まる設計にすることが有効な対策になります。
5-3. 適切な管理形態を選択する
実質利回りを高く維持するためには、運営パートナーである管理会社選びが重要です。
信頼できる管理会社を選ぶことが、運営コストの最適化と高い利回りの維持につながります。
管理委託料(コスト)の安さだけでなく、サービス品質とのバランスが重要です。
具体的には、次のような特徴がある管理会社を選びましょう。
● 入居者を素早く見つける客付け力
● 建物を清潔に保つ管理品質
● 適切な修繕提案
コストがかかっても信頼できる管理会社に任せるほうが、高い入居率を維持でき、トータルの収益は安定します。
なお、支出を最も抑えられるのはオーナー自身が行う「自主管理」ですが、時間と手間がかかるため、管理会社を選ぶほうが得策でしょう。
6. アパート経営の利回りに関する「よくある質問」
アパート経営の利回りについて、オーナー様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
6-1. アパート経営の利回りの相場はどれくらいですか?
物件の立地や構造、築年数によって大きく異なるため、一概に「〇%が正解」とは言えません。
不動産投資サイトによっては「5%~8%程度」という数字が見られますが、利回りが高くなりやすい地方物件や中古物件なども含んだ目安です。
土地活用による新築アパートや都心部の物件、サブリースを利用する場合は、これより低い数値になる傾向があります。
ネット上の相場と比較するのではなく、個別要因を踏まえたシミュレーションで主体的に判断しましょう。
6-2. 土地を持っている状態でアパート経営を始めると利回りはどうなりますか?
土地を持っている状態は土地なしで始める場合と比べて、利回りは高くなります。
アパート経営を始める際の初期投資に土地の購入資金が入らないためです。
また、借入金の返済負担を抑えられるため、キャッシュフローを安定して確保できるでしょう。
6-3. 新築アパートと中古アパート、どちらのほうが利回りは良いですか?
一般的に、物件価格が安い「中古アパート」のほうが、表面利回りは高い傾向です。
ただし、新築アパートはすぐに修繕の必要がないうえに、空室リスクも抑えられ収支が安定しています。
結果として長期的な実質利回りで見れば、新築アパートのほうが良くなる可能性もあります。
6-4. アパート経営はどういった要素が利回りに影響しますか?
利回りに影響する要素は、次の3つです。
● 初期費用(建築費用、土地代、諸経費)
● 家賃収入(入居率、家賃設定)
● ランニングコスト (管理費用、修繕費、税金、利息)
利回りは、家賃収入が増えれば上がり、初期費用やランニングコストが増加すれば下がります。
7. アパート経営は「許容できるリスク」に合わせて収支計画を立てよう
アパート経営では理想的な利回りに決まりきった答えはありません。
表面的な利回りの高さだけで判断せず、「どのリスクに、どれだけのコスト(備え)をかけられるか」を軸にした検討が重要です。
最終的に重視すべきは、計画上の数値ではなく、実際にどれだけのリターンが得られるかです。
目論見としての利回りだけで判断するのではなく、空室や修繕といった現実的なリスクを考慮し、手元に残る実質的な収益性を見極めていく必要があります。
また、高利回りのために、無理なリスクを負わないほうが賢明です。
「一括借り上げ(サブリース)」のように手数料を払ってでも、リスク管理を専門家に任せたほうが安定した収益につながるケースもあります。
判断に迷う場合は、土地活用や賃貸経営の専門家に相談しながら計画を立てましょう。
大東建託では土地活用や不動産経営に関する相談を無料で受け付けています。
計画を作成するうえで必要な利回りの算出やリスクの度合いなど疑問点や不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
■監修者プロフィール
ここりんくす株式会社 代表取締役
小泉寿洋
ここりんくす株式会社代表取締役。上場グループに属する賃貸不動産会社で賃貸仲介、賃貸管理部門に14年半ほど従事。その後、不動産仲介・建築工事・終活サポートの会社経営を経て、現在は賃貸経営・賃貸管理・終活に関するコンサルティング、WEBセミナー講師、不動産・FP系ライターなど各方面で活動中。不動産業界歴は約23年。
【保有資格】
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー1級、終活ガイド1級、遺品整理士他
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング