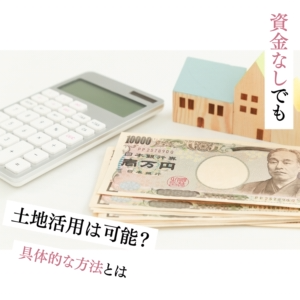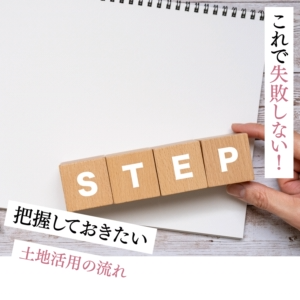【2026年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方
公開日: 2022.10.31
最終更新日: 2026.01.26
所有している土地が空き地のままで相続予定の土地の活用方法が定まっておらず、固定資産税や都市計画税といった税金を支払い続けている土地のオーナー様もいるのではないでしょうか。
「土地活用」とは利用していない土地を、何らかの方法で有効活用して利益を得ることです。
その手法はさまざまで、不動産投資の一例のように収益性のあるマンションやアパートなどの建物を建てるほか、土地を売却して現金化することも土地活用方法に含まれます。
この記事では土地活用の種類と方法、メリットデメリットを解説していきます。
目次
1-1.土地活用で得られる収益
1-2.所有している土地(更地)を放置するとどうなるか
1-3.土地活用の特徴
3-1.マンション・アパート経営
3-2.戸建て賃貸経営
3-3.賃貸併用住宅経営
3-4.月極駐車場経営
3-5.コインパーキング経営
3-6.駐輪場経営
3-7.トランクルーム経営
3-8.コインランドリー経営
3-9.ビジネスビル経営
3-10.テナントビル経営
3-11.商業施設・店舗経営
3-12.ホテル経営
3-13.ガレージハウス経営
3-14.シェアハウス経営
3-15.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)経営
3-16.デイサービス経営
3-17.福祉施設経営
3-18.介護施設経営
3-19.医療施設経営
3-20.保育園経営
3-21.コンビニエンスストア経営
3-22.太陽光発電の設置
3-23.自動販売機の設置
3-24.土地貸し
3-25.土地の売却
6-1.土地活用の目的から選ぶ
6-2.セミナーに参加して情報収集をする
7-1.人の往来が多くない場所でも土地活用はできますか
7-2.どのような目的で土地活用される人が多いですか
7-3.比較的短期間で実施できる土地活用の選択肢はどれですか
7-4.始めるにあたってどのような費用がかかりますか
7-5.どのような方法が自分の土地に適しているのかわかりません
7-6.田舎のような場所にある土地はどのような活用法がありますか
1.土地活用の概要
土地活用は収益を得るための手段、もしくは更地を含む土地をそのままにしておくリスクを軽減する目的で行われるケースが多いです。
それぞれの詳細を確認してみましょう。
1-1.土地活用で得られる収益
建物を貸した人から得る賃料が、土地活用で得られる主な収益です。
アパート・マンションの家賃のほか、ビルのテナント料などが該当し、一般的に好立地で面積が広く最新の設備が整っているなど、好条件の建物であるほど、高い賃料を設定しやすい傾向にあります。
また、コインパーキングの料金、太陽光発電の電気など、建物や施設そのものが生み出した利益も収益の一部になります。
さらに出口戦略の一つとして、収益物件を建てた土地を売却することで利益を得る方法がありますが、これも土地活用で得られる収益の一つといえます。
1-2.所有している土地(更地)を放置するとどうなるか
土地を更地のまま放置するのは望ましくない方法です。
有効活用していない更地にも固定資産税などの税金が課せられるので、利益のないまま税金だけ支払い続けることになるためです。
また、更地の場合、建物(住宅)がある土地と違い、「住宅用地の特例」が利用できないため、減税ができず税金が増えてしまう可能性があります。
※ただし、住宅が建っている場合でも特定空き家や管理不全空き家に認定されると「住宅用地の特例」は適用対象外となります。
※特定空き家:市町村が「放置すると倒壊や衛生環境の悪化など周辺に悪影響を及ぼす」と判断した空き家
※管理不全空き家:特定空き家よりも軽度な状態だが、適切に管理されておらず周辺の景観や安全に悪影響を与える可能性があると市町村が判断した空き家
整備をせずに放置していると、近隣住民から苦情が来ることもあるでしょう。
1-3.土地活用の特徴
土地活用の特徴は、金融機関からの融資を受けて投資ができる点にあります。株式投資などとは異なり、不動産を活用することで、安定した収益を期待できるのが魅力です。
土地活用を行う場合、金融機関の不動産投資ローンが主な選択肢となりますが、アパート経営だけに限らず商業施設や駐車場経営などの土地活用にも適用できます。特定の条件を満たせば住宅ローンが利用できる場合もありますが、活用の幅は限られています。
土地活用は融資を活用できるため、レバレッジ効果を最大化できる点も特徴です。少ない資金でより大きな投資効果が得られることを、レバレッジ効果と言います。自己資金に融資をプラスすれば購入できる物件の選択肢が広がり、より多くの収益が見込める物件が購入できるというわけです。
融資が利用できる投資方法は限られているため、土地活用ならではの特徴の一つと言えるでしょう。
また、土地活用は比較的インフレの影響を受けづらいです。土地活用は実際に存在する「現物資産」を所有することになりますが、こうした現物資産はインフレが起きても価値が変動しにくく、値動きが安定していると言われています。
2.土地活用を行うメリット
土地活用の種類によってメリットデメリットが異なる部分もありますが、土地活用を行うメリットは大きく分けて3つあります。
ここでは活用方法や方式の種類に限らず土地活用のメリットを紹介していきます。
2-1.土地にかかる税負担を軽くすることができる
土地は所有しているだけでお金がかかります。
草刈りなどの維持管理にかかる費用のほか、税金の負担もあります。
税金の負担を軽減しながら安定的な収入を得ることが土地の有効活用といえるでしょう。
ここでは税金の種類について説明していきます。
2-1-1.固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は土地や建物の所有者に毎年課される税金です。
土地も資産になるため土地の価値によって評価額が定められており、評価額をもとに税額が決められます。
固定資産の負担を軽くする方法として、所有している土地が更地であれば土地の上に建物を建てることで、特例措置が適用される場合があります。
<住宅用地の特例>
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 小規模住宅用地(200㎡未満の部分) | 6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 3分の1 | 3分の2 |
上記のように土地の区分によって減税の割合は異なりますが、居住用の建物を建てることで住宅用地の特例が受けられます。
2-1-2.相続税
土地活用を行うことで、不動産にかかる相続税額が低くなることがあります。
基本的な相続税の計算方法は下記の通りです。
<課税遺産総額と相続税の計算方法>
| 課税遺産総額 = 遺産総額(所有物や現預金などの全てを含む遺産)- 基礎控除額 |
| 相続税 = 課税遺産額 × 相続率 - 控除額 |
建物は第三者に貸し出すことで貸家建付地となるため相続税の評価額が下がり、賃貸住宅が建っている土地は相続税評価額が約2割下がります。
また、自宅や店舗などとして使用していた宅地の相続なら小規模宅地の特例措置が受けられ、相続税の評価額が約5割~8割軽減されるため、相続税対策にもなります。
|
相続開始の直前における宅地等の利用区分 |
要件 |
限度 |
減額される |
|||
|
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 |
貸付事業以外の事業用の宅地等 |
① |
特定事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ |
80% |
|
|
貸付事業用の宅地等 |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等 |
② |
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 |
400㎡ |
80% |
|
|
③ |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ |
50% |
|||
|
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 |
④ |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ |
50% |
||
|
被相続人等の貸付事業用の宅地等 |
⑤ |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200㎡ |
50% |
||
|
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |
⑥ |
特定居住用宅地等に該当する宅地等 |
330㎡ |
80% |
||
【出典】「No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(国税庁)
このように土地活用の方法によって相続税の負担を軽減するためには何も建っていない状態の更地を相続しても、建物を建てない限りこれらのメリットを受けられないことがわかります。
軽減措置を受けるためには要件に該当するか否か調べておくことが重要です。
特に小規模宅地の特例措置については細かい要件があるため、相続を受けた際に土地の面積や利用区分を 理解しておくことをおすすめします。
また土地活用の種類によっては税金の軽減措置が認められないケースもあるので、土地の活用法ごとの特色を把握することが大切です。
2-2.定期的な収入が見込める
ここまで説明してきたように、土地をただ所有しているだけでは利益は得られません。
土地活用で安定した収益を 得るためには、建物の建築などをして収益を生み出せる形に変えることが重要なポイントです。
賃貸経営や駐車場経営、店舗経営など活用方法によっては長期的に安定した収入を得ることができるでしょう。
2-3.地域貢献ができる
活用方法によっては、周辺に住む人に大きなメリットをもたらすことも可能です。
例えば医療施設や高齢者住宅を建てて高齢者等が住みやすい街にする、コンビニを建てて早朝・深夜帯の利便性を高めるなどの地域に足りていないもの、求められているもの、悩みを解決するものを提供すれば、 地域貢献につながるでしょう。
3.土地活用の主な種類
土地活用の代表的な種類を紹介します。それぞれの土地の特徴や目的に合わせて、活用方法を選ぶことが大切です。
3-1.マンション・アパート経営
マンションやアパートを建築して入居者を募集し、家賃収入を得る土地活用の方法です。
利回りが高い物件であればそれだけ収入が増える収益モデルの活用方法で、不動産投資の手法として人気があります。
不動産経営は、入居者から安定した家賃収入を得やすく建物によっては多額の資金が必要です。しかし、金融機関から不動産投資ローンを受けて購入すれば、建築費用などの初期投資を抑えたうえで物件を建築することもできるでしょう。
不動産投資は、自己資金が少なくても融資を有効活用して物件建築にかかる建築費などを工面できるメリットがあり、少ない資金で大きなリターンが期待できます。
この効果を「レバレッジ効果」といいます。
例えば自己資金が1,000万円ある場合、自己資金のみで投資する場合と自己資金1,000万円+融資2,000万円で3,000万円の物件を購入するのでは、同じ利回りの場合、年間の収支が変わってきます。
利回りを8%とした場合、年間収支は以下のような違いが生じます。
・自己資金のみの場合:1,000万円×8%=80万円
・2,000万円の融資を受けた場合:3,000万円×8%=240万円
アパートやマンションを一棟所有して賃貸経営をしている場合は、一戸建てを所有しているのと同様に土地と建物どちらにも固定資産税と都市計画税が課せられます。
ただし、小規模住宅用地の特例で200㎡以下の部分においては固定資産税が課税標準額の1/6、都市計画税においては課税標準額の1/3と大幅に減額してくれる制度があるため、アパートやマンション経営をしたいけれど納める税金に不安がある人は小規模住宅用地の特例に該当するか否かチェックしておくと良いでしょう。
>>関連記事:「アパート経営完全ガイド|建築プラン立てから完成後の業務まで」
>>関連記事:「土地活用の選択肢でマンション経営を選ぶメリットとデメリットは?」
3-2.戸建て賃貸経営
戸建賃貸経営は一戸建ての物件を建築して貸し出し、家賃収入を得る土地 活用の方法です。
ファミリータイプの間取りが多く、ファミリー層は一度入居が決まると長い間住んでくれる傾向にあります。シェアハウスとしての選択肢も見込めるでしょう。 また、入居者を確保できれば中長期的に安定した収益を得やすくマンションやアパートよりも広い土地を必要としない特徴もあります。
長期的な安定収入を得ることができるというメリットがある一方、空室時には家賃収入を得られないデメリットもあります。
マンションやアパートを建てるほどの広い土地を所有していない人に向いています。
>>関連記事:「賃貸経営で戸建てを選ぶメリットとデメリットは?注目される理由」
3-3.賃貸併用住宅経営
賃貸併用住宅とは1つの建物を自宅用と賃貸用に分け、賃貸用の部分を貸し出す住居のことです。
賃貸物件と自宅を別々に建てるより、建築費を安価にできるメリットがあるほか、住宅全体の面積のうち、居住部分が50%以上を占めていれば、不動産投資ローンより金利が低い住宅ローンを適用できる場合があります。
(金融機関によっては適用できないケースもあります)
賃貸部分で得た家賃収入で自宅のローン返済ができるため、限られた土地を有効利用できる魅力的な活用法といえるでしょう。
ただし、オーナーと入居者の距離が近いため、プライバシー問題や生活音などお互いが気を遣ってしまったり、マナーの悪い方が入居すると近隣トラブルに発展したりする可能性があります。
トラブルにならないためには、賃貸部分とオーナーの居住部分の間取りを検討することが大切です。生活動線が被らないようにするのも良いでしょう。
>>関連記事:「賃貸併用住宅とは?賃貸部分を設けるメリットや建築するまでの流れ」
3-4.月極駐車場経営
駐車場経営は比較的初期費用を抑えて始めることができ、管理の手間もそれほどかからない土地活用の方法です。
初期費用を抑えることができ建物がない分、将来他の業態に変更できる柔軟性もメリットの一つです。
しかし毎月の賃料がマンションやアパートなどの家賃に比べれば安価なため、収益性が低いことがデメリットといえます。
ローリスク・ローリターン月極駐車場経営はできるだけコストを抑えて手間のかからない土地活用をしたい人に向いていると言えるでしょう。
>>関連記事:「駐車場経営とは?」
3-5.コインパーキング経営
コインパーキング経営は月極駐車場と異なり時間貸しで車の出入りによって収入を得る方法です。
駅前や繁華街など、人の流入が多いエリアでは収益が見込めるメリットがあります。
建物を建てたり入居者と契約を締結したりすることもないため、経営のハードルが低く手軽に始められるでしょう。
一方で機材の導入で初期費用がかかるほか、集客が立地に大きく左右され収入が安定しにくいデメリットがあります。
コインパーキング経営は駅近や駐車場のない商業施設の近隣などの土地が向きますが、手間のかからない土地活用をしたい人にも向いている方法です。
>>関連記事:「土地活用で駐車場経営をする方法|月極・コインパーキングの特徴は?」
3-6.駐輪場経営
駐輪場経営とは、自転車やバイクを安全に駐輪できるスペースを提供し、利用者から料金を得る土地活用の手段です。駅周辺や商業施設の近く、住宅街といった需要の高い場所に駐輪場を設置し、時間貸しや月極契約で運営します。
駐車場と比べてイニシャルコストが少なく、狭小地や変形地といった他の活用が難しい土地でも始めやすいのがメリットといえるでしょう。
また、無人管理システムを導入すれば人件費を抑えられ、安定した収益が見込めます。土地を有効活用できる点も魅力の一つです。
>>関連記事:土地活用における駐輪場経営とは?メリットやデメリット、運営の手順
3-7.トランクルーム経営
保有する土地の敷地内にトランクルームを設置して賃貸する経営方法です。
契約者は自分の荷物を保管するスペースを増やすためにトランクルームを利用します。
近年、都市部を中心に住居スペースの狭小化や収納スペース不足により、自宅に置けない荷物をトランクルームに預ける人が増加傾向にあります。
また、普段使わない物はなるべく自宅とは別の場所に置いておきたいと考える人が、季節物の衣類などを収納するために使うこともあるようです。
あるいは、自宅には置ききれない趣味のコレクションを保管する場所として活用する人もいます。 一般の消費者に限らず、企業が、資材置き場やオフィスに置けない備品置き場として利用するケースもあるため、幅広いニーズが存在します。
比較的場所を選ばず始めることができ、専門業者に土地を一括借り上げしてもらう場合はトランクルームを購入する初期費用が抑えられるメリットがあるため、初期投資額を抑えて土地活用をしたい人に向いているといえます。
>>関連記事:「トランクルーム経営の基本と特徴」
3-8.コインランドリー経営
土地の敷地内に建物を建ててランドリー本体などの設備を設置し、利用者から支払われる利用料で経営をする土地活用の方法です。
利用者は継続的に利用する可能性が高くランニングコストがあまりかからないメリットがあるので、比較的安定した土地活用の方法といえます 。
設備の導入に費用がかかる点はデメリットですが、固定資産税の費用を賄える程度の収入があれば十分な人や、副収入として少額でも安定性を目的とする人に向いています。
>>関連記事:「コインランドリーの経営とは?メリットやデメリット、おすすめの人」
3-9.ビジネスビル経営
ビジネスビル経営はオフィスビルを思い浮かべるとイメージしやすいでしょう。
所有している土地にビルを建設し、企業に貸し出し収益を得る方法です。
アパートやマンションと違い住居系ではないため、部屋数あたりの賃料を高く設定できる メリットがあります。
しかし狭小地のような土地では建てることはできず、建物面積が膨大になるケースが多いため、メンテナンスコストが高額になることや空室が出た場合の金額が大きいことがデメリットとして挙げられ、テナント需要の見極めや継続的なテナント誘致が重要です。
>>関連記事:「土地活用でビルを経営するメリットは?経営に向いている土地の特徴」
3-10.テナントビル経営
テナントビル経営は、店舗を誘致するためのビルまたは建築用の土地を事業者に貸し出す(事業用定期借地権)土地活用の方法です。賃料収入を得られるため、長期的な資産運用に適しています。特にロードサイド型のテナントビルは、飲食店や小売店向けに需要が高く、安定した収益が期待できます。
しかし、初期投資が大きく、空室リスクがある点には注意が必要です。契約期間の管理や、テナントの業種による売上の変動も考慮するべきポイントとなります。
ビルまたは土地を貸し出して収益を得るという点ではビジネスビルと大きな違いはありません。ただし、テナントビルは主に消費者向けの店舗や施設を誘致します。したがって適している立地やビルの規模が異なります。
>>関連記事:土地活用でテナント経営を選ぶメリットやデメリットは?
3-11.商業施設・店舗経営
建物にレストランやショッピングセンター、ドラッグストアなどの地域の需要に合わせたテナントに貸し出すことで、大きな利益が期待できるメリットのある土地活用の方法です。
商業ビルとなればビルを建てて飲食店や小売店などのテナントに貸し出すため、長期間安定した収入を得られることもメリットです。
一方でビルを建てるとなれば戸建てやアパートとは異なり大規模になるため、初期費用が高額になることやテナント1軒ごとの家賃が大きいため、退去発生の際は急激な収入減となるデメリットがあります。
>>関連記事:「土地活用で商業施設を選ぶメリットは?向いている土地の特徴」
3-12.ホテル経営
ホテル経営は、都市部や観光地に適した土地活用の一つです。ビジネスホテルやリゾートホテルなど、ターゲット層に応じた施設を計画することで、高い収益を見込めます。特に、等価交換やリースバック方式を活用すれば、自己資金を抑えながら経営を進めることも可能です。
ただし、運営には専門的なノウハウが必要であり、固定費や運営コストがかかるため、慎重な事業計画が求められます。また、地域の法律や規制に従った建築が必要です。
>>関連記事:土地活用でホテル経営を選ぶメリットと具体的なステップ
3-13.ガレージハウス経営
車を停められるガレージを併設する賃貸住宅を経営する方法です。
ガレージハウスは「ビルトインガレージハウス」とも呼ばれ、賃貸需要が立地にあまり左右されない点が特徴です。
入居者は主に車での移動を前提とするため、駅から遠いなど立地条件があまり良くないエリアでも困らないためです。
通常の賃貸住宅では経営の難易度が上がりそうな場所も、ガレージハウスなら一定の需要が期待できるでしょう。
>>関連記事:「ガレージハウスの経営とは?メリット・デメリットや始めるまでの流れ」
3-14.シェアハウス経営
入居者の部屋とはべつに共同利用するスペースを持つ賃貸住宅を経営する方法です。入居者それぞれに部屋は設けられていますが、リビングやキッチン、トイレ、バスルームなどの部屋や設備は共同で利用するため、同じ広さの賃貸物件と比較して戸数を多めにできるメリットがあります。
シェアハウスのターゲットは主に単身者で、特に学生などの若者に人気があるため、若者が集まるエリアで高い賃貸需要が見込めるでしょう。
>>関連記事:「シェアハウスの経営とは?メリット・デメリットや向いている土地」
3-15.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)経営
高齢者向けの賃貸住宅経営でマンションやアパートと同様に入居者からの賃料で経営をする土地活用の方法です。
一般的な賃貸住宅とは異なり安否確認や生活相談など、高齢者向けサービスが受けられるのが特徴です。
サ高住は一定の要件を満たすことで補助金や税制優遇を受けることができ、サ高住を建てる場合は立地条件が限定的ではなく比較的郊外や田舎でも活用しやすいのがメリットといえます。
一方で「床面積が25㎡以上」、「トイレや洗面設備の設置」といった満たすべき要件があるため、初期投資額が大きくなることや設備が高齢者向きの設備であることから転用性が低い デメリットがあります。
一部屋あたりの面積が広くなるため、広大な土地を保有しているオーナーに向いているでしょう。
>>関連記事:「サ高住を経営するメリットは?利用できる補助制度と税の優遇制度」
3-16.デイサービス経営
デイサービスとは、要介護状態にある高齢者が、日帰りで介護職員などによる入浴、食事、機能訓練などのサービスを受ける施設のことを指します。
デイサービス経営は、高齢化が進む社会において需要が増している土地活用の方法です。介護保険制度を活用し、安定した収益を確保しやすい点がメリットとなります。
また、高齢者施設やグループホームと連携することで、地域に貢献しながら事業の継続性を確保できます。
ただし、介護スタッフの確保や、運営に関する法的な対応が必要となるため、事前に専門家の助言を受けることが重要です。
>>関連記事:土地活用でデイサービスが向いているケースは?メリットやデメリット
3-17.福祉施設経営
福祉施設経営は、障がい者支援や児童福祉施設などを建築し事業者に賃貸する方法で、多様な形態が考えられます。
土地信託を活用することで、資金調達の負担を軽減しながら事業を展開できる可能性もあります。メリットは社会的意義が高く、自治体からの補助金などを受けられる場合がある点です。
しかし、施設の敷地面積や高さ制限など、建築に関する制限が多い点には注意が必要です。
>>関連記事:土地活用で福祉施設を運営するメリットやデメリットは?
3-18.介護施設経営
介護施設経営は、老人ホームやグループホームの運営を含み、高齢者向けの住環境を提供する土地活用の一つです。
安定収入が見込めるため、不動産投資の選択肢として魅力的です。
>>関連記事:土地活用で介護施設を選択するメリット・デメリットやポイント
3-19.医療施設経営
病院や診療所を建てて土地と建物を貸すか土地を貸す土地活用の方法です。
病院と診療所の違いですが、20床以上の入院用ベッドがある医療施設のことを病院と言い、入院用ベッドが19床以下の医療施設を診療所と言います。
社会貢献度や地域貢献度が高く、医療施設は需要が多く生きるうえで必要不可欠の施設・機関であるため、長期的な安定収入が期待できます。
【出典】「医療施設の類型」(厚生労働省)
ただし、病院は第1種2種低層住居専用地域と工業地域、工業専用地域には建築が不可であること、さらに特殊な施設となるため転用が難しく流動性が低いことがデメリットです。
病院は交通の便が良いこと、近隣に住宅が多いなど利用者が利用しやすい立地で長期的な安定収入を目的とする人に向いているでしょう。
>>関連記事:「土地活用で病院を選ぶメリットは?向いている土地の特徴」
3-20.保育園経営
事業用定期借地権を利用し保育園の土地を貸して収入を得るか、建物を建設したうえで土地と建物を貸すことで収入を得る土地活用の方法です。
保育園の場合、建物の建設費用に対して自治体からの補助金が期待できます。
社会貢献もでき、自治体にもよりますが東京都の場合は土地について固定資産税と都市計画税が5年間免除になることが条例で定められています。
保育園の開園は自治体の審査を含め2年~3年かかる場合があるため、開園までの期間は土地活用ができないことがデメリットです。
開園までの期間、自己資金や時間に余裕があり、安定収入を得ることを目的とする人には向いています。
>>関連記事:「土地活用に保育園を選ぶには?主な運営方式やメリットとデメリット」
3-21.コンビニエンスストア経営
土地の所有者が建物を建てて賃貸する方法と、コンビニ経営する業者が土地を借りて建物を建てて運用する方法です。
集客ができなければ失敗する可能性が高いため、道路沿いや宿泊施設の多い場所など交通量が多い場所で経営する必要があります。
そのため、場所が限定的であることが 注意点として挙げられます。
コンビニは住宅関係の建物に優遇される措置が適用外となるため、節税効果ではなく適切な土地を保有していて安定した土地のみの賃貸収入を得る目的である人に向いています。
>>関連記事:「土地活用でコンビニを選ぶメリットとデメリット|向いている土地の傾向」
3-22.太陽光発電の設置
敷地内に太陽光発電システムを設置し、売電収入を得る活用方法です。
「固定価格買取制度(FIT)」という10年~20年程度の期間、買い取り費用が保証される制度があるため、安定した収益を得やすい特徴があります。
経年劣化による発電効率の低下や室外設置のため外的要因からの破損による修繕費がかかるデメリットがありますが、安定収入を目的としたい人に向いています。
>>関連記事:「土地活用で太陽光発電を選ぶメリットは?向いている土地の特徴」
3-23.自動販売機の設置
自動販売機を設置して売れた商品の収益を得る方法です。
かかるコストが比較的低く、管理の手間がかかりにくいので、気軽に始めやすい特徴があります。
また、狭い土地でも実施でき、ほかの土地活用法と併用できる点もメリットといえるでしょう。
ただし、単価が低い分、大きな収益は上げづらいのがデメリットです。
>>関連記事:「土地活用で自動販売機を選ぶメリットとデメリットは?設置できる場所」
3-24.土地貸し
保有している土地のみを貸す土地活用の方法です。
借地利用者である賃借人から地代家賃を得ることができます。
例えば遊休地を保有しているオーナーは、その土地を貸し出せば清掃などの管理も賃借人に任せられるようになるので、収益化できるうえに管理の負担を軽減できるメリットがあります。
土地貸しの契約は「普通借地契約」と「定期借地契約」の2種類に分けられます。
それぞれの違いを簡単にまとめると、次の通りです。
【普通借地契約】
更新を原則とした契約。存続期間は30年以上。
【定期借地契約】
更新がなく契約期間満了時に更地で返却することを条件とした契約。
一般定期借地権の存続期間は50年以上。
事業用定期借地権は、10年以上50年未満。
建物譲渡特約付借地権は、30年以上。
※存続期間を定めなかった場合は30年になる。
事業用定期借地権を除くと、存続期間が30年以上と長期にわたるため、近い将来転用を考えている場合はデメリットになります。
>>関連記事:「土地貸しのメリットと注意点とは?」
3-25.土地の売却
土地売却して現金化する方法であり、まとまった資金が得たい場合などに有効です。
また、土地を売却すれば固定資産税や維持管理費などのランニングコストも軽減できるメリットがあります。
また、土地を手放せば相続時の相続税負担もなくなるので、もし収益化できる見込みのない土地であれば、売却により税金負担を抑えることが可能です。
一方で土地を売却して得た利益に対しては譲渡所得税がかかります。
<譲渡所得税>
|
土地の所有期間が5年以下 |
譲渡所得税:39.63% |
| 土地の所有期間が5年超 | 譲渡所得税:20.315% |
このように土地の売却は売却後の税金が高額になる場合があるため、注意が必要です。
一方、管理の手間を省きたい方や売却して得た現金の使い方が明確になっている方にとっては向いている方法といえます。
ここまでご紹介した土地活用法の特徴を踏まえ、収益性や安定性などの項目を◎◯△☓の4段階で種類別に評価します。
※なお、あくまで一般的な評価であり、立地や建物の状態など条件によって大きく変わる場合もあります。
|
収益性 |
安定性 |
転用性 |
固定資産税対策 |
相続税対策 |
|
|
マンション・アパート経営 |
◎ |
◎ |
✕ |
◎ |
◎ |
|
戸建て賃貸経営 |
◯ |
◯ |
△ |
◎ |
◎ |
|
賃貸併用住宅経営 |
◯ |
◯ |
◎ |
◎ |
◎ |
|
月極駐車場経営 |
△ |
△ |
◎ |
△ |
△ |
|
コインパーキング経営 |
△ |
✕ |
◎ |
△ |
△ |
|
駐輪場経営 |
△ |
△ |
◎ |
△ |
△ |
|
トランクルーム経営 |
△ |
✕ |
◎ |
△ |
△ |
|
コインランドリー経営 |
◯ |
✕ |
◎ |
△ |
△ |
|
ビジネスビル経営 |
◯ |
△ |
◯ |
△ |
◯ |
|
テナント経営 |
◯ |
△ |
△ |
△ |
◯ |
|
商業施設・店舗経営 |
◯ |
△ |
✕ |
△ |
◯ |
|
ホテル経営 |
◯ |
△ |
✕ |
△ |
◯ |
|
ガレージハウス経営 |
◯ |
◯ |
✕ |
◯ |
◯ |
|
シェアハウス経営 |
◎ |
△ |
✕ |
△ |
△ |
|
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)経営 |
◯ |
◎ |
✕ |
△ |
◯ |
|
デイサービス経営 |
◯ |
◎ |
✕ |
△ |
◯ |
|
福祉施設経営 |
◯ |
◎ |
✕ |
△ |
◯ |
|
介護施設経営 |
◯ |
◎ |
✕ |
△ |
◯ |
|
医療施設経営 |
◯ |
◎ |
✕ |
△ |
◯ |
|
保育園経営 |
◯ |
◎ |
✕ |
△ |
◯ |
|
コンビニエンスストア経営 |
◯ |
△ |
✕ |
△ |
◯ |
|
太陽光発電の設置 |
△ |
△ |
△ |
✕ |
✕ |
|
自動販売機の設置 |
△ |
△ |
◎ |
✕ |
✕ |
|
土地貸し |
- |
- |
- |
◯ |
◯ |
|
土地の売却 |
- |
- |
- |
◎ |
◎ |
収益性は複数の入居者から家賃収入が得られるマンションやアパート経営がもっとも有利といえるでしょう。
また、シェアハウスも1つの建物を複数の入居者に賃貸するため、建物の規模に対する家賃収入の割合が大きめになる傾向があります。
安定性も同じく入居者が複数で空室リスクの少ないマンションやアパート経営が有利です。
一方、サ高住、医療施設、保育園なども比較的利用者が離れにくいため、安定収入になりやすいでしょう。
転用性は賃貸併用住宅の場合、賃貸部分を通常の住居に戻し、自宅として転用しやすいという点で有利といえます。
また、月極駐車場やコインパーキングのように建物を建築しないタイプの土地活用は、建物を解体したり改修したりする必要がないため、転用しやすいでしょう。
最後に固定資産税、相続税などの税金対策としては、住宅用地の特例を適用できる住宅系の土地活用がおすすめです。
4.土地活用の進め方
土地活用は手順を踏んで進めていくことが大切です。
土地活用で成功するためにも手順を理解して進めていくことをおすすめします。
Step1.土地活用の相談
初めに行うことは相談です。 土地活用のプロである不動産会社や建設会社などに相談しましょう。
相談する段階ではどの土地活用を行うか決まっていなくても問題ありませんが、相談の内容を明確にしておくことは大切です。
自分に合った土地活用方法の提案やアドバイスしてもらうためには、評判や口コミなどが良い業者へ相談することも大切ですが、土地活用の目的や要望について考えておくことが大切です。 複数社と比較してもよいでしょう。
相談は無料の業者が多く、相談を通して土地活用に対する具体的なイメージやプランを固めていきます。
相談する前に 所有している土地の用途地域、建物を建てる場合は建築基準法で定められている建ぺい率や容積率を調べておくとベストです。
Step2.土地の診断
土地活用の相談の次に、オーナー自身が所有する土地の実測調査をします。
調べる項目は土地の地耐力や周辺状況などが挙げられますが、土地の状況によっては実施できる土地活用が限られる場合もあるため、土地の診断は活用方法の選定上、 重要な工程といえます。
Step3.需要の調査
実際に建築した建物や施設を利用する人がいるかどうか シミュレーションします。
土地活用でアパート・マンション経営を考えている人は、特に周辺地域の利便性や人口の推移などから適切に収益を上げられるかどうか調べることが重要です。
また、マンションやアパートの場合は周辺物件の有無や競合となる近隣の賃料相場も調査することで適切な家賃設定の判断ができるでしょう。
Step4.経営計画の立案
需要の調査が終わればどのような土地活用方法が適しているのか見えてくるでしょう。
賃貸マンションやアパート経営を選択した場合、プランの提案を受けて経営計画を立てていきます。
例えば、金融機関からいくら融資を受けて月々の収入からの返済はいくらなのか、月々の賃料収入から管理にかかるコストはいくらなのか、年間収入や実質利回りはどのくらいかなど、収益シミュレーションしておくことをおすすめします。
Step5.建築計画の作成
経営計画の次は 建築計画の作成です。
建築計画は施工から竣工までのスケジュールや室内外の設備の導入日など工事にかかる全般を決めていきます。
設計が終わり工期が決まり見積もりが出れば次に契約へ進みますが、このタイミングで融資を組む場合は金融機関に審査を出しておくことをおすすめします。
Step6.工事実施・検査
具体的な経営計画と資金計画の目途が立ち、建築工事の内容やかかる費用に納得できたら契約を締結します。
契約後のトラブルを避けるためにも契約時に契約書の内容を必ず確認し、疑問点や納得できない文言があれば相談や質問をすることが重要です。
建物が完成すると専門業者が最終的に検査をします。工事実施の段階で入居者募集を始めても良いでしょう。
Step7.引き渡し・アフターサポート
建物が完成したら引き渡しです。建物管理や賃貸管理は設計・施工した専門業者にそのまま管理委託やアフターサポートを依頼するケースが一般的です。
管理会社選びはその後の経営にも影響してくるため 、長期でパートナーとして力になってくれる信頼できる専門業者を選ぶことが重要です。
5.土地活用で起こり得るリスク
どの活用法にもリスクは一定数存在します。
しかし、リスクを恐れるのではなく土地の活用法ごとのリスクを把握したうえで対策を考えることが重要です。
ここでは 特に検討される方が多い「賃貸アパートやマンション」の経営に該当する7つのリスクと対策を中心に解説していきます。
5-1.空室リスク
賃貸経営で収益を最も悪化させるのは、 空室状態が長く続くことです。
空室リスクは賃貸物件において特に考慮すべきリスクの1つといえます。
周辺の市場ニーズに合っていないことが空室の原因とされているため、事前の周辺環境や市場調査、土地の活用法の見極めが重要です。
5-2.賃料下落リスク
使用感の増加や設備の老朽化(経年劣化)が進行すると建物の価値が下がります。建物の価値低下に伴って賃料も下がることが一般的です。
経営計画を立てる際には、将来的に賃料が低下することを想定した収支シミュレーションを行い、長期にわたって経営ができることを見越した計画を立てることをおすすめします。
5-3.家賃の滞納リスク
空室を埋めるために入居審査を緩和すると、収入や貯蓄額、社会的信用などに不安のある入居者が増え、家賃滞納リスクが高まる可能性があります。
空室を埋めることは賃貸経営にとって重要なひとつですが、毎月安定した家賃収入を得ることが大切です。
入居者のリスクを回避するために信頼できる管理会社を見つけることをおすすめします。
5-4.金利上昇リスク
一括で土地活用にかかる費用を支払うのではなく、金融機関から融資(ローン)を受けているオーナーは金利上昇のリスクがあります。
低金利時代の日本ではその特性を生かして変動金利でローンを組んでいる人も多いのが実態です。
固定金利でローンを組んでいる人への金利上昇の影響は大きくはないものの、変動金利への影響は金利上昇に伴い月々の返済が上がり、家計を圧迫するなどの可能性が高いといえます。
金利上昇のリスクに対して考えられる対策は固定金利で金利変動の影響を軽減すること、借入時に自己資金を多くして借入金を減らしておくことなどが挙げられます。
また、景気や各金融機関の動向に目を配ることも大切です。
5-5.建物の修繕リスク
賃貸人であるオーナーには修繕する責任があります。
アパート・マンション経営では建物や設備などの計画的な修繕や地震や事故などの偶発的破損による修繕が必要になる可能性もあります。
経年劣化のみ視野にいれるのではなく、計画的な修繕積立金の確保をおすすめします。
5-6.自然災害リスク
日本は地震大国と言われるほど地震の多い国です。
災害に対しては火災保険や地震保険などに加入することで対策は万全だと判断している人は多いのではないでしょうか。
しかし、災害の状況によっては保険が適用されない場合もあるため、建物を建てる前に地盤補強や改良、ハザードマップなどで災害リスクのある立地では土嚢など備えておくなど対策をしておくことをおすすめします。
5-7.管理会社の倒産リスク
動産管理会社は毎月管理手数料を得るため、安定した収入があります。
しかし管理会社が倒産する可能性はゼロではありません。
管理会社が倒産すると入居者が管理会社に支払った家賃や退去時に精算する預り金などが回収できなくなる可能性があります。
たとえ管理会社に資産や資金が残っていたとしても倒産し、さらに破産手続きが進んでいると管理会社の財産は破産管財人の管理になるため、優先度の高い税金から支払いを進めていくのが一般的です。
そのため、オーナーへの未回収賃料が回ってこない可能性が高くなります。
管理会社からの家賃送金の遅延や未払いが発生したら要注意です。倒産する予兆を逃さずに早めに管理会社を変更するなど選び方も含め対策を打つことをおすすめします。
6.どの土地活用に挑戦するか迷ったときは
土地活用の方法や種類、手順を説明してきましたが、どの土地活用に挑戦するか迷う人も多いのではないでしょうか。
その場合は最初に情報取集をすることや土地活用の目的を明確にすることから始めると、自分に合った土地活用の方法が見えてきます。
6-1.土地活用の目的から選ぶ
土地活用にはさまざまな目的があります。
例えば収益の獲得、相続対策、資産形成、地域の発展、社会貢献など人によって目的はさまざまです。
目的別に適した活用法と適さない活用法があるため、目的を決めたうえでどの活用方法が選択肢としてあるのかを知ることが大切です。
6-2.セミナーに参加して情報収集をする
土地活用にも不動産投資や老後資金などのセミナーのように専門家や土地活用を行う会社などが主催するセミナーがあります。
セミナーに参加するメリットは最新の情報や当事者が知る情報をキャッチアップできることです。
セミナーには必ず講師の人がいて成り立つため、講師の人に直接質問できる貴重な機会であることもポイントです。
近年ではオンライン形式で参加できるセミナーもあるため、自分の生活スタイルにあった参加方法を選びましょう。
セミナーの主催者や講師がメルマガを運営していることも多いため、メルマガ登録すればセミナー後も継続的に情報収集ができるため、検討材料のひとつとしてチェックしておくことをおすすめします。
6-3.専門家や担当者に相談する
初めて土地活用を検討する人にとって、数ある手法からベストなものを選ぶことは簡単ではありません。
そのため、不動産投資や土地活用の専門家に相談を受けることがおすすめです。
現場でさまざまな土地活用を行っているため、適切な提案や役立つアドバイスをもらえるでしょう。
また、相談をすることで土地活用の知識が身についたり、成功例、失敗例などの事例を多く知ったりできます。
自分自身の知識向上のためにも、わからないことは積極的に問い合わせ、アドバイスを受けることをおすすめします。
7.土地活用に関する疑問
7-1.人の往来が多くない場所でも土地活用はできますか
土地活用の方法さえ選べば可能です。
例えば太陽光発電は日当たりが重要であり、人の往来が影響することはありません。
なお、人口が少ない地域では都市圏と比較して有効な土地活用の方法が異なるので、土地周辺の需要を見極めがより重要になってきます。
7-2.どのような目的で土地活用される人が多いですか
土地にかかる税金の対策がしたい、副業収入を得たい、老後に向けて資産形成をしたいなど、目的は人によってさまざまです。
目的によって適した土地活用法は異なるので、不動産会社などに相談し、ご自身に合った方法を提案してもらうことをおすすめします。
7-3.比較的短期間で実施できる土地活用の選択肢はどれですか
月極駐車場やコインパーキング、トランクルームなどが候補として挙げられます。
上記の土地活用法は、始めるにあたって必要な施設が少ないためです。
ただし、いずれも高収益を上げるのは難しい方法なので、大きく収入を増やしたい場合、時間やコストはかかりますが、アパートやマンション経営など、別の方法を検討することをおすすめします。
また、事前準備や許認可の確認や手続きにかかる時間は、どの方法でも大きくは変わらないのが実態です。
7-4.始めるにあたってどのような費用がかかりますか
活用方法によって必要な初期費用は異なります。建物や施設を建設する土地活用の場合、本体工事費として建物の建築費用が発生します。
また、杭工事や地盤改良を行うための建物附帯工事費、設備の取り付け費用などを行うための外構工事費も考慮しなくてはなりません。
さらに、倉庫やコワーキングスペースなど、施設の種類によっては特有の設備投資が必要になるケースもあります。
>>関連記事:土地活用にかかる初期費用とは?資金調達の方法やポイント
7-5.どのような方法が自分の土地に適しているのかわかりません
市場調査(マーケティングリサーチ)を行い、どのようなニーズがあるかを把握して方法を決めるのがよいでしょう。
市場調査では、土地が位置する地域の需要と供給、土地の周辺環境などを調べます。自分で行うこともできますが、市街化調整区域や都市計画法の規制により、活用できる方法が制限されることもあるため、調査のノウハウがある不動産会社や建築会社に任せるのがおすすめです。
>>関連記事:土地活用のためのマーケティングとは?行う目的や調査項目
7-6.田舎のような場所にある土地はどのような活用法がありますか
介護施設、太陽光発電、キャンプ場など、都市圏と比べて人口が少ない地域では求められる建物や施設が異なります。
例えば、貸し農園や市民農園を開設し、地方の農地を活用する方法も考えられます。また、トレーラーハウスを活用した宿泊施設や、ロードサイドでのレンタルスペース経営も有効です。土地の特性を生かした活用方法を選定すれば、高い収益を見込める可能性もあります。
田舎の土地活用に関しては以下の記事でも詳しく説明しています。
>>関連記事:田舎の土地活用9選|活用法の特徴や成功させるためのポイントは?
8.所有する土地に適した土地活用法を考えよう
土地活用の方法と進め方などをメリットデメリットとあわせて解説してきました。
土地活用にはさまざまな方法があり、それぞれの目的によってどの方法が適切か判断することが大切です。
実際に土地活用を行う際は、所有する土地に適した土地活用法は何か、専門家の意見も聞きながら、慎重に検討する必要があります。
また、市場調査を行ったうえで、収支シミュレーションをしっかりと立て、利益が得られる見込みがあるかどうかのチェックが重要です。
事業開始までのスケジュール確認など、事前準備も怠らないようにしましょう。
土地の収益化や税金対策などで土地活用を検討している人は資料請求や比較サイトなどを利用しつつ気軽にノウハウと実績のある専門業者へ相談することから始めることをおすすめします。
■監修者プロフィール
宅地建物取引士/FP2級
伊野 文明
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。
【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング