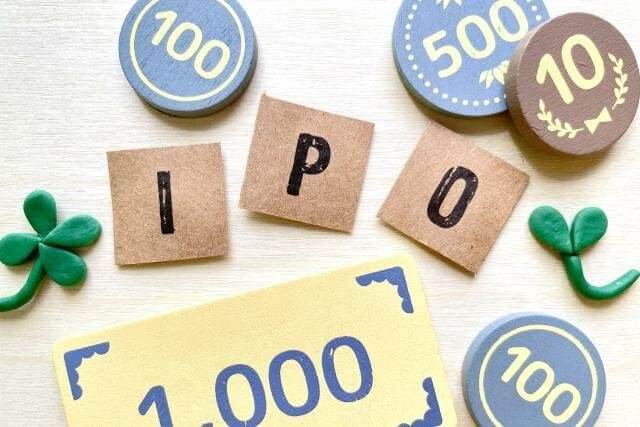土地活用にかかる初期費用とは?資金調達の方法やポイント
公開日: 2025.03.27
最終更新日: 2025.09.17
土地活用とは、利用していない土地を有効活用し、利益を得ることを指します。賃貸経営や駐車場経営、テナント経営など、さまざまな活用方法がありますが、いずれの方法を選ぶにしても初期費用が発生する点を理解しておくことが重要です。
特に、建物の建築費や造成費、諸費用などの負担が大きいため、資金調達方法やコスト管理の知識を持つことが成功の鍵となります。
本記事では、初期費用の種類や資金調達の方法について解説します。
1. 土地活用にかかる初期費用にはどのようなものがある?
土地活用を始める際には、活用方法によって必要な初期費用が異なります。
これらを理解し、事前にどのような費用が発生するのかを把握し、資金計画を立てることが、スムーズな運用と収益性の確保につながります。
1-1. 本体工事費
本体工事費とは、建物の建築費用を指し、土地活用の方法によって大きく変動します。
例えば、アパート経営やマンション経営では、建物の構造や規模によって費用が異なり、鉄骨造やRC造などの耐久性が高い構造を選ぶとコストが増加します。
また、建物の規模が大きくなるほど工事の範囲が広がり、費用も高額になりやすいため、収益性とのバランスを考慮した計画が必要です。
適切な建築プランを選択することで、無駄なコストを抑えながら安定した賃貸収入を確保できます。
1-2. 建物附帯工事費
建物附帯工事費とは、建物を建築する際に必要となる基礎工事や補助工事の費用を指します。
特に、杭工事や地盤改良工事は、土地の状態によって必要になることがあり、地盤が弱い場合には追加の補強工事が発生するため、コストが高くなる可能性があります。
1-3. 外構工事費
外構工事費とは、建物の外周部分に関わる工事費用を指します。具体的には、塀やフェンス、駐車場の整備、庭の造成などが含まれます。
また、照明設備や看板の設置といった視認性や利便性を向上させる工事も必要になるケースがあります。
外構工事は、物件の競争力を左右する要素の1つです。駐車場やエントランス付近の見た目や使いやすさは、入居者の満足度に影響します。
さらに、物件の第一印象を高めるために、エントランス周りのデザインを工夫することも重要です。
植栽や外灯を適切に配置し、清潔感や高級感を演出すれば、より周辺の競合物件との差別化が図れます。
1-4. その他の工事費
土地活用を進める際には、本体工事費や外構工事費以外の工事費も発生します。
例えば、既存の建物がある場合には更地にする必要があるため、建物の解体費用がかかります。
1-5. その他諸費用
新築を建てるときは所有権保存登記や建物表題登記といった登記費用が発生します。
さらに、万が一のリスクに備えるために火災保険や地震保険への加入も重要です。
特に賃貸経営やマンション経営を行う場合、入居者の安心を確保するためにも、適切な保険選びが求められます。
こうした諸費用は、初期投資の一部として資金計画に組み込むことが重要です。
なお、土地活用の初期費用の分類やその内訳の項目については、見積する業者や建物によって異なることも覚えておきましょう。
2. 土地活用にかかる初期費用の資金調達の方法
土地活用を始めるには、まとまった初期費用が必要なのは間違いありません。
ただし、自己資金だけでなく、融資や補助金などさまざまな資金調達方法を活用することで、資金的な負担を軽減することも可能です。
ここでは、資金調達の主な選択肢について解説します。
2-1. ローンを利用する
土地活用の資金調達方法として、金融機関の不動産投資ローンを利用するのが一般的です。
アパート経営などでは「アパートローン」と呼ばれており、収益を生む不動産全般に適用可能でマンション経営やテナント経営にも活用できます。
また、不動産ローンの大きな特徴は、購入する土地や建物を担保として借り入れができる点にあります。
これにより、初期投資の負担を抑えながら事業を進められるのがメリットです。なお、活用方法によっては住宅ローンを利用できるケースもありますが、適用範囲は限定的なので、事前の確認が必要です。
自己資金のみでアパート経営を行うよりも、ローンを活用して規模を拡大すれば、より多くの家賃収入が見込みやすくなるというわけです。
ちなみに、 ローンを利用するとレバレッジ効果を活かすことができます。
レバレッジ効果とは、自己資金だけでなく借入金を活用することで、より大きな資産を運用し、収益性を高めることを指します。
2-2. 補助金を申請する
土地活用の初期費用を抑える方法として、補助金の活用が挙げられます。
補助金を受けられるかどうかは土地活用の方法によって異なり、対象となる事業を選ぶことが重要です。
例えば、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を建築する場合、国の制度を利用すれば建築費の10分の1の補助金が受けられます。
ただし、支給額は「建築費の10分の1」または「一戸当たりの補助金限度額」のいずれか小さい方が適用されます。
ちなみにサ高住とは、高齢者が自由度の高い生活を送りながら、安心して暮らせるよう設計された特徴を持つ住宅形態のことです。
また、認可保育園を建設する場合、国や自治体から建設費や運営費に対する補助が受けられるため、長期的な運営を見据えた資金計画を立てることが重要です。
補助金制度を上手に活用することで、初期投資の負担を軽減し、資産価値を高めることができます。
3. 土地活用にかかる初期費用の資金調達のポイント
初期費用の資金調達では、負担を抑えつつ、無理のない計画を立てることが重要です。
ローンの活用、自己資金のバランスを考慮し、収益性の高い運用を目指すためのポイントを解説します。
3-1. 綿密に資金計画を立てる
土地活用を成功させるためには、収益計画や資金調達方法を検討し、収入と支出を試算した綿密な収支計画を立てることが重要です。
その際は初期費用だけでなく、維持管理費や税金、ローン返済額などのコストも考慮し、長期的な収益性を確保できるかを慎重に判断する必要があります。
また、自分だけで進めるのが難しい部分は、信頼できる会社に相談することも一つの選択肢です。土地活用の実績があり、適切なアドバイスを提供できる専門会社と連携することで、リスクを抑えながら適切な活用プランを検討できます。
3-2. 資金計画はさまざまなケースを想定しておく
土地活用を進める際は、将来の資金需要も考慮し、柔軟な資金計画を立てることが重要です。
例えば、急な入院費用や老後の生活資金など、予期せぬ支出が発生する可能性があり、資金が不足すると事業運営に影響を及ぼすことも考えられます。
また、事業環境の変化に備えることも重要です。
例えば、賃貸需要の変動や金利の上昇、税制改正といった外部要因によって、当初の収支計画が大きく変わる可能性があります。
こうした変化に対応できるよう、想定よりも余裕を持った資金計画を立て、もし急な支出が必要になった場合でも資金繰りが安定するように準備しておくことが大切です。
3-3. ローンを利用する場合にも自己資金を用意しておく
土地活用のためにローンを利用する場合でも、最低でも初期費用の1~2割程度は自己資金を用意しておくのが理想です。
自己資金がほとんどない状態では、金融機関の審査が厳しくなり、希望する融資額を借りられない可能性が高くなります。
また、自己資金があることで、もしもの際のリスクヘッジにもなります。
例えば、予期せぬ修繕費用や入居率の低下による収益減少が発生した場合でも、自己資金があれば資金繰りに余裕を持たせることができます。
安定した資金計画を立てるためにも、自己資金の準備を怠らないことが重要です。
4. 【土地がある人向け】資金がなくても土地活用を始める方法
初期費用にあてる十分な資金がなくても、所有する土地を活用して資金負担を抑えながら土地活用を始める方法があります。
代表的な方法として、以下の3つが挙げられます。
・土地信託
・等価交換方式
・定期借地権
4-1. 土地信託
土地オーナーが土地活用のプロである信託会社に土地を委託し、運用を任せる方法です。
信託会社が建物を建築・管理し、得られた収益の一部がオーナーに分配されるため、初期費用をかけずに土地活用を行うことが可能です。
ただし、どのような土地でも信託できるわけではなく、信託会社が「収益性がある」と判断した土地でなければ契約できません。
また、収益が少ない場合はオーナーに還元される配当金も少なくなるため、必ず安定した収益が得られるとは限らない点は注意しましょう。
4-2. 等価交換方式
土地をディベロッパーに提供(売却)し、ディベロッパーが建物を建築する方式です。
オーナーは土地の一部を手放す代わりに、建物の一部(マンションの区分所有など)を取得できるため、自己資金ゼロで建物を保有できるメリットがあります。
一方、等価交換方式で得た建物は、ディベロッパーとの共有状態になるため、将来的に売却や担保設定を行う際に制約が生じる可能性があります。
また、税制上の特例が適用される一方で、減価償却できる額が小さくなる点には注意です。
4-3. 定期借地権
所有する土地に定期借地権を設定し、第三者に貸す方法です。
オーナーは地代を受け取りながら、土地の所有権を維持できます。
基本的には契約期間満了後は更地で返還されるため、将来的な土地の有効活用にもつなげられます。
ただし、定期借地権の契約は長期間になります(一般定期借地権では50年以上)。その間に他の収益性の高い活用方法が見つかっても、自由に活用方法を変更することはできません。
また、土地に対する固定資産税と都市計画税はオーナーが納めることになります。
今回紹介した方法を活用すれば、資金がなくても土地を元手に活用を始めることが可能です。
各方法のメリット・デメリットを理解し、適切な活用プランを検討することが重要です。
5. 土地活用の初期費用と資金調達のポイント
土地活用には、さまざまな初期費用が発生します。
これらの費用を適切に管理し、安定した運用につなげるためには、資金調達の選択肢を把握しておくことが大切です。
主な調達方法としては、不動産投資ローンの活用が一般的で、土地や建物を担保に入れることでレバレッジ効果を活かし、少ない自己資金でも大きな資産を運用することが可能です。
また、補助金制度を利用し、初期費用の一部を補填できる場合があります。
自己資金が乏しい場合は、土地信託や等価交換方式、定期借地権などを活用することで、資金負担を抑えながら土地活用を進めることもできます。
土地活用を成功させるためには、事前に収支計画を立て、無理のない資金計画を組むことが重要です。
リスクを最小限に抑えながら、活用目的に応じた適切な資金調達方法を選択することが、安定した運用につながります。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング