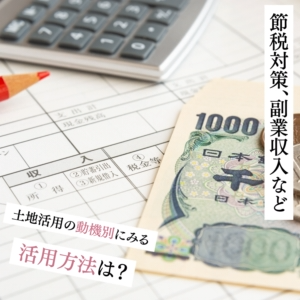土地活用で介護施設を選択するメリット・デメリットやポイント
公開日: 2025.03.29
最終更新日: 2025.09.17
土地活用には多くの方法があるため、どんな活用方法が自分の土地に適しているのか、迷われている方も多いのではないでしょうか。
近年では高齢化社会による高齢者の増加という背景から、介護施設経営で収益を得る方法も注目されています。アパート・マンション経営に適さない土地でも、介護施設なら活用できるケースもあります。
本記事では、土地活用に関する悩みを解決したい方向けに、介護施設経営の基礎知識やメリット・デメリット、成功のポイントについて分かりやすく解説していきます。
1. 土地活用でできる介護施設経営の基礎知識
介護施設経営と一口に言っても、介護施設の種類や経営方式によって、内容が大きく異なってきます。
ここでは、介護施設の種類、各経営方式の特徴、行政機関への申請などについてお伝えします。
1-1. 介護施設の種類について
・有料老人ホーム
有料老人ホームとは、①食事 ②入浴や排せつなどの介護 ③掃除や洗濯選択などの家事 ④健康管理 の4つのサービスのうち、いずれか1つ以上のサービスを提供する施設のことです。
類似の施設に特別養護老人ホームがありますが、特別養護老人ホームは公的施設であるのに対して、有料老人ホームは民間施設となります。有料老人ホームには主に「介護付き有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」の2つの種類があります。
いずれも設置の際には、都道府県等への届け出が必要となります。
介護付き有料老人ホームは、要介護認定を受けた高齢者のための住居施設で、都道府県の認可を受けています。
介護サービス、食事支援、機能訓練、リハビリ、健康管理、レクリエーションなどのサービスを提供する施設です。介護付き老人ホームは、施設の職員が介護サービスを提供する一般型と、外部の介護事業者が提供する介護サービスを利用する外部サービス利用型の2種類があります。
住宅型有料老人ホームは、主に自立~要介護に認定された高齢者が対象(重度の場合は不可)の居住施設です。食事支援、生活支援、健康管理などを行います。入居者が楽しめるイベントやレクリエーションが充実している施設も多くあります。入居者は必要に応じてデイサービスや訪問介護など、自分に合った外部の介護サービスを選べます。
・サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、自由度の高いバリアフリーの高齢者施設で、「サ高住」という略称で呼ばれています。
サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認を行う状況把握サービスと入居者の日常生活の相談に応じる生活相談サービスを必須サービスとします。
有料老人ホームと比べて、要介護度の低い方が入居されているケースが多いですが、オプションとして生活支援サービスを提供している住宅もあります。
・グループホーム
グループホームとは、認知症の高齢者が共同生活を行う高齢者住宅です。
5~9人以下の入居者が、一般住宅と同じような家庭的な環境の下で、入浴、排せつ、食事等の生活支援を受けながら日常生活を送ります。有料老人ホームとの違いは、入居者自身が能力に応じて専門スタッフによる介護サポートを受けながら、料理や掃除、洗濯、買い物などを行う点です。
1-2. 介護施設の経営方式について
・定期借地方式
定期借地方式とは、介護施設の事業者に土地を貸して、借地料(地代)をもらう経営方式のことです。
介護施設の建設や運営は事業者が行います。建物建設や運営の手間がかからないというメリットがありますが、高い収益は期待しづらいというデメリットがあります。
・サブリース方式
サブリース方式とは、土地の所有者が自分の土地に介護施設を建設し、介護施設の事業者に施設を貸与する経営方式です。
運営事業者は事業で得た利益をもとに、建物オーナーに対して建物分の賃料を支払う形になります。
建物の建築費がかかりますが、土地だけでなく建物も貸すので定期借地方式より多めの賃料収入が見込めます。
また運営事業者との契約となるため、施設の入居状況に関わらず、安定した収入を受け取れるメリットもあります。ただし状況によっては定期的な賃料見直しによる賃料減額が発生するリスクもあります。
>>関連記事:不動産投資でサブリース契約を活用するメリット・デメリットは?
・自主経営方式
自主経営方式とは、土地の所有者自身が建物オーナー兼介護事業者となってすべての業務を行う経営方式です。
介護施設の主な収入源は、1割の利用者負担と9割の介護保険を原資とした介護給付費からなる介護報酬です。
自主経営方式の場合、事業運営のノウハウが求められますが、得られた利益はすべて所有者のものになります。
定期借地方式、サブリース方式と異なり、専門企業に頼らずに介護事業者として施設を継続運営していく覚悟と努力が求められます。
1-3. 介護施設の設置について
介護施設は、設置する施設の種類によって、各都道府県への届出や各自治体への申請が必要となります。
また、設備や居室面積などの基準については事前確認が行われます。
届出は事業者が行うもので、自主経営方式を除き建物オーナーが行う必要はありませんが、賃貸経営を円滑に進めるために、建物オーナー側も届出の確認をすると良いでしょう。
介護施設によっては特定のエリア内における事業者数が制限されている「総量規制」が設けられているため、当該施設が建てられない場合があります。 総量規制の対象となる施設は、「特定施設入居者生活介護」に指定されている介護付き老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などがあります。
2. 土地活用で介護施設を選択するメリット
ここからは、土地活用で介護施設を選択するメリットについてお伝えしていきます。
2-1. 収益が安定している
土地活用で介護施設を選択する一番のメリットは、収益が安定していることです。
土地活用で介護施設を運営する際は、介護事業者へ建物を一棟貸しするケースが多いです。建物全体が借上げられるため、空室のリスクがありません。契約期間中は毎月の賃料が固定のため、安定した収益が見込めます。
2-2. 賃貸住宅に向かない立地でも経営しやすい
介護施設は、駅から遠い郊外など比較的条件が悪いとされる立地でも活用しやすいというメリットがあります。
賃貸マンションや賃貸アパートなどの場合、生活環境の利便性が低いと入居率に大きく影響します。
しかし介護施設の入居者は、生活圏がほぼ施設内で完結するため、スーパーや医療施設などの生活施設が遠い場所や、駅から離れている立地でも、支障なく経営できます。
2-3. 固定資産税を軽減できる
介護施設を建設する場合、施設の種類や適用条件によって異なりますが、サ高住などの住宅系施設の場合には、特定の条件を満たすことにより固定資産税の「住宅用地の特例」が適用され、敷地の固定資産税を軽減できます。
住宅用地の特例とは、居住用の建物が建っている土地の固定資産税を、200㎡までの部分は1/6(小規模住宅用地)、200㎡超の部分(一般住宅用地)は1/3まで軽減できる税制優遇措置のことです。
また相続税についても、土地を他者に貸していることから土地・建物の評価額が低くなり、税金対策の効果が期待できます。
2-4. 第一種低層住居専用地域や市街化調整区域に建てられる
都市部の土地には何でも自由に建物が建てられるわけではなく、都市計画法に基づいて土地の利用方法を規制する用途地域制度があります。 介護施設は、テナントなど事業系の建物を建てられない第一種低層住居専用地域にも建てられるというメリットがあります。
また、原則として建物を建てられない地域である市街化調整区域でも、建築許可が下りる可能性もあります。
2-5. 建築時に補助金を利用できる可能性がある
介護施設の場合、建築時に補助金を利用できる可能性があります。
例えば、サ高住の場合、家賃の設定や土地の災害リスクなどの各種要件を満たすことで、建設費用の10分の1が補助金として支給されます。
>>関連記事:サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の補助金はいくら?【令和4年度】
2-6. 管理の手間がほとんどかからない
土地活用として介護施設を選択した場合のメリットは、建物オーナーが貸主として行うべき管理の手間がほとんどかからない点です。
上述した定期借地方式やサブリース方式であれば、事業者に土地や建物を貸し出した後は、手間をかけずに安定収益を確保することができます。
2-7. 地域や社会へ貢献できる
今後も少子高齢化社会の流れは止まらないため、高齢者の居住空間である介護施設を建てることは、地域や社会への大きな貢献となります。社会貢献に関心のある人にとっては、介護施設の建設は大きな意義があると思われます。
3. 土地活用で介護施設を選択するデメリット
ここからは、土地活用で介護施設を選択するデメリットについて解説していきます。
3-1. 初期費用が比較的高い
介護施設を充実させるには、広い土地と建物が必要になります。
また介護施設などの福祉施設の建築費は、設備や居室の床面積などについて一定の基準が設けられていることから、一般的なアパートより初期費用が比較的高額になりやすいことが注意点です。
3-2. 事業者が撤退するリスクがある
介護施設の運営が上手くいかず、借主である介護施設の事業者が撤退するリスクがあります。
要介護状態にある介護老人の入居ニーズはなくなりませんが、近隣に競合する高齢者向け施設が増えるほか、サービス従事者の確保が困難になるなど、さまざまな要因で老人ホーム経営が立ち行かなくなるケースがあります。
3-3. 建物の汎用性が低い
介護施設は設計段階から介護事業者の希望を取り入れて建築されるため汎用性が低く、その事業者が撤退した場合、次の借主(運営事業者)が見つかりにくくなるデメリットがあります。
次の借主となる運営事業者が見つかっても建物のリフォーム費用が高額になるため、最初の事業者の選定と契約は慎重に行う必要があります。
4. 土地活用で介護施設運営を成功させるポイント
ここからは、土地活用で介護施設運営を成功させるポイントについてお伝えしていきます。
4-1. 介護施設に適した立地か見定める
介護施設による土地活用の際は、所有している土地の広さや賃貸需要があるかなど、介護施設に適した立地かどうかを確認する必要があります。
介護施設を建てることが可能な広さの土地は、アパートやマンションなどの建物も建築可能である可能性が高いです。介護施設の建築は一般的に広い土地が必要になり、初期費用も一般的な賃貸住宅に比べて高くなる傾向があります。
また賃貸需要が高い土地であれば、収益性の高いアパート・マンションなどの賃貸住宅経営の方が適している可能性もあります。
介護施設経営とアパート・マンション経営について、収益性を含めたメリット・デメリットを比較検討することも選択肢の1つと言えます。
4-2. 介護事業者の運営実績を重視する
介護施設の運営を任せる事業者は、運営実績をしっかりと確認して決めると良いでしょう。
運営実績が豊富で経営状態が良好な事業者であれば、撤退のリスクを最小化できる可能性が高いと言えます。
賃料が高くても、運営実績のあまりない事業者の場合は、相対的に撤退リスクが高まります。
計画時に提示された賃料金額で会社を選ぶのではなく、業歴が長く運営実績のある事業者を選ぶと良いでしょう。
5. 土地の特性を見極めた上で介護施設経営を検討しましょう
介護施設経営は、安定した収益が見込める、手間がかからない等のメリットがありますが、
一方でアパート・マンション経営に比べて収益性に劣る、事業者撤退のリスクといったデメリットもあります。
どんな土地活用方法にもメリット・デメリットがあるため、自分の土地にはどんな活用方法が適しているのかを調査して決めることが大切です。
まずは土地活用に詳しい専門会社に資料請求や気軽な相談をするなどの情報収集を行って、土地活用の最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
■監修者プロフィール
ここりんくす株式会社 代表取締役
小泉寿洋
ここりんくす株式会社代表取締役。上場グループに属する賃貸不動産会社で賃貸仲介、賃貸管理部門に14年半ほど従事。その後、不動産仲介・建築工事・終活サポートの会社経営を経て、現在は賃貸経営・賃貸管理・終活に関するコンサルティング、WEBセミナー講師、不動産・FP系ライターなど各方面で活動中。不動産業界歴は約23年。
【保有資格】
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー1級、終活ガイド1級、遺品整理士他
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング