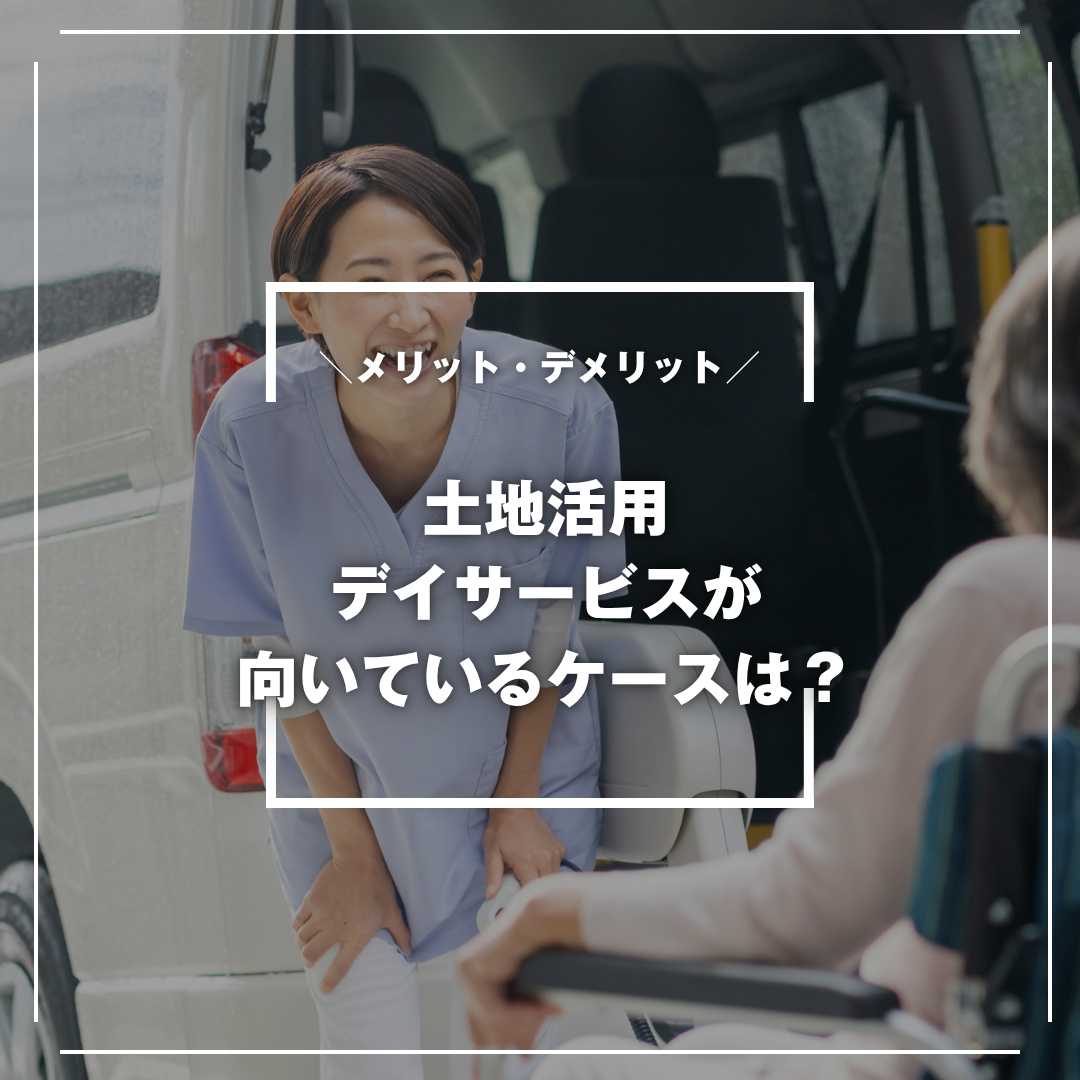土地活用で福祉施設を運営するメリットやデメリットは?
公開日: 2025.03.31
最終更新日: 2025.09.17
土地活用の選択肢として福祉施設の運営があります。福祉施設は幅広い概念であり、高齢者向けの介護施設や有料老人ホーム、児童向け福祉施設、障がい者グループホームなど多岐にわたります。高齢化社会の進行により、こうした施設の需要は高まっていますが、運営には専門的な知識や管理体制が必要です。
この記事では、福祉施設を活用した土地運用のメリット・デメリットを整理し、検討すべきポイントを解説します。
目次
1. 福祉施設の土地活用
福祉施設を活用した土地運用は、現代社会に対応したニーズの高い選択肢です。
しかし、施設の種類や運営方式によって必要な設備や管理負担が異なるため、事前に適した活用方法を検討することが重要になります。
1-1. 福祉施設の需要
福祉施設の需要は増加傾向にあり、今後も拡大が見込まれます。
特に高齢化の進行により、老人ホームやデイサービスのニーズが高まっており、地域によっては受け入れ施設や従業員の不足が課題となっています。
厚生労働省の調査によると、福祉施設の在所率(施設の利用率)は以下のようになっています。
|
福祉施設の種類 |
在所率 |
|
老人福祉施設 |
89.3% |
|
障害者支援施設等 |
92.2% |
|
児童福祉施設等 |
88.9% |
|
有料老人ホーム |
84.6% |
一見すると「施設は十分に足りている」と感じられるかもしれませんが、実際には満床に近い水準が続いていることを意味しており、新規受け入れが難しい状況が常態化しているといえます。
またニュースで報じられているように、待機児童の問題も深刻化しており、都市部を中心に保育施設の定員オーバーが常態化しています。
こうした実情から、福祉施設の整備は「すでに足りている」どころか、今後さらに供給が求められる社会的インフラだと言えるでしょう。
特に、既存施設では対応が難しいエリアや、アクセス性の悪い地域では、新たな施設の開設によって潜在的なニーズを取り込める可能性があります。
1-2. 福祉施設の経営
福祉施設の土地活用では、土地所有者と事業者が役割を分担する形が一般的です。土地所有者は土地を提供し、事業者が施設の運営や管理を担うことで、経営の負担を分散できます。
建物の建設については、土地所有者が建設し賃貸するケースと、事業者が自ら建設するケースの両方があり、契約内容によって異なります。
いずれの場合も、長期的な事業計画を立てたうえで役割を明確にすることが重要です。
2. 土地活用できる福祉施設の種類
福祉施設には高齢者向けや障がい者向け、児童向けなどさまざまな種類があります。
施設の種類によって必要な設備や運営体制が異なるため、土地の条件や地域のニーズに合わせて適した活用方法を選ぶことが重要です。
2-1. 高齢者向け福祉施設
高齢者向けの福祉施設には有料老人ホームやデイサービスなど、入居型と日帰り型の施設があり、それぞれ提供するサービスが異なります。
有料老人ホームは、食事や生活支援、介護サービスを提供する入居型施設で、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなど、要介護度やサービス内容によって種類が分かれています。
一方、デイサービスは日中のみ利用できる通所型の施設で、食事や入浴、機能訓練を提供しながら利用者の自立支援や家族の負担軽減を図ることを目的としています。
このように、高齢者向け福祉施設は入居型・通所型の2タイプがあり、地域のニーズに応じた施設選びが重要となります。
2-2. 障がい者向け福祉施設
障がい者向けの福祉施設には、共同生活を支援するグループホームや、日中活動の場となる就労支援施設などがあります。
障がい者グループホームは、障がいを持つ方が少人数で共同生活を送りながら、生活支援や介護サービスを受けられる施設です。自立を支援するための見守りや生活相談などが提供され、地域社会の中で生活しやすい環境が整えられています。
また、就労支援施設は、一般就労が難しい方に対して働く機会や職業訓練を提供する施設で、軽作業やリハビリを通じて社会参加を促す役割を果たします。
2-3. 児童向け福祉施設
児童向けの福祉施設には、保育園、児童養護施設、放課後等デイサービスなどがあり、それぞれ目的や支援内容が異なります。
保育園は、共働き世帯を中心に需要が高く、待機児童問題の解決にも貢献できる施設です。
特に都市部では用地の確保が課題となるため、土地活用の選択肢として検討されることが増えています。
児童養護施設は、家庭での生活が難しい子どもたちを保護し、生活支援や教育を提供する施設です。
社会的に必要とされる一方、運営には専門的な体制が求められます。
放課後等デイサービスは、障がいのある子どもを対象とし、学校の授業終了後や休日に生活支援や学習支援を行う施設です。
近年、支援を必要とする家庭の増加により、ニーズが拡大しています。
3. 土地活用で福祉施設を選択するメリットやデメリット
福祉施設は社会的な需要が高く、土地活用としての選択肢の一つになります。
しかし、メリットがある一方で、運営や管理に関する課題も存在します。
ここでは、福祉施設を活用する際のメリットとデメリットを整理します。
3-1. 土地活用で福祉施設を選択するメリット
・立地の悪い土地でも経営ができることがある
福祉施設は、アパートやマンションの賃貸需要が低いエリアでも運営できる可能性があります。
例えば、駅から遠い土地でも一定のニーズがあり、高齢者向け施設や障がい者グループホームは郊外でも適した立地とされることが多いです。そのため、事業用テナントや居住用の賃貸需要がない土地でも有効な選択肢となります。
・安定的な収益が期待できる
福祉施設の需要は年々増加しており、長期的に安定した収益が見込めます。
また、一般の賃貸住宅と違い、景気の影響を受けにくく、賃料の変動が少ないことや、一棟を借り上げる経営形態が多いため契約中は空室リスクがないことなどもメリットです。
・管理の手間が少ない
福祉施設の運営は専門の事業者が行うことが多いため、土地所有者の管理負担が軽減されます。
さらに、建物の小規模な修繕は事業者側が負担するケースが多く、土地所有者の維持管理コストを抑えられる点も魅力です。
そのため、土地を活用しつつ、日常的な管理の負担を減らしたい方に適しています。
・社会貢献ができる
福祉施設の開設は、高齢者や障がい者、児童など支援を必要とする人々の暮らしを支える役割を果たします。
地域に必要な施設を提供することで、社会貢献度が高い土地活用となり、行政や地域住民からの評価も得やすくなります。
・補助金や税制優遇を受けられる
福祉施設の運営には、国や自治体からの補助金や税制優遇を活用できる場合があり、初期費用や運営コストを抑えられる可能性があります。
3-2. 土地活用で福祉施設を選択するデメリット
・転用性が低い
福祉施設は特定の用途に合わせた設計が求められるため、事業者が退去した場合に他の用途へ転用しにくいという課題があります。
例えば、老人ホームなどの高齢者向け施設は、バリアフリー設計や広い共有スペースを備える必要があり、一般の賃貸住宅やオフィスとして再利用しにくいケースが多くなります。そのため、契約終了後の活用計画を事前に考慮することが重要です。
・法改正や制度改正の影響を受ける
福祉施設の運営には国や自治体の補助金や介護報酬が関わるため、制度変更の影響を受けやすい点もデメリットの一つです。
例えば、補助金が減額された場合、事業者の経営が圧迫され、賃料の引き下げ交渉が発生する可能性があります。
また、介護報酬の改定により収益構造が変わるリスクもあるため、長期的な安定性を見極めることが大切です。
4. 土地活用で福祉施設を選択する際のポイント
福祉施設の運営には立地や契約内容、事業者の選定が重要です。長期的な活用を見据え、転用のしやすさや制度改正の影響も考慮する必要があります。
ここでは、福祉施設を選択する際に押さえておくべきポイントを紹介します。
4-1. 福祉施設に適した土地がある
福祉施設を運営する際は、立地に応じた施設選びが重要です。
例えば、都市部ではデイサービスや児童向け福祉施設、郊外では老人ホームや障がい者グループホームが適している傾向があります。
都市部は高齢者が通いやすいデイサービスの需要が高く、短時間の利用が可能な施設が向いています。
一方、郊外では広い敷地を確保しやすいため、長期入居を前提とした老人ホームの運営が適していることが多いです。
また、交通アクセスが良い土地では福祉施設以外の活用が適している場合もあるため、他の選択肢と比較検討することも重要です。
土地の特性を活かし、最適な福祉施設の種類を選ぶことで、安定した運営につながります。
4-2. 信頼できる運営事業者を選ぶ
福祉施設の土地活用では、長期的な安定運営のために信頼できる事業者を選ぶことが重要です。
事業者の運営実績や経営状況を事前に確認し、継続的な運営が可能かを見極める必要があります。
もし事業者が撤退した場合、新たな事業者を見つけるまでに時間がかかり、収益の空白期間が生じるリスクがあります。
そのため、契約前に運営実績のある企業を選定し、契約条件を慎重に検討することが大切です。
4-3. 土地活用の専門家に相談する
福祉施設の運営は、初期費用や契約条件、運営リスクなど考慮すべき点が多く、事前の専門的なアドバイスが不可欠です。
特に、福祉施設以外の土地活用の選択肢と比較し、自身の土地に最適な活用方法を見極めることが重要になります。
例えば、賃貸住宅や商業施設と比較すると、福祉施設は安定した需要が期待できるものの、転用の難しさや制度改正の影響を受けやすいという側面があります。
こうしたメリット・デメリットを総合的に判断するためにも、不動産や福祉事業に詳しい専門家の意見を参考にし、将来的なリスクを見据えた計画を立てることが大切です。
5. 福祉施設を活用した土地運用を成功させるために
福祉施設は社会的なニーズが高く、土地活用の選択肢の一つとして有力ですが、すべての土地に適しているわけではありません。
立地や市場の需要、運営事業者の選定などを慎重に検討することが重要です。
また、他の土地活用方法と比較し、長期的な安定性や転用のしやすさを考慮することも大切です。
運営には法制度の影響もあるため、専門家のアドバイスを受けながら、自身の土地に最適な活用方法を見極めることが成功の鍵となります。
■監修者プロフィール
ここりんくす株式会社 代表取締役
小泉寿洋
ここりんくす株式会社代表取締役。上場グループに属する賃貸不動産会社で賃貸仲介、賃貸管理部門に14年半ほど従事。その後、不動産仲介・建築工事・終活サポートの会社経営を経て、現在は賃貸経営・賃貸管理・終活に関するコンサルティング、WEBセミナー講師、不動産・FP系ライターなど各方面で活動中。不動産業界歴は約23年。
【保有資格】
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー1級、終活ガイド1級、遺品整理士他
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング