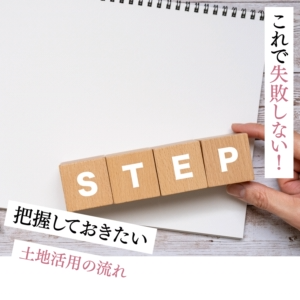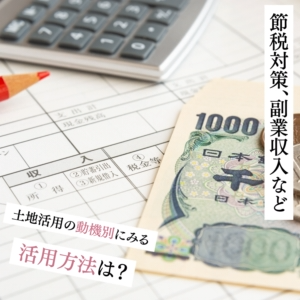土地活用でテナント経営を選ぶメリットやデメリットは?
公開日: 2025.03.26
最終更新日: 2025.09.17
土地活用をお考えであれば、ぜひテナント経営もご検討ください。テナント経営による土地活用とは、主に事業者向けに不動産の一部もしくは全部を貸し出して、賃料収入を得ることをいいます。
今回は土地オーナー向けに、テナント経営で土地を活用するノウハウやメリット・デメリットなど、テナント経営の基礎知識を徹底解説します。
また、テナント経営するうえで押さえておきたいポイントやコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1. テナント経営で土地活用するには?
テナント経営で土地活用する方法としては、所有する土地に建物を建てて事業者に貸す方法と、土地(更地)をそのまま貸し出す方法の2つの選択肢があります。
それぞれの経営方法を比較していただくために、詳しく解説していきます。
1-1. 建物を貸す
土地活用方法として、土地に自分自身で飲食店ビルやオフィスビル、店舗を建てて、テナントを募集する方法があります。
ちなみにテナント用に建物を建てることで、相続が発生した際に「貸家建付地」とみなされ、土地の評価額が下がります。
また、建物部分の評価額も『借家権割合』により減額されます。
賃料収入を得ることができるうえに節税効果があるため、魅力的な相続税対策ともいえるでしょう。
駅前の商業地なのか、それとも都心部の住宅用地なのかなど、土地の立地条件やエリアの特徴によってテナント側の需要が異なります。
どのような業種にニーズがあるのか十分調査したうえで、不動産活用する方法を見極めることが大切です。
建物を貸し出す場合は、テナントと建物賃貸借契約を締結することになります。
建物賃貸借契約とは、建物を使用することを目的とした契約であり、貸し出す期間を定めて契約できる「定期借家契約」と、期間を定めない「普通借家契約」があります。
基本的には、どちらにするか事前に決めてからテナント募集するようにしてください。
もし将来土地を売却する計画があれば、期間満了とともに賃貸契約が終了する定期借家契約を選び、売却や自身が利用する予定がなければ、契約が満了する度に更新も可能な普通借家契約を選ぶとよいでしょう。
なお、事業用のテナントとの賃貸借契約は、定期借家契約が一般的です。
【参照】「定期借家制度(定期建物賃貸借制度)をご存じですか・・・?(国土交通省)」
1-2. 土地のみを貸す
もう一つの土地活用方法として、土地をそのまま貸し出して、事業者が建物を建てる方法があります。
土地を事業用として貸し出す場合は、事業用定期借地権の契約を締結するのが一般的です。
企業は目的に合わせた建物を建てて、契約期間が終了したらテナントが建物を解体し、更地にして土地オーナーに返還するのが一般的な流れです。
ただし契約期間を30年以上50年未満に設定した場合で、建物が引き続き使用可能であるときには、テナント側に建物買取請求権が発生します。
場合によっては契約締結時において、買取請求できない旨の特約を結んでおくことを忘れないようにしましょう。
【参照】:「定期借地権の解説(国土交通省)」
2. テナント経営で土地活用するメリット・デメリット
テナント経営で土地活用を検討している方のために、メリットとデメリットを紹介します。
2-1. テナント経営で土地活用するメリット
テナント経営はメリットが大きいといわれることがありますが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここではテナント経営をイメージしていただくために、代表的なメリットを3つ紹介します。
・収益が大きい
テナント経営は、賃貸契約の相手が事業者になるため、アパート経営や駐車場経営などと比べて収益性が高いのが特徴です。
商業施設のテナントが支払う賃料は、アパートや賃貸マンションの家賃の1.5〜2倍程度であることが多く、賃料単価が高い傾向があります。
ただし、テナントビルは集客力の高い1階が人気で賃料が最も高く、階が上がるにつれて賃料が安く設定されていることが多いです。
また、事業用の場合はテナントが内装や設備に投資しているうえ、収益が見込めている状態で退去することは少なく、賃料増額請求もしやすいのもメリットといえるでしょう。
土地を貸し出す場合は、業種や用途に合った大きさであることが望ましく、大きすぎると賃料単価を高く設定できないことがあります。
しかし、土地のみを貸し出す場合は、初期投資やリスクを被るのは事業者側なので、オーナー側はほとんど初期費用がかからないことがメリットです。
・入居者間でのトラブルが少ない
アパートや賃貸マンションのような賃貸集合住宅は、騒音問題など生活マナーが要因となり、入居者同士でトラブルになることがあります。
しかし事業用のビルでは、テナント同士でトラブルになることは少なく、万が一トラブルになったときの対処について、あらかじめ契約書に定めておくことで回避できます。
・経費を抑えられる
テナント経営の場合、借主であるテナント側が原状回復を行ってから退去するため、リーシングのために多額の修繕費がかかるようなことは多くありません。
賃貸住宅の経営ではこうした費用が一部かかりますが、テナント経営の場合はアパート経営などと比べてメンテナンス費や修繕費が多くかからないため、高い利回りも期待できます。
土地のみを貸し出す場合は、管理費などの経費は原則かかりません。極力経費を抑えて不動産投資をしたい人に向いています。もし除草や清掃が必要な場合は、賃貸契約書にその回数や時期を盛り込んでおきましょう。
2-2. テナント経営で土地活用するデメリット
テナント経営で土地活用する場合も、少なからず注意点があります。
ここでは代表的なデメリットを2つ紹介しますので、「テナント経営で失敗した」と後悔しないためにも、よく理解したうえで慎重に進めましょう。
・景気の影響を受けやすい
テナント経営の場合、借主になるのは通常は企業です。
不況や事業の不振などの影響を受けやすく、状況によっては躊躇なく撤退を決断するかもしれません。事業者向けのテナント経営は収益は大きいものの、アパートや賃貸マンションなど住居に比べて、空室になったときの損失が大きくなる傾向があります。
複数の事業者を誘致したマルチテナントだとしても、退去が重なることがあります。市況や経済に関するニュースには、常にアンテナを張っておきましょう。
・建物の地震保険には加入できない
アパートローンなどの融資を受ける場合、金融機関から地震保険への加入を条件として提示されるのが一般的です。
しかし地震保険はそもそも居住用の建物を対象としているため、商業ビルは地震保険に加入できないことがほとんどです。
保険会社によっては火災保険や地震保険以外の事業者向けの保険を用意していて、特約でつけられることもあります。
しかし保険料が高いことが多く、また加入できたとしても補償額が十分ではないケースもあります。もし地震保険への加入を検討している場合は、事前に保険会社に確認しておきましょう。
|
不動産オーナーがテナントを誘致するために商業ビルを建築する場合、建築基準法で定められた水準を満たす必要があり、かならずしも希望する高さや床面積を実現できる訳ではありません。建築プランを立てる際は建築基準法や用途地域などによる制限を考慮して、設計することになります。 |
3. テナント経営で土地活用する際のポイント
テナント経営で土地を活用する際に、押さえておくべきポイントを3つ紹介します。
3-1. 資産区分と原状回復の取り決めを明確にしておく
建物や設備の不具合が生じたときに、責任の所在がオーナーとテナントのどちらにあるのか判断するためにも、資産区分について明確にしておきましょう。
またどこまでがオーナーの資産で、どこからがテナントの資産なのか明確にしておくことで、原状回復時にも確認しやすくなります。テナントは入居時に大掛かりな内装工事を行うことが多いため、貸し出したときの状態を記録するために、写真を撮影しておくとよいでしょう。
原状回復についても、できるだけ詳細について取り決めしておくことが重要だといえます。
例えば、事業用不動産では、テナントが原状回復費用を負担するケースが一般的であり、テナントがエアコンを設置するために壁に穴をあけた場合は、「退去時にエアコンは撤去し、穴をふさぐ」などと契約書に記載しておくと安心です。
3-2. テナントとの賃貸借契約は定期借家契約を選択する
テナントとの賃貸借契約は、オーナーにとって有利な定期借家契約を選択してください。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類がありますが、更新がない定期借家契約を選んでおくことで、契約が満了するタイミングでテナントを退去させることができます。
しかし普通借家契約でテナントを退去させる場合は、住居とは異なり営業権も発生するため、莫大な立ち退き料がかかってしまうおそれがあります。
定期借家契約には更新はありませんが、オーナーとテナント双方の同意があれば、再契約は可能です。
つまり定期借家契約でも、実質的には契約期間の延長は可能です。
3-3. 土地活用の専門家と一緒に進める
土地活用を成功させるためには、パートナー選びが重要です。ぜひ土地活用の専門家に提案してもらいながら、堅実に進めるようにしてください。
どのように不動産経営していくことが正しい方法なのか、とくに初めての場合は判断がつかないことが多いでしょう。
例えば土地の賃貸借契約に関しても、不動産の知識がなければ大きく損をすることにもなりかねません
4. 土地の魅力を知ることから始める土地活用
ここまで、テナント経営の魅力や注意点について解説してきました。テナント経営は収益が大きく、経費を抑えられるのがメリットです。
しかしすべての土地が、テナント経営に向いている訳ではありません。
例えば駅近で利便性が高く、集客が見込めるような立地であれば、飲食店やオフィスが向いています。幹線道路沿いであれば、トランクルームやコインパーキングのニーズがあるかもしれません。狭小地でも人通り多く視認性が高い土地であれば、貸し看板用の土地として貸し出すことで、土地の使用料を得られるでしょう。
このように土地が持っている価値に合わせて活用することで、高収入を生む可能性を秘めています。
土地がどのような活用に向いているのか市場調査し、不動産会社など信頼できる土地活用の専門家に相談しながら進めましょう。
■監修者プロフィール
株式会社アース・リーグ代表取締役
森田一成
15年間の住宅・不動産専門新聞社の経験、不動産投資セミナーの企画・運営、不動産団体広報誌の企画・取材・原稿執筆などを経て、Webメディア制作・編集、不動産関連のセミナー企画などを行っている株式会社アース・リーグを設立し代表を務める。
【保有資格】宅地建物取引士
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング