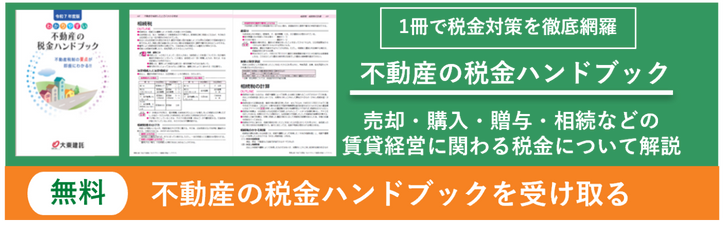相続税の基本の「き」 ~計算方法から基礎控除まで~
公開日: 2022.10.28
最終更新日: 2025.10.23
平成27年から相続税法が改正になり、基礎控除の縮小や最高税率の引き上げが行われました。相続税は「一握りの資産家だけにかかる税金」ではなくなり、また、多くの資産を持つ方にとっては一層、負担が重くなったことになります。
相続税は、一括で現金納付するのが原則です。相続発生後10ヵ月以内という納付期限があるので、短期間に多額の現金を用意しなければならないことになります。納税資金を捻出するために、大切な土地を売らなければならないケースも出てきます。
あらかじめ対策を立てておくことが重要ですが、「どのくらい相続税がかかるのか」によって、とるべき対策も変わってきますし、相続発生までに要件さえ整えておけば大きな節税効果が得られる場合もあります。
しかし、課題の発見・対策の検討から、対策の実行により効果を得るまでには長い時間を要します。近年では遺産分割対策にも注目が集まっていますが、まずは、相続税の計算方法を知り、おおよその税額を事前に見積もっておく必要があります。
相続税計算の第一歩は財産総額の把握
相続税を計算するには、まず「財産が全部でいくらになるのか」を把握しなければなりません。預貯金や株式などの金融資産はもちろん、不動産も金銭で評価します。土地は「路線価」がベースとなり、建物は固定資産税評価額を基に評価します。借入金や葬儀費用といった「マイナスの財産」は控除します。
なお、不動産は利用形態によって評価額が変わります。マンションのような賃貸用建物が建っている土地の場合、
自用地としての評価額×(1−その土地の借地権割合×借家権割合で評価されます。
借地権割合は、都市部の場合60%か70%のことが多く、借家権割合は30%が一般的です。
借地権割合が70%、借家権割合が30%とすると、土地の評価額は
自用地としての評価額×(1−70%×30%) = 自用地としての評価額×79%になります。
自宅や駐車場として使っている場合に比べ、21%評価が下がるわけです。
建物も、賃貸用であれば30%の評価減があります。自宅の建物の場合、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になりますが、賃貸用建物の場合は「固定資産税評価額×70%」で評価されます。
また、「相続人の今後の生活に必要な土地」に対しては「小規模宅地等の特例」が適用され、相続税計算上の評価額を大きく下げることができます。
自宅の場合、最大330㎡まで80%の減額となり、駐車場や賃貸マンション敷地の場合は最大200㎡まで50%減額となります。このような不動産の評価減も踏まえ、財産総額を算定することになります。
平成27年改正で縮小された基礎控除
相続税は、純資産がそのまま課税対象となるわけではなく、純資産から「基礎控除」を差し引きます。この「基礎控除」が、平成27年改正で大きく引下げされました。 平成26年までは...
5,000万円+法定相続人数×1,000万円でした。
妻と2人の子供が相続人の場合、法定相続人数が3人なので、財産総額が8,000万円までは相続税がかからなかったわけです。それが平成27年改正で...
3 ,000万円+法定相続人数×600万円になりました。
法定相続人数が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。都市部に不動産を所有していたら、基礎控除額を上回る水準です。
基礎控除を差し引いた額を「法定相続割合で分けた」と仮定する
財産総額が1億2,000万円で、相続人が妻と子ども2人である場合、基礎控除4,800万円を差し引くと7,200万円です。この7,200万円を、「法定相続割合で分けた」と仮定します。
妻3,600万円(1/2)、子どもがそれぞれ1,800万円ずつ(1/4ずつ)取得したとします。この金額に基づいて、税額を計算します。
相続税は累進課税です。1,000万円までは10%、1,000万円から3,000万円までに対しては15%、3,000万円を超えた分(5,000万円までの部分)に対しては20%です。
これをわかりやすく表したのが相続税の速算表で、妻の3,600万円に対応する税額は、
3,600万円×20%−200万円(控除額)=520万円となります。
同様に、子どもの1,800万円に対する税額は、
1,800万円×15%−50万円=220万円です。
3人合わせると、
520万円+220万円+220万円=960万円となります。
これが「相続税の総額」となります。(基礎控除以外の税額控除は考慮していません)
「3人合わせて、960万円を納めてください」ということです。実際の納税額は、「実際に取得した財産の割合」に応じて按分されます。
たとえば、子供のうち1人が4,800万円(財産総額の4割)を相続する場合、納める相続税額は、
960万円×0.4=384万円になります。
なお、平成27年改正では、「最高税率の引き上げ」も行なわれました。平成26年までは、最高税率が50%でしたが、それが55%に引き上げられました。

| 法定相続分に応じた財産取得額 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0 |
| 1,000万円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
| 法定相続分に応じた財産取得額 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0 |
| 1,000万円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
配偶者の税額は大幅に軽減される
上記の例において、妻が7,000万円の財産を相続したとします。妻が納めるべき税額は、本来であれば 960万円×(7,000万円/1億2,000万円)=560万円 となりますが、配偶者控除を適用すれば、実際は「ゼロ」で済みます。
配偶者に対しては、相続する額が「法定相続分まで」または「1億6,000万円まで」であれば相続税がかからないことになっています。極端な話、財産総額が1億6,000万円以下なのであれば、「全財産を配偶者が相続」とすれば相続税はかからないことになります。
ただし、配偶者に多額の財産を相続させると、その後、配偶者が亡くなった際(二次相続)の相続税が重くなりますので、注意が必要です。
関連記事
相続税に関する専門家の診断も有効に使う
このように、相続税の額はいくつものプロセスを経て算定されます。相続人の数や、不動産の利用形態、場合によっては税額計算をする税理士の経験値などによっても税額は大きく変わる場合があります。「今のままだと、どのくらいの相続税額になるのか」「対策を講じることによって、どのくらいの節税効果があるのか」を、相続申告の経験豊富な専門家の資産診断サービスなどを活用しつつ、把握しておくことが重要です。
「わたしのみらいノート」をプレゼント
 「わたしのみらいノート」は大東建託オリジナルのノートです。自分史を振り返り、保有資産などの整理ができるのはもちろん、円満な資産承継を行うためのヒントがたっぷり含まれています。 今、こちらのページからご請求して頂いた方には、「わたしのみらいノート」を無料でお届けいたします。ご自身の「みらい」、さらにご家族との「みらい」を一緒に描いてみましょう。
「わたしのみらいノート」は大東建託オリジナルのノートです。自分史を振り返り、保有資産などの整理ができるのはもちろん、円満な資産承継を行うためのヒントがたっぷり含まれています。 今、こちらのページからご請求して頂いた方には、「わたしのみらいノート」を無料でお届けいたします。ご自身の「みらい」、さらにご家族との「みらい」を一緒に描いてみましょう。
「税金・相続」関連用語集
- 青色申告
- 青色事業専従者
- 確定申告
- 私的年金
- 固定資産税
- 節税対策
- 相続税
- 不動産取得税
- 任意後見制度
- 定期借地権
- 年末調整
- 印紙税
- 贈与税
- 所得控除
- 登録免許税
- 都市計画税
- 住宅取得控除
- 借地権
- 遺言書
- 成年後見制度
最新コラムの更新情報以外にも、少しでも皆様のお役に立つ
資産承継や賃貸経営に関するホットな情報をお届けします。
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング