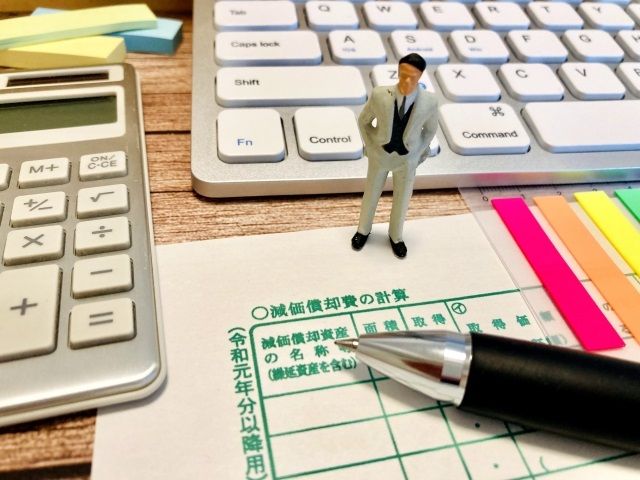アパートの減価償却費まとめ|シミュレーションから見る計算の仕方
公開日: 2024.02.09
最終更新日: 2025.11.27
アパート経営を始めるうえで知っておくべき知識の一つに、減価償却があります。
減価償却とは建物などの固定資産の購入費を、使用期間に応じて分割計上する会計処理のことで、上手く活用すれば所得税などの税金負担を軽減できます。
したがって、これから土地活用や不動産投資を始める方は、事前に理解を深めておくことをおすすめします。
そこで本記事ではアパートの減価償却費の計算について、実際のシミュレーションを用いながら徹底解説します。
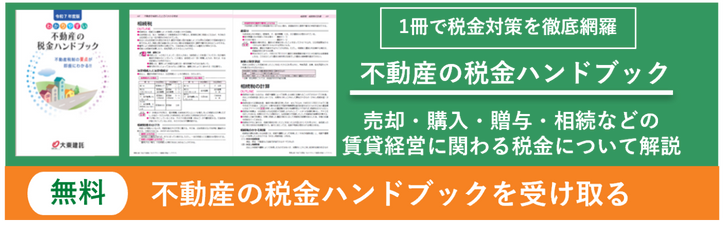
1.アパート経営と減価償却
はじめにアパート経営における減価償却の基本的な考え方を解説します。
1-1.減価償却とは
減価償却とは不動産など固定資産の購入費用全額を一括で経費計上せず、何年かに分けて計上する方法です。
購入した資産が生み出す収支をより正確に、実態に合った形で算出するために用いられます。
建物などの資産は時間の経過に伴って老朽化し、価値が目減りしていくという考え方に基づいており、目減りした分を減価償却費として扱います。
アパート経営、マンション経営などの賃貸物件を運営する場合においては、必ず理解しておくべき考え方といえます。
1-2.なぜアパート経営で減価償却が重要なのか
アパート経営で減価償却が重要な理由は、減価償却を上手く活用すれば税負担を抑えるうえで大きな効果を発揮するためです。
減価償却費は不動産の取得費を法定耐用年数に応じて配分し、その年に相当する分の金額であり、必要経費として計上できます。
減価償却額を計上することによって、不動産経営の会計上の収支が赤字になった場合、青色申告であればマイナス分をオーナーの所得などから相殺できるため、課税所得金額の合計を圧縮でき、所得税額や住民税額の軽減につながります。
あくまで会計上の数値であり、経費として費用計上するものの、キャッシュフローがマイナスになったわけではないので、収益を上げつつ税金負担を抑えられるメリットがあります。
1-3.アパート経営で減価償却できる資産とできない資産
減価償却の対象になるのは、建物と建物附属設備や構築物、器具備品です。
したがって、建物本体以外の電気やガス、空調、給排水設備など附属設備部分についても、減価償却費として計上できます。
一方、土地や更地は減価償却の適用対象外となっています。
土地は建物部分と違い、時間の経過や利用などにより劣化せず価値が変化しないので、建物のように耐用年数を計算できないためです。
また、建物附帯設備の中でも、家屋に取り付けられ構造上一体となっているものは、建物設備としてではなく、建物として減価償却します。
区分けや手続きが難しく明確にしたい場合は、明確にしたい場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
2.アパート経営の際に行う減価償却費の計算
アパート経営における減価償却の基本を理解したところで、実際に減価償却費の計算のポイントを見ていきましょう。
2-1.減価償却費の計算に必要な項目
・法定耐用年数
法定耐用年数とは、固定資産の資産価値が消滅するまでの期間を定めた年数のことです。(償却年数と同じです)
ただし、ここでいう価値消滅はあくまで「資産価値が帳簿上から消滅する」ことを指しており、実際の建物の価値がなくなるわけではありません。
住宅用建物の場合、種類や構造別で異なる耐用年数が定められています。
以下に国税庁が定めている構造ごとの法定耐用年数一覧をまとめます。
| 構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 金属(鉄重量骨造)※(骨格材の厚み4mm超) | 34年 |
| 金属(軽量鉄骨造)※(骨格材の厚み3mm超、4mm以下) | 27年 |
| 金属(軽量鉄骨造)※(骨格材の厚み3mm以下) | 19年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄筋コンクリート造(RC造) |
47年 |
一方、建物附属設備の法定耐用年数は種類によって異なりますが、おおよそ15年程度に設定されているものが多くなっています。
なお、新築物件ではなく中古物件を購入した場合、法定耐用年数すべてを経過した物件は、その法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とします。
計算式にすると以下の通りです。
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
一方、法定耐用年数の一部を経過した物件は、法定耐用年数から取得時の経過年数を差し引いたうえ、経過年数の20パーセントを加えた年数を耐用年数とします。
計算式にすると以下の通りです。
耐用年数 = (法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%
もし上記計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、端数を切り捨てその年数が2年に満たない場合には2年として計算します。
・物件の取得価額
物件の取得価額とは、物件を取得する際にかかった費用のことです。
建物の建築費だけでなく、購入・建設にかかった諸費用も含まれる点に注意しましょう。
以下に取得価額に該当する主な費用をまとめます。
・建物の購入金額
・仲介手数料
・固定資産税精算金
・立ち退き料
なお、土地は非減価償却資産なので、土地の購入金額は物件の取得価額に含まれません。このほかにも取得価額に含まれるものがあるので、わからないときは不動産会社などへ問い合わせ、確認するようにしましょう。
・償却率
償却率とは減価償却費の計算を簡易化するために用いられる割合のことです。
耐用年数と後述する減価償却費の計算方法によって用いる数字が変わります。
償却率がどのくらいになるのかは、国税庁のWebサイトに公開されているので、以下のページから確認するようにしましょう。
2-2.減価償却費の計算方法
減価償却費の計算方法には、定額法と定率法の2種類があります。
定額法は原則として毎年の減価償却費を一定にして計算する方法であり、建物や建物附属設備、構築物は一般的に定額法が用いられます。
一方、定率法は取得価格からこれまでの減価償却費の累計額を差し引いたもの(残存簿価)に、償却率を掛ける方法です。
減価償却費の額は初年度が最も多く毎年減少していくため、経過年数が長くなればそれに応じて償却率も低くなっていきます。
ただし、平成28年(2016年)度改正では、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物の減価償却方法は、定率法が廃止され定額法とすることになっています。
今後アパート建築をする方は、定額法が前提になることを覚えておきましょう。
なお、定額法、定率法の計算式は以下の通りです。
【定額法】
・取得価額×定額法の償却率
【定率法】
・未償却残高×定率法の償却率
5.アパートの減価償却費シミュレーション
実際にアパート経営で減価償却費を活用すると、どのような結果が生じるのでしょうか。
2種類のプランで具体的な数値を用いながらシミュレーションしてみます。
※なお、本シミュレーションでは定額法を用いて計算します。
ケース1:新築の木造アパートで減価償却
はじめに以下の条件でアパートの減価償却費をシミュレーションしてみましょう。
なお、便宜上、物件取得費は諸費用込みとしております。
諸経費には含まれるのは、主に以下のものです。
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・固定資産税
・都市計画税
・仲介手数料
・火災保険料
・ローン手数料
物件取得費はあくまでイニシャルコストなので、固定資産税や管理費や修繕積立金のようなランニングコストは諸経費の中に含まれないことを理解しておきましょう。
ただし、賃貸住宅経営に関わる修繕費やリフォームなどのランニングコストは、減価償却ができるケースもあります。
減価償却費を計上すれば、場合によっては税負担を軽減できる可能性があります。
では、条件に移ります。
【条件】
・物件:新築アパート
・構造:木造
・用途:住宅用
・物件取得費(諸経費込み):5000万円
(内訳:建物価格 3000万円、土地価格 2000万円)
・物件取得日:2022年1月
構造が木造で住宅用の場合、法定耐用年数は22年です。
耐用年数22年の定額法の償却率は、減価償却資産の償却率より0.046であることがわかります。
したがって、減価償却費は以下のように計算します。
減価償却費 = 建物価格3,000万円×0.046= 138万円
本事例では、2022年1月に物件を新築時に取得しているため、2043年分まで毎年138万円の減価償却費を経費として計上し、2044年の申告で減価償却費の計上が完了します。
(定額法の場合、減価償却費は変わらないため)
ケース2:新築の鉄筋コンクリート(RC)造アパートで減価償却
次に以下の条件で同じくアパートの減価償却費をシミュレーションしてみましょう。
【条件】
・物件:新築アパート
・構造:鉄筋コンクリート(RC)造
・用途:住宅用
・物件取得費(諸経費込み):2億円
(内訳:建物価格 1億2,000万円、土地価格 8,000万円)
・物件取得日:2022年12月
構造が鉄筋コンクリート(RC)造で住宅用の場合、法定耐用年数は47年です。
耐用年数47年の定額法の償却率は、減価償却資産の償却率より0.022であることがわかります。
したがって、減価償却費は以下のように計算します。
減価償却費 =建物価格1億2,000万円×償却率0.022=264万円
< 物件取得日が2022年12月のため、初年度(2022年分)は1カ月分のみを月割りで計算します。計算式は以下の通りです。
264万円×(1カ月 ÷ 12カ月)=22万円
したがって、2022年分として経費にできる減価償却費は22万円です。2年目以降は満額の264万円を、耐用年数が尽きるまで毎年経費として計上できます。
RC造住宅の耐用年数は47年のため、2022年12月に物件を取得した場合、2068年分まで毎年264万円の減価償却費を経費として計上し、2069年の申告で減価償却費の計上が完了します。
(定額法のため、毎年の減価償却費は変わりません)
ケース3:耐用年数が残っている中古の木造アパートで減価償却
【条件】
・物件:中古アパート
・構造:木造(法定耐用年数:22年)
・用途:住宅用
・築年数:10年
・物件取得費(諸経費込み):1億2,000万円
(内訳:建物価格 3,000万円、土地価格 9,000万円)
・物件取得日:2025年1月
中古物件の場合は、新築からの経過年数を考慮した耐用年数の再計算が必要です。木造住宅の法定耐用年数は22年のため、次の式で中古の耐用年数を求めます。
(法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 0.2)
(22年 − 10年)+(10年 × 0.2)=14年
したがって、中古アパートの耐用年数は14年です。また、耐用年数14年の定額法の償却率は、減価償却資産の償却率により0.072です。したがって、減価償却費は以下のように計算します。
減価償却費 = 建物価格3,000万円×償却率0.072=216万円
2025年1月に物件を取得しているため、2038年分まで毎年216万円の減価償却費を経費として計上し、2039年の申告で減価償却費の計上が完了します。
(定額法のため、毎年の減価償却費は一定です)
シミュレーションでわかる通り、新築よりも耐用年数が短くなる分、1年あたりの減価償却費が大きくなる点が中古物件の特徴です。
ケース4:耐用年数を超過した中古の木造アパートで減価償却
【条件】
・物件:中古アパート
・構造:木造(法定耐用年数:22年)
・築年数:25年(法定耐用年数)
・用途:住宅用
・物件取得費(諸経費込み):物件取得費総額:6000万円
(内訳:建物価格 600万円、土地価格 5,400万円)
・物件取得日:2025年1月
法定耐用年数を完全に経過した物件の場合は、次の計算式を用いて耐用年数を算出します。
法定耐用年数 × 0.2
22年 × 0.2 = 4.4年
1年未満は切り捨てになるため、耐用年数は4年となります。そして、耐用年数4年の定額法の償却率は、減価償却資産の償却率により0.250です。
したがって、減価償却費は以下のように計算します。
減価償却費 = 建物価格600万円 × 償却率0.250=150万円
2025年1月に物件を取得しているため、2028年分まで毎年150万円の減価償却費を経費として計上し、2029年の申告で減価償却費の計上が完了します。
(定額法のため、毎年の減価償却費は一定です)
法定耐用年数を超過した物件は減価償却の期間が短い分、1年あたりの減価償却費を大きく経費計上できる点が特徴と言えます。
6.減価償却が終わるとどうなるのか
減価償却期間が終わるということは、つまり法定耐用年数が満期に達することを意味します。
アパートなどの賃貸物件は法定耐用年数を超えても利用できるのか、危惧される方も多いと思われますが、法定耐用年数の経過と建物が老朽化する年数は、別物として考えるのが一般的です。
そのため、基本的に法定耐用年数を超えた場合でも、これまで通りアパート経営は続けられます。
法定耐用年数と聞くと建物の寿命のように感じられますが、あくまで減価償却費の計算に使う税務上の指標と捉えておきましょう。
ただし、経年劣化が進んだ建物にはさまざまなデメリットやリスクもあるため、リフォームや修繕、メンテナンスは適時行っていく必要があります。
6.アパートの減価償却について知っておきたいポイント
アパート経営における減価償却は、正しい計算方法の理解が重要です。ここでは、減価償却で知っておきたい代表的なポイントを4つ紹介します。
6-1.改修工事によって耐用年数が延びる可能性はあるか
物件の価値を高めるような大規模な改修工事の支出は「資本的支出」と見なされることがあります。工事によって資産の使用可能期間が延び、実質的に耐用年数を伸ばしたと税務上で判断されるためです。 資本的支出と見なされた場合、減価償却は新たに設定された耐用年数に基づいて行う必要があります。 一方で、原状回復や日常的な維持管理のための工事による支出は「修繕費」に該当し、支出した年度に一括で経費計上できます。 なお、資本的支出か修繕費かの判断は難しいため、税理士などの専門家へ相談して判断してもらうことをおすすめします。
6-2.もし減価償却の計算を間違えたらどうなるか
減価償却費を過大計上していた場合は、過去の申告内容を修正するために更正や修正申告が必要です。また、誤りの内容によっては過少申告加算税や延滞税といった追徴課税が発生する可能性もあります。 一方、過少計上していた場合は、申告後5年以内であれば更正の請求により、納め過ぎた税金の還付を受けられます。
6-3.年の途中で物件を取得した場合はどう計算するのか
年の途中でアパートを取得した場合、初年度の減価償却費は月割りの計算が必要です。取得月の取得月から月数を数え、1年分の減価償却費を数えた月数分で按分して経費計上します。 初年度に関しては1年分の減価償却費を満額で計上できない点に注意が必要です。満額で計上できるのは2年目以降になります。
6-4.建物と附属設備を分けて減価償却できるのか
アパートを新築した場合、建物と附属設備は法定耐用年数が異なります。附属設備は建物より耐用年数が短いため、別々に減価償却を行うことが可能です。 附属設備の価格を明確に分けて計算すれば、建物と合算して償却するよりも短期間で償却して経費計上できるケースがあります。 結果として、経営初期の減価償却費が多く計上でき、税負担を抑える効果が期待できます。 ただし、売買契約書に建物と附属設備の内訳がない場合は、合理的な基準での按分が必要です。合理的に判断するには専門的な知識が求められるため、税理士に相談すると良いでしょう
7.減価償却費の目安を把握しよう
アパート経営では家賃収入によって高い利益を上げた場合、税金負担も重くなりがちです。
減価償却を活用した損益通算ができる青色申告の場合は、有効な税金対策になるので、仕組みをしっかりと把握しておくことをおすすめします。
(ただの支出で終わらせるのではなく、適切な納税を行うことが大事です)
※損益通算とは一定期間の利益と損失を差し引いて課税対象となる利益を算出することです。例えばサラリーマンの給与所得に建物賃貸業で得た不動産所得を合算し、最終的な課税所得を確定させます。
また、経費として計上できるものの種類は、修繕費やリフォーム費用、建て替え費用、ローンの返済(融資利息)などの多岐にわたります。また建て替えを行った場合も経費となります(建物の解体費用も含まれます)。リフォーム工事の場合は必ずしも経費になるかは個別判断となるため、資産計上もあり得ることも留意しておくべきでしょう。
こうした経費の種類のほか、確定申告時の記載方法、注意点なども同時に理解しておくことが大切です。
なお、一定の知識があれば実際に計算式を用いて減価償却費シミュレーションを行えますが、オーナー様ご自身で計算するのが困難であれば、
実績があり、信頼できる不動産会社・建築会社やハウスメーカー、金融機関などへの相談を検討すると良いでしょう。
■監修者プロフィール
税理士法人みらいサクセスパートナーズ 代表
宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上。
現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っている。
また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事。
【保有資格】 税理士、CFP®
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング