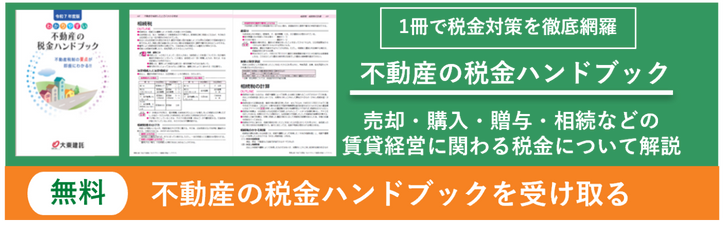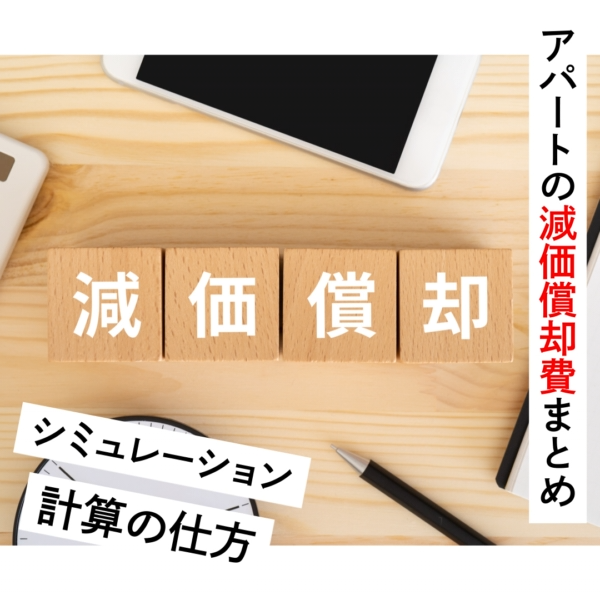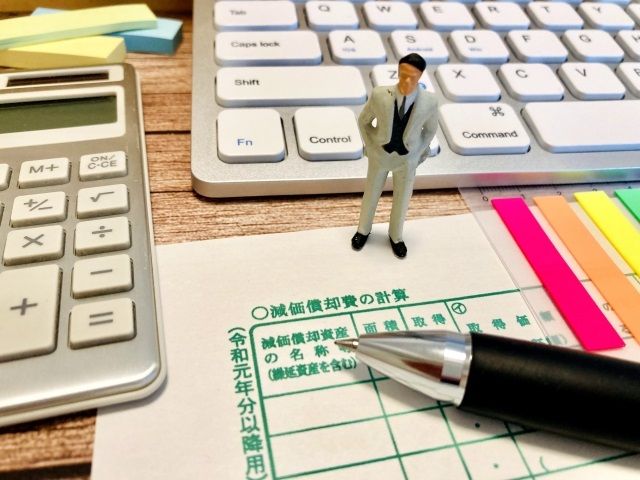家賃収入にかかる税金のシミュレーション|控除できる経費や計算例
公開日: 2025.08.27
最終更新日: 2025.10.24
アパートやマンション経営で不動産所得を得たら、どのような税金がどのくらいかかるのでしょうか。
税金ごとに計算方法や税率、納税のタイミングが異なるため、苦手意識を持っている方が多いかもしれません。
本記事では、家賃収入にかかる税金の求め方と、控除できる必要経費について解説します。後半では税金の計算方法をシミュレーションしていますので、これからアパート・マンション経営を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 家賃収入と税金の概要
不動産経営を始める前に、家賃収入に対する考え方や、かかる税金について把握しておきましょう。
はじめに、家賃収入の内訳と家賃収入にかかる税金、所得税の課税方式について解説します。
1-1. 家賃収入の内訳
家賃収入は、不動産を賃貸に出すことで得られる収入です。
具体的には、入居者から毎月支払われる家賃はもちろんですが、その他に入居者から徴収する管理費や、駐車場代、更新料、礼金なども家賃収入に含まれます。
ただし、礼金は初回のみの収入である点で、毎月の家賃や駐車場代とは異なります。
また、管理費は一般的には入居者の共用部分の維持費としての性質が強いため、家賃本体とは分けて考える場合もあります。
家賃収入は不動産所得に分類され、課税対象となります。ただし、課税所得金額を計算する際には、家賃収入全額がそのまま課税されるわけではありません。
収入から必要経費を差し引いた額が不動産所得として扱われます。
税務署へ確定申告をする際は、どこまでが課税所得金額となるのか把握したうえで納税額を計算しましょう。
1-2. 家賃収入にかかる税金
・所得税
所得税とは、前年の1月~12月の総所得に対してかかる税金です。
入居者から定期的に得る家賃だけでなく、管理費や共益費、駐車場代、更新料、礼金なども原則として不動産所得に含まれ、所得税の課税対象となります。
ただし家賃収入のすべてが課税の対象になるのではなく、所得から必要経費を差し引くことができ、差し引いた後の所得金額に対して税金がかかります。控除できる必要経費については、後ほど詳しく解説します。
・住民税
不動産所得に対しては、地方税である住民税がかかります。
住民税とは都道府県民税と市町村税の2つの税金のことをいい、お住まいの自治体によって税額も異なります。
住民税とは前年の1月~12月の所得に対してかかる税金で、所得金額に応じて税額が決まる「所得割(10%)」と、非課税限度額を超える人すべてが課税対象となる「均等割の5,000円(市町村税3,000円+都道府県税1,000円+森林環境税1,000円)」を合算した額です。
1-3. 家賃収入に課税される場合がある税金
・消費税
家賃収入に課税される可能性がある税金として、消費税があります。
居住用建物の家賃収入は非課税です。ただし、課税売上高が年間1,000万円を超える場合、課税事業者となり、貸店舗や駐車場収入などの課税収入に対して消費税申告義務が生じます。
ちなみに消費税課税業者としてインボイス制度に登録している場合にも、課税取引に対して消費税の申告義務が生じます(ただし居住用の家賃収入は非課税なので、インボイスの発行も不要)。
・個人事業税
法定業種を営む方で、かつ事業所得が年間290万円を超える場合は、個人事業税がかかります。
不動産貸付業は第一種事業に該当し、事業的規模(一般的に5棟10室基準など)に該当する場合は個人事業税(税率5%)が課されます。
個人事業税額は290万円を超えた部分にかかるため、事業所得額から290万円をマイナスした額に、税率を乗じて計算してください。個人事業主は1月1日~12月31日までの所得を、翌年の2月1日~3月31日までに各都道府県税事務所に申告が必要になります。
1-4. 所得税の課税方式
アパートやマンション経営で得た不動産収入は、不動産所得に分類されます。
合計所得金額から必要経費を差し引いた金額が所得となり、総合課税が適用されます。
総合課税とは、家賃収入のほか、給与収入や事業所得などの収入を合算して税額を計算する仕組みのことです。
2. 家賃収入において経費として計上するもの
不動産経営において、必要経費として認められる費用は、家賃収入から控除できます。
課税対象となる所得を減らすことで節税効果が期待できるため、見落とすことがないようにしたいものです。
ここでは、不動産経営の主な必要経費を7つ紹介します。
2-1. 維持管理費
維持管理費とは、建物の資産価値の維持や、入居者が安心・快適に暮らすために必要な経費のことをいいます。
アパートやマンションなど、管理会社に管理や清掃を委託している場合は、その管理委託料も必要経費として計上できます。
確定申告にそなえて、管理会社との契約書や領収書を保管しておくようにしましょう。
維持管理費に該当するのは、以下のような費用です。
・管理委託料
・清掃費
・共用施設の維持費
・設備の保守点検費
・修理費・リフォーム費用
・修繕積立金
・警備費
・防犯対策費
・水道光熱費
・交通費(現地へ出向いた場合など)
・通信費(入居者への書類送付など)
2-2. ローン金利
収益物件購入にあたって、不動産投資ローンを利用している場合は、ローン金利を必要経費として計上できます。
建物に対する貸付けだけでなく、土地や設備に対する借入金も対象ですが、金利が対象であり、元金は含められませんので注意しましょう。
2-3. 損害保険料(火災保険料や地震保険料など)
アパートやマンションの火災保険料や地震保険に加入した場合は、その保険料も必要経費にあたります。
なお確定申告に必要な書類については、保険会社に連絡して明細を準備しておきましょう。
2-4. 減価償却費
減価償却とは簿記上の経費であり、実際には収入から引かれるものではありません。
建物新築(購入)にかかった費用を 法定耐用年数に応じて配分し、毎年経費(減価償却費)として計上することができます。 なお土地は時間の経過とともに価値は減少しないため、減価償却は行いません。
ちなみに法定耐用年数は建物の用途や構造によって異なり、ちなみに木造(居住用)は22年、鉄筋コンクリート造(住居)は47年です。
中古アパートを購入した場合も減価償却できますが、中古物件の場合は残存する耐用年数算出する必要があります。法定耐用年数をすべて経過した場合と、法定耐用年数が残っている場合では計算式が異なり、それぞれ以下のように計算します。
法定耐用年数がすべて経過しているケース
耐用年数=法定耐用年数×0.2
法定耐用年数が一部残っているケース
耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)
上記計算式で算出し、1年未満の端数は切り捨てします。耐用年数が2年に満たないときは、2年とします。
参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
2-5. 税金(固定資産税や都市計画税など)
不動産投資にかかる税金も、必要経費として計上できることを覚えておきましょう。
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となる固定資産税や都市計画税のほか、購入時に発生する不動産取得税、登記に際して納税する登録免許税も対象です。
ちなみに所得税や住民税、法人税は計上できません。
なお経費として計上できる税金は、以下のとおりです。
・固定資産税
・都市計画税(市街化区域内が対象)
・不動産取得税
・印紙税(契約書に貼付)
・登録免許税(登記の際)
2-6. 司法書士費用
司法書士や税理士など、専門家へ支払った報酬(費用)も必要経費として計上できます。
司法書士へ所有権移転登記を依頼したときに支払った手数料や、顧問税理士へ支払う報酬などが対象です。
ちなみに入居者とトラブルになった場合などに弁護士費用がかかった場合は、その弁護士費用も含めて申告できます。
2-7. 青色専従者給与(青色申告をしている場合のみ)
本来従業員へ支払った給与は必要経費として認められませんが、青色申告している個人事業主は、一定の要件を満たすことで家族へ支払った給与も経費として計上できます。
なお所定の期限までに税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出する必要があります。
3. 家賃収入にかかる税金の計算方法
不動産経営をした場合、どのくらいの税金がかかるのでしょうか。
アパートやマンション経営を検討するのであれば、目安となる納税額を試算してみましょう。
家賃収入に対してかかる税金の計算方法を、手順に沿って解説します。シミュレーションも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産所得にかかる所得税と住民税を計算する手順を、流れに沿って解説します。
3-1. 不動産所得の計算
まず、不動産所得を算出しましょう。月々の家賃や駐車場代に更新料などを含めた賃貸経営で得られる総収入金額を算出します。
次に減価償却費や管理会社に支払う管理料、修繕費、保険料など、賃貸経営にかかった必要経費を計算します。総収入金額から必要経費を差し引いた金額が、不動産所得となります。
不動産所得を求める計算式は、以下のとおりです。
|
不動産所得=総収入金額-必要経費 |
3-2. 所得税の計算
不動産所得を算出できたら、税率を乗じて所得税を計算しましょう。
なお所得税の税率は所得が増えるにつれて課税額も増える累進課税が採用されており、分離課税するものを除くと、以下のとおり5%~45%の7段階に分けられます。
|
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
0円 |
|
1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
|
3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
|
6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
|
9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
|
18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
|
40,000,000円 以上 |
45% |
4,796,000円 |
参考:国税庁「所得税の税率」
課税される所得金額に応じた税率と控除額を用いて、以下の計算式で所得税額を求めることができます。
|
所得税額=課税所得×所得税率-課税控除額 |
3-3. 住民税の計算
次に、住民税を計算してみましょう。
住民税は、前年度の所得金額に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」を合計して求めます。
|
住民税=所得割(10%)+均等割(定額) |
所得割の税率は10%ですが、自治体によって異なる場合があります。実際の税率は、お住まいの自治体へお問い合わせください。
均等割は定額で、都道府県税1,000円、区市町村民税1,000円、森林環境税1,000円を合計した5,000円です。
住民税額は、以下の計算式で求めることができます。
|
所得割額=課税所得金額×10%-税額控除額 住民税=所得割額+均等割額(5,000円) |
4. 家賃収入にかかる税金のシミュレーション
家賃収入に対する税金がどのくらいかかるのかイメージするために、ここでは設定した条件をもとに、かかる税金をシミュレーションしてみましょう。
家賃収入のみのケースと、家賃収入以外にも所得があるケース別に、所得税と住民税を計算します。
4-1. シミュレーション例:家賃収入のみの場合
・所得税のシミュレーション
以下の条件にしたがって、所得税を計算します。
条件
・家賃収入:800万円/年
・必要経費:200万円/年
・不動産所得:600万円(800万円-200万円)
・基礎控除:48万円
・所得税率:20%(3,300,000円 から 6,949,000円まで)
・控除額:427,500円(3,300,000円 から 6,949,000円まで)
計算式
(600万円-48万円)×20%-427,500円=676,500円
所得税=676,500円となります。
・住民税のシミュレーション
以下の条件にしたがって、住民税を計算します。
条件
・家賃収入:800万円/年
・必要経費:200万円/年
・不動産所得:600万円(800万円-200万円)
・住民税率:10%
・基礎控除:43万円
・均等割:5,000円
計算式
(600万円-43万円)×10%+5,000円=562,000円
住民税=562,000円となります。
4-2. シミュレーション例:家賃収入以外の所得がある場合
上記不動産所得以外に給与所得があり、課税所得金額が850万円のケースをシミュレーションしてみましょう。
条件
合計課税所得金額:850万円
所得税率:23%(6,950,000円 から 8,999,000円まで)
控除額:636,000円(6,950,000円 から 8,999,000円まで)
計算式
850万円×23%-636,000円=1,319,000円
所得税=1,319,000万円となります。
住民税は、以下のとおり計算できます。
850万円×10%+5,000円=855,000円
住民税=855,000円となります。
なお給与所得者は給与から所得税が源泉徴収されるため、その差額を確定申告で納めることになります。
※実際の税額の計算はその他の控除や税制により影響を受けることがあるため、具体的状況によっては税理士など専門家に相談することをおすすめします。
5. 不動産投資にかかる税金を理解しておくことが重要
不動産投資によって所得が増えれば、所得税だけでなく住民税も高くなります。
また不動産所得が事業規模になれば消費税もかかるため、必要経費として計上できる費用を把握し、税金がいくらぐらいかかるのか事前に試算しておくことが大切です。
大東建託ではお客様の状況に合わせて適切な節税効果を提示します。
不動産経営にかかる税金に関する疑問や節税対策については、ぜひ大東建託にお気軽にお問い合わせください。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング