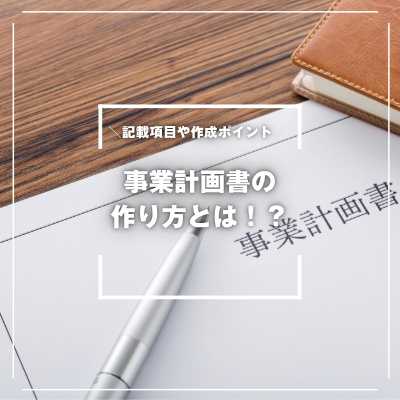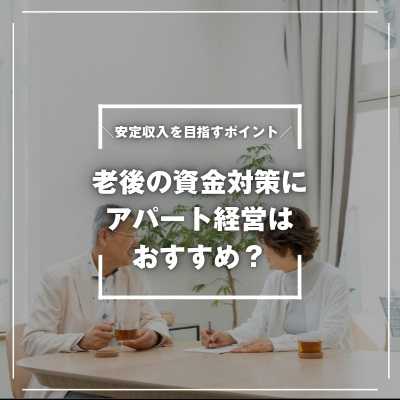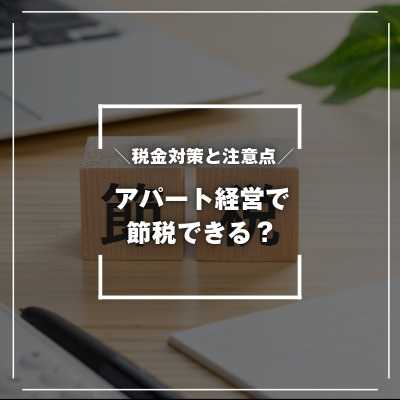アパート経営の損益分岐点とは?計算方法と収支の考え方
公開日: 2025.04.10
最終更新日: 2025.09.26
アパート経営を成功させるためには、損益分岐点を意識することが重要です。損益分岐点とは、収入と支出がちょうど釣り合うポイントであり、利益を得るために最低限必要な収入を表しています。
この記事では、損益分岐点の基本的な知識や計算方法を解説するとともに、経費削減や家賃設定の工夫によって損益分岐点を下げる方法についてまとめました。
また、損益分岐点の関連のある長期的な経営戦略や出口戦略の視点も交えながら、安定したアパート経営を実現するためのポイントも解説しています。
目次
1. 損益分岐点の基礎知識
経営の成功に不可欠である「収入と支出のバランス」。
その指標となるものに「損益分岐点」があります。ここでは、損益分岐点とは一体何なのか、損益分岐点から何がわかるのかを解説します。
1-1. そもそも損益分岐点とは
損益分岐点とは、収益と費用が同額となり、利益がゼロ(収益-費用=0)となる金額を指します。アパート経営では、家賃収入と経費がちょうど釣り合う家賃収入や経費の金額を指します。
損益分岐点を上回る家賃収入があればアパート経営は黒字、なければ赤字になります。
つまり、損益分岐点となる家賃収入とは、赤字経営をしないために最低限稼がなければならない金額のことです。
損益分岐点は一定ではなく、状況に応じて変動します。損益分岐点を下回らないための基本的には方法としては「コストの低減」が挙げられます。
具体的にはアパート経営にかかる管理費や火災保険料などの「固定費」や共用部の光熱費、修繕費といった「変動費」の削減を図る必要があるでしょう。
損益分岐点を下げつつ、家賃とのバランスを最適に設定することで、今よりも利益が発生しやすい状態になります。
逆に、損益分岐点が上がれば、利益が発生しにくい状態になります。
損益分岐点が上がる要因には、空室が増えて家賃収入が減ることや、過剰な投資、固定費(例:保険料やローンの利息)の増加などが挙げられます。
1-2. 損益分岐点からわかること
アパート経営を始めると「今の家賃の設定がコストに合っているのだろうか」と悩む場面が沢山あります。
このような悩みを抱えた際、損益分岐点は、収入と支出のバランスを考える指標となります。
まず、損益分岐点を下回らないための家賃収入、つまり経費を賄うために最低限必要な収入を把握することで、経費に対する適正な家賃設定の目安がわかります。
同時に、最低限確保しなければならない入居率も見えてきます。
もちろん、不動産投資そのものの判断や、アパート経営における中長期の経営計画を策定する際にも、損益分岐点は役に立ちます。
一方で、仮に損益分岐点から算定した家賃が周辺相場よりも高ければ、経費を見直す機会になります。これまでは気付けなかった無駄な支出が隠れており、損益分岐点が高くなりすぎて利益を得にくい経営になっているのかもしれません。
このように、損益分岐点を把握することで、家賃収入が損益分岐点を下回らないために取るべき行動が明確になり、安定したアパート経営が可能になります。
2. アパート経営の主な収入と支出
損益分岐点を正しく理解するには、「収入」と「支出(固定費+変動費)」の関係を理解する必要があります。
ここでは、アパート経営における主な収入と支出について詳しく解説します。
|
収入 |
家賃収入など |
|
固定費 |
ローン返済、管理委託料、各種保険料など |
|
変動費 |
修繕費、共用部分の水道光熱費など |
2-1. アパート経営の収入
アパート経営における主な収入源は「家賃収入」ですが、そのほかにも共用部分の維持管理費である「共益費・管理費」や「駐車・駐輪場賃料」、「礼金」、「更新料」などが含まれます。
これらの収入の合算から固定費と変動費を差し引いた金額が損益分岐点を下回らないようにすることが、多くの人にとっての大まかなアパート経営の目標となります。
2-2. アパート経営の固定費
アパート経営における固定費とは、入居者の数や有無などに関わらず毎月発生する定額の費用のことです。
具体的な固定費としては、管理委託費や共用部分の清掃費、ローンの金利・手数料、土地を借りている場合はその賃料、修繕積立費、税金などが挙げられます。
一般的に固定費は変動費と比べるとコントロールするのが難しい一方、削減に成功できれば損益分岐点を下げる大きな効果が期待できます。
2-3. アパート経営の変動費
アパート経営における変動費とは、アパートの経営状況によって変動する費用のことです。
例えば、入居者募集のための広告宣伝費は空室が少ない状況であればコストをかける必要性は低くなりますし、そもそも立地条件が優れているなどアパートの魅力が高ければ、長期的な変動費に大きな差が生じる可能性もあります。
その他の変動費としては、オーナー負担の原状回復費、修繕費、管理会社と連絡に必要な通信費などが該当します。
アパート経営には、初期費用とランニングコストが発生します。初期費用とは、アパート経営を始めるためのコストであり、代表的なものとして、物件の設計や建築にかかる本体工事費があります。
一方、ランニングコストとは、アパート経営を継続するためのコストであり、主に以下のような費用があります。
・ローン返済費:物件購入時の借入金の返済額(元本+利息)
・管理委託料:物件管理を委託する際の管理会社への手数料。
・修繕費:建物や設備の維持管理や日常清掃、定期清掃などのメンテナンス費、退去時の原状回復やリフォーム等にかかる費用。
日常的に発生する小規模な修繕だけでなく、数年に一度の大規模な修繕費(外壁、室内設備の交換など)も発生することに注意。
・保険料:火災保険や地震保険などの保険料。
・税金:保有する土地や建物に対する固定資産税・都市計画税などの税金。
・その他:共用部分の水道光熱費など
このようにアパート経営には、さまざまな支出が発生します。
これらを適切に管理し、家賃収入とのバランスを取ることで、アパート経営の安定性を確保することが重要です。
3. アパート経営の損益分岐点の計算シミュレーション
一般的な損益分岐点は、収益と費用が一致する金額を指します。
一方で、アパート経営では、初期投資が高額になりやすいため、不動産投資ローンを組んで実施するケースが一般的です。
そのため、仮に損益分岐点となる家賃収入が得られており、会計上は赤字ではなかったとしても、ローンを返済できるだけのキャッシュフローがなければ、アパート経営を続けられなくなります。
アパート経営の損益分岐点を計算する際は、収入と支出、つまりキャッシュフローを基に計算する方法が有効です。
簡単な例で、実際に計算してみましょう。
【例(満室時)】
・アパート経営(全10戸、木造・1K)
・ローン返済額(元利均等返済で毎月25万円ずつ返済(利息を含む))
【収入】
家賃収入:月額家賃5万円、年600万円(満室時:月5万円×10室×12ヶ月)
【支出】
損益分岐点を計算する場合、支出は、収入に応じて増加する「変動費」と、収入の有無にかかわらず発生する「固定費」に分ける必要があります。
これらは支出の中身で判断しますが、ここでは下記のように分類し、他の支出は発生しないものと仮定します。
・変動費
家賃収入の10%(満室時であれば、60万円)
(内訳)管理委託料(家賃収入×5%)、修繕費や共用部分の水道光熱費などの諸費用(家賃収入×5%)と仮定
・固定費
総額年400万円 (内訳)ローン返済費:300万円(25万円×12ヶ月)、保険料:20万円、税金:80万円と仮定
【損益分岐点の計算方法】
損益分岐点となる家賃収入は、下記の式で計算することができます。
「変動費比率」とは「変動費÷家賃収入」のことです。
損益分岐点=固定費÷(1-変動費比率)
この計算式にあてはめると、損益分岐点となる家賃収入が約444万円であることがわかります。
損益分岐点=400万円÷(1-0.1) =約444万円
したがって、満室(家賃収入600万円)であれば、余裕のあるアパート経営ができることがわかります。
この計算式は、たとえば「アパート経営から年200万円の副収入が欲しい」といった場合の、目標となる家賃収入の計算にも応用できます。
固定費400万円に目標額の200万円を足し、同様に「1-変動費比率」で割ることで算定することができます。
目標となる家賃収入=(400万円+200万円)÷(1-0.1) =約666万円
したがって、あくまで計算上ですが、1室あたりの家賃収入を5万5,500円に値上げすることで200万円の収入を達成することができることがわかります。
一方で、アパートの空室率が高まると損益分岐点を下回ることになります。
たとえば空室率が30%(10部屋のうち3部屋が空室)になると、家賃収入は420万円に下がり、損益分岐点を下回ります。
この場合、収支はマイナスとなりますので、損益分岐点を下げるための対策(入居率の改善など)が必要になります。
4. アパート経営で損益分岐点を下げるための方法
損益分岐点が高い状態が続くと、アパート経営の安定性が損なわれます。
ここでは、損益分岐点を下げるための一般的な方法を紹介します。
4-1. なるべく空室を作らない
空室が増えると家賃収入が減少し、損益分岐点を下回るリスクが高まります。
なるべく空室を作らないために、魅力的な設備やサービスを導入して入居者の満足度を高め、長期的に住んでもらえるようにすることなどが重要です。
一方、空室率を下げることのみに注力して家賃を安易に下げてしまうと、将来的に受け取れる収益を押し下げる要因につながる可能性があることも考慮してしなければなりません。
4-2. 適切な賃料を設定する
賃料の設定によって、黒字化までにかかる期間が大きく変わります。
しかし、高すぎる賃料は空室の原因になりますし、低すぎても利益が出にくくなります。
適切な賃料の目安は物件や立地条件によって異なるため、不動産会社に相談することも有効です。
4-3. 耐久性の高い設備を導入する
劣化のしにくい耐久性の高い設備を導入して、修繕の頻度を抑えることで、ランニングコストを削減することができます。
一見すると高額な設備投資に見えるものも、長期的な経営の視点で考えれば結果的に経費削減につながることがあります
4-4. 管理費を見直す
管理の手法や管理委託手数料などの管理費は管理会社によって異なるため、契約先の選定はしっかりと行う必要があります。
適切な管理業務を実施することで入居者満足度が高まることで退去を抑制につながり、家賃の途絶期間の減少と原状回復費の支出回数減少が賃貸経営の安定にも期待できるからです。
また、契約したまま放置するのではなく、コスト削減の余地がないかどうか、修繕や清掃の内容や頻度などを定期的に見直すことも重要です。
なお、自主管理をすれば管理費そのものが削減できますが、入居者への対応などの手間や不動産に対する多くの知識が必要となるため現実的ではありません。
アパートの収益性を維持するために、賃貸物件の管理はプロに任せることがおすすめです。
4-5. 適切に経費計上を行う
経費を適切に計上することで所得税や住民税の負担を軽減できます。
特に減価償却費を活用して損益通算を行うことにより、本業の税負担を抑えることも可能です。
節税対策は税理士や会計士に相談しながら進めましょう。
5. 損益分岐点から考えるアパート経営のポイント
アパート経営において損益分岐点を意識することは、単なる数字の管理ではなく、長期的な経営戦略を立てるうえで非常に重要です。
短期的な収支の変動にとらわれず、将来的な収益や物件の価値を見据えた判断を行うことが成功のカギとなります。
ここでは、アパート経営の長期的な収支の考え方や、物件売却を含めた出口戦略の重要性について説明します。
5-1. 収支の増減は長期的な視点で考える
アパート経営は、長期的な視点で安定した経営を目指すことが大切です。
特に相続税対策も見据えてアパート経営を始める場合は、こうした視点を持ち、より良い経営状態で次世代に引き継ぐことを目指すことも重要となります。
損益分岐点を把握することは、アパート経営において非常に重要なことですが、ここでも長期的な視点が大切になります。
たとえば、突発的な修繕や退去の増加などによって、一時的に損益分岐点を下回ることがありますが、長期的に見ればよくあることです。
こうした一時的な変動に惑わされると、冷静な判断ができなくなってしまいます。
5-2. 出口戦略も含めて考える
アパート経営は、長期的に家賃収入を得るだけでなく、物件そのものを売却することで売却益(キャピタルゲイン)を得ることもできます。
仮に運営中の収支が損益分岐点を下回っていても、物件を高値で売却できれば、最終的に損益分岐点を上回り、黒字となる可能性があります。物件の価値は変動するため、損益分岐点を上回るタイミングで売却することがポイントです。
なお、アパート経営の出口戦略を考える際には、物件の価値を向上させるための取り組みが重要です。定期的なメンテナンスや適切なリフォームを行うことで、将来的により良い条件で売却できる可能性が高まります。
6. 損益分岐点を意識し、長期的に安定した経営を
アパート経営を安定させ、長期的に利益を確保するためには、損益分岐点を正しく理解し、適切な判断を行うことが重要です。損益分岐点を把握することで、必要な家賃収入が明確になり、経費削減や空室対策など次に取るべき行動が見えてきます。
また、短期的な収支の変動に惑わされず、出口戦略も考慮しながら経営を続けることで、リスクを抑えつつ安定した収益を確保できます。損益分岐点を活用し、持続可能なアパート経営を目指しましょう。
もし収益を左右する適正な家賃の設定が難しい場合は、大東建託が提供するプラットフォーム「アセトラ」の「AI不動産投資シミュレーション」をぜひお試しください。
不動産ビッグデータとAIによる分析で、適正家賃や将来の家賃変動・空室リスクの可能性などを予測できます。
>>参考ページ:「アセトラ」のAI不動産投資シミュレーション
■監修者プロフィール
ここりんくす株式会社 代表取締役
小泉寿洋
ここりんくす株式会社代表取締役。上場グループに属する賃貸不動産会社で賃貸仲介、賃貸管理部門に14年半ほど従事。その後、不動産仲介・建築工事・終活サポートの会社経営を経て、現在は賃貸経営・賃貸管理・終活に関するコンサルティング、WEBセミナー講師、不動産・FP系ライターなど各方面で活動中。不動産業界歴は約23年。
【保有資格】
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー1級、終活ガイド1級、遺品整理士他
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング