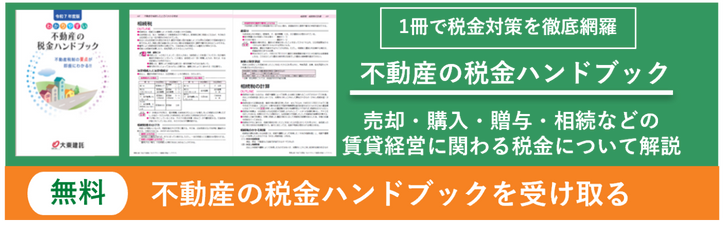アパート経営で節税はできる?固定資産税などの対策と注意点
公開日: 2024.09.27
最終更新日: 2025.10.28
アパート経営は魅力的な不動産投資ですが、成功には適切な税金対策が欠かせません。
多くの投資家が家賃収入や節税を目的にアパート経営を検討しますが、実際にはさまざまな税金が関わります。税負担を抑え、収益を最大化するには、税金の仕組みや軽減措置、適用できる特例を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
本記事では、アパート経営に必要な税金の基礎知識と節税ポイントを解説し、健全な経営につなげる方法を紹介します。
目次
1.アパート経営にかかる税金の種類
アパート経営を始める際、さまざまな場面で税金が発生します。
これらの税金を理解し、適切に対応することが節税の基本となります。
*アパート経営にかかる税金の一覧表
|
税金が発生する場面 |
税金の例 |
|
初期費用にかかる税金 |
不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税 |
|
収益にかかる税金 |
所得税や住民税、個人事業税、法人税など |
|
不動産の維持にかかる税金 |
固定資産税、都市計画税など |
初期費用では、不動産取得税や登録免許税、印紙税などが課されます。
これらは土地や建物の購入時に発生する税金です。
特に、アパート建築時には建築費に応じて課税されるため、注意が必要です。
収益面では、家賃収入に対して所得税や住民税などが課税されます。
不動産所得として計算され、給与所得とは別に課税されるのです。
また、事業規模によっては個人事業税も課税対象となる可能性もあります。
不動産の維持に関しては、毎年固定資産税、都市計画税が課されます。
土地と建物の固定資産税評価額に基づいて計算されるため、アパートの規模や立地によって税額が変わってきます。
これらの税金を適切に管理し、必要経費を正確に把握することで、効果的な節税策を講じることが可能です。
なお、税法は複雑であるため、具体的な節税方法については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、経営を行っている最中には発生しませんが、経営したアパートを相続した際は、それぞれ相続税と贈与税が課せられます。
2.固定資産税の基礎知識
アパート経営ではさまざまな税金が発生しますが、中でも固定資産税は毎年の支出として重要なポイントです。
ここからは、固定資産税の仕組みや計算方法、納付方法などの基礎知識を深掘りし、適切な管理のポイントを解説します。
2-1.固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している場合に課される税金です。
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、市区町村などの地方自治体(東京23区は東京都)が課税を行います。
アパート経営では、土地と建物の両方に対して固定資産税が発生するため、適切に把握しておくことが重要です。
2-2.固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地や建物に関わる税の計算における基準となる不動産の価値である「評価額」に税率をかけて算出します。
この計算には固定資産税を求めるための基準である「課税標準額」が使用され、納税通知書に記載されています。
また、基本的に評価額と課税標準額は同じとなりますが、特例措置などの調整が適用される場合は課税標準額は評価額よりも低くなるケースがあることも覚えておきましょう。
一般的な税率は1.4%ですが、地方自治体によって異なる場合があります。
計算式は以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
正確な税額を把握するためには、毎年の納税通知書を確認し、自治体ごとの税率を把握しておくことが大切です。
2-3.固定資産税の納付方法
固定資産税は、1年分の税額を年4回に分けて納付するのが一般的です。ただし、一括で納付することも可能です。
納付のスケジュールは地方自治体によって異なるため、毎年送付される納税通知書を確認し、適切な時期に納付することが重要です。
なお、年の途中で建物を新築したり不動産を購入したりした場合、固定資産税は翌年度から課税されるのが原則です。
ただし、地域によっては取得した年に不動産取得税や固定資産税の月割り負担が発生するケースもあるため、自治体からの通知内容を必ず確認するようにしましょう。
3.アパート経営にかかる税金ごとの節税対策のポイント
アパート経営で効果的な節税を行うには、各税金の特性を理解し適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、主な税金ごとの節税ポイントを解説します。
これらの方法を活用して不動産所得を最適化し、税負担の軽減を目指しましょう。
3-1.所得税や住民税の税金対策
・損益通算で所得を減らす
アパート経営においては、損益通算を利用することで所得を減らすことが可能です。
損益通算とは、アパート経営から発生する赤字(実質手取りよりも申告上の所得が下回った額)を他の所得と合算することで、全体の所得を圧縮し、所得税額や住民税額を軽減する方法です。
具体的には、アパート経営の初期投資や修繕費用などの経費が収益を上回る場合、その赤字を給与所得や事業所得と合算することで、課税所得を減らすことができます。
とくに、建物にかかる減価償却費は実際の支出を伴わないものですが、経費として計上できるため、帳簿上は赤字となりやすく、損益通算による節税効果が生まれるケースがあります。
また、アパート経営の場合は物件管理の委託料やローンの金利も経費計上することが可能です。
例えば、アパート経営による赤字が500万円で、他の所得が1000万円の場合、損益通算により課税対象となる所得は500万円(1000万円 - 500万円)となります。
この結果、所得税や住民税の負担が軽減されることになるのです。
損益通算を適用するためには、税務署に確定申告を行う際に適切な書類を提出する必要があります。
また、税務の専門家に相談することで、最適な方法を選択し、法的に適切な手続きを行うことが重要です。
・確定申告で青色申告を選択する
アパート経営の効果的な税金対策として、確定申告で青色申告を選択し、青色申告特別控除を受けることが挙げられます。
この方法では、最大65万円(電子申告の場合)の控除を受けられ、課税所得を大幅に減らすことが可能です。
例えば、不動産所得が300万円の場合、青色申告特別控除を適用すると課税所得が235万円に減少し、結果的に所得税と住民税の負担が軽減されます。
青色申告特別控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
-
- 事前に青色申告承認申請書を税務署に提出すること
- 日々の取引を正確に記帳し、複式簿記で帳簿を作成すること
- 決算書類(貸借対照表、損益計算書など)を作成し、確定申告書に添付すること
- 期限内に確定申告書を提出すること
- 事前に青色申告承認申請書を税務署に提出すること
これらの要件を満たすことで、アパート経営者は青色申告特別控除を活用し、効果的な節税を実現できます。
・減価償却を計上する
アパート経営における重要な税金対策の一つに、減価償却の計上があります。
減価償却とは、建物の価値が時間とともに減少していく分を経費として計上できる仕組みです。
アパートの法定耐用年数(木造アパートの場合は22年)の期間中、毎年一定額を経費として計上できます。
これにより、課税対象となる不動産所得を減らし、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
例えば、2,000万円の木造アパートを定額法で償却する場合、年間の減価償却費は約90万円(2,000万円÷22年)です。
この90万円を毎年経費として計上できるため、課税所得を減らす効果が期待できます。
加えて、アパートの大規模修繕や設備追加も重要な節税対策となります。
例えば、外壁の修繕や屋根の改修、エアコンや給湯器の新規設置などのコストは、修繕費や設備投資費として経費計上が可能です。
これにより、課税所得を軽減することができます。
ただし、減価償却の計算や申告には正確な知識が必要です。
また、建物の構造や取得時期によって適用される償却率が異なるため、具体的な計算方法については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
・法人化する
アパート経営の税金対策として、法人化は有効な選択肢の一つです。
個人経営から法人経営に移行することで、新たな節税の可能性が生まれます。
具体的には物件を個人所有から法人所有に切り替える方法や、アパート管理会社を設立し、その会社にアパートの管理を委託する方法という方法があります。
法人がその業務を行うために使ったと認められる費用は経費と認められ、管理会社に管理を委託するというケースでは、設立した管理会社に支払う委託料は、個人の不動産所得を計算する際の必要経費として認められます。
これにより、課税対象となる不動産所得を減らすことができ、所得税や住民税、法人税の負担を軽減することが可能です。
ただし、法人化には設立費用や維持費用がかかり、手続きも複雑になります。また、個人の場合と比べて社会保険料の負担が増える可能性もあります。
そのため、法人化の判断には慎重な検討が必要です。
3-2.固定資産税の税金対策
固定資産税の税金対策としては住宅用地の特例と建物の軽減措置が適用されます。
通常の課税では【課税標準額×税率1.4%】を負担する形になりますが、アパートを建て保有することにより、税率を抑えることができます。
簡単に言ってしまえば、一般住宅用地では、固定生産税の課税価格に対し、小規模住宅用地で1/6を掛ける形で算出される形になります。
下記の表を抑えておきましょう。
|
一般住宅用地 |
小規模住宅用地 |
|
|
固定資産税 |
課税価格×1/3 |
課税価格×1/6 |
|
都市計画税 |
課税価格×2/3 |
課税価格×1/3 |
3-3.相続税の税金対策
相続税の効果的な税金対策として、小規模住宅用地の特例があります。
この特例は、亡くなった人が賃貸用として使っていた土地を、賃貸経営を続ける人が相続した場合、200㎡まで評価額を50%軽減するものです。
対象となるのは、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地、駐車場の敷地、地主が借地人に貸している土地(貸宅地)などです。
適用を受けるには、相続人が相続税の申告期限まで土地を継続して所有し、賃貸経営を続けることが条件です。
ここでいう賃貸経営とは、相当の家賃や地代を受け取っていることが前提で、親族間の格安賃貸は対象外となります。
注意点として、平成30年4月1日の税制改正により、相続発生の3年以内に新たに貸し出した土地には、この特例が適用されなくなりました。
これは、相続直前の賃貸不動産購入による相続税対策を制限するためです。
また、この特例は贈与の際には適用されません。あくまで相続時に利用できる制度であることは覚えておきましょう。
なお、適用には細かい条件があるため、具体的なケースについては税理士や専門家に相談することをおすすめします。
4.アパート経営の税金対策の注意点
アパート経営における税金対策は、経営の安定と収益の最大化にとって重要な要素です。
しかし、適切な対策を講じるためには、いくつかの注意点を把握しておく必要があります。
ここでは、アパート経営の税金対策を行う際に留意すべきポイントを簡潔に紹介します。
4-1.法人化が税金対策になる所得の目安がある
一般的な目安として、法人化による節税効果が得られるのは所得が800万円を超えたあたりです。
個人事業主としての所得税率は累進課税であり、所得が増えるにつれて税率が上がります。
一方、法人税の税率は個人の所得税率よりも一定であり、高所得者にとって有利になる場合があります。
以下の表は、所得税と法人税の税率を比較したものです。
【所得税率と法人税率の比較】
|
所得税の区分 |
所得税の税率 |
法人税の区分 ※資本金1億円以下 |
法人税の税率 |
|
1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
800万円まで |
15% |
|
1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
||
|
3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
800万円以上 |
23.2% |
|
6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
||
|
9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
||
|
18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
||
|
40,000,000円 以上 |
45% |
【出典】:「No.2260 所得税の税率」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
【出典】:「No.5759 法人税の税率」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
この表からわかるように、所得が増えるにつれて個人の所得税率は大幅に上がります。
一方、法人税の税率は比較的一定であり、特に所得が高い場合に法人化することで節税効果が期待できます。
なお、法人化を検討する際には、税務の専門家に相談し、自身の収益状況や将来の計画を考慮した上で最適な選択をすることが重要です。
4-2.一部の節税効果は一時的なことを理解する
アパート経営の税金対策は、減価償却やローン金利など一時的な効果が多く、長期的には節税効果が減少していきます。
例えば、木造アパートの減価償却は22年で終了し、その後は経費計上できなくなります。
しかし、この節税効果を単年度ごとに見るだけではなく、事業開始からの累計(通算)で考える視点も重要です。
初期の節税効果によって生まれるキャッシュフローを有効に活用し、再投資や運用に充てることで、長期的な収益性を高めることができます。
したがって、税対策だけに頼るのではなく、適切な家賃設定や空室率の低下、効率的な管理などを通じて、アパート経営全体の収益性を向上させることが求められます。
4-3.経費にできるものとできないものがある
所得税の節税が可能になる確定申告では、経費として認められる費用と認められない費用を正確に区別することが重要です。
アパート経営に直接関係する各種保険料、借入金の利息、広告宣伝費、修繕費などは経費として認められ、不動産所得から差し引けます。
一方、借入金の元金返済や個人的な支出は経費として認められません。
適切な経費計上は所得税や住民税の負担軽減につながりますが、判断が難しい場合は税理士に相談し、正確な記帳と領収書の保管を心がけましょう。
>>関連記事:アパート経営の経費で落とせるもの一覧|判断基準や計上できないもの
4-4.賃貸物件としての評価を高める
最後に相続税を節税したいと考えている人向けの注意点を解説します。
相続税を節税するためにアパート経営を行おうと考えている場合、建てたアパートに入居者が多く住んでいることが重要になってきます。
アパートの部屋が埋まっていると、多くの人に物件を貸している状態と解釈され、相続税の評価額が下がるからです。
アパートのような賃貸物件の場合、満室の状態は相続税の節税効果が最も高くなります。
したがって、入居者から見て魅力的に映る物件を目指し、なるべく多くの入居者に住んでもらうことが節税のポイントとなります。
4-5.固定資産税の納付期限に気をつける
固定資産税は、指定された期限内に納付する必要があります。アパートを所有している場合も同様で、期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があります。
固定資産税を滞納すると、延滞金の支払いが発生する可能性があります。納付期限を過ぎると、翌日から20日以内に自治体から督促状が送付されることが一般的です。
なお、固定資産税の納付期限は自治体ごとに異なるため、納税通知書で確認し、期日までに適切に納付することが求められます。
さらに、長期間にわたって支払いを怠ると、財産の差し押さえを受けるおそれもあるため、計画的な資金管理が重要です。
4-6.固定資産税評価額を確認する
固定資産税の納付額を正しく把握するためには、固定資産税評価額を定期的に確認することが大切です。建物は経年劣化により価値が下がるため、それに伴い納付する固定資産税も減少していきます。
固定資産税評価額は3年に1度見直され、建物の価値が下がれば、その分固定資産税の負担も軽減される仕組みです。
つまり、築年数が経過するほど税額も下がる可能性があるため、評価額の変動をしっかり確認し、適切に管理することが重要です。
4-7.専門家に相談する
固定資産税をはじめとする税金対策を適切に行うためには、専門家に相談することが有効です。税理士事務所などで専門家に相談することで、最新の税制や適用可能な特例について詳しく知ることができます。
特に、税金に関する専門知識がない場合、自身で対応しようとすると申告漏れや計算ミスが発生する可能性があります。そのため、正確な税務処理を行い、適切な節税対策を講じるためにも、専門家のサポートを受けましょう。
4-8.固定資産税の再審査の申出を行う
固定資産税が高いと感じた場合、再審査の申出を行うことが可能です。納税者は、固定資産評価審査申出制度を利用し、評価額の見直しを求めることができます。
この制度を利用するには、固定資産評価審査委員会に対し、納税通知書の交付を受けてから3カ月以内に申出を行う必要があります。とはいえ、固定資産税の評価について疑問がある場合はいきなり申出を行うのではなく、まずは自治体の担当窓口に問い合わせて評価の根拠や方法について説明を求めると良いでしょう。
5.アパート経営の節税対策は正しい理解と専門家の助言が成功の鍵
アパート経営における税金の仕組みを正しく理解し、適切に納税することは、長期的な経営の安定性と社会的責任を果たす上で非常に重要です。
本記事で紹介したさまざまな税金対策は、法律の範囲内で認められた方法ですが、その適用には専門的な知識が必要です。
税法は複雑で頻繁に改正されるため、最新の情報を常に把握しておくことが欠かせません。また、個々の状況によって最適な対策は異なるため、一般的な情報だけでなく、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
大東建託では、アパート経営に関する幅広い相談を受け付けています。土地活用の方法から、税金対策、資金計画まで、経験豊富な専門スタッフが丁寧にサポートいたします。適切な納税と効率的な経営の両立に向けて、ぜひ一度ご相談ください。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング