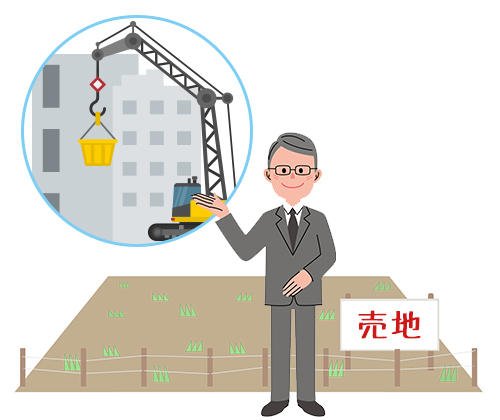賃貸併用住宅をローコストで建てる7つの方法│知っておきたい注意点
公開日: 2023.04.10
最終更新日: 2025.07.22
賃貸併用住宅は、オーナーの自宅のほかに他人に貸し出す賃貸用の部屋を併設した建物です。家賃収入でローン返済が可能な点や節税効果が期待できるメリットなどがあるため、注目度が高まっています。
賃貸併用住宅の投資効率を高めるためには、予算をかけ過ぎずにできるだけローコストで建設するのが理想です。
本記事では、賃貸併用住宅を建てる際の費用を抑える方法7つを紹介していきます。
ただ、費用を抑えることだけにこだわり過ぎると、期待した利益を得られないリスクがあります。記事後半で賃貸併用住宅をローコストで建てる際の注意点も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
>>関連記事:「アパート経営完全ガイド|建築プラン立てから完成後の業務まで」

1.賃貸併用住宅をローコストで建てる方法
ここではローコストで賃貸併用住宅を建てる方法を7つ紹介します。
資金調達や設計段階でしっかり意識すれば、建築コストをかけ過ぎずに収益性を高められるでしょう。
1-1.住宅ローンを利用する
住宅ローンを利用することで、賃貸併用住宅をローコストで建てることが可能になります。賃貸住宅を建てる際は一般的に、自宅用の住宅ローンは使えませんので、アパートローンを利用します。アパートローンは通常、住宅ローンより金利水準が高く、借入期間が短くなる場合があり 、またローン残高の一部を税額から控除できる住宅ローン減税も使えません。
自宅部分がある賃貸併用住宅なら住宅ローンを活用できる可能性があり、金利が高めのアパートローンより総支払額を抑えやすくなるほか、借入期間を長く設定することで毎月の支払い負担を抑えることもできるのです。アパートローンの金利は変動金利で1%台から2%台が多く、1%未満が主流となっている住宅ローン金利のメリットは大きいものがあります。
ただ、賃貸併用住宅で住宅ローンを活用するには、全体の面積のうち自宅部分が50%以上であるなど金融機関が定めた条件を満たす必要があります。賃貸併用であれば必ず住宅ローンの対象になるとは限らないことにも注意が必要です。
>>関連記事:住宅ローンは賃貸併用住宅に使える?ローンの特徴や組むときの流れ
1-2.高さのある建物が建築できる土地を選ぶ
コストを抑えた賃貸併用住宅の建設を検討する場合、高さのある建物を建てられる土地を仕入れることもポイントになります。
敷地にどれだけの高さの物件を建てられるかは、建ぺい率や容積率、高さ制限などの規制内容で異なります。高さに対する規制が緩い土地であれば、小さな土地でも十分な賃貸部分を確保することで期待する家賃収入を得られます。
土地取得費の総額を抑えられる狭小地を仕入れて賃貸併用住宅とすることで、コストを抑えながら収益性を高めることが可能です。
1-3.賃貸戸数を増やし過ぎない
賃貸向けの住戸数を増やし過ぎないことも、ローコストで賃貸併用住宅を建てる方法の一つです。
賃貸戸数が増えることで、キッチンや風呂、トイレ、玄関ドアなどの設備負担が増し、部屋と部屋を仕切る壁の設置コストなども上昇します。戸数を増やすために一部屋が狭くなり、ファミリー層の需要を取りこぼす場合もあるでしょう。
戸数を増やし過ぎない方法としては、ワンルームよりもファミリータイプの部屋を増やすことが考えられます。ファミリーの需要がないエリアでファミリータイプを増やすとリスクが大きくなりますので、間取りを決める際は、周辺の競合物件や需要を調査して適切な部屋数を設定することが重要です。
1-4.外観はシンプルなデザインを採用する
外観をシンプルなデザインにすることで、賃貸併用住宅を建てる経費を抑えることができます。
変形地などで建物が複雑な構造や形状をしている場合、正方形や長方形など建物がシンプルな場合と比べて壁や柱が余計に必要になり、材料費や工事費が膨らみます。
たとえば2階建ての物件なら、1階と2階の面積を等しくすることで壁の形状をシンプルにすることができ、比較的ローコストで建築可能となります。外壁の素材にもコストパフォーマンスが良いものもあります。人目に付きにくい部分はコストを抑えて納得のいくデザインにするなど、費用を抑える工夫が可能です。
1-5.自宅部分にこだわりすぎない
賃貸併用住宅の建築コストを抑えるには、自宅部分にこだわりすぎないこともポイントになります。
オーナーが暮らす自宅部分は、キッチン・風呂・トイレなどの水回りや、クロス、床材などの仕様を注文住宅同様にこだわりたいと考える人が多いでしょう。キッチンなどは特注ではなく既製品を使う、お風呂のミストサウナ機能など金額がかかる機能を付けないなど、使用頻度や使い勝手を考慮して納得できる範囲で機能を抑えることも必要です。
賃貸部分なら一定程度割り切って質素なものを選ぶケースもあります。自宅部分も同様に豪華にし過ぎないようにすることによりローコストで建てることができます。
ただ、賃貸併用住宅を建設するメリットには、家賃収入を得ることで自宅部分にコストをかけられるようになることがあります。暮らし始めた後をしっかりイメージし、後悔がない範囲で費用を抑えることを検討しましょう。
1-6.建材の規格を揃える
賃貸併用住宅の建材の規格を揃えることで、費用を抑えて建築することが可能になります。
建材は建築工事で使われる材料のことをいい、木材・コンクリート・金属・石などさまざまな種類があります。それぞれの建材の中で規格を揃えずに特別に注文すると、仕入れや輸送コストがかさむ要因になります。
たとえば、建築を請け負う会社が普段使用しない輸入建材を使うことで、追加工事や補修が必要な際に思わぬコストがかかります。賃貸併用住宅を建てるオーナーにとって、建築会社などが用意する規格内で建材を揃えることは難しいことが多いですが、可能な範囲で規格を統一することで、コストを抑えることが可能になります。
1-7.外交や設備にこだわり過ぎない
外構や設備にこだわり過ぎなければ、ローコストで賃貸併用住宅を建てることができます。競合する賃貸物件の状況や想定する入居者の世帯構成などによっては、必要以上に豪華なエントランスや高品質の室内設備がなくても需要に応えられることもあります。
入居希望者にアピールするために門や庭木を設置したり、高級なエアコンやトイレなど豪華な室内設備を設置したりするのが有効な場合もありますが、メリハリを意識しながら慎重に建築計画を立てることが重要です。
>>関連記事:賃貸併用住宅の成功例や失敗パターン、後悔しないための重要ポイント
2.賃貸併用住宅をローコストで建てる際の注意点
次に賃貸併用住宅をローコストで建てる際の注意点を3つ解説します。建築費用の抑制にこだわり過ぎて、機能性や快適性の低下によって入居者獲得などに影響を及ぼすことがないよう、ローコスト住宅を目指す際は確認が必要になる点です。
2-1.戸数を減らすと空室時に収益への影響が大きくなる
戸数を減らすと空室時に収益への影響が大きくなるのが注意点の一つです。たとえば4戸の賃貸が可能な木造アパートの場合、1戸の空室で家賃収入は満室時から25%減少します。これに対して、全10戸の場合では、1戸の空室で減少する家賃収入は満室時の10%分に過ぎません。
戸数を減らすと1室への依存度が強まります。空室の発生により、賃貸経営が不安定になる点が戸数を減らすデメリットといえます。
戸数を検討する際には、競合調査を実施したうえで、入居者を獲得しやすい家賃や間取りを検討することが重要です。
2-2.グレードを落とし過ぎると入居者が集まりにくくなる
外構や設備のグレードを抑えると建築費用を低くすることが可能になりますが、グレードを落とし過ぎると、入居者が集まりにくくなるリスクが高まります。たとえば、室内にエアコンが設置されているかいないかで、部屋探しをしている人の印象が大きく変わります。自らエアコンを設置するケースとそうでないケースでは、入居時の初期費用が異なるためです。トイレにウォシュレット(温水洗浄便座)が設置されているかいないかでも、第一印象が変わる可能性があります。
不動産会社などの意見を聴きながら、入居者が求める必要最低限の設備について意識を向けることが重要です。
2-3.ローコストにこだわり過ぎると借入金の返済リスクが上がる
賃貸併用住宅を建築する際にローコストにこだわり過ぎると、将来的に借入金の返済リスクが高くなる懸念があります。
建材や設備の品質を抑えた場合、入居者が集まりにくくなって家賃収入が落ちるだけでなく、改善のための追加工事代が必要となることもあります。安く抑えようとして逆にコストがかかってしまうのです。
たとえば、過度に遮音材などを省いた結果騒音のクレームがきて対応を迫られるケースなどが考えられます。予定していた家賃収入を得られなかったり、コストが膨らんだりして手残りが減り、借入金の返済に回す額が減る事態もあり得ることも頭に入れておく必要があります。
3.ローコストで賃貸併用住宅を建てるなら賃貸経営の知識が必須
家賃収入を住宅ローンの返済に充てられるほか、節税・減税対策にもなるため、メリットが多いおすすめの土地活用方法です。ローコストで実現できれば収益性がさらに高まり効果が大きくなります。
ただ、そのためには賃貸経営の安定が前提です。費用を抑え過ぎてかえって利益が落ちる事態を避けるには、建築プランを作る際に賃貸経営の専門家のアドバイスを受けることも重要です。
入居者の動向や家賃相場など、業界事情に詳しい不動産会社と相談しながら賃貸併用住宅の可否や間取り、設備を検討することで、物件の収益性に差が出てくるでしょう。
賃貸経営の専門家なら、長年にわたるトータルサポートの経験で培った土地活用の企画・提案にはじまり、建物の設計・施工、入居者の募集や管理など賃貸経営をトータルでサポートできます。長年の業務で培った賃貸経営のノウハウをぜひ活用してください。



■監修者プロフィール
宅地建物取引士/FP2級
伊野 文明
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。
【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング