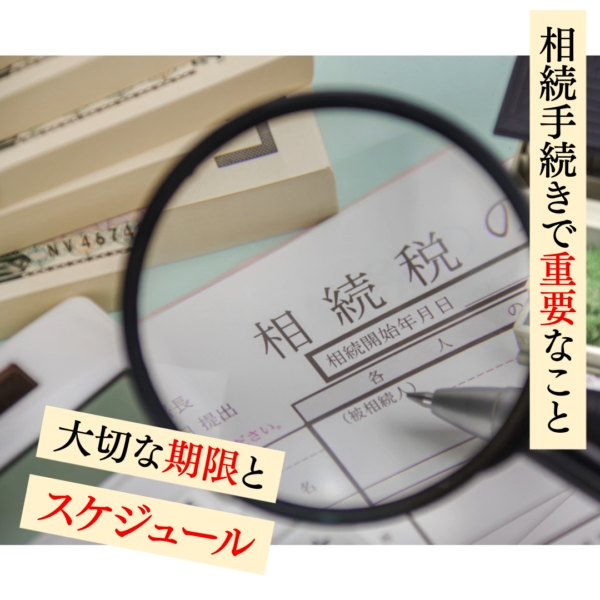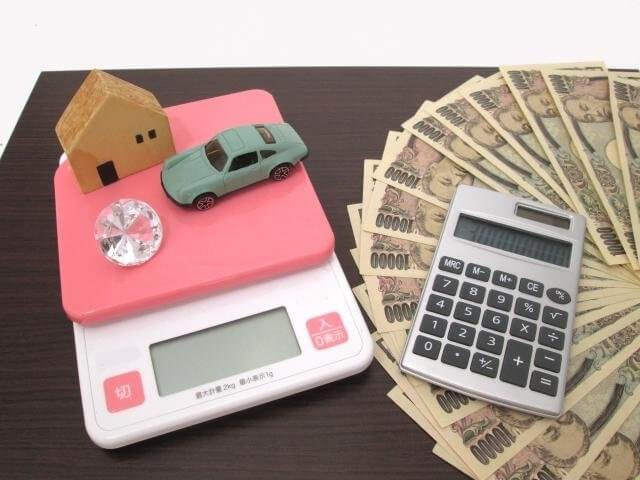アパート経営を兄弟で相続するには?主な分割方法や相続の流れ
公開日: 2025.01.14
最終更新日: 2025.10.28
アパートを親から相続する、またはその可能性がある場合、「兄弟での円滑な相続」は重要な課題です。
不動産は現金のように簡単に分割できないため、誰がどの部分を相続するかで兄弟間に意見の相違が生じやすく、相続トラブルの原因となります。
特に賃貸物件であるアパートの場合、収益を生み出す資産であるため、その収益の分配方法や
管理責任についても問題が複雑化します。
さらに、アパートの資産価値を維持し、収益性を確保することは、相続後の家族全体の経済的安定に直結します。
また、相続税評価額が高額になる可能性があるため、適切な対策を講じて評価額を調整しないと、多額の相続税負担が生じることがあります。
これらの理由から、アパートの相続には慎重な計画と対策が不可欠です。
今回は、アパートを兄弟で相続する際の具体的な流れを解説し、不動産投資の視点から活用できる有効な方法についても紹介します。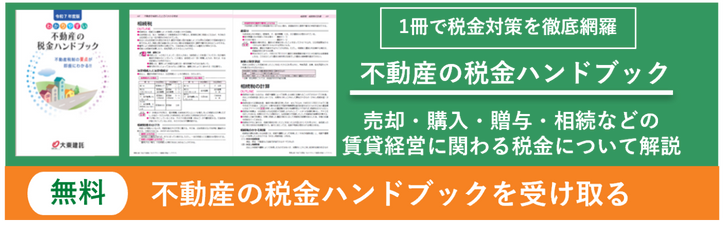
1.相続したアパートを兄弟で分けるには?
*アパートやマンションを相続する方法とは
遺産相続で一般的な分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあります。
アパートの分割方法は、共有者全員の納得と資産価値の維持を両立させるためにも重要です。
ここでは、各分割方法のメリットとデメリットを解説し、実際にどのような場面で有効かを見ていきます。
>>関連記事:中古アパートの経営とは?新築と比べたメリットや物件選びのポイント
1-1.現物分割
現物分割は、不動産や株式などの性質を変えず、そのまま相続する方法です。
アパートの場合、物件を相続人の1人に引き継がせる形で進めます。
この方法は、アパート経営を継続したい場合に有効な選択肢のひとつです。
たとえば、長男が預貯金と株式を、次男が自宅とアパートを引き継ぐといったに有効となるケースが多いです。
メリット
| ●アパートを売却せずにそのまま相続できるため、売却の手間がかからず、物件の現状を維持したまま引き継げる。 |
| ●相続時に売却が伴わず所得税が発生しないため、税負担を抑えることができるケースもある。 |
デメリット
| ●相続財産全体の構成によっては公平な分割が難しく、相続人全員の同意に時間がかかることがある。 |
| ●相続後もアパート経営に付随する管理の手間や金銭コストなどが発生する。 |
1-2.代償分割
代償分割は、不動産などの相続財産を特定の相続人に相続させ、他の相続人には代償金を支払うことで公平性を保つ方法です。これにより、共有名義によるトラブルを避け、円滑な資産の引き継ぎが可能になります。
アパート経営の場合 、長男が評価額8,000万円のアパートを相続し、次男へ代償金として4,000万円を支払うケースが考えられます。これにより、長男はアパートを単独で所有し、次男は現金を受け取ることで公平性が確保されます。
メリット
| ●共有名義の煩雑さを避け、収益物件の入居率や空室管理を1人が一貫して行える。 |
| ●相続時に売却が伴わず所得税が発生しないため、税負担を抑えられるケースがある。 |
デメリット
| ●代償金の準備が必要で、相続人に大きな費用負担となる場合がある。 |
| ●共有者全員の納得を得る必要があり、金額を巡って相続トラブルが発生するリスクがある。 |
1-3.換価分割
換価分割は、不動産や株式などの相続財産を売却し、その売却金を現金として相続人に分配する方法です。
不動産を現金化することで、資産の分割が簡単になり、相続人の納得を得やすいのが特徴です。
たとえば、アパートを8,000万円で売却し、長男と次男に4,000万円ずつ分配するケースが考えられます。
賃貸物件の運営意思がない場合、換価分割は合理的な選択肢です。
メリット
| ●物件の管理や空室リスクを回避でき、相続後のトラブルが発生しにくい。 |
| ●複数人での相続にも対応しやすく、現金分配で揉めにくい。 |
デメリット
| ●市場状況次第で売却が進まず、時間がかかる場合がある。 |
| ●物件が期待より低価格で売れた場合、相続人全員の取り分が減る可能性がある。 |
| ●売却益に対する所得税が発生し、相続税と合わせて税負担が大きくなることがある。 |
1-4.共有分割
共有分割は、不動産を売却せずに共有名義で相続人が共同で所有する方法です。
この方法では、アパートをそのまま維持し、各相続人が持分を取得します。
物件を手放さずに収益性を確保しながら、将来の活用を検討できるのが特徴です。
たとえば、長男と次男が1棟のアパートを共有名義で相続し、
長男と次男が半分ずつの持分を持つケースが考えられます。家賃収入は持分に応じて分配され、運営費用も同じ割合で負担します。
メリット
| ●収益物件を売却せず維持でき、入居率次第で安定した収支が期待できる。 |
| ●複数人での所有により、経済的負担が軽減され、資金計画が立てやすくなる。 |
| ●相続時に売却が伴わず所得税が発生しないため、税負担を抑えられるケースがある。 |
デメリット
| ●共有者全員の同意が必要なため、管理方針や売却を巡って相続トラブルが起こりやすい。 |
| ●空室や修繕が発生した場合、持分に応じて全員で負担するため、意見の対立から問題が深刻化する可能性がある。 |
| ●長期的な共有により資産価値が不透明になり、次の相続時に再度トラブルが生じる恐れがある。 |
関連記事>>『円満』な資産承継を考える際の注意点。トラブル事例と承継までの流れ
2.アパートを兄弟で相続する際の流れ
アパートを兄弟で相続する際は、手続きが複雑になるため、事前に全体像を把握しておくことが大切ここでは、アパート相続の主要なステップを順に解説し、各段階で押さえておくべきポイントを紹介します。兄弟での相続を円滑に進め、将来的な不動産投資や収益性を最大化するためのアプローチを見つけていきましょう。
Step1.遺言書の確認
アパートを相続する際、まず確認すべきは遺言書の有無です。
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従い、相続手続きを進めます。
一方、遺言書がない場合は、法定相続人全員による遺産分割協議が必要です。
この協議では、アパートの価値や収益性を考慮し、誰がどの財産を取得するかを話し合います。
Step2.相続人や相続財産の確認
アパートの相続を進めるには、相続人と相続財産の詳細を確認することが重要です。
法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹が含まれ、それぞれの持分や遺留分の権利が関わります。
次に、アパートの不動産情報を正確に把握します。
所在地や登記情報、固定資産税の状況に加え、ローン残債の有無も重要です。
また、アパート以外の現金や株式などの資産も調査し、相続財産全体の価値と収支を把握することが求められます。
Step3.遺産分割協議
アパートを含む相続財産の分割を決めるには、相続人の間で十分な話し合いを行い、
適切な分割方法を選択する必要があります。
合意が成立した場合、その内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
協議書には、アパートの所有や持分の配分、必要であれば代償金の支払方法を明記し、
相続人全員が納得した上で署名・押印します。
また、相続後には、管理会社や金融機関への連絡も必要です。
物件管理を委託している場合、契約内容の更新や名義変更が求められます。
さらに、ローン残債がある場合は、金融機関と返済計画を再確認することも欠かせません。
Step4.相続登記や相続税の納付
アパートの相続が決まったら、次に進めるべきは相続登記と相続税の納付です。
相続する人の名義に変更するため、法務局で登記手続きを行い、遺産分割協議書などの必要書類を提出します。
また、被相続人の生前の所得については、相続人全員が連署して準確定申告を行い、相続人が所得税を納税します。
さらに、相続税は相続人が被相続人の死亡を知った日(通常は死亡の日)から10か月以内に納付が必要です。
アパートの相続税評価額やその他の資産価値を踏まえた適切な計算で、期限内に税金を支払いましょう。
Step5.アパート入居者への連絡
アパートの名義変更が完了した後は、入居者にオーナー変更の通知を速やかに行います。
物件の管理会社や担当者が変わる場合は、新しい連絡先を通知内で明記し、賃
料の振込先が変更される場合も併せて案内します。
>>関連記事:賃貸事業による節税~相続税の計算方法と気を付けること~
3.相続したアパートを兄弟で経営する場合によくあるトラブルと対策法
親から相続したアパートを兄弟で共有で所有し、共同経営する際、思いがけないトラブルが発生することがあります。
ここでは、よくあるトラブルとその対策法を紹介します。
3-1.兄弟のアパート経営でよくあるトラブル
・管理業務の負担が不平等
兄弟でアパートを共同経営する際、管理業務の負担が不平等になることがよくあります。
一方が積極的に維持管理や修繕に取り組む一方、他方があまり関与しない状況が考えられます。
アパート経営には、物件管理や賃借人対応、修繕、家賃回収など、日常的な業務が多岐にわたります。これらを公平に分担しないと、一部の共有者に負担が集中し、不満が生じやすくなります。
>>関連記事:一棟アパートを売却する前に知りたいこと|全体の流れやかかる支出の例
・収益や経費の分配に関する不満
兄弟でアパートを経営する際、家賃収入や修繕費、税金などの経費の分配が明確でないと、不満が生じやすくなります。
支出や収益が持分に応じて配分されないことがトラブルの原因となります。
たとえば、アパートの収入が予想より少なかったり、予想外の修繕費が発生した場合、意見の対立が起こりやすくなります。
また、兄弟間の力関係が経費や収益の分配に影響するケースもあります。
たとえば、ある兄弟が経営を主導し、もう一方に不利な条件を押し付けると、共有名義での運営がますます困難になります。
・経営方針に関する意見の食い違い
アパートの経営方針を巡り、兄弟間で意見が対立することもあります。
たとえば、空室が続く中、一方が大規模修繕やリフォームを提案し、もう一方がコストを抑え最低限の対応にとどめたいと考えるケースが典型例です。
また、家賃を引き上げて収益性を高めるか、現状維持で入居率を保つかも意見が分かれるポイントです。
さらに、一方が売却を急ぐ一方で、他方が物件を不動産投資として長期的に保持したいと考えるなど、判断の違いが深まることもあります。
問題が複雑化するのは、兄弟だけでなく、それぞれの配偶者や子どもの意見が経営判断に影響する場合です。
多様な意見が交錯すると、共有名義での運営は一層難しくなります。
さらに、共有名義の状態で相続を重ねるたびに当事者が増えていくリスクがあります。
・コミュニケーション不足による誤解
兄弟でのアパート経営では、経営に関する情報や重要な決定事項が十分に共有されないこともトラブルにつながります。
たとえば、経営に関する情報や重要な決定事項が一部の共有者にしか伝わらないことが不信感を招きます。
さらに、兄弟間で不仲になると、その影響はアパート運営にも及びます。
このような問題が拡大すると、共有名義での物件管理が難しくなり、経営が滞る恐れがあります。
3-2.トラブルを回避するための主な対策
・管理や経費の分担、収益の分配、意思決定のルールを明確にしておく
兄弟間でのアパート経営を成功させるには、管理業務や経費の分担、収益の分配、
そして意思決定のルールを事前に明確にすることが重要です。
具体的には、重要事項の決定方法や各兄弟の管理業務の責任範囲、収益や経費の分配の割合を
明確にしておく必要があります。
また、可能であれば、被相続人が健在なうちに遺言書を作成し、
アパートを含む相続財産の詳細をまとめておくことが望ましいです。
・専門家のアドバイスを受ける
兄弟でのアパート経営や遺産分割を円滑に進めるには、専門家の助言を積極的に活用することが重要です。
特に、遺産分割協議書や共同経営の契約書作成には、法律や税金の知識が求められます。
弁護士や税理士、司法書士といった専門家のアドバイスを受けることで、相続時の法的リスクを未然に防ぐことが可能です。
また、不動産の資産価値や収益性を高めるためには、土地活用や賃貸物件の運営に詳しいプロへの相談も有効です。
専門家の関与によって、兄弟間で意見が対立した場合でも、客観的な助言により合意形成が進みやすくなります。
たとえば、アパートを管理するために法人化することで、経営判断を組織的に行えるようになり、相続人間での意思決定がスムーズになります。
また、家族信託を活用することで、財産の管理や分配を信頼できる家族に任せることができ、
相続手続きが円滑に進む可能性があります。
これらの方法は専門的な知識を要するため、適切なアドバイスを得ることが重要です。
・管理会社にアパートの管理を委託する
兄弟でのアパート経営において、管理業務の負担や不平等を解消するために、管理会社への委託は非常に有効です。
管理会社が修繕や賃借人対応、家賃徴収などの業務を代行することで、共有者全員が公平に関与でき、
共同経営のトラブルを防ぐことが期待できます。
また、管理会社のサポートにより、入居率の改善や空室リスクの軽減が見込まれます。
家賃未払いの迅速な対応で、長期的な収益性が確保され、収支バランスの維持もしやすくなります。
>>関連記事:副業でもアパート経営できる!委託管理の上手な活用方法とは
4.兄弟でアパート経営を成功させるために
兄弟でのアパート経営は、資産を守りつつ収益性を高める良い選択ですが、
準備不足や管理の不備がトラブルを招く可能性があります。
トラブル回避には、合意形成と透明な運営が重要です。情報を共有し協力し合うことで、
適切な相続対策が実現し、長期的な収益性を維持しながら、次世代へ円滑に資産を引き継ぐことにつながるでしょう。
■監修者プロフィール
公認会計士
梶本 卓哉
税務署法人課税部門(税務大学校首席卒業)、大手監査法人や大手投資銀行勤務等を経て公認会計士・税理士事務所開設。税務のみならず会計監査やIPO(新規株式公開)実務に強みを有する。
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング