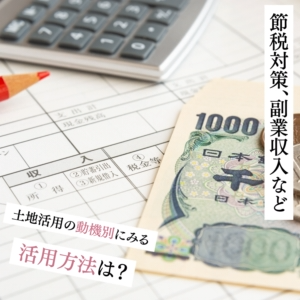補助金が得られる土地活用とは?利用できる補助金や申請時の注意点
公開日: 2025.05.27
最終更新日: 2025.09.17
土地を有効活用したいと考えていても、初期費用の負担が大きく悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんなときにおすすめなのが、国や自治体が提供する補助金の利用です。
特に子育て支援や高齢者の住まいの確保、再生エネルギーの利用など社会的課題の解決を目的とした事業は、補助金による支援を受けやすい傾向にあり、土地活用と相性の良い賃貸経営でも活用できる場合があります。
本記事では、補助金が得られる土地活用の具体例や申請時の注意点について解説します。
1. 補助金が得られる土地活用の方法の例
土地活用では、補助金を活用することで初期投資を抑え、収益性を向上させることができます。
ここでは、補助金が得られる代表的な土地活用の方法について紹介します。
1-1. 賃貸経営
賃貸経営とは、空き地に戸建てやアパート、マンションを建てて人に貸し、賃料を得る土地活用の方法です。
入居者に長く住んでもらうことで、安定した家賃収入を得られるモデルとなります。
賃貸経営は、立地や市場のニーズをしっかりと調査し、適切なプランニングを行うことで成功率を高めることができます。
特に都市部では住宅需要が高く、長期的な資産形成の手段としても有効です。
賃貸経営に関する詳細な情報は、以下の記事で確認できます。
>>関連記事:アパート経営完全ガイド|建築プラン立てから完成後の業務まで
1-2. 保育園の経営
保育園の経営とは、空き地を活用して保育園を設立し、その運営を行う土地活用の方法です。
子育て世帯が多い地域はもちろん、共働き世帯の増加に伴い、保育施設のニーズも年々高まっています。
また、待機児童問題の解決にも貢献できる社会的意義の高い事業であり、補助金による支援制度も整っています。
保育園経営の詳細については、以下の記事をご覧ください。
>>関連記事:土地活用に保育園を選ぶには?主な運営方式やメリットとデメリット
1-3. サ高住の経営
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、高齢者が安心して暮らせる環境が整った賃貸住宅を指し、土地活用方法の一つとして注目されています。
日本の高齢化が進む中、サ高住のような福祉施設の数は不足しており、今後ますます需要が高まると考えられ、高齢者の生活の質を向上させながら安定した収益を得られる事業モデルとなります。
サ高住を経営する際に活用できる補助制度や税の優遇制度については、以下の記事をご参照ください。
>>関連記事:サ高住を経営するメリットは?利用できる補助制度と税の優遇制度
1-4. 太陽光発電の設置
太陽光発電は、ソーラーパネルを設置し、発電した電力を電力会社へ売却することで収益を得る土地活用の方法です。
特に、郊外の日当たりの良い土地に適しており、持続可能なエネルギー供給に貢献できます。
経営方式としては、自分で設備を設置し発電事業を行う「自営方式」と、事業者に土地を貸すことで安定した賃料収入を得る「土地貸し方式」の2種類があり、ご自身の将来設計に応じて選択することが重要です。
太陽光発電についての詳細な情報は以下の記事でご確認ください。
2. 土地活用で利用できる主な補助金
それでは、それぞれの活用方法に対応した具体的な補助金制度を解説します。
補助金をうまく活用し、初期費用を抑えて安定した土地活用につなげましょう。
2-1. 賃貸経営で利用できる補助金
賃貸住宅で土地活用を始めたい方におすすめなのが、「子育てグリーン住宅支援事業」と「子育て支援型共同住宅推進事業」です。
性能の高い住宅や便利な設備が整った住宅は、補助金が得られるばかりでなく入居者にとっても快適で魅力的な物件です。
結果として入居者に選ばれやすくなり、安定した賃貸経営に結びつきます。
・子育てグリーン住宅支援事業とは
カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ性能の高い住宅(GX志向型住宅、子育て世帯等(※1)向けの長期優良住宅・ZEH水準住宅)の新築や改修を補助する事業です。
賃貸住宅についても、グリーン住宅支援事業者と契約し、該当する床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅を新築する場合は補助金の対象となります。
参考として、令和6年度の補助対象となる住宅とその要件、補助金額をまとめます。
|
補助対象 |
主な条件 |
補助金額(※2) |
|
GX志向型住宅 (全世帯対象) |
・断熱等性能等級:6以上 |
160万円/戸 |
|
長期優良住宅(子育て世帯等向け) |
・断熱等性能等級:5以上 ・子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性の技術基準に適合 |
80万円/戸 |
|
ZEH水準住宅(子育て世帯等向け) |
・断熱等性能等級:5以上 ・子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性の技術基準に適合 |
40万円/戸 |
(※1)「子育て世帯等」とは、18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)か、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)をいいます。
(※2)補助金の対象となるのは、要件を満たす賃貸住戸の50%になります。
(※3)子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための追加要件があります。
>>参考:子育てグリーン住宅支援事業事務局HPより
・子育て支援型共同住宅推進事業
子どもの安全・安心対策や、子育て期の親同士の交流に配慮した共同住宅(マンションやアパートなど)の新築や改修を補助する事業です。
補助対象は、子どもの転落防止を施した窓など「子どもの安全確保のための設備の設置」と、交流場所として利用できるプレイロットといった「居住者同士の交流を促す施設の設置」の取り組みに分かれており、新築物件でこの補助金を利用する場合、後者の取り組みは必須とされています。
参考として、令和6年度の補助対象となる取り組みと補助金額を以下にまとめます。
|
補助対象 (※) |
具体的な取り組み |
補助金額 |
|
子どもの安全確保 |
|
新築:事業費の1/10 |
|
居住者同士の交流促進 |
【以下のうち1つ以上を実施(新築は必須)】 |
新築:事業費の1/10 |
>>関連記事:国土交通省HP:子育て支援型共同住宅推進事業について
※「子どもの安全確保」に関する項目の中では、⑥は必須となります(⑥以外も整備水準を満たせば補助対象)。
また、「居住者同士の交流促進」に関する項目では、「子どもの安全確保」の必須項目である⑥の水準を満たす住戸が5戸以上あることが条件です。
2-2. 保育園の経営で利用できる補助金
保育施設の経営で土地活用を始めたい方におすすめの補助金は、「就学前教育・保育施設整備交付金」と「保育所等改修費等支援事業」です。
・就学前教育・保育施設整備交付金
保育所、認定こども園、小規模保育事業所などの新設や改修、防犯・防音対策の整備にかかる費用の一部を、国から交付金を受けて市区町村が実施する補助金です。
・保育所等改修費等支援事業
賃貸物件を活用して保育所等を設置する場合や、認可外保育施設が認可保育所等の基準を満たすために改修を行う場合など、特定のケースにおいて費用の一部を補助する制度です。
こちらの補助金も、市区町村が実施します。
・補助金の対象事業・補助割合
参考として、令和6年度における対象事業と補助割合を以下にまとめます。
|
|
就学前教育・保育施設整備交付金 |
保育所等改修費等支援事業 |
|
補助対象事業 |
・保育所整備事業 ・公立認定こども園整備事業 ・小規模保育整備事業 ・防音壁整備事業 ・防犯対策強化整備事業 ・乳児等通園支援事業 |
・賃貸物件による保育所改修費等支援事業 |
|
補助割合(※) |
【私立】 国:1/2、市区町村:1/4、設置主体1/4 【公立】 国:1/3、市区町村:2/3 |
【私立】 国:1/2、市区町村:1/4、設置主体:1/4 国:1/2、市区町村:1/2 |
(※)取り組む事業の区分や、新子育て安心プランに参加するなど一定の要件を満たす場合、国と市区町村の補助割合が変わるものがあります。
>>参考:子ども家庭庁HP:保育対策関係予算の概要
2-3. サ高住の経営で利用できる補助金
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の経営で土地活用を始めたい場合におすすめの補助金は、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」です。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる住まいの供給を促進するための補助金制度になります。
参考までに、令和6年度の要件と補助金額をまとめます。
|
補助対象要件 |
新築の場合の補助金額 |
|
・高齢者住まい法に規定するサ高住として10年以上登録すること(※1) |
【住宅】(※2) ・新築:1/10(上限70・120・135万円/戸など) ・改修、既設改修:1/3(上限195万円/戸) 【高齢者生活支援施設】 ・新築:1/10 ・改修、既設改修:1/3 (上限1,000万円/施設) |
(※1)登録基準として、床面積が原則25㎡以上、バリアフリーであるなどハード面での基準や、サービス・契約面での基準が別途あります。
(※2)補助金額は床面積や住宅の性能等に応じて変わります。
>>関連記事:国土交通省HP:「令和6年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業」
2-4. 太陽光発電の設置で利用できる補助金
太陽光発電で土地活用をする場合、自治体の補助金を利用できる場合があります。
近年は、蓄電池との併用を補助対象にする取り組みが主流となっていますが、詳細な補助対象は自治体ごとに確認が必要です。
一方、国の補助金としては「需要家主導型太陽光発電導入支援事業」として、再エネ利用を希望する者(需要家)が、新たに太陽光発電設備を設置し、FITやFIP制度、自己託送を利用せずに再生可能エネルギーを長期的に利用する場合などに、太陽光発電設備の導入を支援する事業を実施しています。
>>関連記事:経済産業省資産エネルギー庁HP:「需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金」
2-5. 解体助成金の制度
自治体によっては建物の解体助成金の制度を設けていることがあります。近年は特に空き家の増加が問題となっているため、こうした家屋を撤去して土地活用を始めたい場合は確認してみましょう。
3. 補助金を申請する際の注意点
補助金を活用すれば、土地活用の初期投資の負担を軽減でき、その分利益を上げやすくなります。一方で、補助金を申請する際には注意点もあります。ここでは、補助金申請時に特に注意すべきポイントを解説します。
3-1. 補助金が支給される条件を確認しておく
国や自治体は、さまざまな社会問題の解決につながる土地活用を奨励するために補助金を提供しています。
しかし、補助金にはそれぞれ交付条件があり、条件を満たしていなければ、たとえ社会的に意義のある事業であっても補助金を受け取ることはできません。
自身の土地活用が補助金の適用条件や目的に合っているかを、事前にしっかりと確認することが重要です。
3-2. 期限に余裕を持って準備を進める
補助金はいつでも申請できるわけではなく、公募期限が設けられています。期限ギリギリになってから申請準備を始めると、必要書類の作成や見直しに時間を確保できず、不備によって申請が通らない可能性もあります。
期限が迫ってから条件や必要書類を調べるのではなく、余裕をもって計画的に準備を進めることが大切です。
3-3. 補助金が給付されるまでは資金を立て替えておく必要がある
ほとんどの補助金は、事業を実施した後に、補助対象の一部を「後払い」で交付することが一般的です。
たとえ採択されても、実際に補助金を受け取れるのは、事業が正しく実施されたことが確認された後となります。
補助金が給付されるまでの間は、自己資金や融資を活用して資金を確保しなければなりません。
4. 補助金を活用して土地活用を成功させるために
補助金を活用することで、土地活用の初期費用を抑え、安定した事業運営につなげることができます。
賃貸経営や保育園、サ高住の運営、太陽光発電の設置など、用途に応じた補助金が存在するため、適用条件を確認しながら活用を検討しましょう。
ただし、補助金には申請期限や交付条件があり、資金の立て替えが必要な場合もあります。
適切な準備と計画が成功の鍵です。土地の活用方法にご興味のある方は、大東建託にお気軽にご相談ください。
>>お問い合わせはこちら:土地活用・賃貸経営のことなら大東建託
■監修者プロフィール
ここりんくす株式会社 代表取締役
小泉寿洋
ここりんくす株式会社代表取締役。上場グループに属する賃貸不動産会社で賃貸仲介、賃貸管理部門に14年半ほど従事。その後、不動産仲介・建築工事・終活サポートの会社経営を経て、現在は賃貸経営・賃貸管理・終活に関するコンサルティング、WEBセミナー講師、不動産・FP系ライターなど各方面で活動中。不動産業界歴は約23年。
【保有資格】
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士、相続診断士、終活カウンセラー1級、終活ガイド1級、遺品整理士他
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング