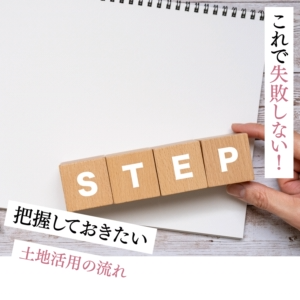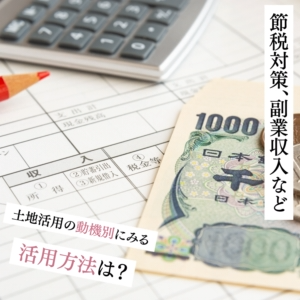土地活用におけるリースバックとは?仕組みやメリット|向いている業態
公開日: 2025.01.24
最終更新日: 2025.09.18
リースバックには大きく分けて2つのタイプがあります。
1つは、自宅や不動産を売却した後も賃貸借契約を結ぶことで住み続けられる「住宅のリースバック」。もう一方は、土地活用の一環として事業者と建設協力金方式で契約を結ぶ「土地活用のリースバック」です。
両者はしばしば混同されがちですが根本的な仕組みなどが異なるため、目的に合わせて適切な情報を収集することが必要です。本記事では「土地活用のリースバック」に焦点を当て、その基本的な仕組みや活用方法、具体的なメリットについて詳しく解説します。この仕組みは、個人だけでなく法人の資金調達手段としても利用されており、近年注目を集めています。
目次
1. 土地活用におけるリースバックとは?具体的な仕組み
最初に土地活用におけるリースバックとその具体的な仕組みについて説明します。
1-1. 土地活用におけるリースバックとは
リースバックは、建設協力金制度を活用した借地事業の一つであり、「建設協力金方式」や「リースバック方式」とも呼ばれる仕組みです。
この方法の最大の特徴は、建設協力金を物件を探している事業者から受け取り、土地所有者がその協力金を使用して自らの土地に建物を建築することです。
その後、事業者が建物を使用して事業を行うという「仕組み」です。土地を手放すことなく収益を生み出せるため、資産の有効活用や長期的な資産価値の維持を図ることが可能です。
1-2. リースバック方式の具体的な仕組み
リースバック方式は、以下の手順で進められます。
Step1.土地活用会社への相談
まず、所有している土地でどのような事業が可能かを土地活用会社に相談します。この段階で、土地の立地条件や市場の需要などを踏まえた最適な活用プランを検討します。
Step2.事業者の選定
活用可能な事業の目処がついたら、リースバック方式で賃借契約を結べる事業者を探します。事業者の選定では、信頼性や業態、収益性などを確認し、最適なパートナーを選ぶことが重要です。
Step3.建設協力金の貸付
事業者と賃借契約を締結した後、土地所有者は事業者から建設協力金を借り受けます。この協力金は通常無利息で貸し付けられ、将来的に賃料から相殺する形で返済します。
Step4.建物の建設
借り受けた建設協力金を使用して、事業者の業態に適した建物を建設します。建物の設計や施工は、事業者のニーズに合わせて進められます。
Step5.賃料の受け取り
建物完成後、土地所有者は建物を事業者に貸し出し、賃料収入を得ることができます。賃料から建設協力金を差し引いた金額が土地所有者に支払われ、安定した収益を確保することが可能です。
2. 土地活用におけるリースバックのメリット・デメリット
土地活用におけるリースバックは、安定した収益を得られる一方で、契約条件や事業者の選定によるリスクも伴います。
そのメリットとデメリットを詳しく解説します。
2-1. リースバックのメリット
・初期投資の負担軽減
リースバック方式では、事業者から建設協力金を受け取ることが可能です。この建設協力金により、土地所有者は建物の建設に必要な初期投資を大幅に軽減できます。自己資金が少なくても土地活用を始めることが可能となり、資金面でのリスクを抑えつつ、土地の有効活用を実現できる点が大きな魅力です。
・空室リスクの回避
リースバック方式では、建物を使用する事業者が契約時点で決まっているため、空室リスクが低減されます。事業者からの安定した賃料収入が見込めるため、収益の予測が立てやすく、継続的な土地活用を実現できます。
・相続税対策
リースバック方式は相続税対策としても有効です。土地は「貸家建付地」として評価されるため、自用地よりも相続税評価額が低くなる可能性があります。また、建物は「貸家」として評価されることで30%の評価減が適用されるケースもあり、全体的な相続税負担の軽減が期待できます。
2-2. リースバックのデメリット
・固定資産税の増加
リースバック方式で建設した建物は土地所有者の資産とみなされるため、土地だけでなく建物に対しても固定資産税が課されます。
特に事務所や店舗といった事業用の賃貸の場合は、アパート・マンションなどの住宅用事業と比べると固定資産税が高くなる可能性が高まります。このため、土地活用を始める前よりも固定資産税の支出が増加する可能性があります。
・建設協力金の返済による収入の減少
建設協力金を活用することで初期投資を抑えられる一方で、協力金の分が月々の賃料から差し引かれる仕組みです。このため、自己資金で建築した場合に比べ、月々の手取り収入は減少します。返済期間によっては銀行融資を活用よりも比較的有利であるケースもありますが、事前に返済が完了するまでの期間、収益の圧迫を考慮する必要があります。
・契約破綻のリスク
リースバック方式では、事業者が契約途中で撤退した場合、建設協力金の返済処理が複雑になるリスクがあります。また、契約満了後に事業者が撤退した場合、新たな借主を探すのが難しいこともあります。特に、建物が特定の業態に合わせて設計されている場合、その用途に適した借主を見つけるのはさらに困難になる可能性があるので注意が必要です。途中解約時に貸付け金の残債の支払いの免除をする特約を設けるなど、回避策を講じる必要があるでしょう。
3. 土地活用においてリースバックが向いている業態の例
リースバック方式は、主として事業用建物の建築に採用されています。
この方式が特に向いているのは、大規模な初期投資を必要とし、長期的に安定した事業運営が見込める業態です。
また、運営に高度な専門知識やノウハウが求められる業態においても、リースバック方式の活用は効果的です。ここでは、具体的にどのような業態が該当するのかを解説します。
3-1. コンビニエンスストアの経営
コンビニエンスストアはリースバック方式を活用した土地活用に非常に適した業態の一例です。
この方式では、土地所有者が事業者から建設協力金を借り受け、実質的な初期出費を抑えながら、自身の名義で建物を所有することが可能です。
さらに、コンビニエンスストアは24時間営業で地域の生活インフラとして需要が高く、長期的な事業運営が期待できます。事業者が撤退するリスクは少なく、安定した収益が見込めるため、土地活用においてリースバック方式を選択する際の有力な候補となります。
>>関連記事:土地活用でコンビニを選ぶメリットとデメリット|向いている土地の傾向
3-2. 保育園や福祉施設の経営
保育園や福祉施設は、リースバック方式を活用した土地活用の有効な選択肢です。
この方式では、土地所有者が事業者から建設協力金を借り受け、施設を建設することで、自己資金の負担を大幅に軽減できます。建設後、施設を事業者に賃貸する形で運営を進めるため、安定した賃料収入を継続的に得ることが可能です。
さらに、保育園や福祉施設は地域社会において重要な役割を担うため、事業継続性が高く、長期的な安定運営が期待されます。このため、地域貢献と収益性を両立できる点が、土地活用の手法として注目される理由です。
リースバック方式を通じて、資産の有効活用と社会的意義の両面を追求できる選択肢となります。
>>関連記事:土地活用に保育園を選ぶには?主な運営方式やメリットとデメリット
3-3. アパート経営
リースバック方式はアパート経営においても有効な土地活用手法です。
この方式では、土地所有者が事業者から建設協力金を受け取ることで、初期費用を賄えるため、自己資金の負担を大幅に軽減できます。その結果、資金的な制約を緩和しながら、賃貸経営を始めることが可能です。
さらに、アパートの管理業務は事業者が行うことが多く、所有者の負担を軽減します。
賃貸運営に必要な専門的な業務を事業者に委託することで、所有者は安定的な賃料収入を確保しつつ、管理の煩雑さを回避できます。このように、リースバック方式は、アパート経営のリスクを抑えながら、効率的かつ安定した土地活用を実現する方法といえるでしょう。
3-4. ロードサイド店舗の経営
リースバック方式は、ロードサイド店舗の経営にも適した土地活用手法として広く利用されています。
ロードサイド店舗とは、主に郊外の幹線道路沿いに位置し、交通量が多いエリアに設置される店舗のことです。このような立地は、車での来店を前提とした業態に最適で、アクセスの良さが直接的に集客力を向上させます。
この方式が特に適している業種には、ファミリーレストラン、スーパーマーケット、ホームセンターなどが挙げられます。これらの業種は広範な顧客層をターゲットとしており、大規模な駐車場を備えることができれば、利便性をさらに向上させ、集客効果を最大化できるでしょう。
さらに、交通量が多いエリアに店舗を構えることで、安定的な収益が期待できるのも特徴です。このような立地条件を活用すれば、継続的な来客が見込め、長期的な事業運営に適した経営が可能となります。リースバック方式を活用することで、土地所有者は初期投資の大きな負担を軽減しながら、収益性の高い店舗経営を効率的に実現することができます。この手法は、土地活用と収益性の両立を目指す方にとって、有効な選択肢といえるでしょう。
>>関連記事:ロードサイド店舗による土地活用の仕組み
4. 土地活用におけるリースバックの可能性と活用ポイント
リースバックは、初期投資の負担を軽減しながら安定した収益を得られる魅力的な土地活用の方法です。
しかし、自分の土地にこの方式が適しているかどうかを判断するのは簡単ではありません。土地の特性や所有者のニーズに応じた最適な活用方法を選ぶためには、専門的な知識や市場動向の把握が必要です。
このような場合、土地活用の専門家に相談することをおすすめします。経験豊富な専門家は、所有者の目的や条件に合った具体的なプランを提案するだけでなく、リースバック方式のメリットとリスクについても丁寧に説明してくれるでしょう。
専門的なサポートを受けることで、リースバックの可能性を最大限に活かし、長期的に安定した収益を得られる土地活用を実現できるでしょう。
参考:大東建託が選ばれる理由
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング