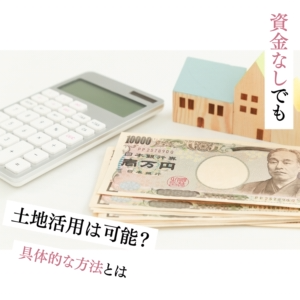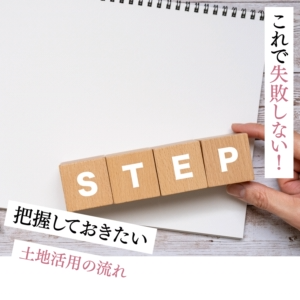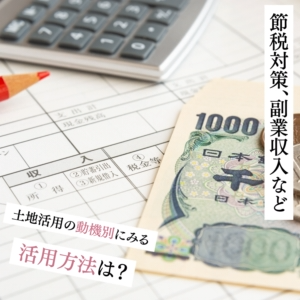グループホームの経営とは?成功へのポイントやビジネスモデル
公開日: 2023.11.10
最終更新日: 2025.09.18
昨今、土地活用方法の選択肢において、障害福祉サービスであるグループホームが注目されています。
グループホームの利用者数は右肩上がりの増加を続けており、令和3年2月実績では全国で14万人(厚生労働省調べ)にも上ります。
国や自治体も補助金や助成金を出しその整備を図っています。これらを利用すれば、立ち上げにかかる費用を軽減できるでしょう。
【出典】障害者の居住支援について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)
この記事では、土地活用におけるグループホームについて説明します。運営方式やメリット・デメリット、具体的な設立の流れ、グループホームに向いている土地についても説明します。
最後までぜひチェックしてください。
目次
>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方
1.グループホーム経営のビジネスモデル
グループホームとは、高齢者や知的・精神障害者の方など、生活に困難を抱えている方が介護サービスや福祉サービスなどの生活支援を受けながら、共同生活を送る住居のことです。
まずは、その仕組みや経営方法などの概要を確認していきましょう。
1-1.グループホーム経営の収益
グループホームの収益は、利用者から収受する利用料と、国からの給付金です。
利用者は、家賃や食費とともに、サービス利用料をグループホーム事業者に支払います。しかしこれはほんの一部で、グループホームの収益の大半は国民健康保険団体連合会(国保連)からの給付金で賄っています。
そのため、利用者は大きな負担なく、サービスを利用できるのです。
1-2.グループホームの種類
グループホームは、主に2種類に分かれます。
・認知症高齢者向け施設
軽度の認知症を患った高齢者が、症状の進行を緩和させるための施設です。
認知症は単調な生活が続くと進行が早まると言われているため、グループホームでの集団生活を通して認知症患者をケアします。建物1棟(1ユニット)に定員10人以内という小人数のグループで共同生活を行う傾向にあります。
・知的障害者や精神障害者向けの施設
知的障害者や精神障害者の自立的生活を支援するための施設です。
こちらも、職員が世話人としてサポートをしながら、日常生活が順調に送れる状態を目指します。障害者グループホームも、建物1棟に10人以内という小規模なグループで共同生活を行う傾向にあります。
1-3.グループホームの経営形態
地主が土地活用としてグループホームを選択するには、主に3種類の方式から選ぶこととなります。初期費用が少ない順に説明します。
・借地方式
グループホームの事業者に土地を貸与し、その借地料をもらう方式です。
この場合、地主は土地を貸しているのみであり、グループホームの建設や運営はすべて事業者が行います。
建物建築や運営にかかる手間や投資が最もかからない反面、3つの形態の中では高い収益が期待しづらい方式と言えます。
・サブリース方式
地主が自らの土地にグループホームを建設し、グループホームの事業者に施設を貸与する方式です。
この場合、事業者はグループホームの入居者それぞれから賃料を得て、地主に対して建物一棟分の賃料を支払います。地主は建物を建築する負担があるものの、借地方式より高い賃料を見込むことができます。
不動産投資のサブリースについては、以下のコラムで詳しく説明しています。
>>関連記事:不動産投資でサブリース契約を活用するメリット・デメリットは?
・自主方式
土地の所有者が自ら事業者として、すべての業務を行う方式です。
グループホームは、厚生労働省の許認可をもらうための運営基準を満たす必要があります。物件の建築から準備、営業活動、運営まで、すべて担うにはノウハウが必須です。
運営にかかる賃料収入から、介護職員にかかる人件費や食費などの費用を負担し、残った金額が地主の利益となります。
最もコストがかかる一方、利益が出た場合はすべて収受することができます。
2.グループホーム経営のメリット・デメリット
グループホームは、アパート経営などの土地活用と比較し、契約期間が長く長期的な収入が見込める、補助金を活用できるなどのメリットがあります。ここではメリット・デメリットを見ていきましょう。
2-1.グループホームのメリット
・長期的な収入が期待できる
借地方式・サブリース方式の場合は事業者との賃貸借契約になりますが、この契約は30年や50年など、数十年単位の長期間となるのが一般的です。また、グループホームの入居者は退去率が低い傾向にあり、長期的な入居になる傾向にあります。
一般的な賃貸アパートに比べ、グループホームは長期間安定した収入を得ることができます。
また、自主方式の場合でも、入居者は比較的施設を長い間利用する傾向にあります。一度入居が決まれば、長期にわたって収入が見込めるのがメリットと言えます。
・補助金制度が利用できる
グループホームは、その整備において補助金を活用することができます。
その最も大きなものが、「施設整備費補助金」です。これは、社会福祉法人等がグループホームや障害者施設、保護施設などの施設を新たなに開設する場合に、整備に必要な費用を国と自治体が補助するものです。
その上限額は、整備に要する経費の4分の3(2分の1を国が補助・4分の1を自治体が補助)と大変大きいものとなっています。
各自治体には窓口が設けられているため、まずは相談するのがよいでしょう。
・ニーズが立地に左右されづらい
グループホームは、利用者のケアやサポートが主な要素となるため、他の賃貸物件のように交通利便性が重視される傾向は少ないです。
立地で重要なのは平和かつ安全なエリアであるということなので、交通利便性の高くない土地にこそニーズがある場合があります。
2-2.グループホームのデメリット
・住民からの反対運動がおこる可能性がある
建物の規模にもよりますが、建設のために行政協議・住民協議が必要になる場合があります。
福祉施設の誘致を嫌がる住民から反対運動に合い、調整に苦労する可能性があるでしょう。
・一棟貸しのためテナントが退去すると収入が落ち込む
サブリース方式や借地方式の場合、法人に建物や土地をまるごと賃貸することとなります。これは前述した安定収入のメリットですが、もしその法人が退去した際、収入が0になってしまうデメリットもあります。
30年や50年の契約期間満了の以前から、契約更新の意思確認を行い、必要であれば後継テナントを探すことが必要です。
・建物の転用がしにくい
グループホームは設備基準・設置基準に合わせた設計をしなければならないため、よくある賃貸住宅への転用は難しいのが現状です。
そのため、基本的には建物の転用は計画に入れず、グループホームとして、長期的な経営をするという前提で収支プランを検討するのがよいでしょう。
3.グループホーム経営はどのような土地が向いているか
グループホームは建築基準法上「寄宿舎」として取り扱われます。
各地方自治体の都市計画法で「市街化調整区域」、もしくは「工業専用地域」に指定された地域には、原則建てることができません(※ただし、「公益上必要な建築物」として自治体に認められる場合には、建設できる可能性があります。詳しくは管轄の自治体へ確認ください。)。
グループホーム経営に向いているのは、周辺に住宅があって落ち着いた場所です。
グループホームを利用するのはその地域の住民です。サポートが必要な入居者が安心して暮らせる場所であることが求められます。
反対に、駅チカなど、公共交通機関へのアクセスの良さはあまり求められません。
また、広さは小~中規模程度のアパートが建てられる広さです。面積では、60坪から100坪ほどの土地が向いています。
4.グループホーム経営の流れ
グループホームは、自主方式で開業するためには様々な手続きが必要です。ここでは、自主方式でグループホーム経営を始める場合の進め方を解説します。
Step1.法人の設立
まず、グループホームは個人事業主の運営ができません。
福祉事業を行う法人を設立しましょう。
法人格であれば問題なく、株式会社、合同会社、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人などが挙げられます。
既に法人格を所有している場合は、その法人を活用しても構いません。
Step2.資金の調達
開業に必要な資金を確保します。
初期費用の多くは建物建設にかかるものですが、それ以外にも法人運営のために資金が必要です。
資金調達先としては、自己資金のほか、国や地方自治体の給付金、金融機関からの融資などが挙げられます。
金融機関の融資や自治体の給付金を利用する場合、福祉事業の実情に沿った事業計画書を作る必要があります。
福祉事業への深い理解が求められるでしょう。
Step3.市場調査・施設の確保
自らの土地がグループホームに向いている土地なのか、市場調査を行う必要があります。
顧客となる高齢者や障害者がそのエリアにどの程度いるのか、競合はどの程度あるのか等を調べましょう。
また、運営については都道府県の条例に定められた設置基準を満たす必要があります。
例えば東京都杉並区であれば、建物の設備基準として1人あたりの居室の面積を7.43㎡以上、ユニットに必要な設備として、定員分の居室のほか、一堂に会せる食堂・居間、台所、トイレ、洗面所、浴室等を備えなければなりません。自治体の基準に則って建築しましょう。
Step4.開業に必要な書類の提出と申請
申請書類については、予め自治体の部署と打ち合わせにより内容をすり合わせ、提出します。
書類審査ののち、現地確認が行われ、基準を満たしていれば事業所を開設することが可能です。申請において必要となる書類の一例をご紹介します。
<法人の情報>
・登記簿謄本
・定款
など
<施設が基準を満たしていることを証明する資料>
・施設の各種図面(平面図など)
・事務所の住所や人員配置について
・従業員の勤務形態
・サービス管理責任者の職務経歴・保有する資格
・設備や備品一覧
など
Step5.従業員の確保
グループホーム経営には以下の人員配置基準を満たす必要があります。
採用活動を行い、スタッフを雇用しましょう。事業者が自ら介護サービスを提供する、介護サービス包括型グループホームの場合の人員配置基準は以下の通りです。
|
役職 |
主な業務 |
人数 |
|
管理者 |
事業所のスタッフや業務の全般的な管理 |
常勤で1名以上 |
|
サービス管理責任者 |
支援計画の作成やサービス内容の管理 |
利用者数30人あたり1名 |
|
世話人 |
食事提供ほか、日常生活の援助 |
利用者4名ごとに常勤1名 |
|
生活支援員 |
食事、入浴、排泄など直接的な介護 |
常勤換算で、①~②の合計数以上 ①障害支援区分3の利用者数を9で除した数
②障害支援区分4の利用者数を6で除した数
③障害支援区分5の利用者数を4で除した数
④障害支援区分6の「利用者数」を2.5で除した数
|
Step6.利用者の集客
許認可が下りれば、いよいよ集客です。
グループホームは、特別支援学校や精神科、ソーシャルワーカー、自治体の相談支援事業などに施設を紹介してもらうことで、効率的に集客を行うことができます。地域のこれらの施設に対して、営業活動を行いましょう。
自主方式でグループホームを開業する流れは以上の通りです。
なお、前述した通り、グループホームの事業者に土地や施設を貸与する場合(借地方式・サブリース方式の場合)は、事業者が開業手続きを行います。地主は、大家として、事業者と土地や建物の賃貸借契約を締結するのみです。
自分に合った最適な方法を検討しましょう。
5.グループホーム経営で社会貢献と土地活用を両立させよう
今回は、土地活用としてのグループホームについて説明しました。
少子高齢化社会の日本においては、特に高齢者向けのグループホームは今後も増加の可能性が見込まれます。
今回ご説明した通り、自主方式による運営はノウハウが必要で、個人では難しい側面があります。
借地方式やサブリース方式であれば、不動産会社のサポートを受ければ十分始めることができるため、まずはそこから検討してみましょう。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング