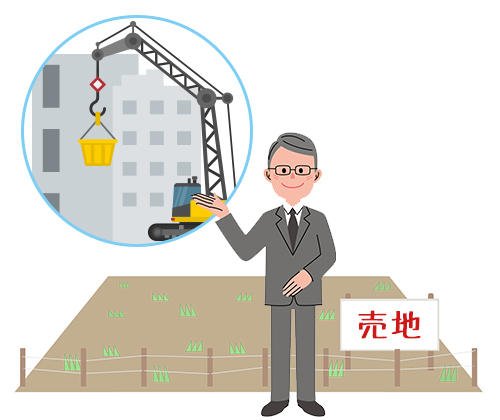アパート・マンション経営に役立つ資格は?必要な知識と資格
公開日: 2023.10.26
最終更新日: 2025.07.24
不動産投資や賃貸経営をするにあたって、資格は必須ではありません。
しかし、不動産系資格の学習をする過程において、金融資産運用や不動産業界で必要となる実務知識を網羅することができます。
基礎知識を身につけておけば、さまざまな場面で適切な判断ができるようになるでしょう。
そこで今回は、アパート・マンション経営を行うオーナーが理解しておきたい、おすすめの資格試験について解説します。
それぞれの資格の違いを試験内容、難易度などの項目ごとに分かりやすく説明します。
>>関連記事:アパート経営完全ガイド|建築プラン立てから完成後の業務まで
>>関連記事:マンション経営の種類|それぞれのメリット・デメリットは?
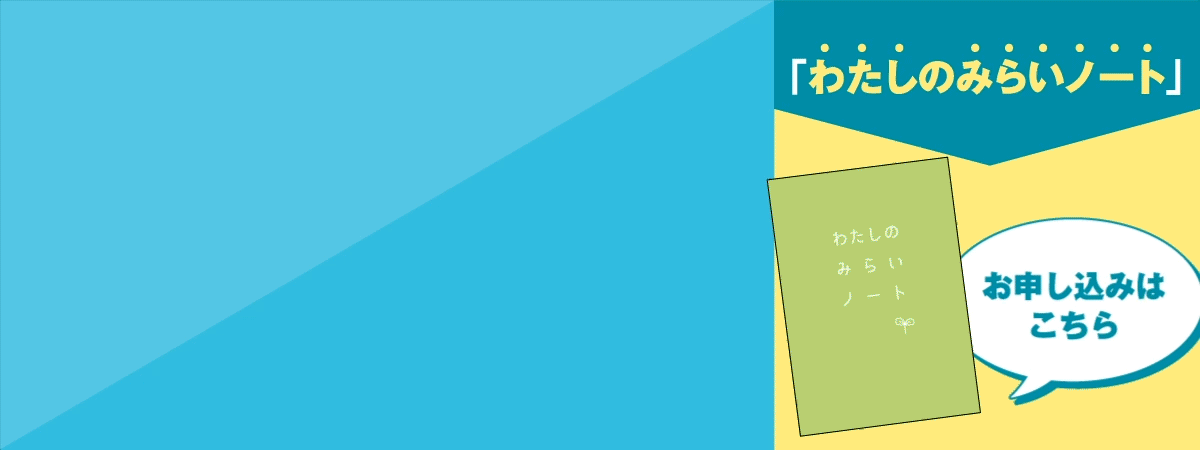
1.なぜアパート経営をするにあたって資格勉強をする人がいるのか
不動産投資では、ローンの組み方やどういった建物を建てるか、どういった管理体制で建物の管理を行うかなど、オーナーが判断しなければなりません。
資格の取得を目指す過程で、法律や会計など経営に必要な知識を学べ、判断できるようになるでしょう。
また、勉強することでアパート経営で起こり得るリスクを知ることができます。リスクと対処法を把握できるため、何かあった際にも適切な判断を下せるようになります。
2.アパート経営に生かせる資格
まずは、アパート経営と関係のある資格を紹介します。
どれも受験しすい資格試験なので、気になったものをチェックしていってください。
2-1.賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、不動産管理の専門家を育成する目的として、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が主催する国家資格です。
この資格は賃貸住宅管理業務を行う会社が営業所ごとに1人以上の設置を義務付けられている「業務管理者」の要件ともなっており、賃貸住宅管理の知識を体系的に習得することができます。
その内容は、賃貸不動産を管理受託する上で必要となる、法令や維持保全に関する事項、賃料等の金銭に関する事項、その他実務全般となります。
賃貸管理会社からの提案や条件を判断する目が養えることから、オーナーに広くおすすめできる資格です。
|
学べる内容 |
賃貸住宅の管理業務に必要な知識 |
|
試験日程 |
毎年11月中旬ごろ(年1回) |
|
試験形式 |
四肢択一、全50問 試験時間は2時間 |
|
受験料 |
12,000円 |
|
合格率 |
27.7%(令和4年度試験) |
2-2.不動産実務検定
不動産実務検定(旧大家検定)は、一般財団法人日本不動産コミュニティーが主催する民間資格です。
2級・1級とあり、賃貸経営を始める大家さんが知っておきたい実務的なノウハウを学ぶことができます。
2級では、賃貸管理運営(満室経営)実務に関する知識を学びます。
具体的には、賃貸経営に必要な法律知識、税務、ファイナンス、満室経営維持に必要な管理実務知識(空室対策)、賃貸借契約の種類と締結方法、リスクへの対処法、リフォームなどの修繕に関する知識、入居者の多様化に伴う賃貸経営実務知識が対象です。
1級では、不動産投資に関する実務知識を学びます。
ライフプランニングに応じた投資スタイル、不動産投資の調査や関連法規、借地取引の基礎、競売の実務、事業収支計画、税務、ファイナンス、建築構造に関する知識など、総合的かつ専門的な不動産投資実務が対象となります。
どちらもDVD教材とテキスト教材がセットになった認定講座があり、受講すると修了試験は5問免除となります。
|
学べる内容 |
大家業務に必要な知識 |
|
試験日程 |
随時(試験会場であるテストセンターにおいて事前予約の上受験可能) |
|
試験形式 |
四肢択一、全50問 試験時間は1時間 |
|
受験料 |
2級 7,700円 1級 8,800円 |
|
合格率 |
認定講座受講者:1級61%、2級76%。 一般検定受験者:1級50%、2級59%。 |
2-3.宅地建物取引士(宅建)
宅建士は、不動産取引の専門家を認定するための国家資格です。
日本では、不動産の取引を業として仲介する業者(宅地建物取引業者)に対して、事務所ごとに一定数の宅建士を置かなければならないと定められています。
不動産の売買契約書や賃貸借契約を締結する際、業者から物件や取引情報の重要事項を説明する「重要事項説明」が実施されます。この重要事項説明書の記名押印、説明は宅建士でなければ行うことが許されていません。
すなわち、不動産会社にとって宅建士は必要不可欠な存在です。不動産取引における民法や借地借家法などの法律知識を深く学べるだけでなく、不動産業者が守らなければならない法律についても学べるため、不動産業者とコミュニケーションを取ることが欠かせない不動産投資においては、勉強しておくと安心な資格といえます。
|
学べる内容 |
不動産取引に関する法律を中心とした知識 |
|
試験日程 |
毎年10月の第3日曜日(年1回) |
|
試験形式 |
四肢択一、全50問 試験時間は2時間 |
|
受験料 |
8,200円 |
|
合格率 |
18.6%(令和6年度試験) |
2-4.土地活用プランナー
土地活用プランナーは、公益社団法人 東京共同住宅協会が認定する民間資格です。
土地活用に関する賃貸管理、建築、税務、法務、事業収支などの様々な専門知識が出題されます。
土地に対して適切な活用方法を提案することができるように設けられた資格ですが、オーナーとしても、自分で受けた提案を判断できるようになるメリットがあります。
失敗を避けることは経営者にとって大切な要素なので、物件取得の前に試験範囲の知識を確認しておくだけでも価値があるかもしれません。
|
学べる内容 |
賃貸住宅の管理業務に必要な知識 |
|
試験日程 |
2025年度は2月・9月の年2回実施。 |
|
試験形式 |
四肢択一、全40問 試験時間は1時間 |
|
受験料 |
7,700円 |
|
合格率 |
相対評価となり合格基準点は変動(2019年9月の試験では、試験結果を集計後、合格率70~75%となるよう合格基準点を設定。合格率は徐々に下げていく方針とのこと) |
2-5.管理業務主任者
管理業務主任者は、一般社団法人 マンション管理業協会が認定する国家資格です。
分譲マンションの管理業者は、管理組合等に対し重要事項説明や管理事務報告を行います。
この際、管理業務主任者が必要とされているため、マンション管理会社などへの就職には有利な資格です。
得られる知識は、マンションの管理事務における全般的な知識です。
管理組合の会計や、建物の修繕計画、マンション管理に関する関連法令などが挙げられます。
|
学べる内容 |
マンションの管理業務に必要な知識 |
|
試験日程 |
毎年12月第1日曜日(年1回) |
|
試験形式 |
四肢択一、全50問 試験時間は2時間 |
|
受験料 |
8,900円 |
|
合格率 |
21.3%(令和6年度試験) |
2-6.サブリース建物取扱主任者
サブリース建物取扱主任者は、NPO法人日本住宅性能検査協会が認定する民間資格で、サブリースを取り扱う不動産会社の経営者・担当者が知っておくべき知識を問うものです。
サブリースとは、不動産のオーナーから物件を賃貸し、入居者に転貸するビジネスモデルです。
この試験では、サブリース業者の担当者が実務を行う上で必要となる基礎知識として、サブリース契約書の契約事例や、過去に実際に発生したトラブル案件などを学ぶことができます。
サブリースに特化した内容のため万人におすすめするものではありませんが、サブリース契約の締結を今後検討しているオーナーであれば、受験を検討してもよいでしょう。
|
学べる内容 |
サブリース業務に必要な知識 |
|
試験日程 |
通信講座のため無し |
|
試験形式 |
通信講座受講とレポート提出により資格付与 講習は約4時間 |
|
受験料 |
認定講習受講料:29,800円 |
|
合格率 |
非公開 |
2-7.不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルティングマスターは、国土交通大臣の許可を受けて公益財団法人 不動産流通推進センターが認定する民間資格です。
この資格は、依頼者からの相談を受け、不動産の利用・取得・処分・管理・経営・投資のアドバイスをする不動産コンサルタントを養成するものです。
試験範囲は事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目と広く、試験方式も択一式試験と記述式の筆記試験の両方を1日かけておこないます。
不動産売買等の仲介業務の担当者が、顧客からの信頼度を上げる目的で取得することもあるものなので、不動産投資をする上では参考になる知識が多く得られるでしょう。
|
学べる内容 |
不動産投資に関する知識全般 |
|
試験日程 |
毎年11月中旬ごろ(年1回) |
|
試験形式 |
50問四肢択一式試験(午前)および記述式試験(午後) |
|
受験料 |
31,500円 |
|
合格率 |
41.8%(令和6年度試験) |
2-8.ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナー「日本FP協会」と「金融財政事情研究会(略称:金財)」の2つの機関が実施する国家検定で、個人のライフプランニングをする上で必要となるお金の知識を幅広く学ぶことができます。
その内容は、ファイナンスの基礎知識や、税金、資産運用、年金制度、生命保険、不動産など様々です。
いずれも個人の生活と大きく関わりのある内容であり、不動産投資家でなくとも勉強時間を割く価値があります。
FP技能検定には、1級、2級、3級の等級があり、日本FP協会と金財によって試験形式や合格率が異なります。
ここでは日本FP協会のFP3級試験内容についてご説明します。
|
学べる内容 |
個人のライフプランニングで必要となるお金の知識 |
|
試験日程 |
毎年1/5/9月上旬(年3回) |
|
試験形式 |
計180分(学科:120分、実技:60分) ・学科試験 三択式の60問2時間 ・実技試験三択式の20問1時間 ※日本FP協会の実技試験科目は「資産設計提案業務」のみ |
|
受験料 |
学科試験4,000円・実技試験4,000円 |
|
合格率 |
学科試験86.2%・実技試験85.8%(令和6年4~9月度試験) |
2-9.日商簿記検定試験(簿記)
簿記は、各地の商工会議所が実施する技能検定です。不動産投資は、家賃収入を得て、経費を支払うというキャッシュフローが日々発生します。
これらのお金の流れを仕訳し帳簿に残し、決算書(個人事業主は確定申告書)を作成できるようになる知識を学ぶことができます。
もちろん、決算書は税理士に委託すれば作成してもらうことができます。
しかし、簿記の知識があれば、お金に強くなり、会計処理や収支計画を自ら建てることができるようになります。
なお、不動産投資をする上では、簿記3級の知識があれば十分実務に活かすことができます。
2級からは工業簿記の知識が求められるため、より専門的な知識を得たい場合は挑戦するとよいでしょう。
3級試験の概要は以下の通りです。
※なお、簿記試験では2020年12月よりネット試験が行われるようになりましたが、以下は従来型(統一試験)の内容です。
|
学べる内容 |
商業簿記に関する知識 |
|
試験日程 |
2023年度は6月、11月、2月に開催 |
|
試験形式 |
記述式、試験時間は1時間 |
|
受験料 |
2,850円 |
|
合格率 |
29.5%(2024.11.17統一試験) |
2-10.マンション管理士
マンション管理士は、公益財団法人マンション管理センターが実施する試験で、マンションの管理の専門家を養成するものです。
前述した管理業務主任者はマンション管理業者の事務所で働く実務者であるのに対して、マンション管理士は管理組合側の立場から、管理組合の運営に関して助言を行う立場であるのが特徴です。
この資格を学ぶことで、マンションの構造や管理規定など区分所有者同士のルール、長期修繕計画、入居者同士のトラブルの対処などの知識を得ることができます。
|
学べる内容 |
マンション管理に関する基礎知識 |
|
試験日程 |
毎年11月中旬ごろ(年1回) |
|
試験形式 |
四肢択一、全50問 試験時間は2時間 |
|
受験料 |
9,400円 |
|
合格率 |
10.1%(令和5年度試験) |
2-11.住宅診断士(ホームインスペクター)
ホームインスペクターとは、住宅の維持管理を目的とし、劣化状況や欠陥の有無を目視で判断し、修繕箇所やその時期、費用などをアドバイスする専門家のことを指します。
この試験では、ホームインスペクターが知っておくべき住宅に関する建築法令、その他法令、劣化の診断で必要となる実務知識、不動産売買に関する知識が問われます。
住宅診断という専門知識ながら、中古住宅を専門とする不動産投資家であれば学んでおくべき価値があると言えるでしょう。
|
学べる内容 |
賃貸住宅の管理業務に必要な知識 |
|
試験日程 |
毎年3/6/9/12月(年4回) |
|
試験形式 |
四肢択一、全50問 試験時間は90分 |
|
受験料 |
15,000円 |
|
合格率 |
39%(令和5年6月試験) |
2-12.土地家屋調査士
土地家屋調査士は、不動産登記に関する専門家として、土地や建物の境界確定や測量を行う国家資格です。
アパート・マンション経営では、所有する土地の境界を明確にし、将来的なトラブルを防ぐために役立ちます。独占業務があるため、専門的な知識を持つことで、他の不動産関連業務と差別化を図ることができるでしょう。
土地家屋調査士は、土地の測量や不動産登記に関心がある人や、不動産関連の仕事をしている人が多く取得しています。不動産業者や司法書士と連携して業務を行うことが多いため、相続や賃貸物件管理に関わる人にも有益な資格です。 資格取得の過程で、不動産登記や測量、民法に関する法律知識が身につきます。
また、アパート・マンション経営においては、自己資金を活用した土地購入時の境界確認や、相続税対策の一環としても活用できる知識を習得できます。
|
学べる内容 |
不動産登記の手続き、測量技術、民法・不動産関連法規、境界確定に関する実務 |
|
試験日程 |
毎年1回(通常10月頃) |
|
試験形式 |
筆記試験(短答式・論文式)および口述試験 |
|
受験料 |
8,300円(令和5年度参考) |
|
合格率 |
9.63%(令和4年度参考) |
2-13.不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産の適正な価値を評価し、公正な価格を算定する国家資格です。
不動産売買や賃貸の適正価格を判断する業務を行い、特に資産形成や相続税対策において重要な役割を果たします。
不動産鑑定士は、不動産会社に勤める人や、投資家、金融機関の関係者が多く取得しています。不動産関連のコンサルタントとして独立を目指す人にも人気があり、宅建業を営む人がスキルアップのために取得するケースもあります。
不動産鑑定士資格を勉強すれば、不動産の価格査定に関する高度な専門知識を習得できます。
特に、土地や建物の評価方法や、市場動向の分析、資産価値の算定に関する知識を深めることができ、アパート・マンション経営においても利回りの最適化や購入時の適正価格の判断に役立ちます。
|
学べる内容 |
不動産評価基準、市場分析・価格査定手法、経済学・会計学・税務、相続税や固定資産税の評価方法 |
|
試験日程 |
年1回(通常5月に短答式、8月に論文式) |
|
試験形式 |
短答式(マークシート)および論文式試験 |
|
受験料 |
13,000円(令和5年度参考) |
|
合格率 |
36.2%(令和6年短答式) 17.4%(令和6年論文式) |
3.アパート経営に関する知識に自信がない場合はどうしたら良い?
アパート・マンション経営を成功させるためには、単に物件を所有するだけではなく、さまざまな知識を身につけることが重要です。不動産に関する基礎知識や経営スキル、会計・税務の理解があれば、経営をスムーズに進めることができ、利回りの最大化にもつながります。
ここでは、アパート・マンション経営に必要な知識について詳しく解説します。
3-1.不動産に関する知識
アパート・マンション経営では、適切な物件を選定し、安定した賃貸経営を行うために、不動産に関する知識が不可欠です。
立地や建物の状態、設備などを見極めることで経営の安定性を高めることができ、表面利回りや実質利回り、キャッシュフローの計算ができると、収益性の高い物件選びが可能になります。
また、間取りや周辺環境を考慮しながら家賃相場を検討することで、賃貸需要を把握し、適切な賃料設定ができるようになります。
さらに、不動産登記や契約に関する法律知識を持っておけば、所有権や賃貸借契約の仕組み、トラブル防止策について理解し、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。
3-2.アパート・マンション経営に関する知識
また、賃貸物件を運営するための知識も必要です。空室リスクや修繕費用、入居者トラブルなど、賃貸経営にはさまざまなリスクが伴いますが、適切な対策を講じることで、安定した運営が可能になります。
入居者募集や退去時の対応、管理会社の活用など、実際の経営に役立つ知識を身につけておけば、スムーズな経営を実現できるでしょう。
3-3.会計や税務に関する知識
さらに、税務の理解があると、節税対策や資産管理がスムーズになります。確定申告や減価償却に関する知識があれば、青色申告を活用して節税メリットを享受することも可能です。また、会計上の損益やキャッシュフローを適切に管理することで、経営の安定性を維持できます。
税理士に業務を依頼することで手続きをスムーズに進めることもできますが、自分で処理できる部分を見極めることでコスト削減にもつながるでしょう。
4.アパート・マンション経営に関する知識を身につけるには?
アパート・マンション経営に必要な知識を身につけるためには、さまざまな方法があります。本やセミナー、コミュニティを活用することで、初心者でもスムーズに知識を得ることが可能です。ここでは、具体的な学習方法を紹介します。
4-1.アパート・マンション経営に関する本を読む
アパート・マンション経営に関する知識を得るためには、まず書籍を活用するのが有効です。不
動産業者やコンサルタント、不動産投資家が執筆した書籍は多数あり、実際の経験談や成功事例を学ぶことができます。初心者向けの入門書から専門的な実務書まで幅広く存在するため、目的に応じて選ぶと良いでしょう。
さまざまなタイプの本を読むことで、多角的な視点から知識を身につけることができます。
4-2.セミナーやコミュニティなどに参加する
また、書籍だけでなく、実際の経験者から学ぶことも大切です。
不動産投資のセミナーやコミュニティ、スクールに参加することで、専門家に相談する機会を得られ、実践的な知識を学ぶことができます。
不動産会社や投資家が主催するセミナーでは、最新の市場動向や経営戦略について学ぶことができ、実際に成功している投資家や経営者と情報交換をすることで、リアルな知識を得られるメリットもあります。
さらに、投資家同士のネットワークを築くことで、有益な情報を共有し合える環境を作ることも可能です。
4-3.専門家へ相談する
知識習得も重要ですが、パートナー選びも重要です。賃貸アパートを個人で管理するのは大変です。
そういったことから、不動産管理会社と管理委託契約を締結し、業務委託するのが一般的です。管理会社にはアパート経営に関する不安や悩みも相談でき、専門的な知識や過去のノウハウに基づいたアドバイスがもらえます。
パートナーを選ぶ際は、仲介や管理の経験が豊富であるかを重視しましょう。豊富な実績を持つ管理会社であればトラブル対応や入居者対応などもスムーズに行ってくれるため、安心して経営を任せることができます。管理会社の実績は、Webサイトや相談の場で確認できます。
5.資格勉強でアパート経営の知識レベルをアップさせよう
今回は、アパート経営で活用できる関連知識を得られる資格について説明しました。
今回ご紹介した資格は、いずれも不動産投資や賃貸経営においてなんらかの形で有利に働くものばかりです。
資格の勉強は体系的な知識を得ることでき、賃貸経営のさまざまな場面で自信をもって判断できるようになります。
不動産運用を成功に導くためにも、まずは気になったものから勉強してみましょう。
また、不動産関連の資産運用の始め方を知りたい場合には、不動産のプロである不動産会社に相談することをおすすめします。大東建託では無料でご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
■監修者プロフィール
宅地建物取引士/FP2級
伊野 文明
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。
【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング