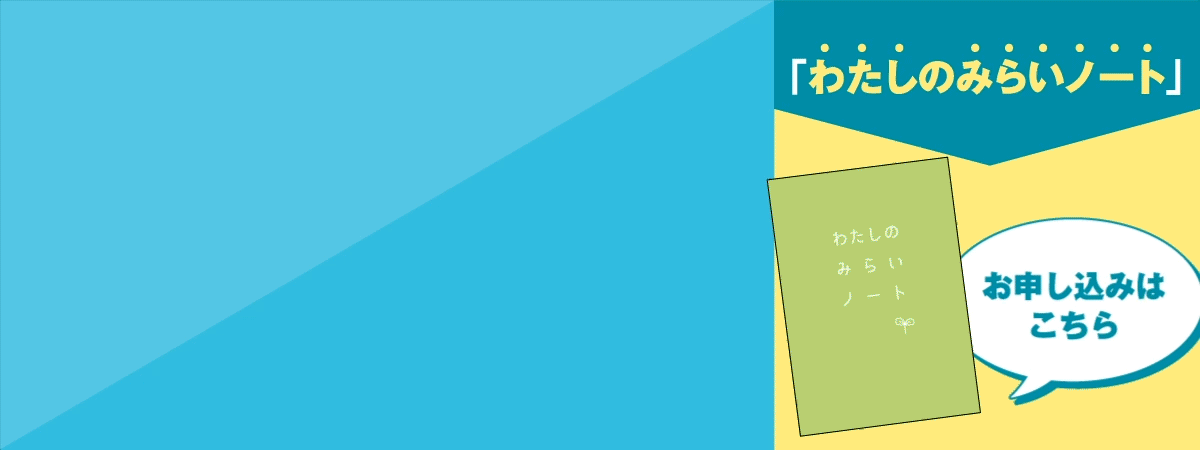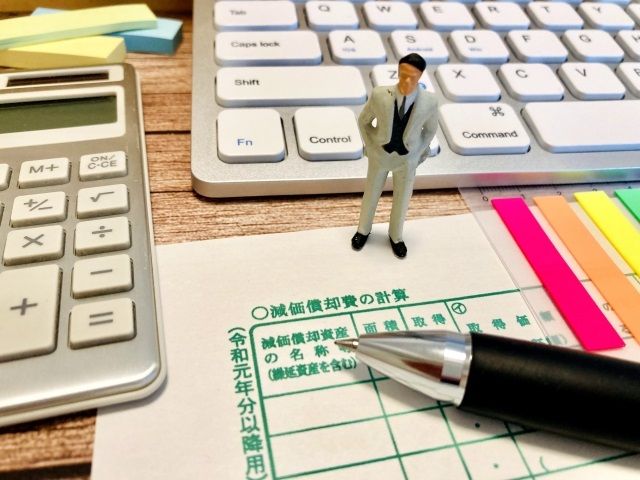アパートやマンションの建て替えを判断する6つのポイントや注意点を徹底解説!費用と流れもわかる
公開日: 2022.10.28
最終更新日: 2025.10.08
アパートやマンションなどの賃貸建物を長年保有していると、「いつかは必ず建て替える時期はくるものの、いつまでリフォームでつないでいくべきなのか」といったことで、悩んだことはないでしょうか?
そういった時に、どのような点に注意して検討するべきなのか、本記事では、賃貸建物の建て替え時期を判断するポイントや、建て替えにかかる費用の目安や流れ、建て替えのメリット・デメリット(注意点)をご紹介します。本記事を読むことにより、漠然とした不安を少しでも解消することができれば幸いです。
>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方
この記事のポイント
- 家賃や修繕費用、所得税など建て替えせずに運用し続けた場合の問題点と建て替えた場合にどんなメリットがあるのか理解することが大切
- 賃貸経営の運営のしやすさや相続税など資産承継の目線から考えることも重要
- 社会的なトレンドや地域のニーズを加味した建て替え計画を考えることが重要
目次
①.今後の家賃収入と修繕費用などの経費を予測し、収入が著しく下がる。(目標の収益からかけ離れる)
③.貸主責任を全うするうえでリスクが発生する可能性がある(老朽化・耐震性に問題がある)
➃.円満に資産承継するうえでの課題が出てくる(相続税や承継)
1.賃貸建物の建て替えを検討する6つのポイント
まず下記のような状況になった場合、一般的に建て替えを検討すべきと言えるでしょう。
- ①今後の家賃収入と修繕費用などの経費を予測し、収支が著しく下がる。(目標の収益からかけ離れる。)
- ②所得税負担が大きく、可処分所得を圧迫している。
- ③貸主責任を全うするうえでリスクが発生する可能性がある。(老朽化・耐震性に問題がある。)
- ➃円満に資産承継するうえでの課題が出てくる。(相続税や承継)
また建て替えを行う上で下記のような点に気を付けなくてはいけません。
- ⑤入居者様の転居など、建て替えをすることとなった場合のリスクを検証
- ⑥入居者ニーズやトレンドを取り込む
それぞれ解説します。
上記を解説する前に参考にマンションを建て替える際の費用の目安を紹介します。
1-1.マンションの建て替えにかかる費用
費用感を把握しておき、建て替えを検討すべきかどうか正しく判断できるようにしておきましょう。
マンションの建て替えは「建築費(新築費用)」だけでなく、既存のマンションを取り壊す「解体費」も必要になります。
建て替え費用・解体費用はマンションの構造や階数、設備の種類によって異なりますが、規模が大きいマンションほど価格が高額になりやすい傾向にあります。
参考までに一般的な坪あたり単価の費用相場を以下にまとめます。
【解体費】
・鉄骨造:3~5万円/坪
・鉄筋コンクリート造:3~8万円/坪
・鉄骨鉄筋コンクリート造:4~10万円/坪
【建築費】
・鉄骨造:70~120万円/坪
・鉄筋コンクリート造:90~120万円/坪
・鉄骨鉄筋コンクリート造:90~150万円/坪
※出典:「建築着工統計調査報告(令和2年度計分)」(国土交通省)
実際に500坪の鉄筋コンクリート造のマンション(8~10階建てを想定)を同じ規模で建て替える場合、どの程度の費用がかかるのか計算してみましょう。
解体費:500坪×5.5万円=2,750万円
建築費:500坪×105万円=5億2,500万円
※坪単価は中央値を使用
つまり、合計で5億5,250万円もの費用が必要になり、特に建築費の負担が大きいことがわかるでしょう。
①今後の家賃収入と修繕費用などの経費を予測し、収入が著しく下がる。(目標の収益からかけ離れる。)
まずは今後の家賃収入や修繕費用などの経費を予測して問題があるようなら建て替えを検討しましょう。
一般的に老朽化した賃貸建物は募集家賃の減少や、入居状況の悪化が予想されます。結果として賃料の低下や空室対策に追われ、キャッシュフローが悪化することが多いです。また、築年数の経過により、修繕が必要な箇所も多くなり、修繕費用も積み重なってきます。
それら、収益面の悪化と修繕などの必要経費の上昇を見込んで、想定している可処分所得が今後も実現できるのか予測しましょう。実現できない場合、新築物件に建て替えることで賃貸経営の状況が改善できるかどうかが、大きなポイントのひとつです。
そのため、建物の劣化具合を見極めて、リフォームや建て替えを検討することが重要です。
②所得税負担が大きく可処分所得を圧迫している。
可処分所得とは、サラリーマンのケースでは、税金や社会保険料などを除いた所得のこと(いわゆる手取り収入)を表しています。
アパート経営・マンション経営では、確定申告時に建物の取得金額を全額まとめて必要経費とするのではなく、その建物の法定耐用年数に応じて分割して計上していきます。(減価償却という)必要経費として計上することで、不動産所得を減らすことができ、所得税の節税につながります。
建物自体の寿命とは違いますが、建物の資産的価値は法定耐用年数通りに目減りしていくこととなります。
法定耐用年数は建物の構造や設備により違い、例えば軽量鉄骨は、19年もしくは27年、重量鉄骨は34年、木造の場合は22年、RC造は47年と定められているので、その期間内は減価償却することができます。
しかし、期間経過後は減価償却費を毎年の経費から差し引くことができなくなり、所得税が急激に増加する可能性も...。
既に所得税が大きく税負担を大きく感じている場合は建て替えの検討をしても良いかもしれません。
新しく建て替えることで、再び減価償却を利用できるようになるため、この点も含めて計算しておくべきだといえます。
また、複数棟の賃貸建物を所有している場合は、同時期に複数棟を建て替えると、減価償却期間が終了するタイミングも重なってしまうので、将来の収支計画を立てたうえで、建て替えるタイミングを調整することも必要です。
③貸主責任を全うするうえでリスクが発生する可能性がある(老朽化・耐震性に問題がある)
建物が老朽化したままだと、台風や地震などの災害時、建物が倒壊したり、一部破損したりして通行人や近隣の住民に被害を与えてしまう可能性があります。こうしたケースでは、所有者が適切な管理をしていたかどうかが問われ、老朽化した建物をそのまま放置していたと判断された場合、損害賠償請求される可能性もあります。特に建築基準法が改正された昭和56年(1981年)6月1日以降に建築された建物については注意が必要です。
この場合、改正後の建築基準法が適用され、新耐震基準を満たさないと違法建築(既存不適格)となるため、耐震性不足などで災害時の倒壊や損傷により被害を出してしまった場合、所有者責任が発生します。
このようなリスクも鑑みて、新耐震基準を満たしていない物件(旧耐震基準の物件も含む)は、耐震補強工事や大規模修繕をおこなうべきなのか、建て替えた方がいいのか費用対効果を検証したうえで検討することが大切です。
➃円満に資産承継するうえでの課題が出てくる(相続税や承継)
建て替えは、相続対策としても有効であり、将来の資産承継を見越して建て替えの時期を決めるのもひとつのポイントです。「継続的な収入源が欲しい」「現金が欲しい」など、複数の相続人で意見が相違するケースも少なくありません。
資産を受け継ぐ相続人にとって新築物件に建て替えられた状態の方がスムーズに賃貸経営を引き継げるという点もメリットだといえるでしょう。
建て替えは、相続対策にどう有効なのか
相続対策におけるアパートやマンションの建て替えのメリットとしてはこれらの点が挙げられます。
- 相続税対策につながる
- 新築状態の方が入居率、募集家賃も高く見込める
- メンテナンスをすぐにしなくてもいい
まず、アパートやマンションなどの賃貸建物は相続税評価額や固定資産税評価額が現金より低く評価されるため、相続税の節税効果が大きく、遺産分割対策含め、相続対策につなげられます。またマンション建替えにかかる建築費用を住宅ローン(アパートローン)で行った場合、相続資産から差し引くことができます。
相続税の算出で利用される相続税評価額は、賃貸用マンションのような「貸家」の場合、以下の計算式によって求められます。
・相続税評価額=建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
このうち、借家権割合は全国一律で「30%」と決まっており、原則として建物によって変わることはありません。
一方、賃貸割合は入居率を表しているため、マンションの経営状況によって変わります。上記の計算式では、入居率が上がれば建物評価額が低くなり、反対に入居率が下がると評価額が高くなる式になっています。
また、賃貸経営を受け継ぐ側としても、老朽化したアパートやマンションより新築状態の方が入居率や募集家賃を高くすることができ、比較的スムーズに経営できるでしょう。相続人は賃貸経営について経験が浅いことが多く、できるだけ不安のない状態(理解)している状態で始められるという点は大きなメリットだといえます。
そのためにも、ご家族に賃貸経営の状況を逐一共有しておくことも効果的でしょう。
順風な賃貸経営を継続するうえでは効率的なメンテナンスも重要なポイントとなりますが、建て替えをすることでしばらくは大規模なリフォームやリノベーションなどのメンテナンスをしなくてもよいといったメリットも生まれます。また、昔と比べ、現在は高耐久な資材も開発されているので、長い目で見ても、メンテナンスコストも抑えられます。
関連記事
⑤入居者様の転居など、建て替えをすることとなった場合のリスクを検証
建て替えをおこなう際には、現入居者との立ち退き交渉をしなければなりません。日本の法律では入居者側の権利が強く保護されており、立ち退き交渉は骨が折れるものです。入居者を退去させるためには、借地借家法により正当事由が必要とされているため、オーナーの権利で一方的にマンションの入居者を退去させることはできません。
そこでオーナーが立ち退き料を支払うことで正当事由の不足を金銭で補填し、居住者の賛同を得るのが基本的な進め方となっています。
また、不動産会社(管理会社)では弁護士法の規制により、立ち退き交渉でできる範囲は限られています。立退料を支払うことで円滑に退去してくれればよいですが、場合によっては裁判に発展してしまうといった可能性も。
円滑に居住者の賛同を得るために、普段から入居者との関係を密にしておくことも大切です。また、現入居者の年齢などによっては、転居先に制限が生じることもあり得ます。入居者にできるだけ不安や負担を与えないように仮住まいを用意するなど、建て替えを検討する際はこうした点も検証しておくことが大切です。
⑥建て替え時はトレンドを取り込むことも意識してみよう
老朽化したアパートやマンションを建て替える際には、トレンドを取り入れることで競合物件に対して差別化することも検討しましょう。
具体的には、以下のようなものです。
- 在宅リモートワークの方に向けたワークスペース
- デュアルライフ
在宅リモートワークの方に向けたワークスペース
新型コロナウイルスの影響により在宅リモートワークの方が増えました。こうした方に向けて、自宅で快適に仕事ができるように賃貸物件の居室内にワークスペースの需要が増え、実際に導入する物件も増えてきています。
ワークスペース導入については、建て替え時だけでなく、リフォームやリノベーションでの対応も検討し、賃貸物件としての価値を上げることも必要です。
>>関連記事:2019年アパート経営で注目のトレンドまとめ
>>関連記事:2020年の3大入居者トレンド「リモートワーク」「外国人入居者」「一人暮らし」
デュアルライフ
都心で働きつつ、週末は自然豊かなセカンドハウスで暮らすといったデュアルライフも最近のトレンドです。
例えば、アパート建て替え時にデュアルライフを検討されている方に向けて、都心であれば必要最低限の生活ができるワンルームマンション、地方であればセカンドハウスとして趣味を満喫できたり、リフレッシュできる空間を演出する間取りを検討したりするといったことが考えられます。
また、現在の新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響もあり、移動や人との接触を避けられるオンライン内見やIT重説が普及し始めています。
ネット環境が整っていれば、自宅や外出先から物件見学や重要事項説明を受けることができるため、このようなニーズに対応していくことも重要視されています。
2.マンションを建て替える際の流れ
では、実際にマンションを建て替える場合、どのような流れで行えば良いのか、4つのステップに分けて解説します。
Step1.建て替え計画を練る
マンション建て替え後の収益性を考慮して、計画を練ることから始めます。
建て替え工事には多額の費用がかかる関係上、建て替え後のマンションの収益性が悪いと損失を被る可能性があるため、事前に費用がいくらくらいかかるか積算したうえで、慎重に検討する必要があります。
また、築年数が古いマンションを現在の建築基準法に沿って建て替えた場合、建築当時に施行された法律が改正されており、容積率の規定が厳しくなっていることから、建て替え前より規模を縮小しなければならない可能性もあります。
なお、建築当時の法令には適合していたものの、その後の法改正によって現在の制限に適合しなくなった建物は「既存不適格建築物」として扱われます。既存不適格建築物は違反建築物ではないため、ただちに取り壊して適法な建物にする必要はありません。
ただし、新たに建築する場合は現行の法律に沿っていなければならないため、容積率の基準は必ず守らなければなりません。
※容積率とは敷地の面積に対して建物の延べ床面積が占める割合で、敷地に対する3次元的空間の制限を指します。
【区分所有建物の場合】
なお、参考までに分譲マンションなど区分所有建物で建て替えを実施する場合の手順を以下に紹介します。
この場合、まず区分所有者による「建て替え決議」を行うことが「建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)」で定められています。
建て替え決議では区分所有者数と議決権の5分の4以上の賛成が必要であり、要件を満たさない場合は否決となり、建て替えを決定することができません。
ただし、実際のところ、建て替えという大きな決断をするのに、区分所有者数の5分の4以上の賛成を得るのは容易ではないため、事前に管理組合総会を開催して区分所有者を集め、長期間の話し合いなどを行ったうえで決議に移るのが基本です。
Step2.居住者の立ち退きを開始する
建て替え計画が決まった後は、新規の入居募集を取りやめ、立ち退きの準備を進める段階に移ります。まずは管理会社に建て替えの予定を伝え、新規の募集を中止しましょう。
その後、マンションに入居している方と立ち退きの通知や交渉などを行います。
しかし、入居者にもそれぞれ都合があるので、入居者が多数いる場合、立ち退きを拒絶したり延期を要求したりする方が出て、合意が得られず難航する可能性もあるため、十分な対策を考えておく必要があります。
立ち退き交渉をスムーズに進めるために、入居している方が少なく、空室が多く発生しているタイミングを見計らって、建て替えを行う方法もあります。
ただし、適切な開始時期はケースによって異なるため、あくまで目安の一つとして考えるようにしてください。
Step3.工事費を確定させる
入居者との立ち退き交渉を進めつつ、建て替え計画を策定して工事費を確定させます。どのような設計が良いか、工事費はどのくらいが適切か、入念に検討するようにしましょう。
建て替えの場合、現在のマンションより階数を増加するケースもあります。
また構造の変更、設備機器の導入の有無(エレベーター、機械式駐車場、セキュリティシステムなど)によって工事費の額が大きく変わるため、事業計画をしっかりと立てたうえで、適切な方法を考えなければなりません。
そして最終的に新しいマンションの設計プランが確定したら、工事業者と請負契約を締結して、工事計画を進めることになります。
Step4.工事を実施する
マンションの建て替えでは、現存するマンションを取り壊す解体工事と、新しく建てる新築工事の2つの工事を行います。
解体と新築工事を別会社に発注するケースもありますが、工程の調整などが煩雑になり、オーナーの負担が増えるため、どちらも同じ会社に依頼するのが一般的です。
また、マンション建て替え時は、工事による騒音や振動が発生する関係上、近隣住民からクレームが来る可能性があるので事前に対策を行いましょう。
特に解体工事は激しい騒音や振動を伴うケースが多く「近隣住民へ事前に訪問して工事の説明をする」「工事のお知らせをポスト投函する」などの配慮は必須です。
基本的にこうした事前連絡は施工会社が実施しますが、万が一、トラブルが発生した場合、発注者が責任を問われるケースもあるので確認は行うようにしましょう。
「建築リサイクル法を遵守している」「解体工事の場合はアスベスト検査を行っている」など、コンプライアンス違反がないかどうかのチェックも重要です。
3.建て替えは計画的に行いましょう
賃貸建物の建て替えの判断ポイントや注意点などをお伝えしました。
不動産投資の失敗をしないために築年数の経過により発生するリフォーム費用や、減価償却がなくなることで上昇する所得税、空室率や家賃下落の入居・管理状況などによって想定している可処分所得から、かけ離れてしまっている場合は、築年数に限らず建て替えを検討した方がよい可能性があります。
少しでも気になる点があれば、まずは専門家に相談することが大切です。
また、次の世代への将来の資産承継においても、古い状態の建物より資産価値の高い新築の状態の建物の方が、受け継ぐ側にとって喜ばれるケースが大半です。円満な資産承継・ライフプランの実現のためにも、ご家族内で早いうちに話し合うことをおすすめします。
大東建託では、土地診断を含めた建て替えのシミュレーションをはじめ、建て替え後の相続税シミュレーションや、ライフプラン診断など無料でおこなっております。また、専門の税理士とのオンライン相談をおこなうことも可能です。
ご家族でお話しする際の参考資料として相続対策や所得税の税金対策などを検討するにもお役立ちできる資料を無料で提供しています。ご興味がある方は、こちらまでお気軽にお問い合せください。
AI不動産シミュレーションのご紹介


1983年福岡生まれ。上海復旦大学卒。
商社、保育園、福祉施設での勤務を経て、現在は不動産の記事を中心に手がけるライター兼不動産経営者。
実際に店舗・住宅を提供している立場から、不動産に関する記事を執筆中。趣味はフットサル、旅行、読書。
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング