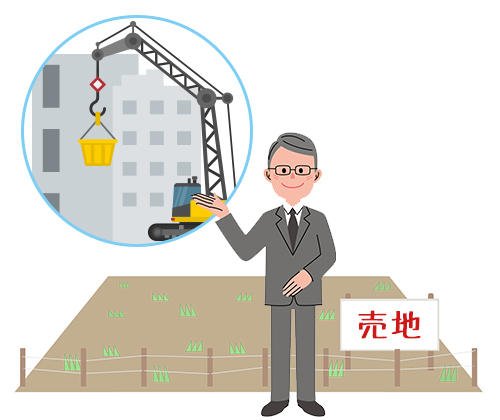アパート経営のデメリットやメリットは?リスク回避への具体的な対策
公開日: 2024.09.19
最終更新日: 2025.09.29
アパート経営は、安定した収入源を得られる投資方法の1つとして多くの関心を集めています。
しかし、投資方法を検討している人の中には、アパート経営が持つデメリットやリスクも把握しておきたいと考える人もいるのではないでしょうか。
この記事では、アパート経営のデメリットとメリットを解説し、潜在的なリスクへの対策を お伝えします。
本記事では、税制優遇による経済的なメリットから、空室や家賃滞納といったリスクへの対処法まで、幅広い観点からアパート経営の要点を押さえています。
これから始める方も、すでに経営を行っている方も運営のヒントになる内容になっていますので、アパート経営の成功に向けてぜひ参考にしてください。
1.アパート経営のデメリットとは?
アパート経営は魅力的な投資方法ではありますが、いくつかのデメリットやリスクが存在します。
これらを把握し、理解することで、より安心してアパート経営に取り組めるのではないでしょうか。
まずは、アパート経営の主なデメリットを詳しく解説します。
1-1.高額な初期費用が必要
アパート経営のデメリットのひとつは、高額な初期費用が必要なことです。
土地購入費、建築費、手数料、諸経費など、多額の初期投資が求められます。
多くの場合、自己資金だけでは不足するため、ローンを組んで融資を受けることになるでしょう。
これにより月々の返済負担は生じますが、レバレッジ効果を活用できるメリットも存在します。
レバレッジ効果とは、少ない自己資金で大きな投資を行い、より高い収益を得る可能性を指すものです。
1-2.維持費がかかる
アパート経営にはさまざまなデメリットがありますが、その中でも見過ごせないのが継続的な維持費の問題です。
固定資産税、管理費、原状回復費用・修繕費用 などの費用が定期的に発生し、所有者の負担となります。
通常、これらの費用は入居者から得る家賃収入で賄われますが、空室が続くと資金繰りに深刻な影響を及ぼすことも少なくありません。
固定資産税は毎年必ず支払わなければならず、物件の評価額に応じて変動します。
また、建物の経年劣化に伴う修繕費用も避けられません。長期的な視点で見ると、大規模修繕などの高額な出費も想定しておく必要があります。
これらの維持費を適切に管理し、安定した収益を確保するためには、慎重な資金計画とリスク管理が不可欠です。
>>関連記事:アパート経営を始めたときにかかる費用と続ける際にかかる費用は?
1-3.立地条件に左右されやすい
賃貸ニーズはアパートの建っている場所に強く影響されるため、慎重な立地選びが不可欠です。
一般的に、交通の便が良い場所や、周囲にスーパーマーケットやドラッグストアなどの生活利便施設が充実している地域、また人口が多いエリアでは賃貸ニーズが高くなります。
これらの条件が揃った場所では、入居率を維持しやすく、安定した収入が期待できます。
仮に、物件自体が魅力的で賃料が安くても、周囲に人が少ない場所では入居者を集めるのが困難です。
人口減少が進む地方都市や、利便性の低い郊外などでは、空室リスクが高まる可能性があります。
このため、アパート経営を成功させるには、エリアのマーケット調査や将来的な人口動態の分析が欠かせません。
立地選びの失敗は長期的な収益に大きく影響するため、専門家のアドバイスを受けることも検討すべきでしょう。
1-4.想定通りの収入が得られるとはかぎらない
アパート経営では想定通りの収入が得られるとはかぎりません。
新築直後は希望する家賃設定が可能ですが、時間の経過とともに賃料を下げざるを得ない状況に陥ることもあります。
さらに、入居者が増えない場合、家賃収入自体が見込めなくなります。
空室が続いたり、入居者の家賃支払いが遅延したりすると、ローンの返済に支障をきたす可能性も。
このような収入の不安定さは、長期的な資金計画に大きな影響を与え、経営の持続可能性を脅かす要因となりかねません。事前の事業計画が大切となります。
1-5.トラブルが発生する可能性がある
入居者との間で起こりうる問題には、家賃の未払い、騒音問題、設備の故障などがあります。
これらのトラブルは、解決に多くの時間と労力を要し、所有者の負担となります。
その他にも、予期せぬ自然災害が発生した場合、建物に大きな損害が生じる可能性もあるので注意が必要です。
地震や台風などによる被害は、修繕費用の増大や空室期間の長期化につながり、経営に深刻な影響を及ぼすことがあります。
これらのリスクに備えるためには、適切な保険加入や緊急時の対応策を事前に準備しておくことが重要です。
また、専門的な管理会社と提携することで、トラブル対応の負担を軽減できる場合もあります。
>>関連記事:不動産投資にはどのようなリスクがある?失敗しないためできることは 
2.アパート経営のメリット
アパート経営には、慎重に対策すべきデメリットがある一方で、魅力的なメリットも存在します。
適切に管理すれば、安定した収入源となり、資産形成にも貢献するでしょう。
ここでは、アパート経営の主なメリットを詳しく解説し、なぜ多くの投資家がこの選択肢に注目しているのかを探ります。
2-1.安定した収入源になる
アパート経営のメリットのひとつは、安定した収入源となる可能性が高いことです。
入居者から毎月家賃を受け取ることで、定期的な収入を得られます。
この安定性は、長期的な資産運用や将来の生活設計に大きな利点をもたらします。
また、アパート経営は経済状況や市場動向に合わせて柔軟に対応できる点も魅力です。
インフレが進行した場合でも、適切なタイミングで家賃を見直すことで、収益の実質的な価値を維持しやすくなります。
なお、市場調査や競合分析を定期的に行い、常に競争力のある物件を提供することも欠かせません。
>>関連記事:アパート経営で得られる年収はどれくらい?シミュレーションで算出
2-2.資産として残せる
アパートは有形資産として残せるのも大きなメリットです。
土地と建物は形のある財産で、長期的な資産価値を持ち続ける可能性があります。
そのため、将来的には、所有するアパートを売却して資金化することも選択肢のひとつです。
不動産市場が好調な時期であれば、購入時よりも高い価格で売却できる可能性もあり、キャピタルゲイン(売却益)を得られる可能性があります。
ただし、資産価値は立地や建物の状態、市場動向などに大きく左右されます。
そのため、定期的なメンテナンスや適切な修繕を行い、物件の価値を維持・向上させる努力が必要です。
また、将来の売却を見据えた戦略的な物件選びも重要です。
さらに、アパート経営はインフレに強い側面を持ち、物価が上昇しても資産価値が下がりにくい特徴があります。
そのため、所有するアパートを将来的に売却して資金化することも選択肢のひとつです。
このように、アパート経営は長期的な視点で見た場合、インフレによる資産価値の低下を防ぐ役割もを果たします。
2-3.税金の負担を軽減できる
アパート経営の重要なメリットのひとつに、税金の負担を軽減できる点があります。
これは主に以下の3つの側面から恩恵を受けられます。
まず、減価償却の活用により所得税の圧縮が可能です。
建物の経年劣化に伴う価値の減少を経費として計上でき、課税対象となる不動産所得を減らせます。構造別に法定耐用年数が定められており、木造の場合は22年、鉄骨造は34年、鉄筋コンクリート造(RC造)は47年で償却できるため、長期にわたって税負担を軽減できます。
次に、固定資産税の減額が可能です。
一定の条件を満たす賃貸住宅は、固定資産税が軽減される特例措置があります。住宅用地の軽減措置により土地の評価額を最大1/6まで、都市計画税を最大1/3まで減額できる上、建物の軽減措置を利用すれば戸建てで3年間、マンションで5年間にわたり固定資産税を1/2に軽減できるため(1戸あたり120平米まで)、これらの制度を適切に活用することで毎年の固定資産税負担を大幅に抑えられるでしょう。
さらに、相続税評価額の減少も期待できます。
賃貸中の不動産は、自用の土地建物と比べて相続税評価額が低く算定されるため、相続税の節税効果があります。
ただし、これらの税制優遇を最大限に活用するには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
>>関連記事:賃貸アパートが相続対策になる理由は?実際の数字でシミュレーション
2-4.自分で住むこともできる
所有するアパートに自分や家族の住まいとしても利用できる点もメリットです。
所有者が建物の一部に居住し、残りの部屋を賃貸に出すことで、自宅を持ちながら家賃収入も得られるという一石二鳥の効果が期待できます。
また、将来的に家族構成が変わった際や、老後の住まいとして活用することも可能です。
さらに、自分で住む部屋については、好みに合わせてリフォームすることができます。
これにより、投資物件でありながら、快適な生活空間を作り出すことができます。
ただし、アパートローンで融資を組んだ場合、その融資は通常「投資目的」として提供されているため、借主がそのアパートに住むことが認められないケースが一般的です。
もし自分や家族が居住する予定がある場合は、賃貸併用住宅ローンなどの別の融資商品を検討する必要があるので、事前に金融機関と相談し適切なローンの選択を行うことが重要です。
>>関連記事:アパート経営をしながら自分で住むことはできる?経営する際の注意点
2-5.サラリーマンの副業として始めやすい
アパート経営は、サラリーマンの副業として始めやすいというメリットがあります。
通常の仕事と並行して行えるため、時間的な制約が比較的少ないのが特徴です。
特に、管理業務を専門の管理会社に委託することで、所有者の時間や手間を大幅に削減することができます。
入居者の募集や選定、家賃の回収、建物のメンテナンスなど、日々の運営に関わる業務を任せることができるため、本業に支障をきたすことなく経営を行えます。
ただし、すべての業務を委託するわけではないので、ある程度の時間と労力は必要です。
また、委託費用が発生するため、収支計画には注意が必要です。
>>関連記事:副業でもアパート経営できる!委託管理の上手な活用方法とは
3.アパート経営におけるリスクを回避するには?具体的な対策の例
アパート経営には複数のリスクが存在しますが、適切な対策を講じることで軽減することが可能です。
ここではアパート経営におけるリスクと具体的な対策例を紹介します。
3-1.空室・家賃滞納リスクへの対策例
空室対策として、入居促進のためのマーケティング調査が重要です。
地域の賃貸ニーズ に沿った間取りや設備を導入することで、物件の魅力を高めることができます。
例えば、単身者向けの物件が不足している地域であれば、1Kや1LDKの部屋を中心に構成するなどの工夫が効果的です。
また、入居者層を明確にし、ターゲットに合わせた広告展開も効果的です。
例えば、学生向けであれば大学の掲示板や学生向けウェブサイトでの宣伝が有効でしょう。
他には、成約率の高い賃貸仲介事業者と連携することで、空室期間を短縮できます。
家賃滞納リスクに対しては、入居者の審査を厳格化し、保証会社の利用を検討します。
さらに、家賃の自動引き落としシステムを導入することで、滞納を未然に防ぐことができます。
また、万一家賃滞納が発生した際には、早期に発見して迅速に対応できる仕組みやノウハウを持つ管理会社と提携することも、滞納家賃の回収を高めるための効果的な手段となります。
定期的な物件のメンテナンスや、入居者とのコミュニケーションを大切にすることも、長期的な入居を促し、リスクを軽減する有効な方法です。
>>関連記事:賃貸仲介のポイント~仲介会社の選び方と重要性~
3-2.家賃下落リスクへの対策例
家賃下落リスクは、アパート経営者にとって重要な課題です。
このリスクに対処するためには、以下のような具体的な対策が効果的です。
まず、定期的な市場調査を実施することが欠かせません。
地域の家賃相場を把握し、適正価格を設定することで、競争力を維持しつつ、急激な家賃下落を防ぐことができます。
次に、他の物件との差別化を図ることが重要です。
例えば、Wi-Fi完備、宅配ボックスの設置、防音設備の強化など、需要に沿ったサービスや設備を提供することで、物件の付加価値を高められます。
これにより、より選ばれる物件となる可能性が高まるでしょう。
信頼できる業者と契約することで、一定期間の家賃収入を保証してもらえる場合があります。
ただし、契約内容を十分に確認し、長期的なメリット・デメリットを慎重に検討することが大切です。
3-3.修繕リスクへの対策例
修繕費はアパート経営に不可欠なコストですが、適切な管理が重要です。
定期的な外壁塗装や設備更新などの通常の修繕費は経営計画に組み込むべきランニングコストです。
定期点検や予防修繕を怠ると、小さな問題が大規模修繕につながったり、建物の劣化で修繕費が急増するリスクがあります。
これに対処するには、長期的な修繕計画を立て、毎月の収益から積立金を確保し、定期的なメンテナンスを実施することが効果的です。
適切な修繕管理により、通常の修繕費をコントロールしつつ、予期せぬ高額修繕のリスクを最小限に抑え、長期的な収益性を維持できます。
>>関連記事:賃貸経営におけるランニングコスト~修繕費の目安と時期~
3-4.金利上昇リスクへの対策例
金利上昇リスクはアパート経営の収益性を脅かす重大な要因です。
固定金利ローンの選択は、金利変動の影響を最小限に抑える賢明な方法です。
将来の金利上昇に左右されず、安定した返済計画を立てられる利点があります。
また、自己資金の割合を増やすことも有効な対策です。
借入金額を抑えることで、金利上昇時の影響を軽減できます。可能なかぎり多くの自己資金を用意することが望ましいでしょう。
収益が安定してきた段階での繰り上げ返済も検討に値します。借入残高を減らすことで、将来の金利リスクを大幅に軽減できます。
事業計画の立案時には、ある程度の金利上昇を見込んでおくことが重要です。
最悪のシナリオを想定し、それでも採算が取れるような計画を立てることで、金利環境の変化にも柔軟に対応できます。
ただし、相続対策を目的とする場合には、自己資金を多く投入することが必ずしも最適とは限りません。
将来的な資産分割を見据え、現金を手元に残しておくことが有効な場合もあります。
3-5.入居者トラブルのリスクへの対策例
入居者トラブルのリスクに対しては、予防と適切な対応が鍵となります。
まず、明確なルール設定が重要です。
入居時に詳細な契約書を交わし、生活ルールや禁止事項を明文化することでトラブルを未然に防ぎます。
さらに、実績豊富で信頼できる管理会社に業務を委託することも有効です。
特に、24時間365日のサポートセンターを自社運営している管理会社であれば、入居者からの緊急連絡やトラブルに対して迅速に対応でき、所有者の負担を大幅に軽減できます。
これにより、入居者の満足度が向上し、長期的な賃貸経営の安定にも寄与します。
>>関連記事:不動産管理会社を選ぶときのポイントは?依頼できる業務の例
3-6.災害リスクへの対策例
災害リスクへの対策は、アパート経営の安定性を確保する上で非常に重要です。
まず、包括的な保険加入が不可欠です。
地震や台風などの自然災害だけでなく、自殺や孤独死による損害も補償する特約付きの保険を選択することをおすすめします。
さらに、建設時には耐震性の高い建材を使用することに加え、耐震性の高い工法を選択することで、建物の構造自体の強度を高めることが重要です。
これにより、災害発生時の被害を最小限に抑え、長期的な経営の安定を図ることができます。
また、災害発生時の対応マニュアルを事前に作成し、入居者や管理会社と共有することで、緊急時の混乱を最小限に抑えることができます。
こうしたオーナー様の自助努力に加え、全国展開している業者で、災害時の対応に豊富な実績と優れたノウハウを持つ企業と提携することも有効です。
これにより、災害発生時に迅速かつ適切な対応が可能となり、被害の軽減と入居者の安全確保に大きく貢献します。
>>関連記事:賃貸経営の5つのリスクとは
4.アパート経営を成功させるにはリスク管理と専門家のサポートが大切
アパート経営には魅力的なメリットがある一方で、さまざまなリスクも存在します。
これらのリスクを適切に管理し、メリットを最大限に活かすことが成功への鍵となります。
空室対策、家賃下落への備え、修繕計画、金利変動への対応、入居者トラブルの解決、災害リスクへの準備など、アパート経営には多岐にわたる知識と経験が必要です。
これらすべてを個人で管理することは非常に困難であり、専門家のサポートが不可欠です。
専門の業者を選定する際には、豊富な実績や信頼性、リスク管理に関する対応力、サポート体制を重視することが大切です。
例えば、長期にわたる借上げ保証や家賃保証のシステムを提供している企業は、経営の安定性を高めるパートナーとなり得ます。
大東建託は総合的な土地活用サービスを提供している企業として、50年以上の実績を持っています。35年間の借上げ保証や空室時の家賃保証など、オーナー様の不安を解消する独自システムにより、安定した経営をサポートします。
アパート経営を検討中の方や、現在の経営に課題を感じている方は、まずはお気軽に資料請求やお問い合わせをしてみてください。
豊富な経験に基づく専門的アドバイスとサポートで、あなたの土地の可能性を最大限に引き出し、安定した収益実現のお手伝いをいたします。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
注目のハッシュタグ
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング