土地信託とは?仕組みとメリット・デメリット、始めるための4つの流れ
公開日: 2023.04.24
最終更新日: 2025.07.15
土地をプロに託して収益の一部から配当金を受け取る土地信託。自分で土地を活用するとなると知識や手間、時間が必要です。
土地活用方法の基礎知識がなく、勉強する時間や自分で土地活用をするノウハウや時間がない人には、選択肢のひとつになるのではないでしょうか。
この記事では土地信託の基礎やメリットやデメリット、土地信託を始める際の流れを解説していきます。
>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方
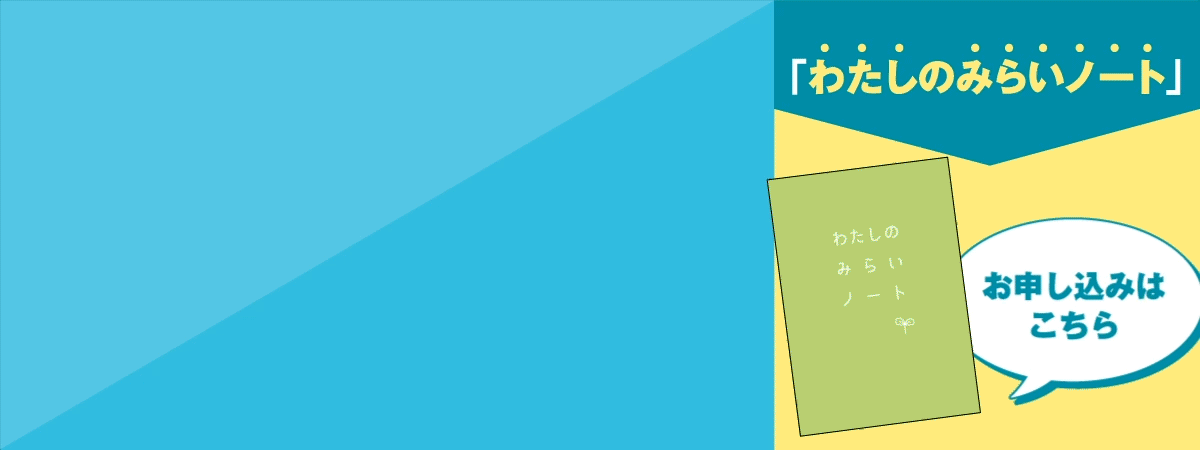
目次
1.土地信託とは
土地活用を委託して最適な活用方法で運用してもらう土地信託は、将来性と安定性を考えて最適な業者に依頼することが大切です。
そのためには最低限、土地信託の仕組みを理解しておくことをおすすめします。
1-1.土地信託の意味と仕組み
土地信託とは、信託会社や信託銀行に所有する土地を貸し出して土地活用を委託することです。
土地信託は土地所有者が資産運用の手段のひとつとして検討できるもので、土地の所有者は委託先が上げた利益から、配当金を受け取ることで収入を得られる仕組みです。
この配当金を受け取る権利を「信託受益権」と呼びます。
管理型信託サービスを提供している建設会社もあり、土地信託と管理型信託が混合している人もいるのではないでしょうか。
土地信託は土地活用を委託して運用する信託方法であるのに対し、管理型信託は委託者が受託者に財産の権利を移転(受益者は信託財産から生じる利益を受け取る権利を持つことになります)し、財産管理や処分を任せる信託方法です。
1-2.土地信託はアパート・マンション経営が一般的
土地信託は基本的に、土地にアパート・マンションを建築し、運営するケースがほとんどですが、テナントを募集する業者や物件管理の会社は、信託会社や信託銀行と別になります。
そのため、運用する業者と建物や設備などを管理するそれぞれの業者に、手数料を支払う必要があります。
2.土地信託のメリット
土地活用の方法で土地信託を検討している場合、事前にメリットを確認しておく必要があります。
2-1.土地活用や経営の専門知識が不要
自分アパート・マンション経営を行う場合、不動産投資の知識が必要です。
土地信託は不動産のプロが土地活用を請け負ってくれるため、不動産投資の知識は必要ありません。
事業計画の立案から土地の運用・管理までをまとめて一任できるため、初心者でも運用ができます。
2-2.相続対策につながる
土地信託を行うと土地の所有権は信託財産として信託会社に移り、土地の委託者は信託受益権を取得することになります。
この状態で相続が発生した場合、相続人は土地の所有権ではなく、信託受益権を相続することになります。そのため相続税対策として、土地を相続するよりも相続税を節税できる場合があります。
2-3.信託受益権を売買できる
配当金が受け取れる信託受益権は売買することができます。
土地の所有者が個人でアパート・マンション経営を行う場合、売却を考えていても入居者がいれば強制的に立ち退かせることは不可能であり、その権利もありません。そのため、権利が売買できることは大きなメリットになるのではないでしょうか。
2-4.資産承継の意思表示ができる
不動産信託の大きなメリットは、自分が元気なうちに契約行為を通して不動産運営(資産承継)の意思を表示することができるという点にあります。
例えば、自分が認知症になった後ではこのような意志の表明は難しくなります。管理会社に委託するよりも経費が大きくかかる代わりに意思表示ができるということは大きなメリットです。
3.土地信託のデメリット・注意点
ここからはデメリットについて解説していきます。
土地活用の方法で土地信託を検討している場合、事前にデメリットを確認しておく必要があります。
3-1.必ず収益が出るわけではない
信託会社が事業運営によって得た収益から経費を差し引いた金額が収入になります。
そのため、収益が少なかったり経費が多かったりするケースなど、信託会社や信託銀行の運用状況によっては配当金が得られないことがあるため、注意が必要です。
また、収益の赤字部分は信託した人の負担になります。金融機関からの借入金を完済してない場合も信託した人の負担になり、信託会社は肩代わりしてくれません。また、信託財産から生じた不動産所得の赤字は、赤字が生じなかったものとみなされるため、他の所得と通算することができないので注意しましょう。
3-2.仲介手数料がかかる
また、土地信託は信託会社に報酬(信託報酬)を払う必要があります。
信託報酬分の利益が圧縮されるため、自分で運用するよりも収益性が低くなり、管理会社に運営を任せるより、費用負担が大きくなるということを覚えておきましょう。信託報酬は自分で運用する際にはかからない費用のため、手数料を負担しても土地信託をするか否かを判断する必要があるのではないでしょうか。
3-3.土地信託ができない土地もある
すべての土地が信託できるわけではなく、土地信託ができない土地もあります。
土地信託は、収益性が見込める土地でないと契約できない可能性があるため、土地信託ができない土地もあることを覚えておきましょう。
3-4.家族信託にする場合の注意点
家族信託は委託者と受託者の二者が合意することで契約が成立します。
相続人が複数いる場合でも、相続人全員の了解を得ずに相続財産の話を進めることができます。
親族のうち一人が受託者として財産管理をすることになるため、親族から不平不満が出る可能性があり、それが原因で親族間のトラブルに発展する場合も考えられます。
※家族信託とは財産の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理し運用できる権利」に分けて後者のみ子どもに渡すことができることをいいます。
相続対策で土地信託を行う場合は借入金の有無や残高、相続する時点で建物があればアパート・マンションの入居数など、事前に把握しておくことをおすすめします。
4.土地信託の流れ
土地信託の流れは下記のように進んでいきます。
Step1 :信託会社・信託銀行に相談する
Step2 :土地信託契約を締結し、土地の所有権を移転する
Step3 :信託会社・信託銀行と事業プランを作成する
Step4 :運用が始まり、配当金を受け取る
順番に流れを説明していきます。
Step1 信託会社・信託銀行に相談する
土地信託を進める最初のステップは信託会社・信託銀行に相談することから始まります。その際、複数の業者から提案をもらって比較検討することが重要です。業者によって専門性や強みなどの意見や提案が異なることもあるため、複数の業者から提案をもらうことで自身の希望や条件に適した提案を見極めやすくなります。
Step2 土地信託契約を締結し、土地の所有権を移転する
信託会社・信託銀行が決まったら手続きに進み、土地信託契約を締結します。土地信託契約を締結することで委託者は「信託受益権」を取得し締結後、土地の所有権移転を進めます。
土地信託契約は委託者の利益をもたらす目的に従い運用することを定めた契約になるため、内容をしっかり確認しておくことをおすすめします。
Step3 信託会社・信託銀行と事業プランを作成する
信託会社・信託銀行はどのように土地を運用するかのプランを策定し、土地の元所有者である委託者に共有します。提案を受けたプランを確認し方向性などの希望を伝えるなど、運用の結果に左右される部分になるため、意見がある場合は伝えておくことをおすすめします。
Step4 運用が始まり、配当金を受け取る
運用が始まると諸経費を差し引いた配当金が委託者に支払われます。諸経費には建設時の借入金の返済や信託会社への信託報酬、建物の管理費などがあります。
アパート・マンションなどの賃貸経営を行っている場合、入居者が少なく空室が多いなどの理由で諸経費以上の賃料収入による収益が得られないと、配当金が支払われない場合もあります。
土地信託は、契約を締結してから10年~30年といった長期の契約になることが多いです契約期間(信託期間)が終了すると建物と土地が地主に返還されますが、自己資金が足りないなどの理由で契約時に組んだローンの支払いが完済してない場合は委託者が返済を続けることになるため、注意が必要です。
5.土地信託を正しく理解して有効な手段か確認しよう
土地信託の仕組みやメリット・デメリット、注意点などを解説しました。
土地活用の選択肢のひとつである土地信託は信託会社に運用を一任できるため、土地活用の知識や経験がない初心者の人や時間がないオーナーでも始めやすく有効な方法ではないでしょうか。ただし、必ずしも配当金を受け取れる保証はないため注意が必要です。
メリット・デメリットや注意点を参考に、自分の目的が土地信託で叶うのか否かを判断した上で、まずは相談というかたちで信託会社に問い合わせしてみると良いのではないでしょうか。
■監修者プロフィール
有限会社アローフィールド代表取締役社長
矢野 翔一
関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。
【保有資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)、宅地建物取引士、管理業務主任者
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング

















