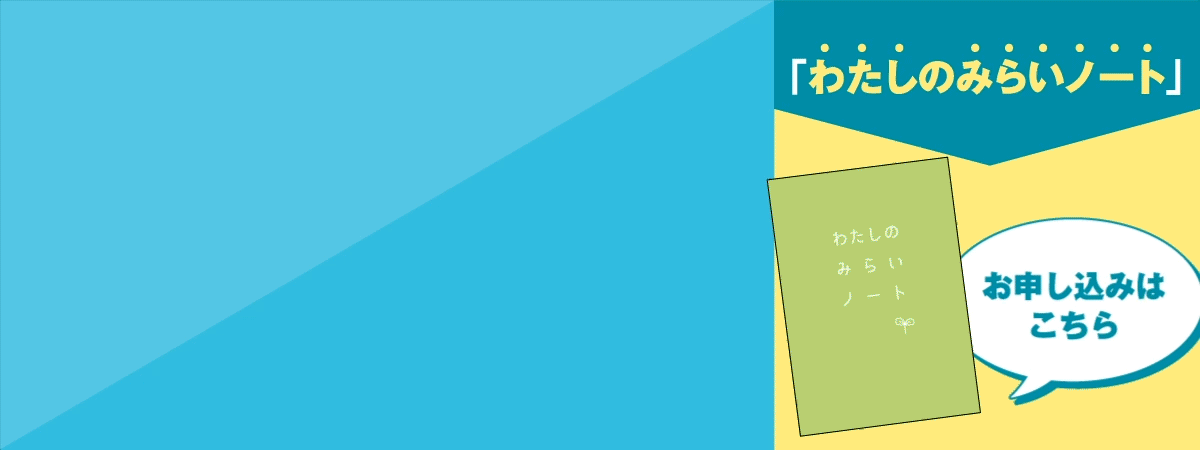空き家で土地活用するには?空き家の活用法や放置するリスク
公開日: 2022.10.28
最終更新日: 2025.08.28
日本では空き家の数が年々増加しており、深刻な社会問題になっています。実際に空き家を所有していても、使い道がなく困っている方も多いことでしょう。
しかし、空き家を管理せず放置していると、建物の劣化が進行し、景観の悪化、悪臭・害虫の発生といった問題を引き起こすほか、固定資産税など税金の支払いも発生するため、早めの対策を講じることが大切です。
そこで本記事では、日本における空き家の現状や放置することのリスク、活用法について解説します。
>>関連記事:【2025年版】土地活用の方法25選|運用を行うメリットや実際の進め方
目次
1-1増加傾向にある日本の空き家
1-2空き家の所有者の活用意向
1-3空き家の所有者が抱えている課題
2-1住宅が劣化しやすい
2-2周辺地域に悪影響を及ぼす
2-3空家法が適用される可能性がある
2-4建物や土地の機会損失につながる
3-1賃貸物件
3-2解体して別の建物を建てる
3-3セカンドハウス
3-4シェアハウス
3-5民泊
3-6古民家カフェ
3-7サテライトオフィスやコワーキングスペース
3-8農泊体験施設
4-1不動産会社に相談する
4-2空き家の状態を調べる
4-3活用方法を決める
4-4収支計画を作成する
4-5工事を行う
1.日本における空き家の現状
初めに日本における空き家問題の現状を紹介します。
今時点で空き家を所有していない方も、将来実家の相続などで空き家を引き継ぐ可能性も考えられますので、ポイントを把握しておくことをおすすめします。
1-1.増加傾向にある日本の空き家
少子高齢化などの影響を受け、日本の空き家は年々増加傾向にあります。
総務省が2023年に実施した調査によると、日本の空き家は900万2,000戸であり、1958年に調査を開始して以来、過去最高の数字となっています。
さらに総住宅数に対する空き家の数(空き家率)は13.8%で、2018年時の調査13.6%から微増しました。これは、日本に存在する住宅のおよそ7戸に1戸が空き家という状態になっていることが明らかになっています。
ただし、ここで示している空き家には、別荘やセカンドハウスとして利用していたり、売却予定で空き家にしていたり、賃貸住宅で借り手が決まっていない部屋なども対象となっています。
今は空き家となっていても将来的に使う予定が定まっている家屋も含まれた数字となっており、全く使う目処の立っていない空き家ではないことを理解しておく必要があります。
一方、空き家になっている住宅のうち、用途が定まっていない「その他の住宅」は385万6,000戸あります。前回の調査から増加しているため、空き家となった家の活用法に困っている人が一定数いると言えるでしょう。
「その他の住宅」は、建て替えなどのために取り壊す予定の住宅や居住者が長期にわたって不在になっている住宅が該当します。
なお、ここ数年で急に増えたのではなく、1958年の調査開始から戸数・空き家率ともに増加し続けていることがグラフから読み取れます。
また、本調査では「現住居以外の住宅を所有している世帯」が、現住居以外に所有する住宅をどんな用途で利用しているか、調査した結果も出ました。
この中で居住世帯のある住宅では、「貸家用」が 69.1%、次いで「親族居住用」が 25.7%となっており、親族が居住する目的がない場合では、賃貸に出す方の割合が高いことがわかります。
1-2.空き家の所有者の活用意向
国土交通省が2019年に実施した調査によると、空き家の今後の利用意向について「空き家にしておく(物置を含む)」と回答した人が28.0%であり、割合としては複数ある回答の中で最も多い数値でした。
また、空き家にしておく理由は「物置として必要」が最も多く、続いて「解体費用をかけたくない」「更地にしても使い道がない」といった理由が上がっています。
空き家といっても、居住する場所としては利用せず物置として利用している方が多い一方、全く使い道がないにも関わらず、解体費用などの問題で放置されている空き家が多く存在することも確認できます。
1-3.空き家の所有者が抱えている課題
空き家の所有者は多くの課題を抱えているのも事実です。
国土交通省の調査では、空き家を管理する上での課題について「管理の作業が大変」と答えた人は全体の29.8%を占めています。
空き家の管理とは、家の清掃、設備のメンテナンス、庭や外回りの除草作業などがあげられますが、こうした対応に負担を感じている方が多いことが理解できます。
また、「住宅を利用する予定がないので管理しても無駄になる」と回答した人は26.0%であり、空き家を有効活用できていないケースがあることを示しています。
>>関連記事:「知っておきたい『日本の空き家問題』の現状とは?!」
2.空き家を活用せず放置することのリスク
空き家を活用せずに放置すると、さまざまなリスクを抱えることになります。また、全く活用していない空き家でも、固定資産税などの税金は支払う必要があるため、利益を生まずにコストだけがかかるマイナス資産となってしまう場合もあります。
そのため住居として使う予定がない場合などは、早い段階で空き家対策を考えることが大切です。
2-1.住宅が劣化しやすい
人が住んでいない家は、老朽化が進みやすい傾向にあります。
人が立ち入らないため、日常的な清掃がされず、換気もおろそかになるため、汚れが蓄積しやすくなります。
さらに人が利用しないために傷んだ箇所や劣化した設備の修繕が後回しになりがちです。
住宅の劣化が進めば、建物の資産価値が落ち、売却する場合の価格を下げる要因にもなるでしょう。
2-2.周辺地域に悪影響を及ぼす
空き家を放置すると、景観の悪化、悪臭・害虫の発生などを招き、周辺の住民に迷惑をかけてしまう場合があるので注意が必要です。
また、劣化した空き家は人の目が少なく、通行人に気づかれにくいことから、不法占拠・不法投棄といった犯罪の温床になりやすい傾向にあります。
さらに老朽化した屋根や壁が損壊し、隣接する住宅や通行人を傷つけるケースも考えられます。
2-3.空家法が適用される可能性がある
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)は、リスクの多い空き家を減少させ周辺住民を保護するための法律です。
空家法では適切に管理されていない空き家を「特定空家」または「管理不全空家」として指定します。
これらに指定された空き家がある土地は「住宅用地の特例措置」という固定資産税の優遇制度の対象外となってしまい、固定資産税が6倍もしくは3倍といったように負担が大きくなる可能性があります。
【参考】住宅用地の特例
|
|
小規模住宅用地 (200m2以下の部分) |
一般住宅用地 (200m2を越える部分) |
|
固定資産税の課税標準 |
1/6に減額 |
1/3に減額 |
なお「特定空家」とは、放置すると倒壊などのおそれがある状態の空き家のことです。
「管理不全空家」とは、窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態の空き家のことを指します。
つまり、災害に伴う倒壊のリスクがある空き家や、景観を著しく損ねる空き家が対象です。
2023年の空家法改正に伴い、管理不全空家も優遇制度の対象外となったことから、適切な管理の必要性は増していると言えます。
2-4.建物や土地の機会損失につながる
使用していない家屋でも、住宅の状態や土地の場所によっては収益を生み出せる可能性があります。
例えば建物を改修して賃貸物件にする方法などが考えられます。
しかし、空き家のままでは建物も土地も有効活用できず、多くの利益が上げられる機会を手放している可能性があります。
立地条件によっては賃貸として活用が難しいこともありますが、その場合は売却して利益を得る方法もあります。
どちらにしても空き家のまま放置するより、所有者にとってメリットのある方法といえるでしょう。
3.空き家の活用方法
空き家を有効活用できれば、利益を生み出す資産になります。主な活用事例や注意点を以下にまとめます。
3-1.賃貸物件
最もよく知られた事例として、空き家を賃貸物件にする方法があります。
ただし、長期間空き家になっていた物件を居住用として賃貸する際は、壁紙の張り替えやクリーニングなどの修繕を施す必要があるため、初期費用がかかります。
また、修繕だけでは状況が思わしくない場合、リフォームやリノベーション工事を実施して、きれいな状態にして賃貸に出すことをおすすめします。
物件を賃貸する場合でも、修繕費や管理費、リフォーム費用は原則としてオーナーが負担する必要がありますが、入居者からの家賃収入が得られるため、長期的な視点ではマイナス要素が小さくなりやすくなるでしょう。
もし賃貸物件にする場合は、エリアの特徴や賃料の相場、建築可能な物件の要件などの情報が必要なため、豊富なノウハウを持つ不動産会社や専門家へ相談して、最適なプランや活用の流れを提案してもらうことをおすすめします。
3-2.解体して別の建物を建てる
空き家を取り壊して更地にしてから土地活用を行う方法もあります。
築年数が古かったり、著しく汚損している空き家などは、収益性の高い施設や住宅を新たに建てることで、利益を生み出す形に変えることが可能です。
建物の解体費や新しい物件の購入費などがかかりますが、事前に解体業者や建築業者と打ち合わせ、綿密な計画を立てて運用すれば、長期に及ぶ収入を得ることも可能です。
3-3.セカンドハウス
セカンドハウスとは自宅と別に所有するもう1つの住まいのことです。
別荘をイメージする方もいるかと思われますが、仕事や生活の拠点として使われることが多く、日常生活のために住居として使う点が別荘とは異なります。
セカンドハウスは固定資産税や都市計画税、不動産取得税の軽減措置の対象になることから、節税対策としても有効です。
3-4.シェアハウス
シェアハウスとは一つの住居に複数人が住み、共同生活ができる賃貸物件のことです。
リビングやキッチン、トイレ、バスルームなどの部屋や設備は共同ですが、入居者それぞれに個室も設けられています。
プライベートな空間を持ちつつ、他の入居者と一括で使えるものをシェアすることで、他の入居者と交流しやすく、賃料も安く抑えられる特徴があります。
特に若者に人気のある手法ですが、ビジネスに適したタイプであるシェアオフィス、コワーキングスペースなども近年注目されています。
3-5.民泊
民泊とは民家を貸し出す方法のことで、主に旅行者などが個人宅に宿泊する行為を指しています。
民泊は法律により定義されたものではなく、一般的に呼ばれている名称です。
以前は宿泊施設を提供する場合、旅館業法の許可が必要だったため、個人宅を民泊として活用するには簡単ではありませんでした。
しかし、2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定され、都道府県知事に届け出れば、旅館業法の許可がなくても個人宅を宿泊施設として提供できるようになったため、民泊としての運用は行いやすくなっています。
3-6.古民家カフェ
古民家カフェは、古くなった民家をリノベーションして、カフェとして運営している店舗のことです。
あえて真新しい建物にはせず、昔ながらの民家としての特徴を活かし、レトロでおしゃれな空間を作ることで、カフェとしての魅力を高めています。
改修するための費用はかかるものの、建て替えるよりも低コストで済むため、立地条件によっては有効な方法といえます。
ただし、カフェのデザインや店内の設備で失敗をすることがないよう、工事の依頼先は慎重に考えることをおすすめします。
>>関連記事:「建物賃貸経営安定化のコツ〜エリアマーケティングとは〜」
3-7.サテライトオフィスやコワーキングスペース
リモートワークの普及に伴い、サテライトオフィスやコワーキングスペースの需要も高まっています。
サテライトオフィスとは、本社や主となる仕事場所とは別に設けられたオフィスのことです。
コワーキングスペースとは、複数の企業や個人企業主が共同で使用する仕事場所のことを指します。作業用の大きなデスクやインターネット環境を整備さえすれば、間取りを変えるような大きなリフォームは必要ありません。
地方都市によっては町おこしの一環として、自治体全体で空き家を活用したサテライトオフィスやコワーキングスペースの設立をサポートしているところもあります。
3-8.農泊体験施設
空き家が都市圏ではなく、山林部のようにのんびりとした雰囲気のある場所に位置しているときに検討できる方法です。
農泊とは農村や漁村に宿泊して、滞在中に地域の食事や暮らしを体験する旅行のことを指します。こうした農泊を楽しむための拠点として、改装した空き家を貸し出す活用方法もあります。
農村地域は、賃貸物件としての需要が低く、新しい入居者が見つかりにくいことが多いです。
しかし、農泊体験施設として活用することで、その不便さがメリットになる可能性があります。のどかな環境や地元の特色を活かした体験を求めている旅行者からの利用が見込めるでしょう。
4.空き家の活用を行う際の流れ
空き家の活用は、ただ単に物件を売却や賃貸するだけではなく、どのように活用するかに工夫が求められます。
特に空き家活用にはさまざまな方法があり、それぞれに必要な準備と注意点があります。これから紹介する流れに沿って進めることで、効率よく収益を得ることが可能です。
4-1.不動産会社に相談する
空き家をどう活用するか悩んでいる場合は、まずは専門家である不動産会社に相談し、どのような方法が適切かを探ることが大切です。
空き家を持て余して困っていることを伝え、決まっている範囲で活用方法を相談すると良いでしょう。
例えば、「なるべく解体せずに原形を残したい」「取り壊して収益を生み出せる方法で運営したい」など、具体的な希望を伝えるとスムーズに話が進みます。
4-2.空き家の状態を調べる
空き家を活用する前に、物件の状態を調査することが必要です。
例えば、アパート経営や賃貸住宅経営を行う場合、建物がしっかりしていないとリフォームや改修費用が大きくなり、収益が見込めない可能性もあります。状態によっては、手間や初期投資がかかる場合もありますので、しっかりと点検し、活用できるかどうかを判断することが重要です。
特に、建築費や初期投資を抑えたい場合は、建物の傷み具合によっては、解体せずに活用する方法や、部分的なリノベーションを施す方法を検討するのも一つの手です。
4-3.活用方法を決める
空き家をどう活用するかの選択肢は多岐にわたります。
例えば、マンション経営やアパート経営として住居スペースを提供する方法や、介護施設やサテライトオフィス、レンタルスペースといった社会的ニーズに応じた活用方法もあります。
その他にも、駐車場経営やコインパーキング、といった土地活用方法も一つの選択肢です。
選択肢が広がる中で、自分の持っている空き家の立地条件や周辺のニーズを踏まえ、最適な方法を選びましょう。
4-4.収支計画を作成する
活用方法が決まったら、次に「収支計画」を作成します。どの方法を選んだ場合でも、初期投資や運営費用、収益の見込みをきちんと立てることが大切です。
賃貸住宅経営など建物を建築する手法の場合、長期的な収益を見込むことができる一方で、初期投資や管理費用がかかる点に留意する必要があります。
また、利用可能な補助金や税金対策を活用することで、収支のバランスを良くすることができます。
4-5.工事を行う
収支計画が固まったら、実際に工事を行います。活用方法に応じて、リノベーションや新たな設備の設置、改装などが必要になることがあります。
特に賃貸住宅の場合は、居住者の快適性を考慮した改修が必要です。
工事が完了したら、いよいよ物件の運営を開始します。
この時、管理会社と連携することで、スムーズな運営が可能となります。 空き家活用は、正しい手順を踏むことで大きな収益源となり得ます。
どの方法を選ぶにしても、しっかりとした準備が成功への鍵となるでしょう。
5.空き家対策は早めに考えよう
使わない空き家を放置していると、さまざまなリスクに加え、管理費や税金の支払いが続くため、メリットはなくデメリットばかり抱えることになります。
しかし、空き家は使い方次第で利益を生み出す資産になる可能性もあるため、空き家を放置されている方は活用方法を検討することをおすすめします。
大東建託では、土地活用に関する相談を無料で受け付けています。空き家の管理に関しては、グループ会社の大東建託パートーナーズにて空き家サポート事業を全国で展開しています。
空き家の管理やメンテナンスだけではなく、活用方法や相続、税金の相談なども受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
|
空き家をどのように活用するべきか、どのような需要があるのか・・・などのお悩みを解消する資料を無料で提供しています。 お申し込みはコチラから |
■監修者プロフィール
宅地建物取引士/FP2級
伊野 文明
宅地建物取引士・FP2級の知識を活かし、不動産専門ライターとして活動。賃貸経営・土地活用に関する記事執筆・監修を多数手掛けている。ビル管理会社で長期の勤務経験があるため、建物の設備・清掃に関する知識も豊富。
【保有資格】
・宅地建物取引士
・FP2級
・建築物環境衛生管理技術者
お悩みから探す
カテゴリから探す
人気記事ランキング